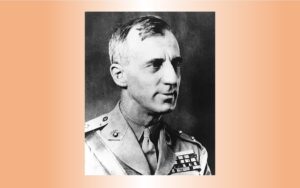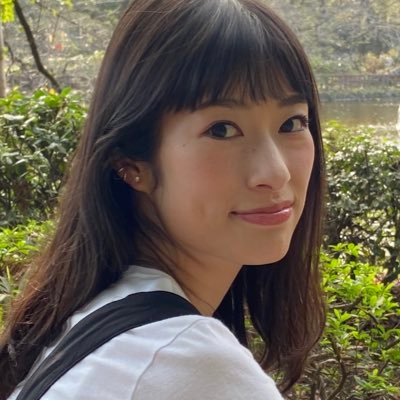砂川闘争と私
安保・基地問題私自身はその後、社会運動やアクティヴィズムという観点、敗戦を経験した民間人という立場からの日本の戦後史を再考するために、個人的な聞き取りプロジェクトを開始した。その一環として、これまた加藤宣幸さんを通じて知り合った仲井富さんに、話を聞くことができた。仲井さんの紹介で、長い裁判闘争を最後まで闘いぬいた弁護士の一人、新井章さんにインタビューすることもできた。新井さんは1931年生まれ、弁護士になったばかりの年に砂川に赴いた。
宮岡さんの『砂川闘争の記録』からも新井さんの話からも、裁判闘争なるものがいかに多種多様に展開されたかがわかる。日米安保条約と行政協定(当時)に守られた米軍と日本政府を相手に、可能な限りの法的手段が模索された。内閣総理大臣による土地収用認定にも、東京調達局による土地測量にも抵抗して、次々と行政訴訟を起こした。基地内侵入のかどで逮捕者が出た刑事裁判では、米軍基地の存在自体を違憲とする「伊達判決」を引き出した。それが60年安保を前に超法規的な手段で覆されるなど、敗訴をくりかえしながらも、逐一はねのけ続けて、果てしなく闘い続けたのである。「大衆的な連帯や行動からも切り離され、人々の関心や記憶が日に日に薄れるなかで、実に根気と辛抱のいる闘いだった」と宮岡さんは書いている。
弁護士たちの闘いの場は、裁判所だけでなく東京都土地収用委員会にもあった。政府が「収用裁決」を求めたのに対し、その請求を認めるか却下するかの結論を下すのが土地収用委員会である。「米軍用地のための土地収用法」にもとづき、行政法的観点から、砂川の土地収用が許されるかどうかを審理するのである。そこで砂川の弁護士たちは、ひたすら審理を引き延ばし、決定を先送りするという戦術に出た。
そして67年、東京都に革新都政が誕生したことで収用委員会の空気が一変した。「美濃部都知事は、あまりこの手続には熱心でないようで」と、収用委員会の側から審理の休止が告げられたのだ。長引いた審理に業を煮やしたのは米軍で、ついに拡張計画を諦めたのだという。新井さんは当初、それが自分たちの勝利だとは思えなかった。あまりにも辛い毎日が続いたからである。その後より深刻に考えさせられたのは、拡張を断念した立川基地の機能が横田に移されたことだった。騒音などの基地問題は横田の住民の闘いに委ねられ、米軍基地そのものもなくなるどころか益々沖縄に集中した。全面勝利とはいえない苦い記憶が残った。
33年生まれの仲井さんにとっては、戦後社会党員となって初めて現場を経験した運動が砂川闘争だった。55年に岡山から上京し、左右再統一したばかりの社会党本部の軍事基地委員会書記および青年部事務局長として、同年10月に砂川の現地支援に入った。それ以来の経験をふり返って仲井さんは、戦後日本の住民運動の勝利も敗北も、すべての原型は砂川にある、と語る。
砂川では、多数の負傷者を出しながらも死者は一人もいなかったが、一人の警官が自殺した。仲井さんは後年、その警官が自分と同郷の貧しい地域の出身だったことを知る。砂川の反対同盟は弔慰金を送って警官の死を悼んでいたのだということもわかり、それにひきかえ全く平然としていた当時の自分を恥じたという。
沖縄の反基地運動の人々からも、警備にあたる地元の警官を思いやる声が聞こえてくる。仲井さんはそこに、砂川の運動倫理に通じるものを感じる。だから日本政府は、莫大な経費をかけて本土の警察を沖縄の警備に動員しているのか。
権力側は、全面的な敗北だったはずの砂川の経験から多くを学び、運動対策と法整備に生かしてきた。そのしたたかさで、沖縄県知事の訴えも県民投票の結果さえも、無視し続ける。しかし、沖縄の人々の「諦めない限り私たちは敗けてはいない」という声は、遠くから支援する私に安易な絶望を許さない。砂川闘争の苦い勝利から学び、実践者・経験者の言葉に真摯に耳を傾けながら、歴史を今につなげて自分の言葉で語り続けたいと思う。