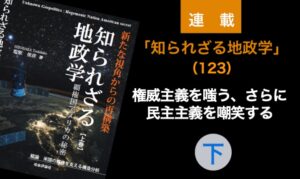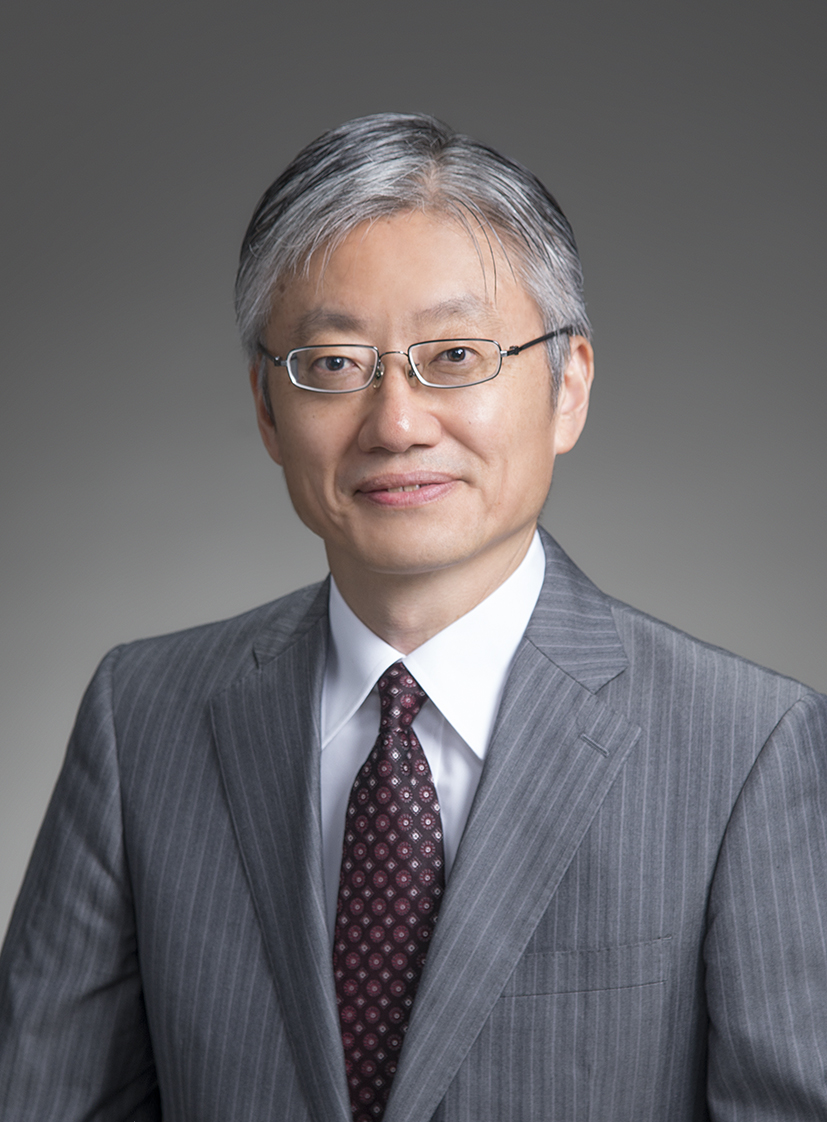第10回 昨日お墓参りをした生涯の友、青木吾朗の突然の死/テレビの報道番組のエースだった吾朗ちゃんの死因/私も経験したあれかぁ?!
メディア批評&事件検証ウェブで読む(推奨):https://foomii.com/00190/20221114100000101917
////////////////////////////////////////////////////////////////
週刊 鳥越俊太郎のイチオシ速報!!
https://foomii.com/00190
////////////////////////////////////////////////////////////////
9日と12日、2回にわたって友人の墓地へ墓参りをした。
今回初めて気付いたが、墓地は全面石で覆われた城のようだ。高齢で足に問題を抱える私のような障害者には、なかなか厄介なものだが。
共に参拝をした若者たちにとっては、尊敬していた先輩プロデューサーへの祈りは欠かせないものの、足場が不自由などはこれっポチも感じていなかっただろう。
小春日和の光の中、我が生涯の友、青木吾朗は静かに眠りについているよう
https://foimg.com/00190/ey7TWJ
「昨年秋、鎌倉にて」
に見えたが、同行した後輩のテレビディレクターたちにはまだまだインパクトを与え続ける存在のように見えた。
私と吾朗ちゃんとの関係は後述するが、ここに46歳、現役バリバリの頃の青木吾朗の姿を伝えるある記録が残っている。
「Director’s MAGAZINE」(August2004)と言う雑誌に掲載された。
「プロデューサー列伝」 No.76
「青木吾朗」
「株式会社テレビ朝日 報道局ニュース情報センターチーフ プロデューサー」という記事だ。
なんと5ページにわたり、インタビューを交えて吾朗ちゃんを掘り尽くしている。
この記事の冒頭に掲げられているのがこの写真だ。吾朗ちゃんらしいちょっと恥じらいを含んだある種の「気どり」が感じられる。私にとっては抱きしめて涙してしまいそうな憎い写真だ。
https://foimg.com/00190/bEVeZI
これから少し「列伝」から引用をさせてもらってテレビに於ける青木吾朗の意味を皆さんにご紹介したい。
記事はこういう出だしで始まる。
少し長くなるが当時の状況を伝えるには欠かせないので引用を続ける。
「惜しまれつつ幕を閉じるTV番組は滅多にない。
『支持される=視聴率が悪くない』という構図があるかぎり、番組をやめる理由はない。逆に、良質な番組であっても一部の支持しか集められなければ続けていくことはできない。
メイン司会者が亡くなったとか、不祥事が起きたという明確な理由があれば話は別だが、番組制作にかかわるスタッフらのテンションは以前と変わらず、視聴者からの信頼も集めているのに、なぜか終わってしまうことがある・・・その数少ない例をテレビ朝日の『ザ・スクープ』(89年10月~02年9月)に求めることに異を唱える人はいないだろう。
従来の堅苦しい報道番組のあり方を一変させ、”観させせる工夫“を盛り込んで成功したのが『ニュースステーション』だとすると、『ザ・スクープ』は地道な調査報道というスタイルを確立して支持を集めた。両番組が世に提示した新しいTV報道の形式は、今日のニュース番組における基本スタイルになっている。
『ザ・スクープ』の表の顔はいうまでもなく鳥越俊太郎氏だ。そして、裏から幾人ものスタッフを支え続けてきたもうひとりの顔が現・報道局ニュース情報センターのチーフプロデューサーを務める青木吾朗その人である」。
次のような一文には驚かされる。
「実は青木氏、意外なことに『報道志望』ではなかったという。『映画会社が演出部門の採用を中断して久しかったので、ドラマをつくるためには TV局に仕事を求めるほかなかったんです。もともと映画好きだったこともあって、あくまで志望はドラマでした。入社してから15年くらいはずっとドラマの部門へ配属希望を出し続けていたんです』」。
そして「バラエティ番組でディレクターを務めていた29歳の時、検証ドキュメンタリーを掲げた新番組『ザ・スクープ』に異動」。
そうかあの頃、私が吾朗ちゃんと人生2回目の対面を果たした時、彼はまだ20代の若者だったのだ。
「Director’s MAGAZINE」によると吾朗ちゃんとの出会いは結構ドラマティックだったようだ。再び引用する。
「鳥越俊太郎氏と二人三脚でやってきたイメージが強い青木氏だが、意外なことに最初の半年はろくに口を利かなかったという。青木氏から見れば鳥越氏は『活字の人』。どこかTVを”舐めて”いると勝手に思い込んでいた。反目し、怒鳴り合ったこともあるそうだ」。
うーん、ここは私にも記憶がある。
テレビ朝日のディレクター達からはなんとなく煙たがられているなあ、ある日突然新聞社から乗り込んできて、テレビのことにあれこれ口を出す私は「地球にやってきた宇宙人だったのだ」と今は思う。
吾朗ちゃんと怒鳴り合った記憶はないのだけれど、言い合い、議論ぐらいはしたと思う。再び引用が続く。
「そんな二人が一気に距離を縮めたのは『ザ・スクープ』で採り上げた『消えた花嫁』問題がきっかけである。
「当時、行政指導でフィリピンなどから農村部へ結婚相手を斡旋する事業が行われていたのですが、一度結婚したフィリピン人女性が逃げ出すという事件が頻発したんです。僕たちは行政による人身売買であるという主張を掲げて、失敗した結婚事例ばかりを取材していた。
すると鳥越さんが『成功した例も見せてほしい』と言った。最初僕は『成功しているように見えるだけで人身売買的な実情は変わらないんだ』と返したんです。
これに対して彼は『それは都会の人間の論理』と譲らない。それであらためて取材してみたのですが、結果としては、彼の言う通りだった。農村で働く青年が『一生、誰にも愛されずに死んでいくのは耐えられない』と言ったんですよ。この言葉が耳に焼き付きましたね」。
この取材をきっかけに鳥越氏と青木氏の関係は激変した。
『ディレクターやプロデューサーの立場にいると、キャスターやコメンテーターのコメントがどこに着地するのか、とても気になるところ。実際に納得いかないことも多い。しかし、鳥越さんにはそういう不安なところがまるでないんですよね。彼はしっかりした歴史観と知識を持っているので、ここいちばんのときでも絶対に外したりしないんです。この二人には、まさに『戦友』という言葉がふさわしい」。
https://foimg.com/00190/GcA4K1
戦友か。頷く自分がいる。
そうか、オレたちゃ「戦友」だったのだ。改めて青木吾朗と自分との関係を見直した。
彼が63歳で亡くなった時私は82歳。だから吾朗ちゃんと私は19歳もの歳の差があったのだ。それなのに簡単に私のことを「彼は」って「彼扱い」されるのには年配者としては抵抗があるんだよ、吾朗ちゃん!!
ま、ホントはそんなことはどうでもよくて吾朗ちゃんとの出会いについて書いておきたい。実にドラマティックな出会いだった。
ドラマ志望だった吾朗ちゃんをお昼の情報番組から全く畑の違う調査報道番組「ザ・スクープ」のディレクターに引き抜いたのは私だった。番組が始まって1ヶ月くらい過ぎた頃、確かそれは1989年11月頃だった。番組スタート時のプロデューサー、日下雄一氏と夕食をしたときのことだった。日下ちゃんは(あ、彼も2006年1月に59歳、食道癌で亡くなった)番組の戦力に不安を持っていたんだろう。ポツリと呟いた。
「これはないものねだりですけど、今昼の番組に青木という若手のディレクターがいるんです。彼がいたらいいんですけど、局が違うので難しいですね」。
局が違うって何?
問い質した。
「いや、鳥越さんにはお分かりにならないと思います。私たち『ザ・スクープ』は報道局の番組で、青木がいるのは情報局です。局が違う人事はあり得ません。この話は私の愚痴ということで忘れてください」。
私は始めたばかりのキャスターという仕事で、幾分気負いもあったんだろう。
よし、それなら一つやってやろうじゃないか!!私を毎日新聞から引き抜いた「テレ朝の天皇」と呼ばれていた「小田久栄門」に掛け合った。
「青木吾朗を私の番組に取ってくれませんか!?」
さすが「天皇様だ」
あっという間に局間人事が発令されて青木吾朗は「ザ・スクープ」の戦力となった。
「初めまして」と挨拶をしたが、よくよく話してみると、青木くんのお姉さん二人とはもう10年前からの付き合いがあった.これは日本航空の広報室次長、深田裕介さん(作家)を間に挟んでのお付き合いだった。よく銀座なんかで飲食をした記憶があった。
その内姉妹の妹さん、R子さんが結婚ということになり、結婚式に招待された。
相手はなんと朝日新聞の社会部のエース記者だった。パーティでは周りは全員朝日の記者ばかり、もちろん毎日新聞の記者などいる訳もなく、肩身の狭い気分だった。
その時、上のお姉さん、 A子さんに「鳥越さん、うちの弟を紹介します」と言われ、視線の先に一人の背の高い若者がいたのを覚えている。
それから何年経ったのか?
もうそんな話は忘れている頃、あの局間の強引人事が行われたのだった。新戦力となった青木吾朗と話すうち結婚式のシーンが蘇って来た。
私たちは「戦友」になる前から「旧友」だったのだ。なんとも縁の深い話だ。
ここでもう一度「Director’s MAGAZINE」の青木吾朗チーフプロデューサーのコメントを読み返してほしい。ここでようやく話が繋がるのだ。
 鳥越俊太郎
鳥越俊太郎
1940年3月13日生まれ。福岡県出身。京都大学卒業後、毎日新聞社に入社。大阪本社社会部、東京本社社会部、テヘラン特派員、『サンデー毎日』編集長を経て、同社を退職。1989年より活動の場をテレビに移し、「ザ・スクープ」キャスターやコメンテーターとして活躍。山あり谷ありの取材生活を経て辿りついた肩書は“ニュースの職人”。2005年、大腸がん4期発覚。その後も肺や肝臓への転移が見つかり、4度の手術を受ける。以来、がん患者やその家族を対象とした講演活動を積極的に行っている。2010年よりスポーツジムにも通うなど、新境地を開拓中。