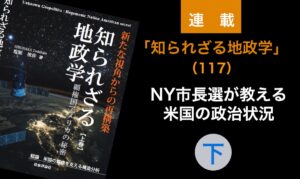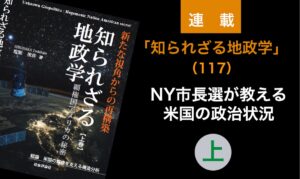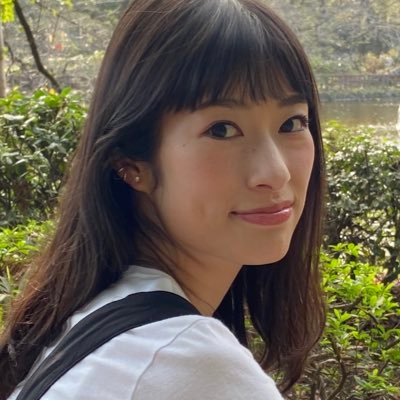ゼレンスキー政権の腐敗実態:日本政府は支援物資の横流しをチェックせよ
国際戦時下でバカンスを楽しむ
まだまだ腐敗ネタは存在する。シモネンコ副検事総長は2022年末、リヴィウの実業家のメルセデスを運転し、スペインに休暇に出かけた。スペインでは、観光地マルベーリャを訪問、10日間のバカンスを満喫していた。
ゼレンスキー大統領の与党、「人民の奉仕者」党のミコラ・ティシェンコ議員で副党首の場合、タイに出かけていた。2023年1月26日、彼はタイ訪問を理由に党と派閥から除名された。
1月30日付の「キーウポスト」(https://www.kyivpost.com/post/11648)は、独特の髪型で有名なユーリヤ・ティモシェンコ元首相が年初、ドバイの五つ星ホテル「ケンピンスキー」のヴィラで休んでいるところを発見されたと報じている。
その後、ウクライナに帰国したらしい。戦争の最中に優雅にドバイで過ごす政治家がいるという事実を知って、ウクライナ国民が怒るのは当然だろう。それだけではない。
戦車からミサイルまで、税金を使って支援している外国政府の国民がこうした事実を知れば、軍事支援に大きな疑問符を投げかけても仕方あるまい。これがウクライナ戦争の真実なのだから。
ほかにも、エネルギー省のガルシュチェンコ大臣、青年スポーツ省のヴァディム・グセイト大臣、戦略産業省のパベル・リャビキン大臣など、多くの部局の責任者が辞職を求められる可能性があるとのうわさもある。2019年末から就任しているデニス・シュミハリ首相でさえ、辞任の危機にさらされている。いずれも、腐敗絡みの不祥事が背景にある。
2月1日に新たな動き
ゼレンスキー大統領がEUの指導者を招いて、ウクライナの長年の腐敗を取り締まる政府の取り組みなどの問題について話し合う2月3日の会合を前にして、ウクライナ政府は腐敗防止に取り組んでいる「そぶり」をみせている。
2月1日、閣議において、国家関税局のヴャチェスラフ・デムチェンコ暫定長官、オレクサンドル・シュツキー同第一副長官、国家林業庁のユーリー・ソトニク第一副長官、国家食品安全・消費者保護庁のアンドリー・ロルドキパニゼ副長官を解任した。さらに、国家関税局のルスラン・チェルカスキー副長官は停止され、懲戒手続きが開始された。
同日、汚職疑惑に関連して全国で数十件の家宅捜索も行われた。そのなかには、ゼレンスキー大統領のかつての盟友、前述したコロモイスキー氏の自宅なども含まれていた。
同日、ウクライナ保安局のサイトに公開された情報(https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-masshtabni-skhemy-pryvlasnennia-40-mlrd-hryven-na-pat-ukrnafta-ta-pat-ukrtatnafta)によると、ウクライナ最大の石油生産会社ウクルナフタおよび石油精製会社ウクルタトナフタの元経営陣による400億フリヴニャ(10億ドル以上)の大規模な横領計画が明らかになったのだという。
この元経営陣には、株主だったコロモイスキー氏が含まれている。2社は2022年11月に政府に接収され、国有化された。ほかにも、税金の詐取などの疑いでキーウ税務署のオクサナ・ダティ署長代理への捜査も実施された。
ウクライナの情報(https://lb.ua/economics/2023/02/01/544409_dbr_vikrilo_kerivnitsyu_podatkovoi.html)によると、捜査の結果、すでに15万8000ドル、53万フリヴニャ、2200ユーロ、高級時計、車などが見つかっている。彼女はキーウに約100万ドルのアパート3棟、キエフ近郊に約20万ドルの家、約15万ドルの車2台をもっているという。
最近になって腐敗防止に積極的に取り組んでいるように政府は振る舞っている。だが、ゼレンスキー大統領が腐敗撲滅を訴えて大統領選に勝利したのは2019年4月のことであり、それ以降、彼がこの問題に真正面から対処してきたとはいえない。こんな大統領のもとへ巨額の資金を助成するのであれば、それなりの明確な支援金管理システムが必要なことは明白だ。
日本の支援は大丈夫か
表にあるロジンスキー地域開発・領土・インフラ省次官は、発電機の購入に絡んでカネを得ようとしたとみられている。ウクライナ国家反腐敗局(NABU)の捜査で、2022年夏にウクライナ政府が16億8000万フリヴニャ(4500万ドル相当)を設備に割り当て、その資金で冬に住民に光と熱と水を提供する計画に基づいて、中央政府と地方政府の一部の関係者が結託し、発電機を高値で購入したことがわかった。
契約締結の援助に対する返礼として、供給者はロジンスキーに40万ドルを渡すことにしたと捜査当局は述べている。ロジンスキー同省次官はこの金額を受け取っている際、拘束されたとされている。
辞任したイワン・ルケリャ氏とヴャチェスラフ・ネゴダ氏という地域開発・領土・インフラ省という二人の次官も発電機の入札に絡んでいた。

Volunteer in orange west gives a box of food donation to fleeing refugees from Ukraine.
日本政府は2022年12月、国際協力機構(JICA)を通じてウクライナに発電機25台を輸送した。楽天は「インバーター発電機 GV-16i」500台をウクライナに寄贈すると発表している。だが、こうした発電機は本当にウクライナで役に立つのか。「ファイナンストラッカー」ならぬ「支援品トラッカー」のようなものをしっかりとつけないと、腐敗の渦のなかに消えるだけではないのか。
米国の場合、2023年1月26日、ヴィクトリア・ヌーランド国務省次官が上院議員に対して、「援助や武器が流用されていない」ことを確認するための措置の一環として、米国政府の監査役がキーウに滞在していることを明らかにしている。岸田首相がウクライナに出向くのであれば、日本も支援物資がしっかりとウクライナ国民のもとに届いているかどうかを確認すべきだろう。
2023年2月1日付のウクライナ側の情報(https://lb.ua/economics/2023/02/01/544483_uryad_yaponii_vidiliv_vidnovlennya.html)によれば、日本政府はウクライナの復興に1億7000万ドルを追加計上したという。これが何を意味しているのかは不明確だが、日本政府は200億円を超える日本国民の税金をウクライナに支援して真っ当に利用されることをどう担保しようとしているのか。国会議員は日本政府に対して、こうした問題を徹底的に追及すべきだろう。
情けない日本のジャーナリズム
ウクライナのジャーナリストたちは、腐敗しきっているウクライナの政治家や高官らの腐敗を、命がけで暴こうとしている。戒厳令下で懸命にウクライナという国家のために頑張っている国民が多数を占めるなかで、こうした腐敗に手を染める政治家や官僚が複数いる現実を、彼らは問いただそうとしているのだ。

Media Interview – journalists with microphones interviewing formal dressed politician or businessman.
こうした彼らの努力に報いるためにも、日本のマスメディアはゼレンスキー政権の実態をもっと正確に報道すべきだろう。とくに、テレビはほとんどこの腐敗ぶりを無視しているようにみえる。報道しないことが日本の利益になるとでも思っているのだろうか。まったく情けない状況にある。
最後に蛇足ながら、最近の戦局について、私の運営するサイトに「ウクライナ戦争の軍事的分析:戦術や装備をめぐる考察」(https://www.21cryomakai.com/%e9%9b%91%e6%84%9f/1576/)をアップロードしておいたので、日本のいい加減な「専門家」よりもずっと的確な私の分析をみてほしい。
〇ISF主催トーク茶話会③(2022年2月26日):鳥越俊太郎さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
※ウクライナ問題関連の注目サイトのご紹介です。
https://isfweb.org/recommended/page-4879/
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)