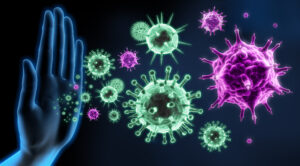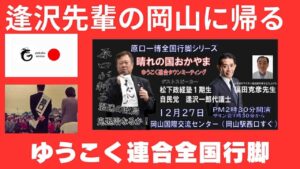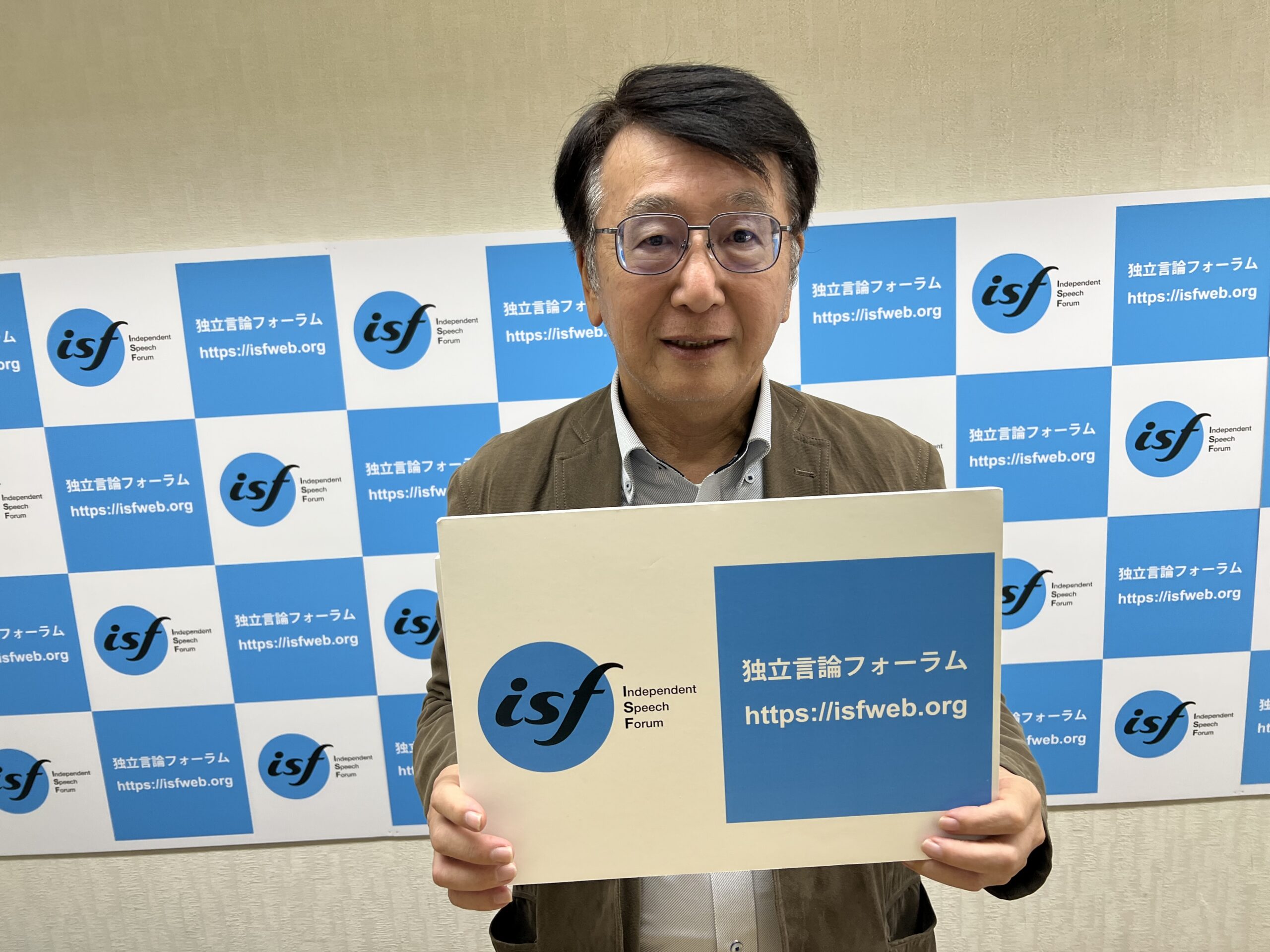種子ビジネスとロシアの排除問題
国際閑話休題
ここで、「閑話休題」として、遺伝子組み換えについて、若干の説明を加えておきたい。そのために、みなさんが読まなければならないのは、スティーブン・M・ドルーカー著『遺伝子組み換えのねじ曲げられた真実:私たちはどのように騙されてきたのか?』(日経BP社)である。
この本を読めば、遺伝子組み換えという危険な技術が政治家、企業経営者、学者、マスメディア関係者によって広められてきたかがわかるだろう。
その手口は、「真実」の無視や隠蔽、安易な権威主義への依存など、複合的な要因によってその危険性を忘却の彼方へと向かわせるというものである。
はっきりいえば、まったくの「詐欺」行為だ。その結果、2015年の段階で、米国の加工食品の大多数(約90%)は遺伝子操作された生産物に由来する成分を含んでいるという。日本もその跡を猛追している。
その手口は、「実質的な同等性」(substantial equivalence)というわけのわからない考え方を使った「ごまかし」にある。
米国の食品安全に関する法律は、すべての新しい食品添加物について安全と証明されるまでは、安全でないとみなすことを求めている。その立証責任は製造企業側にある。
添加物がGRAS(一般的に安全と認識されている)と評価され、テストを受ける義務を免れるためには、その安全性が理論的な推論ではなく、厳しいテストによってすでに証明されていなければならない。
しかし、米食品医薬品局(FDA)は遺伝子組み換え食品を市場に出すために、要件を満たしていないにもかかわらず違法にGRASと認めてしまったのだ。
その論理として、遺伝子操作された食用作物が操作されていない同類の作物と「実質的に同等」と確実に言えれば、本当に安全かどうかを確定するためのテストなしでも、遺伝子操作されていない作物と同じように安全だと考えるというものだ。
しかし、この定義は曖昧であり、遺伝子組み換え食品の安全性を軽視したバイオ産業優先の政策であった。
EUには「予防原則」があり、科学的な根拠が不十分か不確定さのある場合、予防原則による適切なリスク管理を行うことになっている。
しかし、実際には、米国と同じく、遺伝子組み換え食品に実質的同等性を認めており、遺伝子組み換え食品を緩い基準で評価しつづけている。
残念ながら、日本もEUと同じような状況にある。1996年に日本の厚生省(当時)は遺伝子組み換え食品(GMO)の安全性を確認してしまったのだから。
私が警鐘を鳴らしつづけているウクライナ戦争の「要因隠し」も、遺伝子組み換えのやり口と同じような方向で行われている。エスタブリッシュメント(規制権力体制)が「事実」や「真理」をねじ曲げてだましているのだ。
ロシアの問題点
ロシアは種子ビジネスにおいて立ち遅れている。その結果、「種子の潜在的な不足の問題」に直面している。
ロシアの雑誌『エクスペルト』は、農業分野では、小麦や大麦の種まきは何とかできているが、「トウモロコシ、大豆、ひまわり、ジャガイモ、テンサイなどの種子は70~90%が輸入品である」という。
「経済的に成り立つタマネギやニンジンの品種は自前ではもっていない」という指摘もある。つまり、「ロシア市場に種子を供給していたのは、世界的な企業であるバイエル、コルテヴァ、シンジェンタ、BASFが中心であった」のだ。
このうち、米国に本拠を置くコルテヴァは2022年4月、ロシアからの撤退を決定した。3月の段階ですでにロシアでの事業を停止していた。
さらに、2023年2月6日付の「イズヴェスチヤ」によると、シンジェンタ、バイエル、ヌシード(オーストラリア、ヨーロッパ、北米、南米の農場に種子やサービスを提供)は、ロシアの顧客にヒマワリのハイブリッド種子(異なる特性をもつ近交系または純系の品種を交配した一代雑種[F1]の種子)の輸入契約を停止し、商業方針と価格条件を改訂するよう書簡を送った」と伝えている。こうして、ロシアはいま種子不足という大問題に揺れているのだ。
2023年2月中旬の段階で、ロシア農業省は大豆、トウモロコシ、ヒマワリなど、ロシアが外国の品種改良に大きく依存している作物を含む特定の作物の種子の輸入に、来年から割当制導入を提案するようになっている。
2023年3月24日には、ニコライ・パトルシェフ安全保障会議書記の息子ドミトリー・パトルシェフ農業相が閣議において、「農工コンプレクスの輸入独立性を高めるため、2024年から外国産種子の輸入に量的制限を導入する予定である」と発言した。
こうすれば、ロシアの育種家や種苗業者を刺激して種子の生産量を増やし、高収量の新品種をより早くつくることが可能になるというのだ。
具体的に種子輸入の量的制限対象となるのは、ジャガイモ、小麦、ライ麦、大麦、トウモロコシ、大豆、菜種、ヒマワリ、テンサイの種子で、来年1月1日から12月31日まで実施されると予想されている。割当量は、これらの種子の国内生産の伸びをもとに決定される。
なお、ロシアの農工コンプレクスは、テンサイの種子の97%、ヒマワリの種子の77%、トウモロコシとナタネのそれぞれ50%と40%を輸入供給に依存しているとの情報がある。こうした高い依存度のなかで実際にどのような輸入制限を課すのかが注目されている。
気になる種子の脆弱性
2023年2月に『エクスペルト』掲載された「ロシアの種は科学に欠ける」という記事によれば、「現在の種子の平均入手率は約60%に過ぎない」と指摘されている。
全国育種家・種子生産者連合によると、2022年はヒマワリ耕地(1000万ヘクタール)の4分の1しかロシア育ちの種子が播かれなかったという。輸入種子への依存度は、トウモロコシで50%、大豆で約35%とやや低いものの、種子輸入ができなくなれば、ロシア農業は大打撃を受ける。

ヒマワリ種子を採取するためのヒマワリ栽培
(出所)https://iz.ru/1465412/kristina-sumskaia/semennaia-fronda-inostrannye-kompanii-ostanovili-postavki-semian-podsolnechnika-v-rossiiu
別の情報では、「今のところ、ロシアは主要9作物のうち、小麦、大麦、ライ麦、米の種子が足りているだけで、大豆とトウモロコシは40%近く、ヒマワリは60%、テンサイは97%を輸入に頼っている」し、「ジャガイモの種の自給率は10%、キャベツとビートの種の自給率はせいぜい20%にすぎない。足りない種は世界的な企業が輸入したもので、今では国内市場から撤退している」という。
ロシア市場に種子を供給している世界的寡占企業は、ハイブリッド種子を直接輸出するか、ロシアの種子会社のパートナーの施設で、自社の分類された親系統から部分的に再現している。
たとえば、2022年農家が購入したヒマワリの種4万トンのうち2万トンはロシアで生産されたが、ロシアのヒマワリ品種から派生した国内選抜のハイブリッド種子は1万トンにすぎなかった。
2023年2月中旬までの情報では、ヒマワリ種子の輸入に一時的な遅れが生じている程度で、バイエル、シンジェンタ、BASFなどが意図的に種子輸出を手控えているという情報はない。
ただ、2022年に欧州は旱魃に襲われ、種子生産計画が40~60%しか遂行できなかった。このため、市場に出回る種子は少なくなるのは確実で、価格上昇は避けられない状況にある。
余談だが、2023年3月、世界五大穀物メジャーの一つカーギルや、カナダのバイテラは同年7月1日からはじまる新輸出シーズンにおいて、ロシア産穀物の取り扱いを停止する。つまり、ロシア産穀物輸出を停止する。
外国の穀物商社は、穀物輸出のための通関書類を処理するために、数カ月間、ロシア連邦獣医植物検疫局から品質証明書を取得できず、輸出が不可能になっていたから、この停止による直接的な影響はない。
カーギルはロストフ・ナ・ドヌーの河川ターミナル、ノヴォロシースクの穀物ターミナルの25%プラス1株、ヴォロネジ州の穀物加工工場、ヴォルゴグラード州のひまわり種子加工工場を保有しており、バイテラもロシア国内の港やターミナルを所有している。
これらについては、両社ともに操業を継続する。ただ、2社は輸出貿易を停止するために、インフラ資産を所有する意味がなくなることから、こうした資産の売却を計画している。
育種をめぐる課題
ロシアはDNAマーカーを利用した選抜育種といった分野でも遅れている。DNAマーカーとは、生物のもつ DNAの塩基配列の違いを目印として利用する手法だ。
農業分野では、育種目標となる形質の表現型と連鎖した DNAマーカー(抵抗性品種に特異的にみられる DNA配列を目印としたものなど)を利用することによって、簡便に抵抗性や品質などの遺伝的な違いを選抜(MAS)し、形質の短期間での改良につなげるといった手法がとられている。
MASは茎、葉などの組織の一部を用いて環境条件に影響されることなく遺伝的な違いを調べることができるため、効率的な品種改良が可能なのだ(鈴木孝子著「DNAマーカーを利用した選抜(MAS: Marker assisted selection)育種の成果と展望」を参照)。
これまでは、より多産で天候、病気や害虫に対して耐性がある新しい品種やハイブリッド品種を得るために、平均12〜20年かけて系統の交配を繰り返す必要があった。
しかし、21世紀になって、ハイブリッドを生み出すのに必要な時間を短縮できるマーカー育種の利用が広がっている。科学者が植物のDNAから目的の遺伝子を見つけ出し、その配列を記述(マーカー)することで、非常に早い段階で子孫に残すことができる。
その結果、植物育種家は、植物の成長・増殖を待つことなく、芽や新芽の段階でその形質や遺伝子を特定することができる。
また、その後の品種改良の際も、何世代もの交配を経てランダムに見つけるのではなく、確実にその形質を持つ種子のみを植えつけられるようになった。
その結果、新品種(特定の形質を持ち、似たような子孫を残すことができる種子)やハイブリッド(似たような形質を持つ子孫を残さない植物)の開発が3~4年程度ですむようになっているのだ。
しかし、ロシアの民間育種・種子会社であるアストラやガブリッシュなどでは、マーカー育種の経験が未熟であり、世界の最先端からは大きく遅れている。
2023年3月の『エクスペルト』では、アトラス社が2020年からバイエル社のナタネ純系についてマーカー育種法で取り組んでいることが紹介されているが、その見通しを評価するのは困難な段階としている。
①マーカー材料が十分に移植されていない、②ロシアにおける開発と組み合わせるような有用な形質を持つ胚種を選択できていない――といった問題点があるという。
興味深いのは、同じ悩みをかかえているBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)のなかには、反独占の立場から巨大寡占企業との間での技術協力や技術移転が進められている点だ。
たとえば、2022年2月のロイター電によれば、ドイツのバイエルはインドで次世代のGM綿花種子の栽培を申請し、高収量で除草剤耐性のある品種を同国に導入する計画が復活したと政府筋が明らかにした。
同年11月、ブラジル農務省(MAPA)は、米国からのGMトウモロコシおよび大豆の輸入を促進するための規範的指示を発表した。
ロシア政府もこうした動きを見習おうとしている。3月21日付の「ヴェードモスチ」によれば、外国の種子会社がロシアで事業を継続するためには、国内の科学機関とのジョイントベンチャー(JV)設立(外国企業の持ち株比率は49%を超えない)を義務づける規制案が農業省で検討されているという。2023年9月1日からの施行が計画されている。
ロシアの植物育種では、主に数十の国立科学研究所や教育機関、それらに付属する育種・種子センター(BSC)がかかわってきた。
伝統的な育種法を用いて、小麦、大麦、豆類、油糧種子、野菜作物のユニークな品種の育種に取り組み、成功してきた。
近年、41の新しい選抜・育種センターが設立されているが、MASなどの最新技術では後塵を拝している。こうした現実がロシア農業の将来性を疑問視する見方につながっている。
だからこそ、科学機関と農業企業の効果的な相互作用のための「プラットフォーム」となることが期待されている「アグリバイオテックパーク」の設立への政府助成も行われるようになっている。だが、ロシアは緒に就いたばかりだ。
ここで紹介した問題は、ウクライナという穀倉地帯にもかかわっている。それについては、次回の拙稿「米国のイラク侵攻20年が教える米エスタブリッシュメントの「悪」:それはウクライナ戦争へと続いている」で論じることにしたい。
〇「ISF主催トーク茶話会:羽場久美子さんを囲んでのトーク茶話会」のご案内
〇「ISF主催公開シンポジウム:加速する憲法改正の動きと立憲主義の危機~緊急事態条項の狙いは何か」のご案内
※ウクライナ問題関連の注目サイトのご紹介です。
https://isfweb.org/recommended/page-4879/
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)