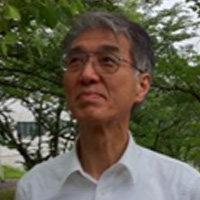「原発政策大転換」の本命 六〇年超えの運転延長は認められない
核・原発問題東京電力福島第一原発事故から三月十一日で一二年が経過する。
岸田文雄政権は、それまでの「原発依存からの脱却」の方針を捨て、原発推進へと大きく舵を切った。原発の安全神話により過酷事故が起きた「福島の教訓」を忘れた暴挙といわざるを得ない。このままでは将来に大きな禍根を残すだろう。
政府は今国会で原子炉等規制法(炉規法)や電気事業法を改正する予定だ。そのうちの最も大きな変更点は、現在最長六〇年とされている原発の運転年数を事実上無制限化する「原発延命政策」である。これは老朽炉を酷使するだけであり、およそ政策とさえ呼べない乱暴なものだ。しかも、その運転延長年数には「長期運転停止期間」と、世界にも例のない不定形の延長期間を持ち込もうとしている。
唐突に原発推進が目玉政策に
「GX実行会議」で原発の新増設や運転期間延長など政策大転換を決定したのは昨年十二月二十二日。
「エネルギーの安定供給と気候変動対策」を名目とするが、その根拠は極めて薄弱。原子力に依存する産業界や原子力ムラへの貢献が最大の理由だ。
国の将来を左右するエネルギー政策の大転換を、非民主的な方法で決めるプロセスにも正当性はない。政府自ら作り出した「エネルギー危機」を理由とするマッチポンプ式でもある。
そして次世代型原発の開発や建設との実現性のない構想を加えて、あたかも「安全な原発による推進」であるかの偽装までしている。二〇一一年の東京電力福島第一原発事故後の「可能な限り原発依存度を低減する」との方針は、事実上放棄された。
この政策は、内閣府の「GX実行会議」という場で決められた。
GXとは、「グリーン・トランスフォーメーション」のことだという。
「過去、幾度となく安定供給の危機に見舞われてきた我が国にとって、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換する、戦後における産業・エネルギー政策の大転換を意味する」と、GXは説明されている(「GX実現に向けた基本方針」より)。
これがどうして原発推進に姿を変えるのか。原発がクリーンエネルギーなど「3・11」以前の安全神話時代の妄想でしかない。
福島第一原発事故で広大な地域が汚染され最大十六万四千人余が避難を余儀なくされた。今も傷は癒えず、「震災関連死」と呼ばれる犠牲は増え続けている。なかったかのような議論の進め方は、あまりにも酷い。
首相が原発政策転換の意思を示したのは八月末、経産省が原子力小委員会などで報告書を急造し、四カ月後のGX会議で方針が決まる。このドタバタの動きは、昨年二月に発生したロシアによるウクライナ侵攻でエネルギーコストが急上昇し、世界的に原発を再評価する動きが始まった時期に付合し、機会を逃すなとばかり原子力推進派が原発活用政策をねじ込み、GX会議に押し込んだのだ。
GX会議には電力会社や既存の大企業の代表者が中心で構成されており、議論は非公開。不透明極まりない。
すでに進行している電力自由のもとで電力市場で競争にさらされる日本の電力会社は、いまさら原発の新増設に投資することは難しい。
さらに、次世代と銘打った原発は、すでにフランスのアレバ社が建設を進めていたが、一基あたり一兆円を超える巨額の建設費と困難な建設工事で、政府が推進方針を示しても進まない状況が続いている。日本で同様の次世代原発を導入しようとしても同じ困難に直面することは明らかだ。
このような「エネルギー危機」は自然エネルギーシステムを中心にした分散型のシステムの開発や電源システム改革で、十分まかなえるものだ。
結局、電力会社にとって最も有利な、既存の原発をできる限り使い続ける方針が政策の本命とみて間違いない。
原発の運転延長の狙うものはなにか
目玉政策の「原発の運転延長」とは、どのような仕掛けだろうか。
それは二〇二二年十二月二十三日付けの原子力関係閣僚会議作成「今後の原子力政策の方向性と行動指針」に記載されている内容で分かる。
まず、「運転期間の延長など既設原発の最大限活用」として、以下の項目が設定されている。
「運転期間の取扱いに関する仕組みの整備」「立地地域等における不安の声や、東電福島第一原発事故を踏まえて導入された現行制度との連続性、技術的な新陳代謝の確保等にも配慮して、現段階における仕組みとしては、引き続き運転期間に上限を設けることとする」とし四〇年規制が生きているかの印象を与えている。
これは、原子炉等規制法改正時に二〇年の延長申請ができる規定を設けた際に、例外的として延長を認めながら、美浜3、高浜1・2、東海第二の延長を次々に許可してきた規制委の現状を見れば形骸化することは明らかだ。
この結果、既存の原発はすべて六〇年超運転を行おうとする。
延長の条件としてあげているのは、「電力の安定供給の選択肢確保への貢献、電源の脱炭素化によるGX推進への貢献、安全マネジメントや防災対策の不断の改善に向けた組織運営体制の構築」だという。
前の二つは、そもそも原発政策の大転換をもたらした所与の条件である。これらの事情がなくなったと認めるときには期間延長を止めるのかというと、そんなことはありえない。一度決めてしまえば、ずっと延長を認めることになるから、条件ではなく延長する理由を書いているにすぎない。
「延長を認める運転期間については、二〇年を目安とした上で、以下の事由による運転停止期間についてはカウントに含めないこととする」との記載こそが延長期間の定義だが、あまりにもあいまいで、どうとでも導き出せてしまう。
具体的に指摘する。
その1「東日本大震災発生後の法制度(安全規制等)の変更に伴って生じた運転停止期間(事情変更後の審査・準備期間を含む)」について
原子炉等規制法の改正法は二〇一二年九月十九日に、条文の多くが施行されているが、特定重大事故等対処施設(特重)については五年間の猶予が設けられていて、その間に短期間再稼働した原発もある。では基準日は二〇一七年九月以降を指すのか、判然としない。震災で止まったものはその日だとしたら、制度改正までの空白期間はどう考えるのか。
計算可能な最大期間を取れば東海第二が震災で止まって以降動いていないので二〇一一年三月十一日を基準日とすると、仮に二〇二四年九月に再稼働をした場合一三年六月を加算して実に七三年六月も稼働することができるということになる。
その2「東日本大震災発生後の行政命令・勧告・行政指導等に伴って生じた運転停止期間(事業者の不適切な行為によるものを除く)」について
事業者の不適切な行為以外で、行政機関が「運転停止」を命じたり、指示したりするなどあり得ないし、できない。法律の根拠もなく、そのようなことをしたら訴訟になるだろう。
これまでの経過で考えられるのは浜岡原発が民主党政権時代に菅直人首相の要請で停止したことくらいだが、これもその後、炉規法改正によって止まっているのだから、わざわざこんな規定を設ける理由がない。これは意味がわからない規定だ。
その3「東日本大震災発生後の裁判所による仮処分命令等その他事業者が予見しがたい事由に伴って生じた運転停止期間(上級審等で是正されたものに限る)」について
脱原発を目指す訴訟による差止(本訴では勝訴しない限り止められないし、それで止めた例はないが、仮処分の場合は即時止めることができる)への対抗手段として出てきたものだ。しかし上級審で覆されたとしても、いったんは司法の場で差止の判断が成されたことを、遡って事実上訴訟の効力がなかったことにしようとするものであり、三権分立の司法権への侵害で違憲だ。
規制委も「規制の虜」に
世界の原発は、スイスのベツナウ原発が五三年運転しているなど、長期間運転は普通だといった認識が原子力関係者にはあるらしい。確かに米国には原子力規制委員会が最長八〇年まで運転できる許可を出している原発がある。しかし実際に六〇年以上も運転している原発は存在しない。八〇年の許可を得ているのに経済性がないなどで早期廃炉になった原発もある。
日本の原発は、当初は輸入品だった。米国から「ターンキー方式」で導入された原発が福島第一原発であり、1号機から3号機まで連続してメルトダウンを起こしたのは偶然ではない。
加えて、今から四〇年以上も前に建設された原発は、今では使用できない可燃性のケーブルが使われていたり、地震想定などが極めて甘かったり、圧力容器や格納容器やコンクリート材の材質が悪いなど、安全性に重大な問題がある原発ばかりである。
これをさらに長期運転するとしたら、安全性はどうやって確保するのか。その責任を負うのが規制委だ。しかし、原子炉等規制法に定める運転期間を超える運転を経産省が許可しても、規制委が厳しく審査するというのだが、信じることはできない。
新たな規制方針は三〇年目に高経年化評価を行い、その後は一〇年ごとに稼働できるかどうか審査するとしている。しかしこの方法は震災以前に行っていた高経年化評価と同様のサイクルである。内容はいまだ分からないが、今の二〇年延長運転許可でさえ、可燃性ケーブルのままだったり地震・津波・火山対策の評価が甘いなどの問題がある。これが抜本的に変わるなどは、今の規制委の姿勢では考えられない。
一方、運転期間の延長に際し、諸外国では運転期間の制限を設けていないと主張する人には、では日本ほど地震や津波の脅威がある原発が世界にどれだけあるのかと問いたい。また、日本の原発はすべて海に面して建てられており、海沿いの原発では常に塩分の影響を強く受けているので、劣化も早い。一度海水が炉心まで浸入すれば使用不能になる。
日本以外でも海岸立地の原発はあるが、加えて地震の影響を受けている原発はほとんどない(台湾くらい)。
原発から三〇キロ圏内に九〇万人を超える人々が住んでいる原発もない。さらに日本海側の場合、豪雪の影響も受ける。これは避難路を断ち、外部電源系統を遮断し、救援も阻むリスクがあるが、これらがすべて重なっている原発は日本以外には存在しないのである。
このような現状に対し、規制委は六〇年超の規制緩和について予め反対しないことを決めていた。
原子炉等規制法には明確に四〇年+二〇年を原則として明記されているにもかかわらず、それを超える期間運転することを認める経産省の方針を、利活用を決めるのは規制委ではなく経産省であるとして、規制委は関与しないとしているのだ。
安全神話により原発震災を引き起こしたことを反省して運転期間を最長でも六〇年に制限することで老朽原発の持つリスクを減らそうとしたにもかかわらず、これが規制ではなく利活用方針の変更であると勝手に決めて更なる延長を認めること自体が規制側の責任放棄だ。
現在でも規制委が「規制の虜」(国会事故調委)となり、機能不全に陥っているのに、さらに運転期間を延長することを認めてしまうのだから、その姿勢は厳しく批判されなければならない。
注:「規制の虜」とは、規制当局の側よりも規制される側が専門知識や情報を有していることで、規制側が事業者の言いなりになり、規制そのものが機能しなくなることを指す。それを排するためには、規制側にも高い知識と能力が求められるが、二〇年運転延長問題の時にも審査書及びそれに至る審査会合で事業者の主張がまかり通るケースをしばしば見てきた。
「次世代革新軽水炉」と称する 原発の正体
「今後、地域理解や安全向上に係る取組、次世代革新炉の開発・建設の進展や、国際的な基準の確立、安定供給に係る社会的な情勢の変化等を継続的に確認しつつ、制度に係る予見性確保等の観点から客観的な政策評価を行うこととする。また、仕組みの整備から一定の期間を経た後、必要に応じた見直しを行うことを明確化する」と書かれている。
これは震災後に比較的早期に再稼働をしている原発もあることから、停止期間を加えても採算性が悪い、特に関電と原電の原発を念頭に置いたものであろう。
さらなる運転期間の延長を目論むこと、そして延長しても二〇五〇年頃には期限が切れる日本原電東海第二と敦賀2号機への対応で加圧水型軽水炉を二基、敦賀原発3・4号機として敦賀市に建設することを想定しているものと思われる。
震災前から計画中の敦賀原発3・4号機は、ウェスティングハウス社製のAP1000型で計画されており、この建設を推進すると思われる。
このタイプを「次世代革新軽水炉」と呼ぶのだが、すでにフランスのアレバ社が欧州加圧水炉(EPR)として世界で六基建設を進め、そのうち中国で建設された二基が運転を開始している。しかし残りの四基はいずれも建設期間が大幅に延び、中には訴訟も絡んで、極めて高価な原発だ。
そのうちフィンランドのオルキルオト3号機は二〇〇五年に建設が開始されたものの、現在も建設は終わらず、総額一兆四千億円もの費用がかかり、二〇二二年十二月二十七日に営業運転を予定していたが三台すべての二次系給水ポンプの羽根車に亀裂が生じる欠陥も生じ、運転開始時期も見通せない。
フランスのフラマンビル3号機も二〇一二年運転開始予定が二〇二二年を過ぎても稼働できず、二〇二四年にまで延びるという。そのため建設費の総額は一兆八千億円を超える。
イギリスのヒンクリーポイントCは、二基を計画しているが合計で約四兆~四兆一七〇〇億円に達するという。運転開始時期も一基は二〇二七年頃を想定しているもののさらに大幅に遅れるという。
すでに稼働している中国の台山1・2号機は、運転直後に1号機の燃料損傷が見つかった。しかし中国はすぐに原発を止めず、運転を継続しようとしたためEPRを建設したフランス・フラマトム社が中国の頭越しに燃料損傷が起きていることを米国のメディアにリークした。批判が高まったこともあり、中国は運転を止めて損傷燃料を交換した。EPRは日本の定義では次世代革新炉だ。しかし余りに費用がかかり、建設期間も長期化している。
原発の利用政策拡大は さらなる原子力災害を生み出す
政府は原発に加え、再処理工場を含む核燃料政策を推進するという。これでは第二、第三の原子力災害のリスクが増えるだけだ。
原発の利活用推進と同時に、核燃料サイクル政策の推進も資源エネルギー庁の「原子力利用に関する基本的考え方」で一章を割り当てる課題だ。
核燃料サイクル事業は国の政策であり電力会社が勝手に行っているものではない。
中心のプルトニウム・ウラン混合燃料(MOX燃料)の価格は輸入ものでもウラン燃料の一〇倍、六ヶ所再処理工場を稼働させてMOX燃料加工工場で生産すれば三〇倍に達するとの試算もある。しかも燃料の燃焼性能はウラン燃料の七五%ほどしかなく、合わせて燃料としての価値はウラン燃料の四〇分の一ほどだ。
この計算を炉心全部でMOX燃料を燃やすとする電源開発大間原発(青森県大間町で建設中)に当てはめると、MOX燃料を国内で製造するとした場合、一炉心の燃料体価格はウラン燃料の五〇〇億円程度に対して一兆五〇〇〇億円にもなる。しかも性能は通常の燃料より短いので、三年しか燃やせない。言い換えれば、毎年五〇〇〇億円規模の燃料費がかかる。原発が一基建設できるほどの値段だ。ウラン燃料価格の三〇倍ではきかないとしたら、さらに金額は上振れし、到底競争力がない発電システムになってしまう。
プルサーマル計画は当初、「高速炉燃料サイクルへの繋ぎ」としてしか存在しなかった。しかし高速炉計画が消滅したためプルトニウムを燃やせるのは原発しかなくなり、この計画が主になった。
その時点でドイツなどのように、核燃料政策の見直しと再処理事業の中止が最も合理的な判断だった。
MOX燃料の炉心安定性はウラン燃料よりも悪いこともあり、性能も悪くリスクも高い計画をプルトニウム利用政策と核燃料サイクル政策と称して推進することに今も合理性はない。
さらに日本は公約として使うあてのないプルトニウムを持たないとしている。原子力委員会によれば、分離したプルトニウムは四七トンを上限として、これ以上保有しない。毎年プルサーマル計画により原発で燃やすプルトニウムは二トン弱にすぎないから、二〇年以上もプルトニウムを取り出す必要はない。
六ヶ所再処理工場の建設を取りやめ、現在存在する使用済燃料をできるだけ安全な方式、敷地内乾式貯蔵に移行することをまず進めるべきである。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
「独立言論フォーラム(ISF)ご支援のお願い」の動画を作成しました!