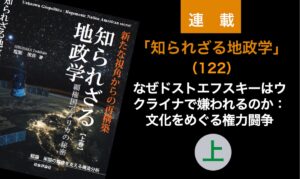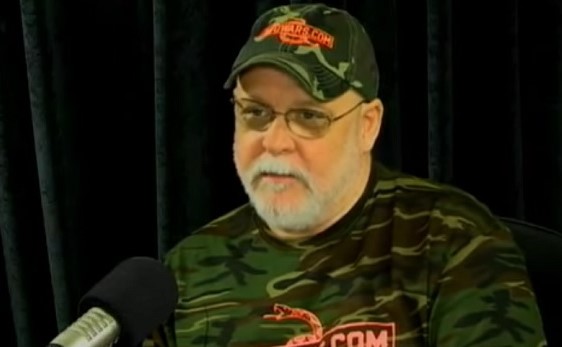堕ちた糞溜め【シンクタンク】ランド研究所の“敗戦”……/~ウクライナの「ベトナム化」で半世紀前の失敗を繰り返す乱鈍【ランドン】集団
国際その他
米国の戦争シンクタンク《ランド研究所》が二〇一九年に「ロシアを弱体化させる戦略としてウクライナを手駒【てごま】に使って地域紛争を引き起こして経済封鎖せよ」という提言を作成していたことは本誌(鹿砦社『紙の爆弾』)で一度ならず暴露したが、その“超限戦”計画が思惑どおり進まず“ベトナム戦争”のような泥沼の長期戦になりそうだと気づいたランド研究所は今年一月に『長期戦を避けるには』と題する提言を出してロシアと和平交渉すべしと言い出した。
今や米国は「世界の警官」どころか、自分で放火して自分で火消しを叫ぶ、悪質極まる“偽善の放火魔”に成り果てたのだ。
ランド研究所とは何であったのか?
米国カリフォルニア州のサンタモニカに本拠を置く《ランド研究所》は、第二次世界大戦の終結からほどない一九四八年の五月十四日に発足した“戦争シンクタンク”である。
第二次世界大戦における連合国の勝因については、必ずしも統一的な結論が得られない。しかしとにかく米国は、ヒロシマとナガサキを二発の原子爆弾で空爆したのが決定打だと信じている。
(ただしナチスドイツ“第三帝国”の帝都ベルリンを制圧したのはソ連軍だったし、連合軍が欧州大陸に上陸してドイツ軍への反攻を推し進めた契機を成【な】したノルマンディー上陸作戦はたしかに米軍の大規模戦力が多大な貢献をしたけれど、他の連合国の軍隊と共同戦線を張ることが出来たからこそ、ドイツ軍を蹴散【けち】らして第三帝国の本陣【ほんじん】に攻め入ることも可能となったわけだ。
大日本帝国を打ち負かしたのも、同様の事情があるわけで、たしかに原爆攻撃はヒロシマとナガサキの人々に途方【とほう】もない破壊と死をもたらしたが、帝国政府はそれでもなお、戦争を続けるつもりでいた。ところがソ連がいきなり〔連合国首脳によるヤルタ会談での「約束」を守るかたちで〕「日ソ中立条約」を破棄して八月九日未明に日本に宣戦布告して攻め込んできたので、日本の戦争指導部〔天皇および政府と軍部のトップ〕は大慌【おおあわ】てで「ポツダム宣言」の受諾〔すなわち敗戦の受けいれ〕を決めたわけである。米軍のナガサキへのプルトニウム爆弾攻撃は、ソ連が宣戦布告したあと、その日の午前中に行なわれている。)
第二次世界大戦によって、海軍力よりも空軍力が勝敗の鍵を握ることがハッキリわかった。そもそも日本軍の連合艦隊によるハワイ真珠湾「奇襲」攻撃だって、空母から飛び立った航空部隊によって行なわれたわけである。そして、日本が史上初めて行なった、中国の都市の一般市民に対する無差別空襲や、ドイツ軍のミサイルジェット機「V1号」やミサイルロケット「V2号」を使ったイギリスの大都市への無差別空爆、連合軍による第三帝国のドレスデンなどの大都市への無差別空爆、米軍による日本全国の主要都市への無差別空爆、そしてヒロシマとナガサキへの原爆投下は、いずれも航空戦力の手柄【てがら】だったわけである。
そんなわけで、米国では、第二次世界大戦が終わると、一九四七年に陸軍から航空部隊を独立させて「空軍」を創設した。同年には、戦争スパイ機関《戦略軍務局(OSS)【オフィス・オヴ・ストラテヂック・サーヴィシズ】》が発展的解消を遂【と】げて《中央諜報庁(CIA)【セントラル・インテリヂェンス・エイヂェンシー】》も創設されている。米ソ冷戦が始まる気配を感じながら、米国の軍事体制は“平時の国防”にむけた機構改革を遂【と】げたのであった。
当時、発足したばかりのアメリカ空軍の最高幹部のなかに、原爆開発で“科学動員”を成功させた「マンハッタン計画」をこのまま解散させるのを惜【お】しむ者たちがいた。彼らは戦闘機の生産企業だったダグラス社の協力を得て、その社屋の一部を借りて、雇い入れた科学者たちを囲い込んで、空軍の将来像などについての調査研究に当たらせた。この空軍“御用達【ごようたし】”の“コンサルタント会社”は「研究と開発(Research ANd Development)」の頭文字をとって、「ランド法人組織【コーポレイション】(RAND Corporation)」という名前がついた。
「法人組織【コーポレイション】(Corporation)」というのは、元々、「人体」を指す言葉であるが、法人格をもった「身体【からだ】」、つまり会社や財団法人などに使われるようになった。日本では、このアメリカ空軍“御用達”の「研究と開発の法人組織【アール・アンド・ディー・コーポレイション】」のことを、その活動内容がわかるように「ランド研究所」と訳してきた。
米ソ冷戦の“勃興”とともに生まれた《ランド研究所》は、ゲーム理論をもちいて米ソ核戦争での“必勝戦略”を追求してきた戦争シンクタンクである。同研究所の創設に携【たづさ】わった戦略空軍部隊のカーチス・ルメイ将軍は、日本の諸都市とりわけ東京大空襲の成功で一躍、名を上げた“鬼将軍”であるが(なのに日本政府は「航空自衛隊の創設に貢献した」として佐藤栄作政権時代の一九六四年に、小泉純也防衛庁長官〔=前首相・小泉純一郎の父親〕と椎名悦三郎外務大臣の推薦にもとづき、ルメイ将軍に「勲一等旭日大綬章【くんいっとう・きょくじつだいじゅしょう】」を授与【じゅよ】している)、彼の“核戦争”に対する考え方は、ソ連が西ヨーロッパや米国に侵攻する兆【きざ】しを見せたときは、持てる核兵器のすべてを使ってソ連の大都市すべてを無差別に先制攻撃して、ソ連を殲滅【せんめつ】してしてしまえばいい……という単純明快なものだった。
しかし一九五〇年代なかば、米ソともに(ヒロシマ・ナガサキに投下した原子爆弾〔=核分裂爆弾〕の一〇〇〇倍以上の破壊力をもつ)水素爆弾〔=核融合爆弾〕を持つにいたった現状をみて、当時の共和党アイゼンハワー大統領(=第二次世界大戦では欧州戦域の連合国軍最高司令官だった)は、核戦争は始まってしまえば「全面核戦争」に帰結するのでアメリカは生き残れない、と悲観して、ソ連との「緊張緩和【デタント】」を追求するようになった。
ところがランド研究所は、「まずソ連の軍事施設を水爆で絶滅すれば、ソ連は降参してくるから米国は生き残れる」という楽観的な“段階的攻撃”戦略を提唱して、核軍拡を煽【あお】った。つまり、ソ連の軍事施設を水爆による徹底的な攻撃で殲滅【せんめつ】したのちも、米国が核兵器の“余力”を保持していれば、万が一、ソ連が白旗を揚げずに戦いつづけようとしても、第二段階としてソ連の都市という都市を水爆で殲滅【せんめつ】すればいい、という極めて楽観的な見通しなのであった。
水爆による米ソ全面核戦争の可能性に怖【お】じ気づいたアイゼンハワー大統領を尻目に、いっそうの核軍拡と、水爆先制攻撃(ただしルメイ将軍が好む一挙的な無差別大量絶滅【メガデス】ではなく「はじめは軍事施設、つぎに都市攻撃」という段階的攻撃)戦略を、アメリカの軍や政府のお歴々【れきれき】に売り込んだのは、ランド研究所のハーマン・カーンという人物であるが、彼は“相撲力士【スモーレスラー】”なみの巨体を揺さぶりながら、漫談芸人【スタンダップ・コメディアン】のような毒舌やシャレを交【まじ】えて、数億人が死ぬような絶滅戦争のシナリオを“講演”して、ワシントンやペンタゴンの高官たちの笑いを誘ったのである。
巨漢ハーマン・カーンの“笑いの爆弾”は軍部と政府の高官たちをみごとに“洗脳”した。ちなみに、この科学者というよりも、全盛期のビートたけしのような乗り[←これらの文字に傍点]で“水爆戦争計画”を売り込むハーマン・カーンは、存在そのものが異色であった。スタンリー・キューブリック監督は、ハーマン・カーンを“モデル”に用いて、一九六四年に、全面核戦争の狂気を皮肉るブラックコメディー映画『博士の異常な愛情~または私は如何【いか】にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』を作った。

【図2】映画『博士の異常な愛情』のポスター

【図3】左がハーマン・カーン博士、右が『博士の異常な愛情』の主人公ストレンジラブ博士
一九五七年十月にソ連が史上初の人工衛星「スプートニク1号」の打ち上げに成功したが、米国は海軍などが手がけていた人工衛星の打ち上げで派手な失敗が続いた。人工衛星の代わりにロケットの先端に核弾頭を積めば、いつでもアメリカを攻撃できる“地球軌道周回兵器”になるわけで、アメリカでは「天空から水爆で狙ってくるソ連の恐怖」を誇大妄想して、国民的なヒステリーが起きた(そのヒステリーを煽ったのは、軍事予算の増額を目論【もくろ】む軍部や軍需産業界やその“代弁者”として活躍したランド研究所の御用学者と、マスコミなのであったが……)。
「スプートニック・ショック」がきっかけで、米国では爆発的な核軍拡と、ミサイル開発を中心とした空軍戦力の拡張が進められることになる。そして民主党は、アイゼンハワー政権がミサイル開発を怠【おこた】っていたことを攻撃し、若いジョン・F・ケネディが大統領選に出馬して、共和党の「反共の旗手」リチャード・ニクソンに僅差【きんさ】で勝つこととなる(この「勝利」については、選挙得票に不自然な点があり、八百長で勝ったのではないか、と指摘されたものである)。
原水爆を運搬・投下する爆撃機の開発製造から、ミサイルロケットの開発製造へと空軍戦力の重点が移り、米国政府に《航空宇宙局(NASA)》が創設されたが、ランド研究所はその経営管理にも貢献した。そしてケネディ政権に乞【こ】われるままに、ランド研究所の科学者たち(彼らは「ランダイト(RANDite)」と呼ばれた)が政府の高官として大量に雇われ、ランド研究所の“文化”であった「ゲーム理論」やら「システム分析」などの科学的経営管理手法を、行政分野に移植する役割を担った。
「ランダイト」たちには共通した信念があった。それは第二次世界大戦で“実証”した米国の「正義」を力強く全世界に波及させれば、全世界が「アメリカ化」して“王道楽土”になる、という信仰である。
ランド研究所の中心的なイデオローグは、ニューヨークのような大都市にユダヤ人移民の息子として生まれ、大恐慌の前後にトロツキズムに気触[かぶ]れたという共通点があった。つまりランド研究所の“公認教義”は、スターリン主義的な独裁によるソ連の存続を絶対に許容せず、“世界革命戦争”によって“革命”を全世界に広めていく、というものだったのだが、その「革命」とは、もちろん“共産主義革命”ではなく“アメリカ的自由資本主義”の移植を指していた。
一九六三年十一月にケネディが暗殺されてテキサス出身のリンドン・ベインズ・ジョンソンが大統領に就くと、ジョンソンは、“世界の果て”東南アジアのヴェトナムの地域紛争に並々ならぬ関心を持った。ヴェトナム独立をめざす現地の戦士たち(=通称「ヴェトコン」)は、ソ連や中共(=共産主義“中国”すなわち「中華人民共和国」)の“共産主義”に気触[かぶ]れて反乱を起こしているに違いない、と信じ込み、ヴェトナム内戦をヴェトコンに勝たせてしまったらアジア大陸はドミノ牌【はい】倒しのようにバタバタと“赤化(=共産主義化)”してしまう、と誇大妄想を抱いて、ヴェトナムなんぞ“アジア辺境の後進国”なんだから空爆で叩【たた】いてやればすぐに“降伏の白旗”を上げるだろう、とナメてかかったのである。……そういう次第で、第一次「東京五輪」の二ヶ月前、一九六四年八月初めに米軍はありもしない「東京【トンキン】湾で北ヴェトナム軍艦が米軍艦を攻撃した」というホラ話をデッチ上げて、それを根拠に「リメンバー!トンキン湾【ベイ】”!」とばかりに、本格的な“北ヴェトナム空爆”(=北爆)を開始して東南アジアでの戦争にのめり込んでいった。ランド研究所の連中は、例の“宗教的使命感【トロツキズム】”に駆【か】られて、ヴェトナム戦争に大賛成し、その後押しをした。
(ちなみにヴェトナムは“シナ文明”を影響を強く受けた“漢字文化圏”である。おなじ“漢字文化圏”の朝鮮半島で二十世紀半【なか】ば以来、伝統的な「漢字」表記が“民族的表記手段”であるハングル文字に急速に置き換えられてきたように、ヴェトナムでも十七世紀にフランス人カトリック宣教師が考案した「チュ・クオック・グー(Chữ Quốc ngữ / 𡨸國語) 」というローマ字に基づく表記体系が現在は公式に用いられている。だが元来「ヴェトナム」という国名は中国語の「越南」に由来する現地読みだし、「トンキン」湾は「東京」湾、「ハノイ」市は「河内」市の現地読みである。現在でもヴェトナムの辞書に掲載されている語彙(現代語)の七割以上は漢字語とされているが、いまやヴェトナムで漢字を学ぶ人々はごく限られており、漢字を使用できる人の数は減少の一途を辿【たど】っているという。)
ところが、ベトナムの独立戦争が、ソ連や中共に誑【たぶら】かされて“ナントカ主義”で行なっている類【たぐ】いではなく、正真正銘の――アメリカ植民地が宗主国イギリスと戦争して独立を勝ち取って「合衆国」になったときのように――独立戦争だとわかって、ランド研究所の内部でも、この戦争から手を退【ひ】くべきだという声が現【あら】われた。その急先鋒が、同研究所で将来を嘱望【しょくぼう】されていたダニエル・エルズバーグ博士で、彼は“米国の東南アジア侵略の現代史”の調査を任【まか】されていたが、その膨大な報告書を研究所から持ちだして複写【ゼロックス】し、新聞社に持ち込んで、世間に暴露したのである。これによって、米国が「トンキン湾会戦」という自作自演の芝居を弄【ろう】して戦争を始めたことも、現地の戦況は米軍が圧倒的に不利で勝利の見込みがないことも、それにも拘【かか】わらず米国政府が戦争を強行しているせいで圧倒的な米国の青年(出征兵士)と現地ベトナムの一般市民が犠牲になっていることが、世界に知れ渡った。
民主党ジョンソン政権が始めたベトナム戦争を「やめさせる」ことを公約にして大統領になった共和党のリチャード・ニクソンも、その口舌【こうぜつ】とは裏腹【うらはら】に戦争をエスカレートしていることが世に知れて政治的な窮地【きゅうち】に立たされ、よせばいいのにニクソンとその取り巻きは、CIAやFBIの工作員を中心に結成した「配管工【プラマー】」と称する非合法工作部隊を使って、エルズバーグ博士ら「ベトナム反戦」知識人へのスパイ工作を展開したが、ウォーターゲートビルの民主党“選挙対策本部”に強盗に押し入って発見され、大統領じきじきに関与した「ウォーターゲート事件」に発展して、七四年八月にホワイトハウスから逃げ出した。そして翌年春には、米国が支えてきた南ベトナムの首都サイゴンが「ベトコン」の攻勢によって陥落し、米国は東南アジアから敗走したのである。
ケネディとジョンソンの子飼いとして活動していたランド研究所の「ランダイト」たちは、ニクソン大統領が辞任し、ベトナム戦争にもボロ負けして米国の世界的信頼が急落したこの時期に、“アメリカ的価値観こそ至高【しこう】であり、これを立ち直らせて世界に広めねばならない”という例の信仰心――奇形的なトロツキズム――に呼び覚まされて、元カリフォルニア州知事だったロナルド・レーガンら右翼勢力と糾合【きゅうごう】した。いわゆる「新派の保守勢力【ネオ・コンサーヴァティヴズ】」(=ネオコン)は、こうして生まれた。学生時代にトロツキズムに染まったシオニストの(中年になって美酒と美食を愉【たの】しみ、ビア樽【だる】のような肥満腹を持て余【あま】している)ランド研究所系の「知識人」と、アメリカ第一主義の右翼勢力が、ここで“結婚”を遂【と】げたわけだ。
一九八〇年の選挙で共和党のロナルド・レーガンが大統領になると、大量の「ランダイト」が政権の重職に採用された。レーガン政権はランド研究所の“思想”を採り入れて、「大幅減税と小さな政府」「福祉の削減」「戦略防衛【スターウォーズ】構想」などと次々と実現させた。レーガンは、彼が「悪の帝国」と呼ぶところのソヴィエト連邦を、民族問題と経済破綻で内部崩壊させることができると真剣に信じていたので、自【みづか】ら爆発的な軍拡を進めて、ソ連の軍拡を誘導した。イソップ童話の「膨【ふく】らませた腹の大きさを競うカエル」の話のように、自【みづか】ら大規模な軍拡を見せつけて、ソ連に競【きそ】わせて財政破綻に追い込もうとしたわけだ。
「ランダイト」の知恵袋たちのアドバイスによって大軍拡を続けたことが、どれほどの影響があったか不明だが、とにかくソ連では共産党トップの老人たちの死亡が相次ぎ、八五年に若いゴルバチョフが“国家元首”に就【つ】いて、「情報公開【グラスノスチ】」と「立て直し【ペレストロイカ】」を柱に据【す】えた行政改革を開始した。
しかしこれはソ連社会を根源から揺さぶる重大な“革命”だったわけで、翌年に“ソ連邦”内部の“ウクライナ議会型【ソヴィエト】社会主義共和国”でチェルノブイリ原発の爆発火災が起きたことも影響してではあろうが、ソ連は社会が過剰に不安定化していよいよ国家経営が立ち行かなくなり、八九年には「ベルリンの壁」崩壊、そして九一年十二月にはソヴィエト連邦そのものが解体して世界地図から消えた。
ソ連が消滅して、超大国としての米国だけが「生きのびた」。これは「ランダイト」たちの宗教的信念ともいうべき悲願だったのだが、「悪の帝国」が実際に消えてみると、軍産複合体の“メシのタネ”がなくなってしまった。かくして米国の軍産複合体は、大慌【おおあわ】てで、ソ連に代わる「悪の帝国」を探し始めた。
一九九〇年代前半のこの時期、日本も「悪の帝国」にされかけたのである。民主党クリントン政権は、中共(=中華人民共和国)を新しい「悪の帝国」にしようとしたが、すでに中共の産業に莫大な投資を始めていた経済界から異議が出て、このときは「中国主敵論」を見送った。
そして結局、北朝鮮やイラクやイランなどの“アメリカ的価値観”が通用しない国々が「ならずもの国家」に指定された。アフガニスタンなどは、一九七九年にソ連の軍事侵攻をうけて、米国が対ソ戦争への支援を続けてきた国である。一九八八年のハリウッド映画『ランボー3/怒りのアフガン』をみればわかるように、一時は“兄弟同志”的な友好国だったのだ。イラクにしても然【しか】り。七九年のイスラム革命で、それまで友好国だった米国に“煮え湯”を浴びせたイランが憎くて、八十年代のイラン・イラク戦争のときは、米国はイラクを支援していたのだ。しかしこうした国は、一九九〇年以降の「新たな冷戦」を求める気運のなかで、「得体の知れないイスラム教の国」だからという理由で、米国の潜在敵国「ならずもの国家」にされてしまった。
よその国を喰物【くいもの】にする
ランド研究所トロツキズム擬【もど】きの腐った根性
ランド研究所の誕生から最近までの歩みを大雑把【おおざっぱ】に見てきたが、その本質は、公共的な資格審査を受けてもいない「民間」の御用学者が、政府からカネをもらって、“現代科学”で偽装した“神学的”なパラダイムで、米国の核戦争や戦争全般についての“思いつき【アイデア】”を政府や軍部の実務者に吹き込む、というものである。
ここで厄介【やっかい】なのは、ランド研究所の「ランダイト」たちが、力づくと謀略で“世界革命”を拡げてゆくというトロツキズムの方法論で、“アメリカ主義【ニズム】”を全世界に敷延【ふえん】する、という妄想的な使命感を持っていることだ。原爆攻撃の連発と、カーチス・ルメイ流の日本全国の主要都市の大規模空爆で、大日本帝国を“石器時代も同然の焼け野原”に変えた第二次世界大戦の直後であれば、“アメリカ主義”を理想視も出来たかもしれないが、そもそも“アメリカ主義”とは何なのか? ちょっと考えれば、そんなものは虚【うつ】ろな自己欺瞞にすぎないことが判【わか】るはずなのだが……。
★ ★ ★
私は本誌(鹿砦社『紙の爆弾』)の昨年六月号(絶滅戦争の作り方)で、ランド研究所が二〇一九年に『ロシアを“強奪”するには:有利な土俵で競うのだ』(Extending Russia:Competing from Advantageous Ground)と題する三五〇頁を超える報告書(→https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3063.html)を出していたことを指摘した(その概要は『ロシアを消耗させて不安定に追い込む:損害犠牲を背負わせる戦略の評価』〔Overextending and Unbalancing Russia:Assessing the Impact of Cost-Imposing Options〕という全編十二頁のパンフレットで読むことができる。→ https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html)。
この報告書は、要するに次のような提案をしていた――
「【1】ロシアの弱点は経済領域にある。
米国との競争において、ロシアの最大の弱点は、経済規模が比較的小さく、エネルギー輸出に大きく依存していることだ。ロシア指導部の最大の不安は、体制の安定性と耐久性に起因する。
【2】ロシアにストレスをかける標的として最も有望なのは、エネルギー生産と国際的圧力の領域である。
我が国〔=米国〕が自然エネルギーを含むあらゆる形態のエネルギー生産を継続的に拡大し、他国にも同様の生産を奨励することは、ロシアの輸出収入、ひいては国家予算や防衛予算に対する圧力を最大化させる。この報告書で検討した多くの方策の中で、最もコストやリスクが少ないのはこの方法である。さらにロシアに制裁を科【か】せばその経済的潜在力を制限することができる。但しそのためには、少なくとも、ロシアにとって最大の顧客であり最大の技術・資金源であるEUを巻き込んだ多国間の政略を行なう必要があり、これらの同盟国はこうした政略の遂行上、米国自体よりも大きな意味をもつ。
【3】ロシアをおびき寄せる地政学的策略は非現実的であったり、二次的な結果を招く恐れがある。
多くの地政学的策略は、米国をロシアに近い地域で活動せざるを得ない境遇に追い込み、結果的に米国よりもロシアの方が安価で容易に影響力を行使することができるようになる恐れがある。
【4】政権の安定を損なうイデオロギー的策略は、逆にエスカレートする大きなリスクを伴う。
戦力態勢の変更や新戦力の開発など、多くの軍事オプションは米国の抑止力を強化し同盟国を安心させるが、モスクワはほとんどの領域で米国との同等性を求めていないため、ロシアを無理矢理奮闘させて消耗できるような策略はごく一部である。」
ランド研究所の戦略提言は、米国自身が傷つかずに、ロシアを挑発してその国家経済を不安定化して弱らせる、という構想に他ならない。「地政学的策略」の議論のなかで、ロシアと戦わせるための“アメリカにとって最も好都合な手駒【てごま】”はウクライナである、という結論を出していた。昨年の二月二四日から現在に至るまでの展開は、まさにこのランド報告書どおりに進んできたのである。
ところがランド研究所は今年の一月になって、『長期戦を避けるには:ロシア・ウクライナ紛争の道程と米国の政策(Avoiding a Long War:U.S.Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict)』(https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA2510-1.html)を発表した。六四頁にわたるこのレポートの主張は要するにこうだ――
【1】今回の戦争ではロシアもウクライナも決定的な勝利を収められそうにない、
【2】ゼレンスキー大統領はロシアをウクライナから追い出すと豪語しているが、これも不可能だ、
【3】このままではNATOとロシアとの戦争に発展し、核戦争にもなりかねないが、これは米国に国益を脅【おびや】かす重大問題だ、
【4】ウクライナにとっては失地回復が重要だろうが米国の国益はそれと異なるわけで、戦争が長引けばNATOと米国との関係に亀裂が入り、武器も不足し、中国と対抗できなくなる恐れが大きい、
【5】ウクライナの領土の一部がロシアの支配下に置かれるのはやむを得ないわけで、米国は早めにロシアとの交渉による解決を図るべきだ。
四年前の『ロシアを“強奪”するには:有利な土俵で競うのだ』報告書で戦争を煽【あお】っておきながら、実際に戦争になってみたら自分にも“核戦争の火の粉”が降りかかりかけない展開になって怖【お】じ気づき、ウクライナを捨てて逃げる算段である。なんとも卑怯【ひきょう】で冷血なのが、二一世紀のランド研究所が垣間見せている“アメリカ主義”なのである。
とりあえず我々にとって重要なのは、こういう卑怯な連中の“土俵”やら“喰物【くいもの】”にならぬよう頑張【がんば】ることしかない。我々はランド研究所を「シンクタンク」と呼んできたが、「“考え(think)”が詰まった“溜め池(tank)”」は「ティンクタンク(think tank)」と発音するのが正しい。「シンクタンク(sink tank)」は「掃【は】きだめ」、もっといえば「肥【こえ】つぼ」である。ランド研究所の場合は「糞溜【くそだ】め」ということになろう。“合理主義者”の声色【こわいろ】で、熱狂的で(無反省という意味で)得体の知れない“アメリカ主義”を力尽【ちからづ】くで押しつける“腐れトロツキスト”あるいは“腐れイエズス会”のような“革命”の押し売りは、金輪際【こんりんざい】やめてもらいたいものだ。
【参考文献】
『ランド~世界を支配した研究所』(アレックス・アベラ著/牧野洋訳、文藝春秋、二〇〇八年)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
●ISF主催トーク茶話会:孫崎享さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
●ISF主催公開シンポジウム:「9.11事件」の検証〜隠された不都合な真実を問う
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内