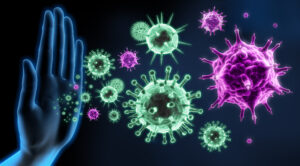浦島太郎の経済学に今日的経済力学の鉄槌が下る
社会・経済このところ、二つのフレーズが経済メディアを賑わしている。その一が「悪い円安」、その二が「国際収支の発展段階説」だ。両者は、日本経済が迎えている一つの局面の現れであり、要因でもある。この構図には、長年にわたる日本の経済運営の認識不足が関わっている。
「悪い円安」は現在進行中の円相場の下落に関する言い方だ。このところの円相場は、久々に125円を割り込み、130円を伺う展開になっている。本稿をお目に止めて頂ける段階では、既に130円台入りしているかもしれない。20年振りの円安局面到来だ。この状況を巡って「悪い円安」論が飛び交っているのである。

price of btc is going to breakout
筆者は、この「悪い円安」という言い方に強い違和感を覚える。なぜなら、敢えて「悪い」という枕詞をつけるこの表現は、その背後に、円安は基本的には「良い」のであり、歓迎すべきことだという認識が根を拡げているからだ。この裏返しが、円高は基本的に「悪い」ことであり、円高進行は回避しなければならないという認識だ。
これは実におかしい。一国の通貨の為替相場に基本的な良し悪しなどない。当面する経済状況と為替動向が整合しているか否か。それが勘所だ。いついかなる場合においても、円安は良くて円高は悪いなどと思い込むことこそ、「悪い」ことだ。
そこで現状をみれば、確かに、目下の日本経済にとって円安は不都合だ。かつて輸出大国だった日本は、いまや、輸入大国だ。規模の大きい成熟経済において、これは当然の姿だ。生産も消費も、輸入に多面的に依存している。サプライチェーンがグローバル化しているから、輸出産業の生産が拡大すれば、それに伴って輸出産業自体の部品・素材の輸入が増えるという関係が定着している。このような国にとって、自国通貨の価値下落は企業部門にとっても家計部門にとってもコスト高につながる。
しかも、コスト圧力が高まったからといって、そのことが輸入数量の減少をもたらすとは限らない。生産においても消費においても、輸入品が構造的に組み込まれているからだ。つまり、今の日本において、円安進行は円建て輸入額の膨張につながりやすい。輸入数量が、輸入品の単価上昇に反応して減るというメカニズムが働き難いためである。今の日本においては、輸入の価格弾力性がすっかり低くなっている。
輸出面についてみても、状況は大きく変化している。かつて、日本が輸出主導型成長の国だった時、円安は価格競争力の強化を通じて輸出数量の増加をもたらした。だが、今の日本では違う。今の日本の輸出構成は、輸出主導型成長の時代に比べて高度化している。輸出単価の低さで勝負するような品目に輸出動向が依存しているわけではない。したがって、円安が進行しても、それが輸出数量の顕著な増加にはつながらない。日本の輸出もまた、価格弾力性が低くなっているのである。

Aerial view of freight ship with cargo containers on the sea. See similar photos: : http://www.oc-photo.net/FTP/icons/cargo.jpg
かくして、今日の日本においては、円安は輸出増をもたらさず、輸入増をもたらす。したがって、今日の日本にとって円安は貿易収支の赤字化要因になっているのである。つまり、貿易赤字がイヤで、あくまでも、貿易黒字の拡大を追求したいというなら、「円安大歓迎」という発想にはそもそもならないはずだ。ところが、日本の政策責任者たちも、企業経営者たちも、いまなお、時代錯誤的な円安礼賛感を払拭出来ない。だから、わざわざ「悪い円安」などという言い方をすることになる。今の円安が「悪い円安」なのではない。今は「円安が悪い」。そういう時代になっていると認識すべきだ。
ところが、安倍晋三すなわち筆者流に言えばアホノミクスの大将が2012年に政権を手に入れた時、彼は「私が選挙に勝利したことで、株価は上がったじゃないですか。円安になったじゃないですか。」と胸を張った。
円安を実現したことを勲章だと思っていたのである。だが、彼がもたらした円安は、上記のような構造の中で、実は貿易赤字の拡大につながるばかりで、さしたる輸出増につながったわけではなかった。通貨価値の変動が引き起こす力学について、アホノミクスの大将は著しく時代遅れな理解しか持ち合わせていなかったのである。彼の経済学は浦島太郎の経済学だった。
さて。以上を踏まえて、「国際収支の発展段階説」という第二のテーマに目を向けよう。これは、国々の国際収支構造が、それらの国の経済的発展段階を反映して変化をたどるという考え方だ。国際収支の発展段階は6つある。「未成熟債務国」・「成熟債務国」・「債務返済国」・「未成熟債権国」・「成熟債権国」・「債権取り崩し国」だ。
今の日本は、「未成熟債権国」から「成熟債権国」の段階に向かいつつある。成熟債権国の貿易収支は赤字になる。上述のように輸入依存度が多面的に高くなるからだ。だが、貿易収支に所得収支(対外資産がもたらす所得受け取りと対外負債に関する所得支払いの差分)を加えた経常収支のレベルでは黒字になる。所得収支の黒字額が貿易収支の赤字額を上回るからだ。つまり、それだけ対外資産の規模が大きい。この段階の経済はモノの輸出に支えられているわけではない。カネの輸出に主導されているのである。今の日本は資本輸出大国なのである。
そのような日本にとっては、円高が相性がいい。円の購買力が大きければ、それだけ安上がりに対外資産を増やせる。資本輸出国の通貨の価値は高いことが整合的だ。それなのに、浦島太郎の経済学からの切り替えが効かない人々は、いまなお、円高を天敵視する。
さて、ここから先が問題だ。成熟債権国段階の次に来るのが、債権取り崩し国段階だ。この段階では、経常収支が赤字化する。貿易収支の赤字を所得収支の黒字で相殺出来なくなるからだ。経常収支の赤字化自体が、一義的に問題だというわけではない。経常収支が赤字だということは、国内的にみれば、総需要が総供給を上回っていることを意味する。
別の言い方でいえば、投資が貯蓄を上回っているのである。それだけ経済活動が活発化していると解釈してもいい。だが、投資が貯蓄を上回るということになると、貯蓄不足分を何とか捻出しなければならない。いかにして貯蓄不足を補うのか。そのためには、海外からの資本流入に頼るほかはない。アメリカ経済は、長らく、このやり方で経常赤字ポジションを維持して来た。
今の日本にこれが出来るか。どんどん安くなる一方の円に、海外の投資家たちがどれだけ資産価値を見出して、対日投資に力を入れるか。世界が金融政策の正常化に向かい、金利引き上げを進めようとしている時、日本の金融政策は頑として「量的緩和」に固執している。金利上昇で政府の債務返済負担が増えることを、何としても避けようとしているからだ。中央銀行が政府のためにカネを振り出す打ち出の小槌と化している。
かくして、内外金利差がどんどん広がれば、海外から資金が入ってくるどころか、日本から資金が流出して行ってしまうかもしれない。そのような展開になればなるほど、円安が進行する。そして貿易赤字がさらに拡大する。そうなればなるほど、海外からの資金流入に依存して経済を回すというシナリオは成り立たなくなる。かくして、日本経済は資金枯渇のために干上がる。ミイラ化だ。浦島太郎の経済学に対して、今日的経済力学の逆襲が始まった。
 浜矩子
浜矩子
1952年生まれ。一橋大学経済学部卒業。三菱総合研究所初代英国駐在員事務所長、同社経済調査部長、政策経済研究センター主席研究員などを経て2002年より同志社大学大学院ビジネス研究科教授。専攻はマクロ経済分析、国際経済学。主な著書に「愛の讃歌としての経済」(かもがわ出版)、「スカノミクスに蝕まれる日本経済」(青春出版)、「人はなぜ税を払うのか」(東洋経済新報社)、「共に生きるための経済」(平凡社新書)など。