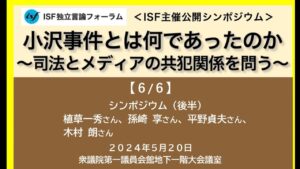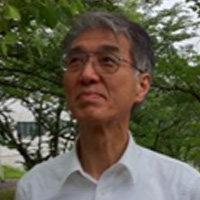フランス年金改革反対デモと「周縁」からの民主主義
国際政治「年金改革」の中身
木曜日には、パリの拙宅近くの公園大通りに朝市が立つ。3月23日にも市場に行った。ところが、ガランとしてテントも立っていない。この大通りはバスチーユ広場につながっていて、そこが、年金改革反対デモの出発点になるのだ。
デモの出発は午後2時である。バスチーユ広場ではよく集会やデモがあるのだが、昼食時には終わるこの通りの市場が中止されることはない。それだけ、大規模になると予想されているのだろう。
エマニュエル・マクロンが「右」でも「左」でもない大統領を標榜して2017年5月に当選した時、労働法改革など一連の社会保障・労務改革を掲げた。年金改革はその最後で、2019年の夏を目標に設定されていた。
はじめの労働法改革は、前任のフランソワ・オランド大統領の時代に大きな反対運動が起きて進まなかったものだ。しかし、労働組合連合との対話もうまくいって、とくに混乱もなく2017年の秋には終わった。
黄色いベスト運動があって遅れたが、2019年の後半にいよいよ年金改革に着手した。12月に改革の骨子が発表されると、頑固さで知られる労働総同盟CGTなどがストライキに入った。年末年始、パリのバスや地下鉄が止まった。
法案は日本の衆議院にあたる国民議会に上程され、翌2020年3月に「強制採決」(後述)にまで至ったが、新型コロナ禍で廃案になった。
そして昨年、マクロンは再選され、新型コロナも一段落し、再び懸案に着手した。大晦日の恒例の挨拶で大統領は、「(国民の連帯の証である)賦課方式の年金制度を維持するために、もっと長く働かなければならない。いまは借金で資金を調達し続けている。このままでは制度が脅かされる」と語りキックオフした。
さっそく年明けの1月3日にエリザベット・ボルヌ首相はフランス第一の組織で穏健派の民主労働同盟CFDT(この次にCGTが拮抗している)と対話をしたが、反応は芳しくなかった。
骨子が発表されると一斉に反対の声が上がった。マクロン与党の一角をなすMODEMのフランソワ・バイルー党首も拙速を批判した。しかし、前の法案とは別の新たなものとして1月23日に国会に上程された。そのとき社会保障財政補正法案としたのだが、こうすると50日以内に国会で採択しなければならないからである。
改革の主な内容は、①年金受給資格年齢の引き上げ②年金拠出期間の延長③特別制度の廃止と一般制度への統合である。
①は現行の62歳を64歳にする。なお、この年齢で退職して年金を受け取る義務があるわけではなく、その後働き続けてもいい。ただし、この年齢に達しない場合は、政府が特別な早期退職制度を設けない限り受給額が減額される。
②の拠出期間は、4半期ごとに「1」として計算する。であるから1年で「4」となる。年金受給資格年齢になっても拠出期間を満たしていない場合は、期間に応じて減額される。現行は168(42年)である。これを27年までに172に延長する。
③は、フランスでは年金は政府管掌ではなく、民間企業給与労働者をカバーする一般制度のほかに、職種ごとに独立した特別制度がある。特別制度の中には優遇された特権的なものもあり長年問題となっていた。これを一般制度に一本化しようというものである。
政府が目をそらす「生活の現実」
現在はもっぱら①と②に焦点が当たっている。③には原則賛成のCFDT、おなじく穏健派のCFTC、幹部社員組合のCFE・CGCも①②に反対している。
CFDTが特に問題にしているのは、受給資格年齢の延長だ。現在の受給資格年齢は62歳で満額拠出期間は42年だから、20歳から働き始めた人は、受給資格年齢に到達後すぐに年金を得られる。ところがこれが64歳になると、あと2年待たなければならない。
「年金改革に反対なのは、フランス人が働きたがらないからなのでは?」
よく言われることだ。独立組合全国連合UNSAのアラン・ジェルゴー書記長に質問した。すると彼は、「フランス人は、働くのは好きなんです」と即答した。
「62歳を64歳に強制することがよくないんです。選択の余地がない。働きたい人は70歳でも働けばいい。企業ごとに仕事の条件は違います。今回、企業経営者、MEDEF(フランスの経団連)はまったく発言していません。彼らは55歳になると解雇する。高齢すぎるからです。政府もこういう現実には目をつぶっています」
たしかに、フランス人が怠け者であるわけではない。年金をもらったら遊んでいるわけではない。NPOなどでは年金生活者をよく見る。彼ら高齢者ボランティアに支えられているといっても過言ではない。
また、企業が高齢者を嫌うのも事実だ。とくに、ブルーカラーや普通の事務職はむずかしい。64歳なんてまだ若い、と思われるかもしれないが、就職先はみつからない。
年金は、多くのフランス人にとって死活問題である。日本のように多額の退職金はなく、エリート学校出身者以外は賃金が高いわけでもないので、貯蓄も少ない。なお、年金受給金額は、満額で生涯の最も賃金の良かった25年間の平均年収の50%である。
国会上程を待たずに1月19日に反対運動は始まった。フランスには、代表的な労働組合連合が8つあるが、全てが反対して統一行動を起こした。13年ぶりである(あの時も年金がテーマだった)。
労働組合が話し合いを尊重する姿勢は悪いことではない。だが、時には厳しい態度をとらなければならない。闘うときには闘わなければならない。もちろん、労働貴族の利益のための闘いではだめだが。緊張関係がなければ経営者も政権も横暴になる。
1月19日のデモの参加者は内務省発表で、全国で112万人、パリでは8万人であった。第2波の1月31日にはパリで8万7千人、全国で127万人が参加。1995年以来の社会改革に反対するデモとしては第1位となった。
新しい形の年金改革反対運動
今回の抗議行動には、いままでの年金改革反対運動とは違った感じがある。単に「長く働きたくない」とか既得権の確保というものではない。黄色いベスト運動と共通するものがある。
いまや社会の対立軸は「上」と「下」である。法外な報酬をとる大企業経営者やマネーゲームに終始する金融投資家などがいる一方で、中小企業経営者や労働者といった「働く人々」の生活はいっこうに楽にならない。この不満が、18年秋に黄色いベスト運動として爆発した。
今回のデモ参加者の「なぜ貧乏人が年金財政のバランスをとるために支払わなければならないんだ」という声が端的にあらわしている。
年金改革もまた、庶民を馬鹿にするような言動や、富裕連帯税の実質的廃止などですっかり「上」であることを露呈してしまったマクロンを筆頭に、机の前に座っているだけの、いつまででも仕事が続けられる政治家や官僚、エリートが数字だけを見て勝手に決めたものだ。庶民のことなどまったく考えていない。
「上」と「下」について地理学者の視点から、グローバリゼーションやファイナンス世界の恩恵を受ける「中心(メトロポール)のフランス」とむしろ犠牲になる「周縁のフランス」に分化していると明快に分析したクリストフ・ギュリーは、年金反対の抗議行動について、「ここ数10年にわたって西側を席巻してきた社会的、政治的、文化的な抗議の同じ運動の一部である」と言う。
「黄色いベスト」は組織的運動ではなく、また、反ルペン派の極右が取り込もうとしたこともあって鎮静化した。しかしその不満はマグマのように沈殿している。統一デモの動員は第6波の3月7日に全国で128万人を記録更新してから減って、3月15日の第8波では48万人となった。ところが、3月23日には、109万人と倍増した。
この日、デモに「民主主義の擁護」という新しい性格が加わった。政府が憲法の49条の3の規定を使ったのだ。この条項は、政府が責任をコミットメント(約束)すると投票なしで可決通過とされ、これに対抗するには内閣不信任案しかないというものである。日本でいえば、強行採決したようなものだ(実際、日本のマスコミでは「強制採決」と呼んでいる)。
2020年にも使ったが、あの時には、新型コロナ流行を前に審議を前倒ししようとしたためだった。今回は、マクロン与党が過半数に届いておらず、伝統右派の共和党の賛成を得ようとしたが難航していたからである。
フランスは半大統領制といって内政の責任者は首相だが、この条項の使用の決定はマクロンの意思だったらしい。
内閣不信任案は3月20日に出された。共和党の議員19人(共和党議席数の3分の1)が造反したため9票差での辛うじての否決であった。
世論をなだめようと、2日後の22日昼に、フランスの2大テレビ局でマクロン大統領の共同インタビューが放送された。「(私への支持率が低くても)私が全て責任を負う」など大見えを切るが、「支持率よりも公共の利益が大切だ」とまったく謙虚さはなく、「強制採決はボルヌ首相が決めた」など、責任転嫁までする。
失言癖も相変わらずで、デモやストの参加者をアメリカで議会乱入したトランプ支持者と同列に見るとか、デモの参加者が人民を代表しているわけではないとか、民衆を逆なでする言葉も飛び出し、火に油を注いだ。番組直後の世論調査では、71%が納得できなかったという。また「マクロンは良い大統領だ」と答えたのは、24%に過ぎなかった(BFMTV、調査ELABE)。
全国津三浦々の「街頭」で声を上げる
日本でしばしば政権担当者は、専制を糾弾されると、「選挙で選ばれたのだから民主主義に則っている、民意の反映である」と弁解する。フランスの場合、直接選挙で選ばれた大統領とそれが指名する首相が政権を持っているという違いがあるが、マクロン大統領もまた「街頭が決めるのではない、われわれは選挙によって委任されたのだ」と言った。
しかし、国民は白紙委任したわけではない。そもそも、選挙ではテーマごとに投票するわけではない。全体としては支持しているとしても、特定のテーマについては反対のこともある。
そのときには、「街頭」で意思表示する。デモは、代議制の欠点を補完する民主主義の重要な要素である。
フランスでは、集会や演説をすることなく、組合連合ごとに隊列を組んで時間になると歩き出す。景気づけにロック音楽を流し、ディスクジョッキーばりにシュプレヒコールをするものもある。
出発点のバスチーユ広場は、出発時間から一時間たってもまだたくさんの参加者が残っていた。この光景を見ながら確信した。「街頭」の力は、人が出て道を埋め尽くす、しかも整然とデモ行進が行なわれるというところにこそある。決して、警官隊を権力の象徴だとして投石や火炎弾で戦うことではないのだ。
よく、「デモが暴徒化して」などといわれるが、あれは、ブラック・ブロックとよばれる過激派や狼藉を働こうとするいわゆる壊し屋がデモに混じって暴動しているだけである。デモとは無関係だと言っていい。
日本やフランスなど切迫した圧政のない国では、暴力行為は、権力に打撃を与えない。むしろ、権力を利する。このような社会運動の時に権力が使う常套手段が、暴力に嫌気がさして運動が民衆の支持を失っていくことだ。
街に出ることは大切である。今はインターネットがあるというが、いくらネットの中で騒いでもバーチャル空間だけで起きていることであって、政権には痛くもかゆくもない。世論調査もバーチャルな数字に過ぎない。せいぜいが、政権与党内での権力争いに利用されるだけだ。
「街頭」は見える形でプレッシャーをかける。政権との間で緊張関係が生まれる。ネットや世論調査は、この道を埋め尽くす人々の背後には莫大な数の「声」があるということで力を持つ。
前出の地理学者ギュリーは今回の特徴として、「伝統的な『左翼』のデモとは異なり、とくに『周縁のフランス』の中小都市で、低所得者層も多い民間部門の従業員がデモを盛り上げた」と指摘する。示唆に富んだ言葉である。いくら大都会で大きなデモをしても、一部の人の現象であって地方には「声なき声がある」と切り捨てられてしまう。全国津三浦々で声を発することが重要だ。
4月14日、憲法院が違憲審査の結果を発表した。違憲とされた箇所は無効になるのだが、受給資格年齢など主要な条項は合憲と認めた。マクロン大統領はその夜のうちに署名して、翌朝、法律は公布された。しかし、直後の世論調査では66%が抗議行動を支持し、1週間前の調査より2%増の60%が組合に動員を続けてほしいとしている(RTL、調査会社THI)。
政府は、とにかく法律が既成事実になれば沈静化するだろうという読みである。マクロン辞任、法案撤回を叫ぶデモの参加者も、結局はこのままいってしまうだろうということはわかっている。だが、それでも街に出るのだ。自分の1票では変わらないだろうと思いつつも投票所に足を運ぶのと同じだ。デモをするという過程が重要なのだ。やめてしまえば権力の緊張感はなくなり、好き勝手な政治をする。
バスチーユ広場に戻ろう。ディズニーランド労組の代表に聞いた。ちなみに、アメリカとは違ってディズニー・フランスは30年前から労働組合と協定を結び、活動に理解を示しているのだとか。
「私たちは働きたくないというわけではないんです。考え方、人生の設計の問題です。人生は労働だけではない。フランスでは憲法でも労働法でも、そういう哲学の下に作られています。人がどう生きるかが問題なのです。いま財源のことしか語らない。本質を語っていない」
日本で年金問題というと、もっぱらお金のことだけが語られる。しかし、まず問われるべきは「どう生きるか」なのではないか。そこから制度は構築されていくべきものなのではないか。
年金だけではない。いまやあらゆる分野で、金勘定と効率だけで議論がされている。
(月刊「紙の爆弾」2023年6月号より)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
●ISF主催トーク茶話会:川内博史さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
●ISF主催公開シンポジウム:「9.11事件」の検証〜隠された不都合な真実を問う
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内