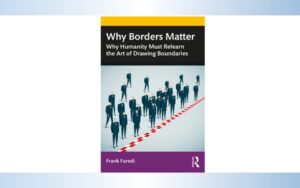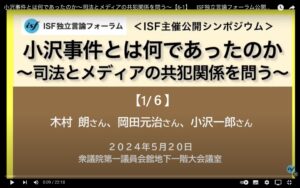第31回 母校の痛い失態で判った本田氏の信州大学異動の画策
メディア批評&事件検証大阪大学の若杉長英教授が類(たぐい)稀なる才能の持ち主と見てとった本田克也という若者の素晴らしさは、常に世界の動きにいち早く目を付け、果敢にその技術を取り入れていったことである。いわば興味と努力。そしてなんといっても鑑定の正確さだ。その何物でもない。
新しい職場の上司である若杉教授は、何をかいわんや、行動力のある法医学者で、その2年後には第3回目となる日独の国際学会の開催(2回目はドイツ開催)を控えていた。特にDNAの研究については「阪大でもDNA研究を立ち上げたい」という旗印で、本田助教授に全面的に協力してくれ、これまでゼロであった研究室を完全にセットアップしてくれたのだ。厳しい半面、「やりたいことは思いっきりやれ」と背中を押してくれる上司だった。
同大には共同研究施設があり、当時最先端の機器が設置され、本田助教授はそれを駆使して新たなDNA型鑑定の領域を切り開いた。それがドイツのフンボルト大学ベルリンのルッツ・ローワー氏を中心としたグループとともに開発した、Y染色体STRの研究である。

ベルリン歴史博物館を会場に「第1回法医学的Y染色体ワークショップ(Forensic Y User Workshop)」を主催したルッツ・ローワー氏(右から2人目)たち。1996年4月20日撮影

フンボルト大学ベルリン。同年4月19日撮影
ドイツのベルリンを中心に開催された「法医学的Y染色体ワークショップ(Forensic Y User Workshop)」には、日本でただ1人、本田助教授が1996年4月の初回から参加した。これは性犯罪の切り札ともなり得る技術であった。
しかも体得した技術で、裁判所嘱託の国内の難題な殺人事件の真犯人を突きとめるのだから、たまらない。特筆すべき成果の一つは、晴山事件だ。一般の人たちには馴染みのない事件かもしれないが、日本弁護士連合会(日弁連)では、知らない弁護士はいないというほど力を入れた北海道を舞台にした事件だった。
晴山事件は、1972年から74年にかけて、北海道空知郡月形町で3件の強姦殺人・強姦致傷事件が起きたというものである。1972年5月、月形町在住の19歳女性が帰宅途中に 行方不明となり、翌日に自宅付近で全裸死体で発見された。さらに3カ月後、砂川市在住の19歳女性も帰宅途中に行方不明となり、7日後に樺戸郡新十津川町の山林内において全裸死体で発見されたことから、同一犯の連続強姦殺人事件として捜査が進められていた。
2年後の74年5月に空知郡奈井江町で発生した別件の強姦致傷事件(被害者は死亡していない)の容疑で同月 26日に逮捕された晴山廣元氏(当時40歳)が上記2件の犯行を「自白」し、死刑判決が下されていた。晴山氏は無罪を主張していたが、新証拠がなく、再審請求の決め手を欠いていたのである。

晴山被告の死刑判決を報じる新聞
重機運転手の晴山被告は一審では、76年6月に無期懲役の判決だったが、被告、検察がともに控訴した。その控訴審では、原判決を破棄して死刑の判決。晴山被告は上告したが、90年10月に棄却され、死刑判決が最高裁で確定した。
それでも晴山死刑囚は92年9月に札幌高裁に再審請求し、3件全てについて冤罪を主張した。再審請求審では、それまで8回の三者協議が行われ、弁護側の補充意見書2通、検察官意見書2通(添付資料も含め)、その他証拠開示や事実の取り調べ(特に鑑定)、進行などに関する意見書を検事、弁護士の当事者が提出していた。
ところが、意外なところから突破口が開けた。1991年に北海道大学の法医学教室から東京大学法医学教授に異動となった高取健彦教授が、北海道大学に保管していた、晴山事件の被害者から採取した膣内容拭いガーゼ片の一部を東京大学に持ち出し「こんなものがあるから鑑定したらどうか。やるんだったら、うちの山田良広(現神奈川歯科大教授)にやらせたい」と裁判所に打診したのだ。最新のDNA鑑定を東大で成功させることで手柄を狙ったのだと思われる。
弁護団は「なんでそんなものがあるなら、これまで隠していたのだ」と怒り狂ったが、2件の被害者の膣内容物を拭い取ったガーゼ片が北海道大学と東京大学に保管されていることを知り、ただちにその保全を求めた。そのうえで当該ガーゼ片についてのDNA鑑定を請求していた。これに対して検察官は、試料の費消について危惧を述べるのみで、DNA鑑定自体について強いて反対する姿勢は示していなかった。
札幌高裁は、すぐにガーゼ片の保全に動いた。93年2月初めにガーゼ片の保管経緯について、被害者両名の司法解剖執刀医の石橋宏元旭川医大法医学教室教授と寺澤浩一北海道大法医学教室教授を証人尋問し、同月15日、北海道大学に保管されていたガーゼ片を領置し、同年7月5日には、東大に保管のガーゼ片も領置した。
再審請求としては、国内初の裁判所嘱託のDNA型鑑定で検察、弁護側の鑑定人による複数鑑定をする方向で検討されていた。そうはいっても実は、札幌の北海道合同法律事務所の笹森学弁護士は、疲れ果てていた。彼は自ら担当した、「晴山事件」の再審請求事件でDNA鑑定をやってくれる研究者を全国、地元の北海道から九州まで探し回っていたが、すべて断られていたからだ。
理由は、1981年6月の深夜に九州の大分市のアパートで18歳の女子短大生が殺害されているのが見つかった「大分みどり荘事件」にある。この事件では1991年10月31日の上記事件の第12回公判で日本で初めての裁判所の職権によるDNA鑑定が筑波大学で行われることが決まった。これは奇しくも、足利事件で菅家利和さんが捨てたゴミから精液が付着しているティッシュペーパーを取ってDNA鑑定を行い、逮捕される1ヶ月前のことである。
ところですでに第8回公判が行われた1991年5月23日には裁判長がDNA鑑定を打診したということがニュースとなり、毎日新聞朝刊の1面には、「DNAで犯罪捜査」の見出しで「警察庁が5月22日に、DNA鑑定について、鑑定方法などを統一したうえで制度として犯罪捜査に導入することを決めた。この鑑定制度の導入により、わずかな血痕、体液、皮膚片から個人の特定が可能となり、日本の犯罪捜査は指紋制度の発足(1911年)以来の大転換となる」とする記事が掲載されていた。おそらく大分みどり荘事件公判の進行をおそれた科警研は、足利事件でこれに先んじたいという覇権争いを仕掛けた可能性もある。
というのも、足利事件では当初、被害者の半袖下着などが遺体が見つかった翌日には渡良瀬川で押収された。栃木県警の科捜研が肌着から精子を確認。科警研に2度にわたり、DNA型鑑定を要請したにもかかわらず、無下に断られていた。ところが翌年91年8月、警察庁の国松孝次刑事局長の肝いりで92年度から4年間でDNA型鑑定を全国の県警に導入するために、DNA型鑑定機器を5都府県に配備する費用として旧大蔵省に初年度予算1億1600万円を概算要求した。獲得するためのアドバルーンを上げなければいけなかったのだ。栃木県警は当初、菅家さんではなくて別の男を犯人ではないかとして追いかけており、菅家さんの精液がついたティッシュペーパーを入手するや、DNA型官邸を渋っていた科警研が鑑定すると言い出し、鑑定して被害者の下着と菅家さんのDNAが一致として任意同行して逮捕した。そしてそれまで予算額をゼロ回答だった旧大蔵省が同年12月の復活折衝で満額回答をしたいきさつもある。
ちょっと脱線したが話をみどり荘事件に戻そう。この鑑定を受けたのは、当時、本人が立ち上げたばかりのDNA多型研究会(現日本DNA多型学会)運営委員長だった筑波大学の三澤章吾教授だった。三澤教授自身はDNA鑑定の経験はなかったから、同教授としてはこの鑑定は当時、大学院卒業後、研究生として大学に在籍していた本田医師にやってもらう予定でだった。というのは、三澤教授と原田勝二助教授はずっと犬猿の仲で、三澤教授が信頼して仕事を任せられる関係にはなかったからだ。しかも、原田助教授は医師ではなく研究者ではあっても鑑定の経験などまったくなかったし、法廷証言にも不慣れだった。
しかし、後進に手柄をとられたくない、と思った原田助教授は、当時仲が良かった信州大学の教授に就任したばかりの福島弘文氏と話をつけ、本田医師を、筑波大から追い出す画策をした。この話に三澤教授を見事に乗せ「本田君を研究生のままにしておくのは、彼の将来によくない。福島先生が大事にしてくれるというので、出した方が彼のためになる」と耳元で囁いたという。本田医師は泣く泣く、同年10月に筑波大を離れることになる。
もし、本田医師が筑波大に残ってこの鑑定をやっていたらどうなったか、まったく違っていたかもしれない。なぜなら試料は膣内溶液の混合試料からのSTR鑑定であり、これはその後、本田助教授が研究を進めていくテーマでもあったからである。
三澤教授からの大分みどり荘事件の鑑定書は、嘱託から2年後の93年8月12日に福岡高裁に提出された。ここで取られたDNA鑑定は、対象試料からACTP2 (ACTBP2)と呼ばれるSTRの部位をPCR法で増幅させるというものだった。科警研は足利事件ではNCT118というVNTRを鑑定に用いていたのに対して、これは、より短い断片を検出するため、高精度とされるSTRをDNA鑑定に用いた日本で初めての例だったのだった。
その結果、被害者の膣内容物が含まれたガーゼ片からは被害者と同一のDNA型しか検出されなかった。しかし事件現場から採取された毛髪のうちの1本からは被告人と同一のDNA型が検出されたという。したがって、鑑定書では被告人と証拠試料は一致という結果であったが、原田助教授は裁判所の尋問では、一致ではなく「類似性がある」という言葉で逃げた。その理由は、STR型の検出に用いた方法が、精度の悪い電気泳動法でしかなかったからである。科警研のMCT118と同様に、このSTRでも検出技術に問題があったのだ。
ただ科警研とは違って、原田助教授はこの方法の限界を認めた。その結果、95年6月30日、裁判は覆され、被告人に無罪判決が出された。この結果は法医学界に広まり、多くの大学の鑑定人に恐怖を与えたのである。というのは鑑定では「一致」として出されていたものが、裁判の証言で弁護団により完璧に覆されたからである。
この事件では鑑定方法の未熟さに加えて、鑑定書を書いたことのない原田助教授の経験のなさが災いした。しかも原田助教授は三澤教授と犬猿の仲なので、相談することなく独断で鑑定し、鑑定書を書き上げたことも大きい。結果として、弁護団は少なくとも50カ所を超える鑑定書の記載ミスに気づいてそこを証人尋問で追及した。
当時三澤教授は、1994年5月から法医学会理事長を勤めていたが、そのときのショックはなみなみならぬものであった。学会での会員や理事からの冷たい視線も相当なものであったが、実際に鑑定を行ったのは、仲が悪く三澤教授への貢献もほとんどしたことがなかった原田助教授である。当時すでに大阪大学に異動していた本田助教授はこう語った。「弟子である自分が助けられなかったことにも申し訳ない思いだった。自分の鑑定より、弟子の将来を優先する教育者としての人格性にも改めて感謝したことであった。一方、三澤教授は自分の名前で行った以上、すべての責任を自ら背負い、原田助教授の悪口は一言も言わなかったことに感銘を受けた。師のそのような姿を見て、表での法廷では真っ向に論争を挑んだ相手でも、その論敵を陰で悪口を言うことはしてはならないのが法医学者である、と肝に銘じたのである」と。

犯人として一審で無期懲役の判決を受けた、輿掛良一さんは95年6月の控訴審で、晴れて完全無罪判決が出された。捜査機関の暴走を監視する大学側の鑑定でも冤罪を作ってしまったのだ。それだけに影響は大きく、大学でのDNA鑑定は万事休すの状態に陥ったのだ。
この大分みどり荘事件で、大学でのDNA鑑定の信頼性が大きく損なわれ、我が国のDNA鑑定にとっては闇の時代を迎えつつあった。一方、足利事件では科警研が名乗りを上げ、DNA多型学会でも実際のDNA鑑定でも科警研が主導する流れが作られていく。そのため、どの大学も疑心暗鬼でDNA鑑定で叩かれることにすごく過敏になっていたのである。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
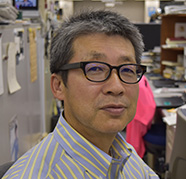 梶山天
梶山天
独立言論フォーラム(ISF)副編集長(国内問題担当)。1956年、長崎県五島市生まれ。1978年朝日新聞社入社。西部本社報道センター次長、鹿児島総局長、東京本社特別報道部長代理などを経て2021年に退職。鹿児島総局長時代の「鹿児島県警による03年県議選公職選挙法違反『でっちあげ事件』をめぐるスクープと一連のキャンペーン」で鹿児島総局が2007年11月に石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞などを受賞。著書に『「違法」捜査 志布志事件「でっちあげ」の真実』(角川学芸出版)などがある。