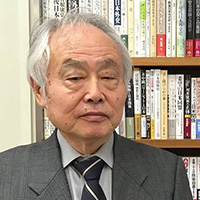ロシアによる核兵器使用はありうるのか:「カラガノフ論文」の重要性
核・原発問題長崎原爆投下の映像
(出所)https://www.bbc.com/japanese/video-53660360
ウクライナ戦争をめぐって、「ロシアによる核兵器使用はあるうるのか」と尋ねられることがある。これまでは、「よくわからない」と答えるようにしてきた。だが、ごく最近になって、残念ながら「ありうる」と答えなければならない状況に立ち至っている。
私は、2010年7月に『核なき世界論』を上梓したことがある。「本書は、核廃絶という夢を一途に追いかける「物語」である。最初から、夢と言わざるをえないところにひけ目を感じつつ、愚直にこの問題を探究してみたい」という文章からはじまっている。こんな経験をもつ私にとって、核兵器の使用をめぐる問題は「悪夢」としかいいようがない。しかし、そうした悪夢が「現実」になろうとしているいま、この問題から目を背けるわけにはゆかない。
カラガノフ氏の論文
2023年6月13日、「困難だが必要な決断:核兵器の使用は人類を地球規模の破局から救う可能性がある」という論説が公開された。著者は、ロシアで著名な外交・安全保障問題の専門家、セルゲイ・カラガノフ氏である。この挑発的なタイトルの論考はすぐに注目を集めている。そこで、彼の主張を紹介するところからはじめよう。
彼は、「高まる脅威」という話からスタートしている。それは、ウクライナ戦争を取り巻く「現実」を出発点とする、彼なりの率直な見通しに基づいている。すなわち、「ウクライナで部分的な勝利、あるいは圧勝を収めたとしても、西側諸国との衝突が終わらないことはますます明白になっている」というのだ。なぜかというと、最低限の勝利として、ドネツク、ルハンスク、ザポロジエ、へルソンの4地域を完全に解放しても、あるいは、現在のウクライナの東部と南部全体を1、2年以内にロシア側に解放するといった大成功を収めたとしても、ウクライナの一部には、さらに憤慨した超国家主義者が武器を満載した状態で残っており、その傷は出血し、合併症や戦争の再発を避けられない恐れがあるからだ、と彼はいう。「とんでもない犠牲を払ってウクライナ全土を解放しても、ほとんどが我々を憎む人々で、廃墟と化すのであれば、状況はもっと悪くなる可能性がある」と、彼は指摘する。拙著『復讐としてのウクライナ戦争』で指摘したように、「復讐が復讐を呼ぶ」事態のなかでは真の平和は訪れない。こうした見通しがロシアにとっての脅威となっているというわけだ。
カラガノフ氏は、ウクライナ全土の「解放」はウクライナの中部と西部の反発とゲリラ戦を招くだけで、「魅力的な選択肢」とはみていない。彼が描く「より魅力的な選択肢」は、東部と南部の解放と統一、そしてウクライナの残党に降伏を迫り、完全に非武装化することで、緩衝材となる友好国をつくることだという。もちろん、これは、ウクライナ政権を支持する欧米の意志を断ち切り、戦略的に撤退させることができた場合にのみ可能となる。しかし、こんなことは不可能だから、別の角度からの議論が必要となる。
西洋を憎む世界観
そこに登場するのは、西洋を憎む世界観だ。そこにあるのは、「西洋は、主に武力によって政治的、経済的秩序を押し付け、文化的支配を確立することによって、5世紀にわたって全世界から富を吸い上げてきた機会を失いつつある」という認識だ。この機会喪失に対して、西洋は防御的だが攻撃的な対立を展開しており、そう簡単に終止符は打たれそうもない。
カラガノフ氏にいわせると、雪崩のような下降を止めるために、欧米は一時的に糾合し、ロシアの手を縛ろうとしていることになる。米国にとっての理想を言えば、「米国は我が国を爆破して、新興の代替大国である中国を根本的に弱体化させたいだけなのだ」とのべている。
こうした世界的な状況が今後、「悪化の一途をたどる」と、カラガノフ氏は強調する。「休戦は可能だが、和解はできない」ときっぱりと指摘している。ゆえに、怒りと絶望は、波状攻撃と作戦で拡大しつづけ、西側の動きのベクトルは、「第三次世界大戦の勃発に向けた漂流を明確に示すものである」という。「それはすでにはじまっており、欧米の支配層の偶発的あるいは増大する無能と無責任によって、本格的な大火災に噴出する可能性がある」とまで書いている。加えて、人工知能(AI)の導入、戦争のロボット化は、意図しないエスカレーションの脅威を増大させるとまで記している。
核のエスカレーションに対する恐怖を回復せよ
カラガノフ氏は、「75年間の相対的な平和のなかで、人々は戦争の恐怖を忘れ、核兵器さえも恐れなくなった」と述懐する。核兵器への恐怖が過去4分の3世紀の動態的平和を可能としていたのに、その恐怖がいまや消え去り、ハルマゲドンが迫っているというのである。
ゆえに、「核のエスカレーションに対する恐怖を回復させなければならない。そうでなければ、人類は破滅する」と、カラガノフ氏は書く。
では、どうすればいいのか。
再び、カラガノフ氏の根拠があるとは思えない主張に耳をすませてみよう。彼はつぎのように書いている。
「我々はあと1年、2年、3年と戦争をつづけ、何千何万という優秀な兵士を犠牲にし、現在ウクライナと呼ばれている地に住む歴史的に追い詰められた悲劇的な住民を何万何十万と犠牲にすることができる。しかし、この軍事作戦は、欧米に戦略的後退、あるいは降伏を強いることなしに、決定的な勝利で終わることはできない。我々は、西洋に、歴史を巻き戻そうとする試みを放棄させ、世界支配の試みを放棄させ、自分自身と向き合い、現在の多層レベルの危機を消化させなければならない。ざっくり言うと、西側諸国がロシアと世界の行く末に干渉せず、ただ「失せろ」と言うことが必要なのである。」
これは、カラガノフ氏による欧米諸国への脅しである。「しかし、もし彼らが引き下がらなかったらどうだろう。彼らは完全に自己保存の感覚を失ってしまったのだろうか?それなら、感覚を失った人たちに正気を取り戻させるために、多くの国の標的を集団で攻撃しなければならない」とまで記している。この集団攻撃はロシアとベラルーシによる核攻撃を指しているのだろうか。
勝者は裁かれない
カラガノフ氏は率直につぎのように語っている。
「もしロシアが核兵器を使用したなら、中国はそれを非難するだろう。しかし、米国のイメージと地位に強力な打撃が与えられることを心のなかで喜ぶだろう。」
他方で、カラガノフ氏は、「インドや、核兵器保有国(パキスタン、イスラエル)を含む世界の多数派諸国にとって、核兵器の使用は道徳的にも地政学的にも容認できないものである」と指摘している。ただし、もし核兵器が使用され、「成功」すれば、核のタブー(核兵器は決して使用してはならず、その使用は核のハルマゲドンに直結するという考え方)は切り崩されることになるという。この核のタブーは米国が植えつけた神話にすぎないことがわかれば、別の反応が期待できるというのだ。略奪や大量虐殺を行い、異質な文化を押しつけたかつての抑圧者たる米国や欧州諸国の敗北に、「グローバルサウス」の多くの人々が満足感を覚えるかもしれないからだ。もちろん、ロシアへの支持をすぐに得られるはずもないが、「しかし、結局のところ、勝者は裁かれることはない」のであり、「救世主は感謝される」はずであると、カラガノフ氏は主張している。
もちろん、この救世主はロシアを意味している。そして、欧米の政治文化に侵されていない、世界の他の国々は、「我々が中国を残忍な日本の占領から解放し、植民地を植民地支配から脱却させたことを、感謝の念をもって記憶している」はずだから、核兵器を使用しても大きな戦争、すなわち第三次世界大戦は回避できるとみている。核兵器を使用してから数年後には、「中国が現在我々の後ろにいるように、中国の後ろに位置する」ことで米国との交戦を防ぐことができるとものべている。
独我論を糺す
紹介したカラガノフ氏は、「私」にあてはまることが万人にも妥当するとみなす「独我論」に陥っている。わずかな核使用が地球規模の核戦争の回避につながるという身勝手な考えが、地球上に住む人々に理解してもらえる正当性をもつと信じて疑わない姿勢は批判されるべきだろう。
ただ、カラガノフ氏の主張が今後、ロシアによる核使用を正当化するための論拠として利用される可能性はある。今後の戦争継続がロシア側に「何千何万という優秀な兵士」の犠牲をもたらすくらいなら、「核兵器を使ってウクライナを殲滅しろ」という論理がロシア国内に広がる恐れはある。それは、米軍が日本に2発の核兵器を使用した論理とよく似ている。米国が日本にしたことと同じことを、なぜロシアがウクライナにしてはならないのか。こうした疑問がロシア国内において大真面目に語られるようになるだろう。
思い出してほしいこと
私はいま、『新しい地政学の構築』(仮題)という本の執筆作業をしている。その過程で、The American Establishment, Leonard Silk & Mark Silk, Basic Books, Inc., 1980という本を読んだ。そこには、米国の支援を受けていた南ベトナムのゴ・ディン・ジエム大統領の話が出てくる。「1963年11月1日、ジエムと弟のゴ・ディン・ヌーは、サイゴンの路上で、アメリカ製のM-113装甲兵員輸送車のなかで南ベトナム軍将校に殺害された」と書かれている。ジエム政権は独裁的でインコ主義的な一族支配を特徴としていたが、米国政府は同政権を支援していた。結局、仏教旗の掲揚禁止に反抗したデモ隊を政府側が射殺した後、仏教徒の大規模な抗議行動が起き、米国によって訓練されていたベトナム共和国軍(ARVN)の将校によって処刑された。
何がいいたいかというと、いまはウクライナを軍事支援している米国だが、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領がいつまでも対ロ強硬路線を叫んでみても、いつはしごを外されてしまうかわからないということだ。
このように歴史をたどってみると、米国政府の支援がきわめて政治的であることに気づく。こうした過去の経緯を知れば、いつまでも戦争を継続するがいかに無意味であるかわかるだろう。
拙稿「ウクライナ戦争の即時停戦を求める声を知らしめよ」で書いたように、「即時停戦、前提条件なしの交渉」に向かわなければ、核兵器の使用という事態が迫りくるだけだろう。事態はどんどん悪い方向に向かっている。
いい加減にしろ、マスメディア
最後に、私がここで紹介したカラガノフ氏の論考を紹介するマスメディアは日本にはないと書いておきたい(2023年6月15日現在)。要するに、とても重要な情報について、日本国民に伝えようとしていないのである。こうして、日本でも、米国でも、欧州諸国でも、情報操作(マニピュレーション)がまかり通っている。
いま世界を支配しているのは、民主主義を支える情報自体が意図的に操作されているという「現実」だ。いわゆる「ディスインフォメーション」(意図的で不正確な情報)を民主主義国家自体が流し、国民を騙しているのである。
ごく最近わかったことだが、2023年6月13日付の「ニューヨークタイムズ」によれば、「ニュージーランドの公共ラジオ放送局は、ウェブサイトに転載したロイターとBBCによる20本近くの記事が不適切に編集され、その一部に親ロシア的な傾斜がつけられていたことを明らかにした」という。
具体的には、ウクライナの民主化運動であるマイダン革命を「クーデター」と呼んだり、ロシアの2014年の違法なクリミア併合を「住民投票の後に」行われたと表現したり、「ネオナチ」がウクライナのために戦っているという「誤った主張が含まれていた」と記事は書いている。この指摘はまったくおかしい。「ウクライナの民主化運動であるマイダン革命」は、2014年2月21日から22日にかけて、当時のウクライナ大統領ヴィクトル・ヤヌコヴィッチをロシアに追い出すという武力によるクーデターそのものであった。とても民主化運動などといえたものではない。クリミア併合は「住民投票の後に」実施されたことも事実である。ウクライナには、超過激なナショナリストがおり、彼らがウクライナ戦争の一翼を担ってきたことも事実である。
ところが、ニュージーランドの公共ラジオ放送局はこうした事実さえ「親ロシア的な傾斜」と断じていることになる。ニュージーランドがそうであるのなら、日本のNHKも同じだろう。しかし、これではウクライナ戦争の本質が隠蔽されてしまう。少なくともマスメディアが勝手な判断で別の主張を隠蔽してはならないはずだ。判断は視聴者に委ねればいい。
ところが、世界中の主要メディアは勝手に真っ当な情報を報道しないという偏向をつづけている。こんな世界に民主主義など存在するはずもない。ほとんど、北朝鮮と同じような情報操作が行われていると極言したくなるほどだ。
こうしたマスメディアの誤った報道姿勢が「核使用という悪夢」を現実のものに近づけていることに気づいてほしい。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)