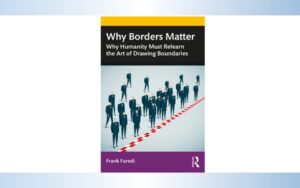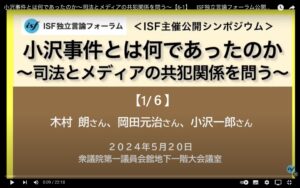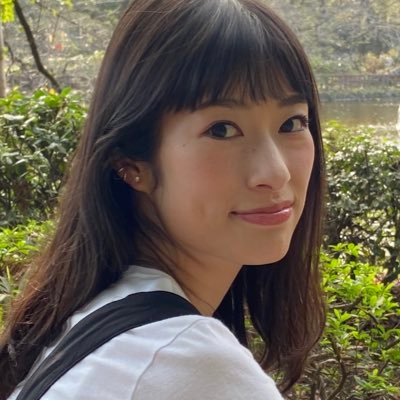2022年度平和大学講座「戦争を超え、和解へ――諸宗教は訴え行動する」/人類が生き残るために「敵を愛すること」は可能か?
国際はじめに
今年初めに原子力科学者会報で発表された終末時計は昨年から30秒進んで、人類の絶滅が1分30秒後となった。それは2022年2月から始まったロシアのウクライナ侵攻における核戦争のリスクの増加と、ロシアによるチェルノブイリ及びザポリージャ原子力発電所付近における戦闘により、放射性物質の広範な汚染のリスク増加が影響している。しかし、それだけでなく、世界の人口増加、資源の枯渇といった困難な問題を前にして、世界が混乱と衝突と戦争の時代を迎えてしまう可能性が色濃くなってきたからでもあろう。
倫理学者の加藤尚武は「殺し合いをする動物はヒトだけである」として、ウクライナ戦争に人類絶滅の予兆を見ている。加藤によれば、動物の戦いでは生きるための目的が果たされれば、戦いは終わる。動物が弱肉強食だという偏見が動物行動学によって否定された現在、「どうしてヒトだけが殺し合いをするのか」と質問をしながら、「非人間的行為が人間の本性の発露であるという思想は生き残っている」として、近現代の国家による大量殺戮の歴史を検討している。
このような地球規模の深刻な問題を前にして、持続可能な平和な世界を残すために、歴史を生き延びてきた宗教が背負う役割は決して小さくはない。とくに、同じ神を奉じる「アブラハムの宗教」、つまりユダヤ教、キリスト教、イスラームの信者数は世界人口のほぼ六割を占めるが、これらの宗教が過去から現在にいたるまでの相克と対立を乗り超えて、まずこの21世紀を血と涙の世紀としないために、手を携えて「平和を作り出す」ことが切実に求められている。そのために、これらの宗教の教えと歴史を振り返って、どのように諸宗教が永続的な平和を作り上げることに貢献できるかを考える必要がある。
1、平和を作り出す共同体

世界宗教と呼ばれる仏教やキリスト教には、それぞれの基本的な教義として、人間精神の平安、つまり「魂の救済」が掲げられている。仏教においては、それは現世的な事物に執着しない「無」や「空」の教えであり、キリスト教では「汝の敵を愛せよ」という究極の隣人愛として教えられる。「無」や「空」の思想も「隣人愛」の教えも、現実の人間社会で実現することは不可能な教えであり、まさに究極の「宗教的理想」である。しかし、宗教においては、理想が高尚であればあるほど、その宗教がこの世に「平和」を導くものとして評価される。
これらの宗教が理想としてもつ正義や愛の教義は、たんに暴力を排除したり避けたりするだけでなく、むしろ積極的に「平和を作り出す」ことの必要性を教えている。ユダヤ教、キリスト教、イスラームのセム的三宗教のなかで代表的な教えは、イエスの「山上の垂訓」であろう。マタイによる福音書五章九節(聖書協会共同訳『聖書』)には「平和を造る人々は、幸いである。その人たちは神の子供と呼ばれる」とある。「山上の垂訓」はさらに以下のような究極の愛を教えている。
あなたがたも聞いているとおり、『目には目を、歯には歯を』と言われている。しかし、わたしは言っておく。悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい。(マタイ、5章38~39節)
あなたがたも聞いているとおり、『隣人を愛し、敵を憎め』と言われている。しかし、わたしは言っておく。敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。(マタイ、5章43~44節)
「目には目を、歯には歯を」という報復罰はメソポタミア一帯に伝統的に存在した戒律であり、ユダヤ教もイスラームもこれを継承している。報復罰は一般には野蛮な罰則規定であると受け取られることもあるが、「目をやられたら、報復は目だけにしなさい」という制限をかけた規定であり、報復行為がそれ以上に拡大しないことを意図していた。この戒律を遵守することは神の意志に従うことであり、それによって社会の平安が保たれる方途でもあるが、イエスはこれらの規範をあえて破るような説教をすることによって、無償の愛に基づく「隣人愛」の本質を教えようとしたのである。
これに対してイスラームでは、「神を恐れる」という意味の「タクワー」の精神が隣人愛の思想と対比される。タクワーとは神に対する恐れを表すが、自らを低くして絶対的な神に全身全霊で従うことを意味している。神の前で徹底して謙虚になれる人は、他人に対しても優しくなることができる。そういう意味では「タクワー」はキリスト教の「隣人愛」にも通じる教えである。
しかし世界史をみれば、究極の隣人愛を掲げるキリスト教も、また思想的には現実の歴史社会から一線を画してきた仏教においても、まったく政治的社会的側面にかかわらないでくることはできなかった。霊肉二元論の立場から精神世界を社会的世界より上位に据えたはずのキリスト教においては、皮肉なことに、事態はいっそう「政治的」である。西暦392年にキリスト教がローマ帝国の国教として採用されてからは、歴史社会の中心として「教会」があらゆる過酷な営為に参加してきたということは、西洋史を紐解けばすぐに明らかになる。
一方、三大世界宗教のひとつであるイスラームの教義では、現実社会の執着から逃れてひとり魂の救済を求めるような思想も、敵でさえも愛せよという、実現不可能な究極の愛の精神をも、教えられはしなかった。むしろ、現実社会のただ中にあって日常生活を営み、政治参加をすることにおいて、神を恐れ神に従うことが求められた。イスラームでは、信者が過酷な歴史社会に直面しながら生きることそのものが、宗教的な修行であり「ジハード」(正戦)でもあった[1]。
この点ではイスラームはユダヤ教と似ている。現在では、ユダヤ教徒がそのまま生物学的に「イスラエルびと」、つまりユダヤ人であるということはいえないものの、宗教学的にはユダヤ教は「民族宗教」のひとつとして分類される。倫理規定を含むさまざまな契約を結ぶ相手として、イスラエルの神によって選ばれたイスラエル民族が、約束の聖地イスラエルを求めて民族の興亡史に深くかかわることが宗教の根幹であるために、ユダヤ教もまた過酷な歴史社会と直面してきた。
そういう意味では、ユダヤ教の「イスラエル」に象徴される選民思想は、イスラームではあらゆる人間に要求される普遍的な選民思想に置き換えられる。神の唯一性とムハンマドの預言者性を認める人間は、国籍、人種、社会階層などを問われず、イスラームの「選民」を形成する。イスラームではこれを信者の共同体「ウンマ」[2]と呼ぶのである。
イスラームにおける魂の救済は「ウンマ」に所属することによって実現される。人間はウンマの成員となり、歴史社会をウンマと共に生き抜くことによって、来世で楽園に入ることができる。社会から脱出することによってでもなく、実現不可能な高度な理想に殉じることによってでもなく、現実社会のなかで神の指針に従って人間としての自然な生を生きることこそが、イスラームの教えの根幹なのである。
ユダヤ教の「イスラエル」、キリスト教の「教会」、イスラームの「ウンマ」は、いずれもそれぞれの信徒の意識が収斂していく宗教の中心点でもある。これらの中心点の役割こそが、宗教史の要点でもあり、将来へむけて平和を作り出す責任ある母体ともなる。したがって、これら母体が協働することができるなら、持続可能な世界を維持していくための宗教の役目を果たすことができるかもしれない。
2、「暴力」とは何か?
過去の人類の歴史を振り返ってみれば、気候変動による地域環境の悪化と自然資源の枯渇が険悪な政治・経済的問題をもたらすとすれば、人類社会が諸問題の解決方法として暴力に頼ってしまう可能性は否定出来ない[3]。それゆえあらためて暴力とはなにか、ということについて考えておく必要がある。
私たちは安易に「暴力には反対だ」などというが、しかし、「暴力」と「非暴力」をわけるものはなにかという問いは、じつはきわめて難しい問いである。たとえば、一定の条件下では暴力は、その暴力を超える利益があり、その利益が必然的であるとみなされる場合には、必要悪と認められることがある。たとえば歴史を通じて、国家間の戦争は、人間が行なう暴力のうちでは最大の暴力であり破壊行動であるが、これは「暴力」とはいわれない。現代でも、中小の戦闘的集団がテロ活動を行なって数人から数千人の市民を殺すことは許しがたい「暴力」であると考えられるが、国家の正規軍による軍事作戦によって数万人もの人々が犠牲になることは「暴力」とはいわれない。
「国家」は国民から支持されている公権力であるという正当性を主張しているからであり、そのために一般に戦争は「暴力行為」とはいわれない。しかし、市民の集団が公権力に対抗することは、市民の側では「非暴力」の抵抗運動であるとしても、公権力の側からは許されざる「暴力」である。視点を変えれば、発展途上国などで貧困と政治的混乱のために数百万人の幼児が適切な治療を受けることができず、一歳の誕生日さえ迎えられないということも、じつは「暴力」のひとつであるが、これついては直接の加害者が特定できないこともあって、誰も「暴力」だとは思わない傾向がある。
このようにみていくと、「暴力」とはなにか、という問いについて、私たちは二つの次元をわけて考えることができる。ひとつは一般的に「暴力」と呼ばれる行為であり、「被害者の意志に反して、明らかな意図をもって、被害者の身体に傷害を加えたり破壊したり、その所有物に被害を与えたりする」ことで、いわば直接的な破壊行為である。いまひとつは、「困っている人を意図的に放置し、あるいは無視し、その結果、重大な障害や死がもたらされることになる」というもので、こちらは間接的な破壊行為である。
一般的には前者が「暴力」と呼ばれているが、後者もれっきとした「暴力」である。後者は被害者の人権や尊厳を無視し踏みにじるという行為であり、貧困、人種差別、性差別、出自差別、言論弾圧、思想信条の差別、などが含まれるであろう。このような考えから、学者のなかには「暴力とは、組織的であれ、形態的であれ、個人的であれ、直接的であれ、間接的であれ、被害者の同意を超える圧倒的な力という手段を用いて被害者に与える破壊行動のことである」と定義するものもある[4]。
地球環境問題が人類史的な課題となりつつある時、サステナビリティに関わって暴力の意味について問いなおすなら、国家の戦争だから許容されるという暴力観、直接的行為だけを暴力とみなす暴力観などは、とくに、地球環境に対する暴力という側面も含めて、大きく考え直されなくてはならなくなっている。
それでは、宗教との関係はどうであろうか。
3、宗教と暴力

宗教的大義名分を背景にした「暴力」は、その宗教共同体の正義・平和・福利を目的にして行なわれる修行としての聖なる戦いであり、一般には、たんなる「暴力」とは区別して考えられている。
世界のどの宗教も、長い歴史のなかで、一切の暴力とかかわらないできたものはない。たとえ物理的な暴力を行使しなかったとしても、精神的、心理的な暴力にまで範囲を広げるなら、暴力批判から逃れられる宗教などない。しかし、宗教は本来、人々に平和を説き、さまざまな欲望の束縛からの解放方法を教え、与えられた命を穏やかに生きるように諭すものではなかったのか。仏教の「無」や「空」の教えも、キリスト教の「隣人愛」も、イスラームやユダヤ教の「戒律」も、苦しい現実の生を生きる人々に与えられる「魂の救済装置」ではなかったのか。選民思想を基盤とするモーセの十戒でも「人を殺してはならない」と記してある。イスラームの聖典クルアーンでも、人の命の大切さについて、以下のように教えている。
・・・人を殺した者、地上で悪を働いたという理由もなく人を殺す者は、全人類を殺したのと同じである。人の生命を救う者は、全人類の生命を救ったのと同じである(と定めた)。そしてわが使徒たちは、かれらに明証を齎した。だが、なおかれらの多くは、その後も地上において、非道な行ないをしている。(クルアーン五章三二節)
この「人」とはいったい誰を指すのだろう。ユダヤ教では神に選ばれたイスラエルの民だけを指すのかもしれない。実際にユダヤ教の祈祷文には「神よ、イスラエルにだけ平和を与えたまえ」といった内容のものもある。イエスもユダヤ人として生まれユダヤ人として生きた人である。イエスのいう「人の命」はユダヤ人だけを、あるいはイエス後に発展した異邦人伝道を予期して「イエスを信じる人々」だけを意図しているのであろうか。そうであれば、宗教にはそれぞれの宗教の囲い込みが成立しており、その枠外にいる人は「ヒト」として扱われないということになる。枠外にいる人々として、まず思い浮かぶのは異端や魔女、悪魔つきとして排除されてきた人々のことであり、他の宗教を報じる異教徒たちのことである。ひとつの宗教だけを絶対の真理として扱い、他の宗教思想を異教や邪教として退ける立場からみれば、「ヒト」とは同じ宗教の信者でしかありえない。
初代のキリスト教徒たちは、イエスは、自分の命を犠牲にして、人類を罪から救うために身代わりとなって十字架刑で死亡したと考えた。イエスの死と復活を「贖罪の死」として、罪からの解放であると定義したのである。このようなイエスの思想を最もよく表す章句は前述のマタイによる福音書の「山上の垂訓」である。
「目には目を、歯には歯を」という報復罰はメソポタミア一帯に伝統的に存在した戒律であり、この戒律を遵守することは神の意志に従うことでもあった。イエスはこれらの規範をあえて破るような説教をすることによって、無償の愛に基づく「隣人愛」の本質を教えようとした。しかし、教会は「あなたの敵を愛しなさい」は現実には実行不可能な理想であり、その代わりに「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」(マタイ、7・12)のほうを黄金律として人々を導いたのである。
4,聖戦思想の確立
「あなたの敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい」という究極の愛の理想を教えたキリスト教は、まさに究極の平和を教える宗教であるが、前に触れたように、そのキリスト教が歩んできた歴史はけっして平和的とはいえない。土井健司は、「キリスト教とキリスト教を信じる者とは必ずしも一致しません。キリスト教の中にはさまざまな考え方があるのです。しかし、いかなる理由からでも積極的に戦争、紛争、暴力を行うことはキリスト教的ではありません」[5]として、キリスト教とキリスト教徒を分けて考えるように勧めている。この考えにはたしかに説得力があるが、しかし、キリスト教徒がいなければキリスト教は存在しないということを考えるなら、崇高な宗教的理想と不遜な信者の行為とは完全には切り離して議論することができないように思われる。この考えはどの宗教にも当てはまる。
ある宗教が歴史のなかで生き残っていくためには、その宗教を信じる複数の人間がいて、社会と密接な関係をもっていなければならない。そういう意味では、宗教はいまでも社会の統合理念として潜在的な力を有している。そのために宗教と暴力の結びつきは、たとえ出家主義の宗教であっても、どのような宗教にも見られる現象である。「魂の救済装置」という役割を果たすはずの世界宗教が、歴史上、安易に暴力や戦争とかかわってきた理由として考えられることは、いかに精神主義を掲げる宗教であっても、宗教そのものが原理としてもっている「社会性」という性質が暴力や戦争に深くかかわっているからである。私たちは、このような宗教がもつ危険性についても、あらかじめ考えておく必要があろう。
このことは今般のロシアによるウクライナへの侵攻にも当てはまる図式である。ロシアもウクライナもオーソドックス(正教会)が主流の国であり、正教会同士の覇権争いが政治に深くかかわってくる地域でもある。正教会は、一つの国に一つの教会組織をおくことを原則として、それぞれの地域の政権と密着した独自の儀礼を維持している。特に近年、ロシア正教会の政治的志向が注目されていた。
近年では、イスラームが暴力や戦争と結びつけて語られやすいが、問題は宗教と社会との関係性にある。当初から社会性を意図して展開してきたイスラームでは、イスラームとイスラーム教徒ムスリムを分けて考えることは、なおさら難しい。
イスラームの好戦性をあげつらう際によく使われる「ジハード」[6]は「奮闘努力」と訳される言葉で、本来は信仰上の努力をさす用語であり、対外的な戦闘を意味する場合でも、極めて厳しい制約をもった防衛戦争を指すものであった。しかし、どの時代にあっても、どのような形のジハードであっても、ジハードを掲げる集団にとっては、当然のことながら、彼らのジハードは「真正な」ジハードだと主張される。
さらに悪いことに、原則として教団組織や本山制度をもたないイスラームでは、戦闘的なジハードを「異端的」と決めつけ禁止するだけの政治力をもつ機関は、どこにも存在しない。新しい案件は、イスラーム共同体ウンマ全体が一致して賛成することによって「正統的」となる、というイスラーム共同体の「イジュマー(全員一致)」の原理を持ち出すなら、現在のテロリスト集団の掲げるジハードは正統的なジハードではない。しかし、ウンマの見解の一致を確認することは、イスラームがまだ小さな集団であった時代でも困難なことであったが、ムスリムの人口が世界中で16億から20億人といわれる今日では、まったく不可能なことである。特に1948年以降、イスラエル建国をめぐってパレスチナ問題が発生すると、イスラーム教徒の側からの深刻な抵抗運動が起こることになった。
歴史的にも現代まで、現実にはウンマの見解の一致は、イスラーム法学者の見解の一致をもって代用されてきたが、それもイスラーム世界全体に普及し受け入れられるようになるまでには長い時間がかかる。今日のようにグローバル化が進展した時代ではインターネットなどの通信手段を駆使して、世界中の情報が一挙に入手できるが、逆に情報が多すぎると真偽の判定が難しくなり、法学者間の速やかな見解の一致が妨げられているようにもみえる。
今日のアメリカの国際政策の背景にはキリスト教保守派の見解が大きな影響を与えているということは、周知の事実である。あの9・11の衝撃的なテロ事件の直後に、当時のブッシュ大統領はおもわず「十字軍」という言葉を口にしたが、これは一時の興奮状態による「失言」では決してない。イスラーム教徒から聖地エルサレムを奪還するという聖戦思想を掲げた十字軍運動は、1095年以降、さまざまにかたちを変えながら、じつに200年間も続いたのである。西暦2000年に前ローマ教皇ヨハネ・パウロ二世が過去の十字軍の攻撃について、イスラーム側に対して正式に謝罪をしたにもかかわらず、十字軍運動は現在にいたるまで、キリスト教徒、ムスリムの双方の深層心理に深い陰を落としている。
キリスト教では、イエスやパウロの死後ほどなくして、徹底して非暴力を説き「あなたの敵を愛し、敵のために祈りなさい」とまで教えたイエス・キリストの説教は省みられなくなり、「神が望めば」神の名による戦争が正当化されるという「正戦思想」が浮上してきた。しかし、この思想はもともとユダヤ教から受け継いだ「聖戦思想」を展開したものであり、ヘブライ語(旧約)聖書の思想でもあった[7]。キリスト教もまた、イエスが命をかけて排除した伝統的な「イスラエル」の聖戦を再現させ、公式教理のなかに植えつけてしまったのである。
5、命の価値の差異
現代の私たちがかかえるもうひとつの大きな問題は、宗教によって異なる「命の価値」の差である。歴史的にみると、イスラームだけでなく、キリスト教、ヒンドゥー教、仏教にも暴力の影が染みついている。中世から近代に目を向けると、キリスト教徒による反ユダヤ主義という凄まじい暴力が絶え間なくユダヤ教徒に向けられていた。この傾向はいまでもさまざまに形を変えて生き残っている。しかし、20世紀の後半以降、暴力の犠牲になるのは、圧倒的にムスリムがおおい。パレスチナ、アフガニスタン、シリア、イラク、イランなどで、毎日のように多くのムスリムが殺されている。俯瞰的に世界の紛争を眺めてみると、一般のムスリムは前述のパレスチナ問題が深刻化する中で、紛争や混乱の当事者というよりむしろ被害者となっている。
世界ではパレスチナ紛争のほかにも、10年以上も続いているシリア、リビア、イエメンの内戦、イラク戦争、アフガニスタン問題などの影に隠れているが、スペインのバスク独立紛争、北アイルランド闘争、南部アフリカの部族間闘争、中南米の麻薬密売や反政府テロ活動、インドやスリランカでの宗教対立など、キリスト教徒、ヒンドゥー教徒、仏教徒などがたがいにいがみあっている。しかし、ムスリムによる暴力はことさら大きく報道される傾向にあり、いかに数多くの市民が犠牲になろうとも、彼らの死は悼まれることが少ない。この世界で、悼まれる死と悼まれない死が存在することは、言い換えると人間の命の価値に厳然とした差異が存在することは、宗教と暴力の連鎖を断ち切ることを困難にする大きな要因のひとつである。
残念なことに、このような、意識的に遠い他者の苦痛や死の意義を認めないような立場は、他者の痛みに共感しない立場であり、これからも頑固な習慣として残っていくかもしれない。しかし、私たちが地球市民として全地球的な次元で永続的な平和構築を目指すためには、このような独善的な偏見にもとづいた差異を解消することが必要となってくる。
6、宗教的理想をもう一度
加藤尚武は、未来には平和と基本的人権が護られる世界が実現するだろうかという問いには、「人間の本性は変わらないからそれは実現しないという答えをだれもが知っている」として「地球に住むすべての個人が、生存と自由の権利が保障される日までは、人間性という観念は有効なのである」と結論づける。
それでは「人間性」とは何を意味するのか?加藤は「非人間的行為が人間の本性の発露であるという思想は生き残っている」として、近現代の国家による大量殺戮を解説する。そこから考えると、「人間性」とは加藤の言うように「殺し合いをする動物はヒトだけである」という本性であるから、その人間性が克服される日は、「戦争のない世界が、どうしたらできるか。悲願とか、理想とかを語らないで、現実的な生活者の言葉で、戦争のない世界への道を示さなくてはならない」という。
ここで象徴的な言葉は「現実的な生活者の言葉」であるが、これはいったいなにを意味するのだろう?歴史を概観すると、確かに非人間的な殺戮は大きな野心を持った権力者によって引き起こされることがおおい。この度のウクライナ攻撃も異常な野心を持った権力者によって引き起こされている。だからこそ、征服欲に満ちた権力者ではなく、「現実的な生活者の言葉」によって、戦争のない世界ができるかもしれない、ということなのか。そう考えると、イエスが「敵を愛しなさい」といった意味が理解できるように思えてくる。
宗教的な視点から考えると、暴力や殺戮は、神の意志では決してないという冷静な判断をする人々は、どの時代にもいるであろう。それらの「現実的な生活者」が多数派であり、しかも豊かな知識と宗教的信念をもって、巨大な権力に非暴力の抵抗をすることができるなら、過激な聖戦思想も巨大な国家権力による国家テロをも排除する力になることができるかもしれない。
ここでわたしたちは宗教がもつ本来の役割をもう一度思い出してみることが必要である。「魂の救済装置」として出発した宗教は、どの宗教も非暴力を説いている。「あなたの敵を愛しなさい」というイエスの言葉は現実には実行不可能な理想であるが、「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい(マタイ、7章12節)」という教えなら、誰でも実行することができよう。「敵を愛する」ではなく、こちらのほうを「黄金律」として尊重したのも人間にとって実行可能な自然な教えであったということができるかもしれない。
イエスの山上の垂訓は「あなたがたも聞いているとおり」という言い出しでヘブライ語聖書の律法、つまりユダヤ教の戒律と対比しながら、あまりにも理想的で現実には実行が不可能な厳しい道徳率を説いている。究極の隣人愛である「敵を愛しなさい」という教えとともに、イエスがなぜ、人間には実行不可能な教えを命じたのであろうか。
八木誠一によると、「神の支配」のもとでは、人間の行為は定められた律法によって決定されるのではなく、「神の支配」によって決定されるのであり、人間の側の意図的な判断を超えていることになるという[8]。「敵を愛しなさい」というイエスの教えは、実際には実行不可能な究極の愛を命じることによって、人間の能力や「意図的な判断」を超えた絶対的な神の計画やその崇高な命令を、逆説的に私たちに教え示しているのであろうか。それにしても「敵を愛する」ことは、私たちにとって、何よりも難しいことかもしれない。
そこで私たちにできることは、キリスト教にみられる「隣人愛」や「黄金律」の教え、ユダヤ教の「十戒」、イスラームの日常生活上の道徳規範(シャリーア)と「タクワー」の精神、あるいは仏教の「慈悲」の精神など、これらの意義をもう一度、その根源に立ち返って考えることではないだろうか。
翻って現実をみつめてみれば、20世紀の後半から各地で台頭してきた宗教復興運動の隆盛は、近代政治体制を導いた政教分離政策がますます形骸化していることを示している。そこでは、政教分離政策は現代政治にとって最善策であったのかという疑問が湧いてくる。現実に宗教思想の影響を完全に排除した政権など、世界のどこにもないからである。
前近代のヨーロッパのような、政治権力に教会権力、あるいは宗教的権威が結託することは、今日では避けなければならない。そういう古典的な意味での政教一致には、もはや意味がないであろう。しかしそのいっぽうで、いまや宗教本来の精神や理想を政治や社会に応用するという、新しい発想の宗教観を考えるときにきているのではないかと思われる。
たとえばモーセの十戒に従って紛争による殺戮を回避し、イエスの「隣人愛」の精神に従って国際政治や地球環境を考え、あるいはイスラームの「タクワー」の精神にたちかえって謙虚に平和構築を進め、将来の人類の平和的な生存を考えるなら、宗教の理想が永続的な地球環境を維持していくための重要な役割を果たすことができるであろう。このような考えについては、複雑な国際政治や環境問題を考えるうえで、宗教的理想などなんの意味もない、むしろ子供だましにしかすぎないという反論が返ってくるかもしれない。
しかし、インドの独立の父、マハトマ・ガンジーやアメリカのM.L.キング牧師の「非暴力的抵抗運動」が現代の私たちにも感動と勇気をあたえ続けている現実を考えるなら、「宗教的理想」にも国際政治や経済を動かすだけの力があることを認めざるをえないであろう。
こんにちの宗教的暴力は、たんに宗教的要因だけで起きているのではないが、その背後には、相互の無理解が横たわっていることも憂慮すべき点である。宗教と平和を考えるために必要なことは、宗教間・文明間対話を実行し続けることである。国際政治や環境問題においても多宗教間でたがいに理解しあい協働することが、いまほど求められているときはない。
持続可能な平和な世界と自然環境を地球上の子孫たちに残すために、国際政治や環境問題の解決にあたって、歴史を生き延びてきた宗教が背負う役割と責任は、こんにち、ますます大きくなっている。科学万能の時代に暮らす私たち人間の側も、人智を超えた神・仏の教えに、謙虚に耳を傾けることが大切になってくる。とくに同じ一つの神を奉じる三つの宗教、ユダヤ教、キリスト教、イスラームは、「アブラハムの宗教」という共通性を掲げて、暴力を放棄し平和を作り出すために協働することが、いま、このときにあって、緊急の課題である。たがいに正統性を主張していがみあって地球環境を破壊し、命の差異をことさらに強調して他者を排除するような時間は、わたしたち人間に、もはや残されてはいないのである。
現下のロシアによるウクライナ侵攻は、この侵攻をロシアに正義がある聖戦とみなして、プーチンを援護するロシア正教会のキリル総主教の責任も大きい。ロシアはウクライナに敗北すれば核戦争に持ち込むと公言していると聞く。核戦争になれば、世界中の人々が平和裏に生存することができなくなる可能性が大きい。ウクライナの人々だけでなく、この地球上のすべての人々を護るために、高位の宗教指導者として、本来ならイエスに従っているはずのキリル総主教にこそ、勇気ある翻意を期待するものである。
八木誠一は「敵を愛し、迫害する者のために祈れ」とは、「相手が誰であろうと――悪人であろうと、何をしようと、基本的に隣人として受容し、共生を肯定するのが当然かつ自然なのである」という。私たちにはイエスの言葉を実行することは不可能に近いが、この言葉の重みを、覚悟をもって学ぶことが、今現在、私たちに残された唯一の解決策なのかもしれない。
主な参考文献
アームストロング、カレン『聖戦の歴史』(塩尻和子・池田美佐子訳)柏書房、2001年
石川明人『キリスト教と戦争』中公新書,2016年
市川 裕『ユダヤ教の歴史』山川出版社、2009年
エスポズィート、ジョン『グローバルテロリズムとイスラーム』(塩尻和子・杉山香織監訳)明石書店、2004年
加藤尚武「ヒトは人間性を守ることができるか」
『生存科学』Vol. 33-1、2022年9月、3-21頁
黒川知文『ロシア・キリスト教史 土着と服従と復活』教文館、1999年
小杉 泰『興亡の世界史06、イスラーム帝国のジハード』講談社、2006年
小原克博、中田考、手島勲矢『原理主義から世界の動きが見える』PHP選書、2006年
塩尻和子『イスラームを学ぼう―実りある宗教間対話のために―』
秋山書店、257頁、2007年
塩尻和子『イスラームの人間観・世界観』筑波大学出版会、2008年
塩尻和子「ジハードとは何か――クルアーンの教義と過激派組織の論理」、
『変革期イスラーム社会の宗教と紛争』明石書店、分担37-61頁、2016年
聖心女子大学キリスト教文化研究所編『共生と平和への道』春秋社、2005年
土井健司『キリスト教を問いなおす』ちくま新書、2003年
八木誠一『新約聖書の構造』岩波書店、2002年
註
[1] イスラームとジハードなどの関連性に関する解説は拙著「ジハードとは何か―クルアーンの教義と過激派組織の論理」『変革期イスラーム社会の宗教と紛争』、37-61頁、『聖戦の歴史』14-16、96頁にもユダヤ教、キリスト教との関係と対比が説明されている。
[2] 「ウンマ」は言語的には「民族」であるが、血縁的な部族ではなく、いわゆる民族の枠を超えた、神の啓示を受け入れる救済史のなかの信徒集団であると考えられる。それぞれのウンマに預言者が遣わされるとされ、それがモーセのウンマ、イエスのウンマ、ムハンマドのウンマなどである。ムハンマドのウンマは最後の最大のウンマと考えられ、神の規範が実現する場であると考えられ、イスラームのウンマと呼ばれるようになった。
[3] ノーマン・マイヤーズ、ジェニファー・ケント監修、田近英一、『六五億人の地球環境』、Dojin 選書、2009年、「戦争の危機」、270-281頁。ここでは明確に人類社会が戦争への道を進む可能性が論じられている。
[4] Glen H. Stassen and Michael L. Westmoreland-White, “Defining Violence and Nonviolence” In J. Denny Weaver and Gerald Biesecker-Mast, eds., Teaching Peace: Nonviolence and the Liberal Arts (New York: Rowman and Littlefield, 2003), p. 21.
[5] 土井健司、『キリスト教を問いなおす』、筑摩書房、2003年、56頁。
[6] ジハードは、原則論としては、ムスリムに許された唯一の戦争というかたちをもつ。しかし、この「戦い」は目的ではなく、手段として許可されたものであり、イスラーム史上、当初から定義づけが難しいものであった。義務としてのジハードには、宗教的修行的なものと、連帯義務と個別義務を含む集団的なものに分けられる。しかし、防衛戦争への参加は個人的義務という考えもあり、法学派によって判断が分かれる。中田考「イスラームにおける寛容」(『宗教と寛容』竹内整一、月本昭男編、大明堂、一九九三年)213-214頁。
[7] ヘブライ語(旧約)聖書にはイスラエルの民が異邦人と戦う多くの戦闘場面が語られており、イスラームのクルアーンにも異教徒や背教者を追放し殺してしまえと命じる章句もみられる。しかし、聖典の文言だけを取り上げて、それがただちに暴力の容認につながるとみなすことは意味がない。聖典の記述はしばしば比喩的に用いられており、暴力表現でさえも、神の力を誇示し精神的な修行を勧めるための一種のレトリックであると解釈することができるからである。
[8] 八木によれば「神の支配のもとに生きる人間には(つまり自己レベルでは)、相手が誰であろうと――悪人であろうと、何をしようと――相手も神のもとにある人格なのだから、基本的に隣人として受容し、共生を肯定するのが当然かつ自然なのである。そのうえで相手に対して何をするかは創造的自由の事柄であって、あらかじめ規定できることではない。イエスはその一例を示している。」八木誠一『新約思想の構造』125頁。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内