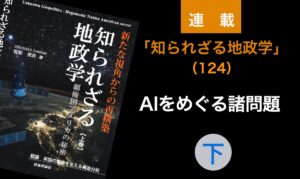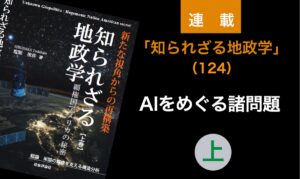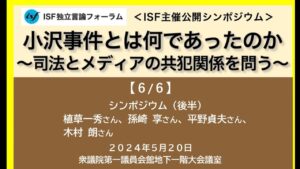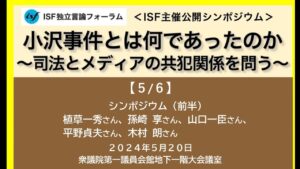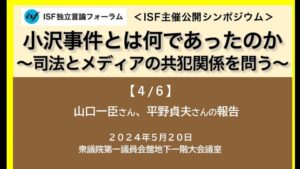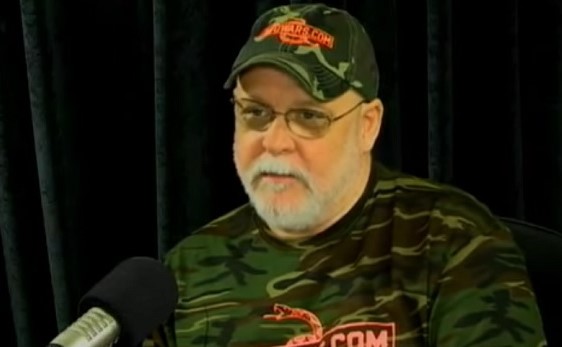書評:倫理学からのコロナワクチン後遺症への詳細で説得的な考察 ――國部克彦『ワクチンの境界 権力と倫理の力学』アメージング出版、2022年
映画・書籍の紹介・批評
コロナ、ワクチン後遺症などの問題への哲学・倫理学からの反応・応答はいまだ少ない。医療倫理、生命倫理という分野もあるが、著者國部氏のような先鋭な問題意識のものは寡聞にして知らない。タイトル名は、ワクチンの接種者と非接種者の間で生じた分断という意味で命名されたが*、同時に広く、コロナワクチンにたいする肯定派と批判派との分断状況も意味するだろう。まさに国民の間で、いろいろな場面で、この問題をめぐって深い亀裂および対立が生じている**。
*本書、17頁参照。以下本文中に、適宜頁数を挿入する。
**この書評で断定されるように見られる評者の主張の根拠として、拙論「コロナ禍からワクチン後遺症の時代へ」、『フラタニティ』第29号、2023年を参照。また著者がネット文献などで引用したものは、できるだけ確認した。
著者は大学の経営学研究科の教授であり、社会環境会計、経営倫理などが専門であると紹介されている。本書奥付に著者による経営関係の著作が並んでいるが、本書のような内容の著作は初めてのようだ。倫理学からのアプローチとして、人文系からの貴重な考察といえよう。ミシェル・フーコー、ハンナ・アーレント、ジョルジョ・アガンベン、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインら、いわゆる現代思想の代表者を登場させて、魅力的な本に仕上げている。以下では、倫理学からの考察がいかなる問題提起をするのかを紹介・検討して、さらにいくつかの興味深い論点について論じたい。
Ⅰ 倫理学はコロナワクチン問題に何ができるのか
本書は、とくに個人の倫理と責任について鋭い問題提起をしており、その点で、19世紀の哲学者・数学者ウィリアム・クリフォードの論文「信念の倫理」(51頁以下)を紹介している。彼によれば、たとえその判断が結果的に正しくても、軽々しくものごとを信じることは悪であり、罪であると、厳しく糾弾する。そして何かを信じる前に、徹底して「調べる義務」を万人がもつという。評者自身の苦々しい体験でいえば、コロナワクチンの危険性についてある程度わかっていたが、クリフォードのいう「調べる義務」を怠り、三回目まで接種してしまったことがあった。あとで述べるように、著者はワクチン問題に関連して、関係組織の倫理的責任を追及する。
さらに著者は、ハンナ・アーレントの主張する「凡庸な悪」(23頁)の問題を取り上げる。まさにこれが、ナチスの全体主義の本質に潜み、それを推進する悪なのである。ナチス幹部であったアドルフ・アイヒマンは当時、ユダヤ人虐殺の指示を出してきた人物であるが、戦後、彼の裁判を傍聴し続けた彼女は、彼が実は残忍な極悪人などではなく、ただ思考を停止して上からの指示を忠実に実行した平凡な人間であると喝破した。著者は現在、「コロナ感染症対策が、国家権力を利用して、国民を思考停止にして『凡庸な悪』を生み出している」(23頁)と説明する。まさにこれこそいまや、全体主義が進行している証拠であろう。この傾向を阻止するのは、「人間の内面から生じる倫理の力でしか」(23頁以下)ないという。
ところで「凡庸な悪」(207頁)という表現は、日本の思想界でしばしば注目され、引用されてきたが、個人倫理の観点から、たしかにそれは考えるべき重要問題であるだろう。私たち一人一人が「凡庸な悪」にいつのまにか染まっていないかということである。だが評者としては、アーレントの専門家ではないが、悪の問題は、これに尽きるのかという素朴な疑問をもっている。もしアイヒマンが「凡庸な悪」であるならば、むしろそれを産出して支える「根源的な悪」というのが事実として考えられるのではないかと思う。ヒトラー、ゲッベルスらの悪がそれであって、ゲッベルスは最後までヒトラーとナチスを正当化して、狂気に陥りつつ、妄執にとりつかれながら、戦争を敗北に至るまで遂行した。『ゲッベルス』を読むと、彼が「凡庸な悪」とは別の巨大な悪であることがよくわかる*。それは「根源的な悪」とでもいうべきであり、それがまさに多くの「凡庸な悪」を生み出したといえよう。さらに評者は、のちほど議論する、フーコー的な規律的権力と生権力をもつ「システム」のなせる悪というものも想定できるのではないかと考える。
*平井正『ゲッベルス メディア時代の政治宣伝』中公新書、1991年参照。同書はゲッベルスがいかに異常な人間であるかを詳細に描いている。
Ⅱ コロナワクチン問題への政府、学界、マスコミなどの態度
以下では、本書にそって、政府、学界、マスコミ、情報会社などにたいする倫理的責任の問題を紹介・検討したい。評者は倫理的責任の追及の背景に、用意周到に用意された、かつ豊富な事実認識があることを理解して、おおいに参考となった。評者もそうしたいい加減な情報が広まっていることは知っていたが、そのしっかりした論拠をつかんではいなかったのである。まさにそこでは、倫理が倫理にとどまらず、事実認識と論理によって裏打ちされている。
まずは内閣府・厚労省の連名で掲載されたもので、首相官邸 HPに見られるという。そこではコロナワクチンの情報として6点挙げられているが、二つ紹介したい(62頁以下)。第一は、ワクチンは高い効果をもち、2回の接種によって95%の有効性があり、発熱、咳も防ぐという主張である(ファイザー社の調べ)。この点で著者は、この数字の出典もなく有効性の説明もないと批判する。そして著者自身が引用する岡田正彦の著書でも、ファイザー社の数字のからくりが批判されている*。
*岡田正彦『本当に大丈夫か、新型ワクチン』花伝社、2022年、76頁以下参照。
第二は、ワクチン接種のメリットが副反応のリスクよりも大きいため推奨するという主張であり、このわかりやすい説明は政府機関のみでなく、学界を含む専門家やマスコミまで定番のように使われたという(68頁)。著者によれば、メリットとデメリットを比較して前者が上回るという根拠が示されていないため説得力がないし、検証するという態度がない限り、頭から信じろといっているに等しい(クリフォードのいう「調べる義務」の欠如)。評者が付け加えるに、接種後の副反応のみではなく、そこから後になって生じる後遺症の問題をリスクないしデメリットとして考えれば、それを指摘する多くの専門家や医師がいるので、彼らの言い分を検証しなければ真実はわからない。実際、「全国有志医師の会」が立ち上げられ、政府ワクチン事業の即時中止を求めている*。そこでは医師を中心に1300人以上の関係者が結集して全国規模で活動している。患者の会も存在しており、彼らの言い分と向き合わなければ、デメリットの実態は本当にはわからない。実際評者は、三回目接種の半年後に帯状疱疹が発症した。この病気は後遺症としては、2022年の時期でそれ以前よりも4倍に増加しており、いまでは珍しくはないものだ。政府・厚労省がワクチン接種を推進している以上、後遺症の情報は国民の間に拡散しない。だから後遺症にかかっても、それと認識していない国民も現段階で多いはずだ。
*全国有志医師の会、ホームページ参照。https://vmed.jp/
それでは、専門家や医師たち、さらに学会はどう判断するのか。
専門家個人としては、著者は忽那賢志、宮坂昌之の両教授の見解を取り上げ、科学的な認識や実証の手続きとして不十分であると批判する(80頁以下)*。それにたいして著者は、岡田正彦名誉教授の異なる批判的な見解も挙げる(90頁)。こうして「科学者によって解釈が異なることは十分にあるわけですから、それを前提にして意見を受け止めなければ」(90頁)ならないと指摘される。このさい政府寄りの見解をもっている専門家がおおむね一流であり、批判的な専門家が二流の凡庸な人たちだというわけではけっしてない。
*忽那は「読んではいけない『反ワクチン本』」(『文芸春秋』2021年10月号)で、「不妊になる」「卵巣にmRNAが蓄積する」などの、反ワクチン論者の主張を批判する。評者の知る限り、長尾和宏監修『ここまでわかった「コロナワクチン後遺症」』(宝島社、2023年)が、反ワクチン論者の総結集の書(ほかに平畑光一、小島勢二、岡田正彦、藤沢明徳ら)であると思われる。そこでは、ワクチンを打つと不妊症になるなどの後遺症については言及されていないようである。
では学会全体ではどうか。日本感染症学会は国民に接種の努力義務があるといわれながら、最終的には個人の判断にゆだねられると提言する(92頁)。著者はここに食い違いがあると指摘するが、評者は大まかな合意点をとって妥協したのだろうという印象をもつ。日本産婦人科学会では、ワクチン接種の努力義務は妊婦には適用されないと国会で可決されたにもかかわらず、あいかわらずワクチン接種を推奨し、それどころかその夫(パートナ―)にも接種を要望している。これはまさに政府・厚労省寄りの立場であり、それでいいかどうか検証されなければならない、と著者は主張する。まさにその通りだろう。日本小児科学会では、12歳以上の健康な子どもには接種の意義があるとされ、稀に重症化すると付加されている(96頁)。著者はどうしてこういう提言になったのか、まったく不明だと批判する。評者は子どもへのワクチン接種が危険かつ不必要だという専門家の意見も知っているので、ここでも論争点があるだろうと思う。
評者はこうした各学会の正式の見解をはっきりとは知らなかったのでおおいに参考とさせていただいた。いずれにせよ、ここに政治的影響もあり、組織全体の利害関係も絡むので、これが科学的判断を示しているとはとてもいえないだろう。良心的な医師、専門家たちの警告などは排除されることだろう。とはいえ著者は、こうした見解の食い違いや不明瞭性について、「因果関係は客観的に説明できない」、そもそも「因果関係は主観的である」という方向へと導いて結論づけようとする。評者はせっかくの考察がこういう方向へと展開されることにはおおいに違和感がある。科学は基本的に、客観的に存在する因果関係を追究するものだからである。この点をのちほど議論したい。
Ⅲ コロナワクチンをめぐる「デマ」「誤情報」「陰謀」の問題
さらに著者はマスコミや情報会社のあり方も批判するが、その点を含めて、倫理的問題ともなる、ワクチンをめぐるデマやウソについてさらに展開する。
まずは河野太郎ワクチン担当大臣のサイトにある「ワクチンデマ」について議論される(108頁以下)。そこでは、ワクチンで不妊が起きる、卵巣にワクチンの成分が蓄積する、ワクチンで遺伝子が組み替えられる、治験が終わっていないので安全性が確認できない、ADE(抗体依存性増強現象)が発生する、などがデマとして非難されている。だが、ここに「正しい」情報が含まれている可能性があり、すべて誤情報ということはできないと正当に指摘される。著者の調べによれば、実は河野のいう「デマ」は、内容的に、厚労省発表の「新型コロナワクチン(mRNAワクチン)注意が必要な誤情報」にそのまま継承される(113頁の表5を参照)。詳細は省くが、ここであらたに、「ワクチン接種が原因で多くの方が亡くなっている」が「誤情報」として付加されている。著者によれば、すでに1000件以上の接種後死亡例が確認されており、「ワクチンが原因で死亡したわけではない」とまでは断定できないとされる。実際、2023年の現時点では、すでに接種後2000人以上の方が亡くなっており、コロナワクチンがそこに大きく関わっていると主張する専門家が何人もいるわけで、著者がここで厚労省を批判するのはまさに正しい。そこには「調べる義務」(クリフォード)がないがしろにされている。
さらに著者によれば、ツイッター社のSNSも、誤情報を削除するという方針を掲げる。「COVID-19について、悪意のある勢力や強い権力による意図的な陰謀を想起させる、以下の誤った情報」(116頁)に内容として、パンデミックはでっち上げだ、予防接種は人口抑制のための取り組みの一環だ、ワクチンは危険で、その副反応は政府、医療業界によって隠蔽されている、などの事例を列挙する。評者はこうした方針が現実にはっきりと存在することを知らなかったが、まさに驚くべき事実である。こうして検討の余地のある情報が「陰謀」とみなされ、大っぴらに削除されるわけであり、これはさきの河野大臣や厚労省の「デマ」「誤情報」の認識とは、別レベルのものであろう。同様にユーチューブを運営するグーグルは、さらに強い規制をポリシーとして掲げている(118頁以下)。たとえば、「ワクチンが慢性的な副作用…を引き起こす」というような内容は、それがまさに専門家によって現在、そのように詳細に指摘されてきているのに、あからさまに削除されてしまうのだ。評者は長年ネット検索をして、SNSやユーチューブが不当に情報を削除しているのは実感していたが、こうした確固たる方針があるとは知らなかったので、おおいに驚いている。これはまさに「完全な情報統制」(120頁)というべきものだと、著者は断定する。さらにまた、読売新聞、NHKテレビなどの日本のマスコミにも、危険なワクチンデマを流し、そこに陰謀を企てる少数者がいるという構図があると指摘される(121頁以下)。
以上のように、政府・厚労省、専門家、学界、マスコミ、SNSやユーチューブなどのネット情報も、世の中に「デマ」「誤情報」「陰謀」があると称して、かえって逆に、彼ら自身が不確実な情報を流していることが明らかになった。こうして著者は厳しく彼らの倫理的責任を追及するわけだが、まさにその根拠に、事実認識の周到さと説得的な論理展開があることを実感した。この個所の著者の論法は実に鋭く、おおいに参考になった。ところで倫理的にいうと、「ウソをつかない」という大原則があるが、世界に何らかの大きな陰謀があると批判する側にもウソがあるだろうが、上記の信頼されるべき機関にも大きなウソがあることが判明したわけである。
Ⅳ 興味深い二つの論点
本書にはその他にもいくつかの興味深い論点がある。ここで二つ取り上げたい。一つは「独裁化するリベラル」の問題であり、もう一つは規律的権力と生権力をもつ「システム」に関わる問題である。
第一の問題は、米国でいえば、共和党のトランプは保守的であるはずだが、感染症対策にこだわるよりも、むしろ活動の自由を重んじているように見える。他方、民主党のバイデン大統領は接種の義務化などを推進して、自由を規制しているように見える。この現象には評者もどこか違和感を感じてきたが、著者はこの問題をうまく解説していると思われる。
つまり民主党などのリベラル派は、かつて国王、宗教、伝統的価値観、性差別などの抑圧からの解放を目指したが、そこで理性的秩序や社会的規律を重んじ、さらにできるだけの平等を確保しようとした。そこにコロナの感染の問題がはいるとどうなるか。ワクチンを打ちたい人だけが打つというのでは感染は収まらず、コロナからの解放を目指すために、社会的規律の精神でワクチンを義務化せざるをえない。それにたいして、なぜ保守主義者がワクチン接種に慎重になるかというと、過去の伝統や宗教に抵触しない限り、感染症対策はおのずと緩いものとなるからだ。こうして保守主義は伝統から現在を見るので、それに反しない限り、新しいワクチンなどには注目しない。これにたいしてリベラルは、伝統から自由になって新しい価値観を創りたいので、ワクチン義務化という新しい規範にこだわることになるとされる。
著者はこの二つの思想は排除しあうものではなく、二つがセットになって人間社会はうまく動くと考える(150頁)。ところが日本はこの二つの思想の区別があいまいになっており、ひたすら外国、とくにアメリカを見て判断するだけになっているという。このあたりの説明はとても興味深いものであった。
第二の問題は、フーコーらの現代思想に関わる。学校、工場、病院などの組織で、「匿名の権力」(170頁)として自己規律型の人間を育てる規律的権力、および人口などを調整する生権力、をもつ「システム」の存在である。生権力は衛生状態、医療水準などを管理して人間社会に大きく貢献もしたが、この「史上最強の権力システムである生権力」(181頁)は、コロナなどの感染症にたいして、薬、ワクチン、ロックダウン、緊急事態などによって戦争状態にはいる。著者によれば、生権力は人間をもっとも深いところから統治することを究極目的とするので、病気を作りだしつつそれを治療するという活動のなかで膨張してきた(182頁)。システムによって人々が監視されているという構図は、実は陰謀論者が描く世界と酷似するといわれる(190頁)。そこに特定の黒幕は存在しないが、あたかもシステムは不気味な感じで擬人化されているといえよう。評者はここで「システム」のもつ悪を語りたい気持ちである。さらにここから「凡庸な悪」(193頁)も発生するといえよう。著者によれば、この近代社会のシステムがすでに私たちを一部としてそのなかに取り込んでいるので、それへの抵抗はむずかしいが、そこであえて「システムへの抵抗」(195頁以下)の道を探り、人間の尊厳を回復しようとする。
一体このシステムとは何か。評者にはそれがあたかも、人間の心理をコントロールする不気味なエイリアンのように見える。著者の説明では、生権力としてのシステムは生命体ではないからそれ自体で権力を行使できず、政治家、役人、科学者、専門家、経済人などを使って機能するものであり、その背後で政治、科学、経済などのサブシステムが形成される。
システムのあり方は、経済的な物象(商品、貨幣、資本)が人格化して人びとを規制し、逆に人びとがシステム内の駒となる(本書でいうと「役者」としてふるまう)という意味でマルクスのいう物象化現象に似ている。マルクスの物象化論が資本主義社会の経済システムによる現象として科学的に解明されるのにたいして、フーコーのいうシステムとは曖昧模糊として、その実体が確定されない。その代わり、たしかにここで、巨大社会に取り込まれて生きていく現代人のもつ、不確かな感覚と無力感が巧みに描写されているといえよう。
著者はこのシステムを前にして、それにたいする抵抗の困難さとともに問題解決への展望も語る。
著者によれば、民主主義のプロセスに従って抵抗してもまずは成功しない(196頁以下)。さらに、政治家への陳情も効果はあまりなく、議員に立候補してもシステムは支援しないし、少数派では無力。科学者が論文化しても黙殺されるし、経済界、医療業界は経済行為のみを目指し、学界のトップは選べない…。ところが著者は徐々に展望を語り始める。まずは各人がめいめい非組織化された行動をとる、そのうちに共感の連鎖が生まれるかもしれない。事実、過去の公害訴訟、薬害訴訟は少数派の抵抗運動から始まったのだ(211頁)。評者も、フーコーが提起する同性愛の問題も、最初は少数派だったが、いまやLGBTQの世界的な運動につながっていることを連想する。
そのさいに著者自身が重要と考えるのは、「因果原則から予防原則へ」(228頁)転換すべきだという認識である。科学的に実証される因果法則がまだ不明であるとしても、将来の予測されるリスクを考慮した場合、予防的取り組みをおこなうべきだということである。とくにコロナワクチンの副反応や後遺症の場合、その因果関係が十分に解明できないという理由で、厚労省が「因果関係不明」ばかり連発する状況では、犠牲者が増えるばかりである。ワクチン接種を中止することが最良の予防原則の適用であろう。
こうして著者は、自我という主観的対象も、社会のなかで生きていくうちに、多くの他者や自然との相互作用のなかでできあがってきたものだと、あらたに指摘する。哲学者西田幾多郎が個人の特性も「社会的意義なる基礎」のうえに現れてくると述べたことを引用しつつ、著者は利己というさいの「己」というものも、実は「自分の中にある社会的自我」なのだと喝破する(235頁)。だからこうして、個人倫理も、広く社会倫理へと拡大していき、一人一人が社会全体に関心をもち、それに加わろうとする姿勢が重要だということになろう。したがってこの点で、システムに抵抗するためにも、少数派の活動を注視するのが倫理的にも意味があると考えられる。さきに全国有志医師の会の活動を取り上げたが、科学者や医師のなかにも、少数派であるが、これが真理や事実であると主張する、一群の抵抗者・批判者が存在する。残念ながら、彼らの活動は本書の叙述には現れなかった。それが描かれれば、本書の展開がもっとリアルになったことだろう。
最後に気になったこととして、章立てには改めて書かれてはいないが、「因果関係は客観的に説明できない」(97頁)、「因果関係は主観的にしか決められない」(98頁)という本書の主張がある。これは、肝心なところでしばしば指摘されるものであり、叙述の説得性を妨げているように見える。そうすると一体、単なる仮説と検証された理論の区別は何なのか。「予防原則」の前提に設定される「因果原則」とはどういう性質のものなのだろうか。この哲学史的由来は、18世紀の懐疑主義者のデイヴィッド・ヒューム(99頁)と科学哲学者カール・ポッパー(129頁)である。ヒュームでは、因果関係とは客観的結合の関係ではなくて、習慣によって引き起こされる単なる印象にすぎない。ポッパーの「反証可能性」では、原理的に反証できる可能性がなければ科学ではなく、反証に耐えた考えだけがよい理論なのである。評者は哲学のなかでも認識論、論理学、弁証法などが専門分野である。詳細はここで展開できないが、科学とは一般に客観的な原因・結果の究明をするものであり、この点からすると、ヒュームとポッパーの認識論は一面的であり、著者はこの点で不十分な因果論に陥っているといえよう。
真理とは何かの問題が大前提にあるはずだが、これが説明されずに展開されている。真理観には、真理反映説、真理合意説、真理整合説などがあり、そのなかでも素朴なものから洗練されたものまで多様にある。評者では、真理とは特定の対象の性質、構造、本質の、何らかの条件のもとでの正しい反映としての認識であり、その意味での意識内での対象の観念的再生産であると定義される。正しい反映であるから、その認識をもとに多くの関連する現象を正しく把握できるし、実践的にも応用できる。そして、たしかに人はあらかじめ予測したり、仮定を立てたりしてしか対象にアプローチできない。そういう意味では、複雑な対象になるほど、予測したものしか認識できないということはありうる。またあらかじめ理論装置や専門知識を主体的にもっていないと、何も認識できない。またほかの専門家の追試、ピアレヴューがやられてこそ、真理かどうかが検証される。そこで議論ののち一致した認識こそ、対象の何らかの条件のもとでの正しい反映にほかならない。ポッパーの反証可能性は真理認識への有効な条件であるが、検証可能性と対になって真理認識に近づくであろう。そして真理は一度きりで固定的に獲得して終わりというものではなく、より正確に深く探求される過程のなかにある。
そのほか「100分の1の倫理」と功利主義批判など、興味深い論点があったが、割愛させていただいた。本書は倫理学によって何ができるかを説得的に提示したが、だがその前提に、著者が示した多くの正しい(事実認識であるところの)情報の獲得と適切な論理展開があることを実感した。コロナワクチン問題という医学的な現象に人文系の立場がどう対応できるか、画期的で貴重な試みであるので、本書が幅広く読まれることをおおいに期待したい。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
●鳥集徹さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
●ISF主催公開シンポジウム:東アジアの危機と日本・沖縄の平和
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 島崎隆
島崎隆
一橋大学経済学部を卒業ののち、群馬県で高校教諭。現在、一橋大学社会学部名誉教授、社会学博士。ヘーゲル、マルクスらのドイツ哲学に関心をもってきたが、日本の学問研究には「哲学」が不足しているという立場から、多様な問題領域を考えてきた。著書として以下のものがある。『ヘーゲル弁証法と近代認識』『ヘーゲル用語事典』『対話の哲学ー議論・レトリック・弁証法』『ポスト・マルクス主義の思想と方法』『ウィーン発の哲学ー文化・教育・思想』『現代を読むための哲学ー宗教・文化・環境・生命・教育』『エコマルクス主義』『《オーストリア哲学》の独自性と哲学者群像』。