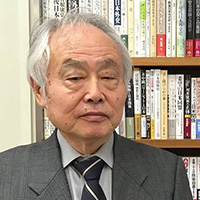【書評】塩原俊彦『ウクライナ戦争をどうみるか「情報リテラシー」の視点から読み解くロシア・ウクライナの実態』、花伝社、2023年
映画・書籍の紹介・批評
塩原俊彦氏が、2014年の「マイダン革命」以来、主要メディアや多数派の研究者とは異なる視点から、ウクライナ危機について発言してきた専門家であることは、ISF読者の皆さまならば、よくご存じだと思います。元全国紙記者と研究者という二重の視点を持つ塩原氏は『ウクライナ・ゲート「ネオコン」の情報操作と野望』(2014年)、『ウクライナ2.0:地政学・通貨・ロビイスト』(2015年)、『プーチン3.0:殺戮と破壊への衝動 ウクライナ戦争はなぜ勃発したか』(2022年)、『ウクライナ3.0:米国・NATOの代理戦争の裏側』(2022年)、『復讐としてのウクライナ戦争:戦争の政治哲学―それぞれの正義と復讐・報復・制裁―』(2022年、いずれも社会評論社)といった比較的専門性の高い一連の著書を刊行してきました。とりわけ2022年刊行の著書群で、著者は一貫してロシアを厳しく批判しています。けれどもその一方で、米国のウクライナへの2014年以来の干渉政策、特にウクライナ・ナショナリズム扇動が、今日の戦争を引き起こす原因になったという側面を強調し、より包括的な議論をするよう、注意を促してきました。このように、これまで有力な異論を述べ続けてきた専門家である塩原氏が、特に若い世代に向けて構想したと思われるのが、『ウクライナ戦争をどうみるか』です。これまでの塩原氏の著作群がロシア・ウクライナ情勢の詳細な分析に焦点があったのに対し、本書の力点は、メディア論・情報リテラシー論に置かれています。
「まえがき」では、「意図的で不正確な情報」を意味し、いわゆる「だまし」につながる「ディスインフォメーション」という概念が紹介されます。ロシア語由来の言葉であることが示す通り、ロシアの情報操作が「伝統」であると書かれています。けれども、本書の特徴はむしろ、欧米のメディアおよび政府やウクライナ発のディスインフォメーションにも警戒を促していることにある、と私は思います。
第1章「情報リテラシーをめぐる基本構造」では、発信・媒介・受信という情報移動のそれぞれの場面で、「だまされない」ための注意が必要、と指摘されます。
まず情報受信者については、ダニエル・カーネマン『ファスト・スロー:あなたの意思はどのように決まるか?』(早川書房、2014年、上下)に基づき、次のようなだまされることを容易にするような傾向がある、と論じられます。即ち、ロシア=悪といった連想を働かせる「プライミング効果」、慣れ親しんだものを好んでしまう「認知容易性」、信じたいものを信じてしまう「確証バイアス」、最初の印象の重みが高いため後で入ってくる情報を軽視してしまう「ハロー効果」等です。こうした印象やバイアスに囚われてしまうのが「システム1」であり、それを超えた深く批判的な思考ができるのが、「システム2」であるとされます。具体的には、グレタ・トゥーンベリさんの勇気や健気さに心を動かされるのがシステム1です。それに対して、ロシアの独立系メディア『ノーヴァヤ・ガゼータ』のユーリヤ・ラティニナ記者のように、歴史を振り返りつつ、「イデオロギー的闘争における子ども利用は全体主義イデオロギーの古典的サインである」とあえて冷や水を浴びせ、冷静な再考を促すのがシステム2です。
情報発信者としては、政治家、官僚、学者等が挙げられます。大きな影響力を持つこれらの発信者の顕著な偏りについては、一方的ないわゆる「ロシア悪玉論」等、周知のことと思います。特に大学教員が醸し出す権威によるハロー効果で、「やはりそうなんだ」といった「確証バイアス」が働く、とされます。
著者がより重視しているのは、主要な情報媒介者たるマスメディアであるように見えます。マスメディアは「第四権力」を自称しながら権力者と結託しており、ベトナム戦争のトンキン湾事件の誤報、イラク戦争前の大量破壊兵器の誤報などにも、メディアが加担してきた、とされます。政府を厳しく批判する報道もあるからこそ、マスメディアと政府の癒着は見えにくい、と巧妙な仕組みを暴く指摘には、蒙を開かれます。
ディスインフォメーションがはびこるとされるのは民主主義が未熟なロシアだ、というのが定番であり、塩原氏もそれを否定していません。けれども返す刀で、加計・森友問題で首相自らがディスインフォメーションを流し、2017年衆院選の結果までが歪められたではないか、と糾弾する著者の筆致は辛辣ですが、反論しがたいものです。
第2章「2014年春にはじまった? ウクライナ戦争」では、ウクライナ戦争を題材として、いわゆる「だまし」の解説が具体的に行われます。2014年にウクライナで起こった「マイダン革命」を米国が支援して、いわゆる過激派の人々を扇動して暴力的な「クーデター」に仕立て上げたのが対立の始まりだ、というのはロシア側の見方でもあります。けれどもだからといってこうした見方に正当性がないともいえないということが、米国人であるオリヴァー・ストーン監督の『ウクライナ・オン・ファイヤー』も参照しつつ、論証されます。当時のウクライナのヤヌコヴィッチ政権を打倒するという結果が達成できたから、それが正当な選挙によらなくてもいいではないか、といった「結果主義」(結果よければ全て良しといった考え方)が厳しく批判されます。厳格な選挙による政権交代といった過程こそが民主的正統性を確保するにあたって極めて重要である、ということになるでしょう。さらに問題なのは、米国のヴィクトリア・ヌーランド国務次官を代表とする「ネオコン」とも呼ばれる好戦的な勢力が『ワシントン・ポスト』『ニューヨーク・タイムズ』といった主要メディアを味方につけ、「民主革命というよりもクーデター」といった見方をそもそも伝えないように図ることです。日本のメディアもおおむね欧米メディアに追随している、との指摘もなされます。けれども、「米国が支援したクーデターが、今日に至る一連の危機を招いた」といった見方は、米国の国際政治学の泰斗であるジョン・ミアシャイマー氏らからもなされています。
こういった一連の介入政策の結果、ウクライナはロシアと対立するようになり、米国に従わざるを得ない保護国のようになっていったとされます。ドンバスの両「人民共和国」が、ウクライナ政府と結んだ二つの和平合意「ミンスク合意」は実はウクライナの軍備増強のための「時間稼ぎだった」、と仲介者だったドイツのメルケル元首相が告白した、という事実も極めて重要です(注1)。最初からドイツ、フランス、というよりもむしろその背後にいた米国は、交渉による内戦の平和的解決を目指していなかった、人民共和国の後ろ盾だったロシアをだまして挑発していた、というようにすら、見えてしまうのです 。それに加えて塩原氏は、(ゼレンスキー政権が)ミンスク和平合意を履行しようとすると、ウクライナ国内の過激ナショナリスト勢力に脅迫されるのでできなかった、といった日本の一般メディアではほとんど報道されていない事情も明かしています。こういった事情を総合して、ウクライナとロシアという主権国家同士の戦争は確かに2022年2月に開始されましたが、内戦という意味での実質的戦争、またはNATO対ロシアの代理戦争は、2014年に既に始まっていたのではないか、といった見方が説得的に示されています。
第3章はまさに「ウクライナ側の情報に頼りすぎるな」と題されています。そもそもウクライナは戦時下で過酷な情報統制を行っており、批判的メディアは弾圧されています。そういった事情もあり、「ゼレンスキー政権にとって好ましい情報を流すのが公共放送の役割」と指弾されています。具体的には、例えば、ロシア軍が学校や病院を攻撃している、といった映像の多くは偽動画ではありません。けれども、アムネスティ・インターナショナルも指摘したように、ウクライナ軍が意図的に学校や病院に陣取り、ロシア軍がそういった施設を攻撃するよう仕向けているという側面を知れば印象が変わるのでは、と問題提起されます。『ニューヨーク・タイムズ』の報道として、ウクライナ軍の管理下にあったリシチャンスクの住民の多くは、ウクライナ軍兵士らの振る舞いにへきえきし、その敗北を願っている、といったエピソードも紹介されます。他方で塩原氏は、マリウポリで捕虜となったウクライナのナショナリスト系兵士らがロシアの収容所で爆殺された事件について、責任をウクライナ軍の攻撃に着せたロシア側の主張は噓であろう、と様々な情報源を分析しつつ推測しています。かつてチェチェンとダゲスタンでの紛争を新聞記者として取材した経験を持つ塩原氏が、「戦争では決して片方の言い分だけを信じてはならないのだ」と説くくだりは、説得力があります。戦争開始前から「腐敗国家」として知られたウクライナですから、欧米が供給している武器が正当に使われているか、欧米も疑っている、といった事実も我々は知っておかねばならないでしょう。
第4章は、「なぜ停戦できないのか」という問いを立てています。大元の理由としては、既に言及した「帰結主義」と関わりますが、「結果だけを重視する立場は勝つか負けるかという結果だけに固執し、曖昧で不透明な停戦を嫌うからだ」と分析されています。勝ち負けをどうしてもはっきりさせようとして殺し合いが続くことで、最も犠牲になるのはウクライナとドンバスの住民達であることも、思い起こさなくてはならないと私は思います。
背景として、NATO諸国は武器供与以外にもウクライナ軍兵士の訓練にも関わり、自分達は血を流さずにロシアを弱体化する代理戦争を実質的に行っている、という側面も押さえておかねばなりません。戦闘や制裁以外にも、『ニューヨーク・タイムズ』のような主要メディアがロシア=ファシストといった学問的に不正確な見方を拡散し、憎悪と扇動によって戦争を長期化させている側面もあるとされます。他方でバイデン親子のウクライナの資源会社「ブリスマ・ホールディングス」を通じた腐敗疑惑を巡る情報を、意図的に抑圧してきたのが、同じ主要メディアなのです。これに関連して、ノルドストリーム爆破事件はロシアではなく米国等が仕掛けた、といった米国のベテラン・ジャーナリスト、シーモア・ハーシュ氏による報道がありました。ガス輸入が途絶えて国民が苦しんでいるのに、米国に追随するばかりのドイツをはじめとする欧州の政治家らの情けない実態も指摘されます。
これまで具体的な「だまし」の手口と実態を見てきましたが、第5章では「だまされないための対策」という実践的な対抗手段が提示されます。長年大学教員として教育に携わってきた塩原氏が勧めるのは、自ら作文をしてみる、という作業です。心の中でもう一人の自分と会話する訓練を積み、「反省力」を鍛え、まさに自分の頭で考えるという修業を続けることで、情報の「良き受信者」になれる、と論じられます。こうした作文には、他者に自分の見解を理解してもらうという目的も含まれているので、学生のみならず、幅広い世代にとって有効な手段ともいえるでしょう。そもそも他者志向で多数派迎合の「フリーライダー」に成り下がり、テレビに代表される「インフォテイメント」(インフォメーション+エンタテイメント)に流されているようでは、何歳になっても、立派な大人だとはいえないと認めざるをえません。そういった情報提供をしているマスメディア関係者が「あまりに不勉強」で「官僚や政治家、学者にだまされている面がある」、という著者の見方に私は反論できません。
こういった厳しいメディア批判や権力者批判の一方で、私達情報の受け手の「だまされる」側の責任も問うているのが、本書の特徴でもある、と私は考えています。伊丹万作監督の『戦争責任者の問題』に述べられている「『だまされていた』といって平気でいられる国民なら、おそらく今後も何度でもだまされるだろう。いや、現在でもすでに別のうそによってだまされ始めているにちがいないのである」「まず国民全体がだまされたということの意味を本当に理解し、だまされるような脆弱な自分というものを解剖し、分析し、徹底的に自己を改造する努力を始めることである」といった厳しい言葉は―残念なことに―今でも有効であるように思われます。
ウクライナでの戦争は、遠いところで起こっている私達とは無関係な出来事である、ともいえないのが恐ろしいところです。塩原氏は第5章の最後で、ウクライナで戦争を行っているロシアを批判しつつ、少なくとも2014年の「クーデター」以来、ウクライナに介入・扇動を続けてその原因を作り出した「米国のネオコンないしリベラルな覇権主義者」をもう一つの「悪」として名指します。塩原氏は中国と米国の代理戦争に私達が巻き込まれる可能性を指摘していますが、ウクライナが対ロシア戦略の前衛として米国に利用されて甚大な被害を被っているように、私達日本人は米国の対中国戦略のコマになりつつあるのではないか、と改めて問い直すべきでしょう。「台湾有事は日本有事」といった、中国の内戦への介入という意味では、日中戦争の再来ともいえる侵略の汚名を招きかねない文句には強く警戒せねばなりません。その上で、東欧でも東アジアでも危機を煽り続けてきた米国の戦略の犠牲になっているウクライナの悲惨な境遇から、教訓を汲まねばならないと切実に思います。
以上が本書の概要です。著者の真実探究者としての誠意と熱意の一端を伝えることができたでしょうか。ちなみにISFの掲げる理念は「真実探究と戦争廃絶」ですが、私は著者のように本気で真実探究を行うことなしに素朴に「戦争反対」を唱えても、決して戦争廃絶は達成できない、という意味で理解しています。
私が著者の教育者、啓蒙家としての良心を感じるのは、「この本に書いてあることも少なくとも疑ってかからなければならない」(第1章4)とわざわざ断っていることです。古典的な啓蒙の課題としての「自分の頭で考えること」は、21世紀の今も達成されざる課題であるようです。それどころか、人心を惑わす情報伝達(操作)技術の発展により、益々困難になりつつある、とも私は感じています。メディアやユーチューブ等のプラットフォーマーの偏向はウクライナ問題に限ったことではありませんので、本書の教えは、現代の他の問題にも適用可能、と私は考えています。
私は塩原氏の見方に大変多くのことを学ばせていただき、学者として信頼を寄せていますが、本書で一点だけ気になるのは第5章の「陰謀論に注意せよ」のくだりです。いわゆる「ユダヤ人陰謀論」のような感情に訴えて差別を扇動するような話に注意が必要、というのは著者のご指摘通りです。けれども、「自分とは対立する意見に対して、それが正当な批判かどうかを吟味することなく、気に食わない意見を、『それが陰謀論だ』とラベリングして、意見を封殺してしまうことにつながる」ことがありうる、と思われるからです (注2)。もっとも、2014年以来、少数意見を貫徹し続けてきた塩原氏は、こういった側面にも気付いておられることでしょう。
私が塩原氏の一連の著書や記事に触れて最も尊敬するのは、次のような事情です。つまり、ロシアや米国でも認められたベテラン研究者であるにもかかわらず、謙虚にも「評論家」を名乗って、しらけることなく偏向した学会やメディアの言論状況に、本気で怒り、正面から異議を唱え続けていることです。日本の主要メディアで根本的に異なる方向の報道をするところがほとんどないのは遺憾ですが、ISFには塩原氏の記事が毎週のように掲載され、しかも無料で読むことができます。これは現在のメディア状況を考えてみると、大変異例なことです。
本書刊行をきっかけに、ウクライナ問題を巡る著者の根拠ある異論がより幅広い社会層に周知され、より総合的で、一方的でない議論が行われるようになることを願ってやみません。塩原氏は現在、地政学に関する大著を執筆中と聞いていますが、今後も論壇を啓発し続けてくださることを期待せずにはいられません。
[1]メルケル元首相の告白について、塩原氏はいち早くISFで解説記事を執筆しておられます。「メルケル発言の真意:紛争・戦争を望んだ『ネオコン』の存在」、2022年12月22日。https://isfweb.org/post-12515/
[2] 秦正樹『陰謀論 民主主義を揺るがすメカニズム』中央公論新社、2022年、226頁参照。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
●ISF主催公開シンポジウム:東アジアの危機と日本・沖縄の平和
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
「独立言論フォーラム(ISF)ご支援のお願い」の動画を作成しました!
 嶋崎史崇
嶋崎史崇
独立研究者・独立記者、1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系研究科修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。ISFの市民記者でもある。 論文は以下で読めます。 https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評・インタビュー・翻訳に力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント: https://x.com/FumiShimazaki