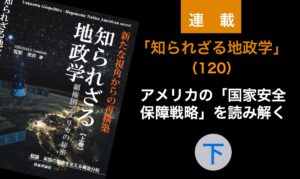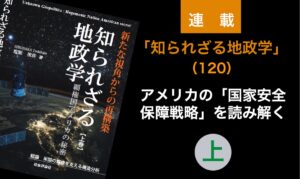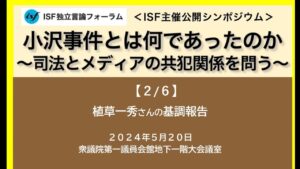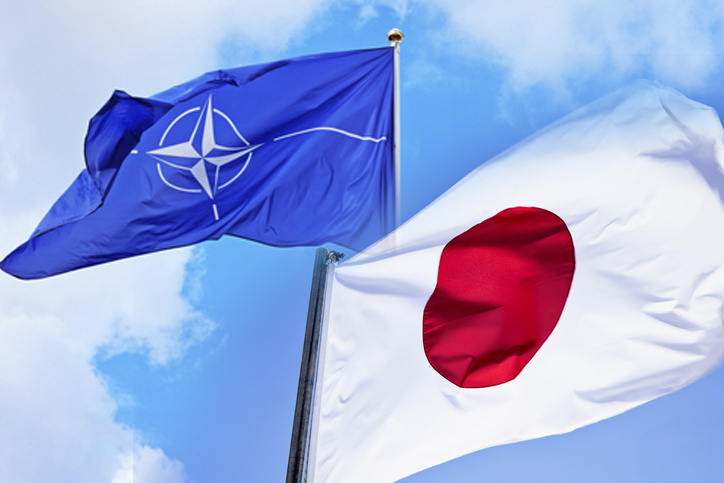
ロシア・ウクライナ問題に便乗 「NATO東京事務所」構想が示す岸田凡愚政権
社会・経済国際マクロン大統領の主張の正当性
岸田文雄政権の対米追従が止まらない。
8月18日に行なわれた日米首脳会談では「新型ミサイルの日米共同開発」が合意された。ここまで米国と一体化した政権は過去にないし、これでは日本は進んで敵対国作りに勤しんでいるのと同じだ。自国の国益優先で対処してくる米国が、この先、政策を転換するかもしれない。そうなったら日本は梯子を外される可能性が増大する。そういうことを考えて外交を行なっているのか。
日本の国是とは何か。国益とは何か。それがまったく見えてこないことが、岸田政権の最大の問題である。その最たるものが、NATO(北大西洋条約機構)への急接近だ。7月12日にリトアニアの首都・ビリニュスで開催された首脳会議では、東京にアジア初の事務所を設置することが提案され、フランスの反対がなければ正式な採択も見込まれていた。先延ばしとなったものの、年内の採択を目指して調整を続けていく、とされている。
マクロン仏大統領はNATOが「北大西洋条約機構」の略であり、アジア・オセアニアなど「インド太平洋」とは切り離すべきだと主張。東京への事務所開設はNATOの「域外」であり、「反対だ」と表明している。
本来はワルシャワ条約機構が解体された段階で、こちらも無くならなければならなかったが、いまだに存在している。しかも、1949年、ソビエト連邦に対抗するために生まれた軍事同盟のNATOを、米国の対中戦略に従い拡大することへの懸念が持たれるのは当然だ。
マクロン大統領は4月に訪中し、習近平国家主席と首脳会談を行なったのち、「EUは米中対立と距離を置いて、第3極を目指すべきだ」「台湾における緊張の高まりはEUに利害がない」と述べた。それゆえ日本国内の報道は、多くがマクロン大統領の親中シフトと捉え、批判している。
日本にとって、自国に連絡事務所を開設させるのは、ロシア・ウクライナ問題を奇貨とし、NATOを対中包囲網に活用しようということになる。岸田首相はそれが我が国の安全保障や防衛強化に資すると考えているのだ。
しかし、加盟国の地理的な条件をみれば、NATOはマクロン大統領が言うように「北大西洋条約機構」であり、旧ソ連に対する軍事同盟であり、欧州の話である。そして日本は、ロシアとの関係悪化は避けられないとしても、目下対立しているわけではない。ロシア・ウクライナの問題を利用してNATOに入っていくにも、大義名分が見当たらないのである。
なおかつ、中国の脅威とは、あくまで米中対立に根ざしたものにすぎない。NATOが米国主導であることはいまさら言うまでもないが、それでもフランスの大統領が、中国との関係において独自の姿勢を示したのは、一国のトップとして道理のあるところだ。
日本が中国を脅威と捉えるならば、NATOではなく、アジアの和平を構築するための安全保障関係をつくるべきだ。しかし、分断を利用して新たな分断をつくるという、姑息な戦略に走っているのなら、古来からの国是である「和を以て貴しとなす」「八百万尊重」の精神に反しているといえよう。
「戦後レジーム」から逃げた岸田政権
NATOへの急接近によって、岸田政権が目指すものとは何か。
日本は明治維新以降、富国強兵路線に転換したあげく、大東亜戦争に敗北し、米国の従属国家に成り下がった。アジアの中で西欧的な路線を追求したために、歴史のひずみをつくってきたといえる。すでに国内に130以上の基地をはじめとした米軍施設が置かれ、首都の空域すら規制を受けるほどに、自国の主権を確保できない状況にある。
それを解消するのではなく、NATOの一部になったと見せかけることで、戦後78年のひずみを覆い隠すことができるのか。憲法も改正できず、自衛隊の戦闘法規すら整備されていない状態で、見せかけだけ作ってどうするのだ。日本の理念・国益を示すのをあえて放棄し、対米従属体制に屋上屋を架しているにすぎないのである。
たしかにドイツは東西冷戦のさなか、EU(欧州連合)やNATOが構築される過程で、近隣諸国との関係改善を成功させた。しかし、ドイツと日本では地政学的条件が全く異なる。ドイツはヨーロッパ大陸の中心に位置し、近隣国と安全保障・経済面などで利益を共有している。一方、アジアの島国である我が国が米欧のお仲間を自称したところで、国際的な地位など望むべくもない。
今求められているのは、日本という国のあり方、日本人としての誇りとは何かを示すことである。経済でいえば、失われた30年からどう脱却するかだ。その内実を放置し、虚勢の国家へとひた走って国家再興があるのか。
外務省のホームページを開けば、「NATOと協議」といった言葉がたびたび出てくる。菅義偉内閣で内閣官房参与を務めた高橋洋一氏は、「日米安保だけでは心もとない」「中国が仏エアバスを買ったのなら『では日本はワインを買います』と言えばいい」などと宣った。繰り返すが、地理的条件の異なるNATOと日本が同じ目線で利害得失を語ることなどありえない。
岸田政権は昨年末から、安保3文書を変え自衛隊の敵基地攻撃の付加や軍事予算の倍増を、国会に諮らずにやった。軍備に5年間で43兆円をつぎ込むというのは、米国の兵器を爆買いするということだ。バイデン米大統領と会うたびに肩に手を置かれるのが、もはや恒例となっている。獲物を捉える動物の仕草と同じで、一国の首相を遇する態度ではなく、まさに米国のいけにえとしか見えない。
NATO首脳会議のウクライナ支援の共同宣言の場では、バイデン大統領が岸田首相を指して、「話す予定はなかったんだが、言わせてほしい。この男が立ち上がり、ウクライナを支援すると思った人は欧州や北米にはほとんどいなかった」「彼は防衛予算を増やし、日本を強化した。改めてこの公の場で感謝したい」などと述べた。岸田首相ははにかむような表情を浮かべたが、恥を恥とも思わず有頂天になっている。
バイデン大統領は6月の支持者集会で、「私は3度にわたり日本の指導者に会い、防衛費増額を説得した」と発言したのだ。
反中・反ロの行く末は歴史が示している
戦後、主権国家としての姿勢が打ち出せない中で、安倍晋三政権が解釈改憲により、2014年に集団的自衛権の行使を容認した。憲法改正こそ目指すべきだが、姑息な手段で自衛隊員を他国の戦争に駆り立てている。
その自衛隊では定員割れが続いている。自国の理念を示す代わりに「自由、民主主義、人権、法の支配といった価値観の共有」を繰り返し、それが日本とNATOの利害得失の一致となるかのように主張している。
しかし、その実はただの反中国・反ロシアにすぎない。NATOの加盟国でも、ドイツやハンガリーなどはロシアとの関係を独自に強化し、フランスは中国との関係を維持している。アングロサクソンの路線に従っていくことに、はたして正当性があるのか。本誌前号では「日米イデオロギー一体化による日本国民の解体」を指摘した。令和版脱亜入欧の結果は、歴史が証明している。

「ロシア包囲網」の企てに日本が参加することは、G7の申し合わせ事項だから致し方ないのだろう。だが、我が国の国益を考えるとともに、ロシア・ウクライナの歴史的な関わり等をしっかりと認識すべきだ。
反ロシアへののめり込みも、危険きわまりない。大正時代のシベリア出兵と同じ轍を踏むことになる。ロシア革命後の混乱の最中、チェコ軍支援の口実で日本はシベリアに出兵するが、結果的には多数の犠牲者を出して撤兵。何も得るものはない無謀な介入派兵だった。同様の過ちを繰り返してはならない。「欧州情勢は、複雑怪奇なり」になっては遅いのだ。
8月18日、麻生太郎元首相が台湾で口にした「戦う覚悟」発言も、火薬庫に火のついたマッチを投げ入れるような妄言である。自ら「新しい戦前」をつくりだしてどうする。今は「平和構築の覚悟」こそ必要であり、そのための外交努力である。隣国と軋轢を生むだけでは、能無しと言うほかない。
8月22日には、南アフリカのヨハネスブルクでBRICS(ブラジル・ロシア・インド・中国・南アフリカ共和国)首脳会議が開催され、ロシアはラブロフ外相が出席、プーチン大統領もオンライン参加。サウジアラビアやイランなど6カ国が新たに加盟することで合意した。加盟申請は22カ国に及び、同数が興味を示しているとされる。今回の会議では、ドルに代わる新たな国際基軸通貨まで検討された。ポストWW2体制は、すでに崩壊を始めていると言って過言ではない。
それこそが世界情勢だが、日本は独立主権の回復を考えず、対米従属を深化させている。経済力がさらに低下するなか、産業基盤の強化ではなく、投資などのマネーゲームによる利ざや稼ぎ国家の路線を歩もうとしている。BIS(国際決済銀行)の規制によって財政規律を強化しようというのも本末顛倒だ。
アメリカンスタンダードに何でも合わせることで、日本経済が地盤沈下していく。日米半導体協定も不平等そのものだったではないか。我々は万邦共栄の精神に基づき、各国に和平を説くことを、さらに目指すと改めて宣言する。
(月刊「紙の爆弾」2023年10月号より)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
● ISF主催トーク茶話会:船瀬俊介さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 木村三浩
木村三浩
民族派団体・一水会代表。月刊『レコンキスタ』発行人。慶應義塾大学法学部政治学科卒。「対米自立・戦後体制打破」を訴え、「国際的な公正、公平な法秩序は存在しない」と唱えている。著書に『対米自立』(花伝社)など。