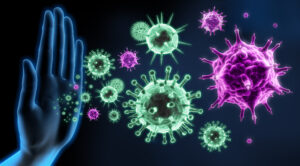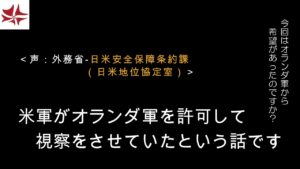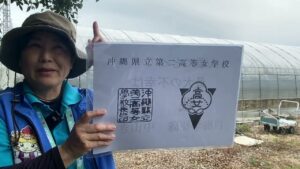ネオコンの理論家ロバート・ケーガンの論考を斬る:「トランプ独裁は不可避になりつつある。私たちはふりをするのをやめるべきだ」への批判
社会・経済国際政治「この記事は塩原俊彦氏のブログ『21世紀龍馬会』の12月4日付記事の転載です」
ネオコンの理論家で、「ワシントン・ポスト」の意見投稿欄の寄稿編集者を務めるロバート・ケーガンは、2023年11月30日付の記事「トランプ独裁は不可避になりつつある。私たちはふりをするのをやめるべきだ」を公表した。そこで、この論考について批判的に紹介したい。
ロバート・ケーガンの品性
その前に、まず、彼の人となり、品性について紹介したい。拙著『復讐としてのウクライナ戦争』で紹介したように、ジェフリー・サックスが2022年6月27日付で公開した、「ウクライナは最新のネオコン災害である」というタイトルの小論において、「米国は世界のあらゆる地域で軍事的に優位に立たなければならず、いつの日か米国の世界または地域の支配に挑戦する可能性のある地域の新興勢力、とくにロシアと中国に立ち向かわなければならない」を主要メッセージとする「ネオコン」(新保守主義者)の源流が説明されている。
私はこの拙著のなかで、つぎのように記述しておいた。
「このネオコンの源流については、1970年代にシカゴ大学の政治学者レオ・シュトラウスとイェール大学の古典学者ドナルド・ケーガンの影響を受けた数人の知識人のグループを中心に発生したとしている。前者は1937年に米国に移住したドイツ生まれのユダヤ人であり、後者はリトアニア生まれのユダヤ系で、幼少期に米国に移住した。ネオコンの指導者には、ノーマン・ポドレツ、アーヴィング・クリストル、ポール・ウォルフォウィッツ、ロバート・ケーガン(ドナルドの息子)、フレデリック・ケーガン(ドナルドの息子)、ヴィクトリア・ヌーランド(ロバートの妻)、エリオット・アブラムズ、キンバリー・アレン・ケーガン(フレデリックの妻)などがいる。」
このロバート・ケーガンの品性については、拙著『知られざる地政学』〈上巻〉の第5章 覇権国アメリカの煽動とエスタブリッシュメントの正体」において書いておいた。ニコラス・スカウ著『驚くべきCIAの世論操作』に登場するケーガンについて紹介したのである。少し長い引用になるが、サービスしよう。
「そこで、ニコラス・スカウ著『驚くべきCIAの世論操作』を紹介しておきたい。そこには、調査報道記者として名高いシーモア・ハーシュが、ホワイトハウスはいまに至るまで、ビンラディン殺害作戦は米国単独の企てであったと主張しつづけ、パキスタン軍の情報機関である軍統合情報局(ISI)トップの将軍たちには、奇襲作戦について事前に知らせていなかったとしてきたことについて、「しかし、それは虚偽であり、オバマ政権の説明に含まれる多くの点も同様である」と報じた話が紹介されている。
このスクープに対して、政権側の反論を最初に掲載したのが「CIAの忠実な友である『ワシントン・ポスト』紙だった」と、スカウは書いている。ハーシュの話は「まったくのナンセンス」と、匿名のCIA職員がのべたというのだ。ハーシュの記事が基本的に正しかったことはその後証明されている。つまり、「ワシントン・ポスト」は「仲間」のCIAを守るため、平然と「嘘」を垂れ流しつづけたのである。
1980年代のCIAとホワイトハウスによるメディア操作のもっとも顕著な例として、ニカラグアの反政府武装組織「コントラ」をめぐる話も紹介されている。このコントラをめぐる問題でスクープを書いたAP通信のロバート・パリーの話が実に興味深い。彼は1980年代半ばに、国家安全保障会議(NSC)の外交広報局(OPD、正式には国務省のラテンアメリカとカリブ海地域に関する外交広報局[S/LPD])のロバート・ケーガンと親しく話しているとき、彼がのべた内容をつぎのように書いている。なお、ケーガンはすでに紹介したようにネオコンの論客であり、「ワシントン・ポスト」のコラムニストを務めるまでになった人物だ。
「私はそうした話題を取材してみて、誇張されたり、正確ではないと判明したりすればそう書くわけですが、彼らとしては気に入らない。だから私はもう取り合わないようにしました。するとあるときケイガン(ママ、引用者注)がこう言ったのです。『その調子でやり続けるおつもりなら、われわれはあなたを問題視化(´´´´)せざるを得なくなりますね』と。さりげない口調でしたが、それが相手の本音でした。いわば手の込んだ情報管理作戦といったところですね。」
いわば、30年以上も前から、国家とマスメディアは「癒着」関係にあり、国家の指示通り報道することが慣例化してことになる。」
このように、ケーガンは、「当局」のためには、公然と「問題視化」によって、ジャーナリストを排斥・排除することを厭わない人物ということになる。「権力」に擦り寄るという目的のためには、手段を選ばず、情報操作など当然と考える人物ということになる。そんなネオコンだからこそ、大量破壊兵器開発というまったく根拠のない情報をもとに、イラク戦争をはじめさせたことを想起してほしい。
ケーガンの全体としての主張
まず、全体として、「トランプ独裁は不可避になりつつある。私たちはふりをするのをやめるべきだ」において、ケーガンが言いたかったことをのべておこう。
要するに、トランプ大統領が誕生すると、米国はトランプ独裁になる可能性が高い。ゆえに、希望的観測はやめて、厳しい現実を直視しようというのである。それは、安易な妥協やふりをするのをやめる主張となって提言されている。どうやら、トランプ独裁という「脅し」をアピールして、多くの読者に反トランプ感情を煽り立てようとしているかにみえる。だが、民主党については、その分裂を嘆くだけで、バイデン大統領候補の魅力については何も書かれていない。
雪崩を打ってトランプ支持へ
長い論考なので、順番にその内容を紹介する。
まず、現状において、トランプが共和党指名争いで圧倒的に優位に立っていることが示されている。RealClearPoliticsの世論調査平均(11月9日から20日までの期間)では、トランプはもっとも近いライバルを47ポイントリードし、他の候補を合わせても27ポイントリードしているというのだ。さらに、「彼は最新の世論調査のすべてでバイデン大統領と同数か上回っており、他の共和党の挑戦者たちが自ら表明した存在理由を剥奪している」と書いている。
ゆえに、ケーガンは、「何らかの奇跡が起きない限り、トランプは間もなく共和党の大統領候補となる」と指摘する。問題は、そうなることで、政治勢力図がトランプに有利な方向に、迅速かつ劇的に変化すると予想されることだ。これまで、共和党のエスタブリッシュメントたちは、トランプが有罪判決を受け、自分たちがトランプに対抗することなく、その方程式から排除されることを望んでいることを公言してきたが、トランプがスーパーチューズデーに勝利すれば、すべては終わり、雪崩を打ってトランプ支持が増加するというのである。「対抗馬として立候補している候補者の大半は、トランプ氏に向かって疾走し、トランプ氏の寵愛を奪い合うだろう」と予言している。
以下のケーガンの記述は、なかなか興味深い。
「トランプ氏が指名され、トランプ氏とバイデン氏の二者択一になったら、これまでむしろ果敢にトランプ氏に反対してきたウォール・ストリート・ジャーナル紙の社説はそうし続けるのだろうか?内輪もめはなくなり、外敵との戦いだけになるだろう。要するに、あらゆる方向からトランプ支持の津波が押し寄せるということだ。勝者は勝者である。そして、世界のあらゆる権力を行使する妥当な可能性がある勝者は、だれであろうと支持を集めるものだ。それが権力の本質である。」
こうなると、マスメディアもトランプにスポットライトを当てるようになる。それがますますトランプの追い風になる。
他方、民主党については、「分裂状態を維持する可能性が高い」とケーガンはみている。ジル・スタインとロバート・F・ケネディ・ジュニアはすでにそれぞれ第三者と無所属のキャンペーンを開始し、主にポピュリスト左派からバイデンに迫っている。ジョー・マンチン3世上院議員(民主党)がウェストバージニア州での再選を断念し、代わりに大統領選へのサードパーティ出馬を考えたことは、「壊滅的な打撃を与える可能性がある」とまで書いている。
そのうえで、「トランプ大統領の時代には、ウクライナへの本格的な侵攻も、イスラエルへの大規模な攻撃も、インフレの暴走も、アフガニスタンからの悲惨な撤退もなかった。トランプが適任でないことを、まだ信じていない人に説明するのは難しい」と指摘している。おそらく、この指摘は正しい。バイデン大統領であったからこそ、つまり、彼がケーガンの妻、ヴィクトリア・ヌーランドを国務省次官に呼び戻し、ネオコン的な好戦姿勢をロシアに示さなければ、ウクライナ戦争は起きていない可能性が高いのだ。彼女は夫と同じくネオコンであり、クリミア奪還のためにロシアと戦うことに何ら躊躇はなかったはずだ。
ケーガンは、トランプの法廷闘争が禍根を残す点についてのべている。裁判を利用して権力を誇示しようとするトランプは、裁判のテレビ放映を逆手にとって裁判所や法の支配といった既存の体制に歯向かう姿を見せつけることで、トランプの熱烈な支持者からより一層愛されるのだ。「彼はキングコングのように腕の鎖を試し、いつでも自由になれることを感じ取っているのだ」と、ケーガンは記している。
さらに、「裁判官たちは、共和党の推定候補者を法廷侮辱罪で刑務所に入れるだろうか?」と、ケーガンは問う。そうしないことが明らかになれば、法廷内のパワーバランスは、そして国全体のパワーバランスは、再びトランプに移る。裁判のもっとも可能性の高い結果は、司法制度がトランプのような人物を封じ込めることができないことを示すことであり、ついでに言えば、トランプが大統領になった場合の歯止めとして無力であることを明らかにすることだろう、とケーガンはいう。
こうした経緯を経て、トランプが大統領に選ばれると、米国はどうなるのか。
独裁化と復讐の連鎖
ケーガンは、「トランプ大統領の任期は独裁政権になるのだろうか?」と問い、「確率はかなり高い」と書いている。そこで問題になるのが「復讐」(vengeance)だ。「彼の復讐への深い渇望は、退役軍人の日の公約である「共産主義者、マルクス主義者、ファシスト、そして急進左翼の悪党どもを根絶やしにする」という言葉に垣間見ることができる」とし、彼らは、「私たちの国に害虫のように住みつき、嘘をつき、盗み、選挙で不正を働き、合法であれ違法であれ、アメリカとアメリカンドリームを破壊するためなら何でもする」というトランプの発言に、ケーガンはトランプの心に刻み込まれた深い恨みをみている。
さらに、不気味な指摘をしている。「結局のところ、復讐(revenge)しようとしているのはトランプだけではないだろう。彼の政権は、自分たちの敵のリストを持つ人々で埋め尽くされるだろう。彼らは、政府内の信頼できない人たちを「根絶やしにする」ことを唯一の、大統領に認可された使命と考える、「審査された」役人たちの断固とした幹部である」というのだ。「つまり、総統の欲望を先読みし、総統が喜ぶと思われる行為によって寵愛を受けようとし、その過程で自らの影響力と権力を高めるのである」という記述は、ヒトラーの再来を予言する内容になっている。
この復讐はおそらくメディアにも向けられる。「Fox Newsは彼らを擁護するのか、それとも非難を増幅させるのか」と問うケーガンは、「米国の報道陣は、トランプとその聴衆に迎合する組織とそうでない組織とで、現在と同じように分断されたままだろう」とみる。そのうえで、「支配者が報道機関を「国家の敵」だと宣言した政権では、報道機関は重大かつ絶え間ない圧力にさらされることになるだろう」とのべている。
ケーガンは、トランプによる復讐の連鎖が確実である事情をつぎのように説明している。
「トランプは、現政権が自分の再選を阻止するために司法制度を不正に利用したと主張し、間違いなくそう信じている。自分がすべての権力を手にしたら、同じことをするのが正当化されるとは考えないのだろうか?もちろん彼は、まさにそうすることをすでに約束している。自分に挑戦する勇気のある者を迫害するために、職権を行使するのだ。」
こうした安易な復讐劇こそ、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』で指摘したキリスト教神学に基づいている。
独裁へと漂流する米国
ケーガンは最後から二つ目の文で、「私たちは、集団的な臆病さ、自己満足、故意の無知、そして何よりも自由民主主義への深いコミットメントの欠如がもたらす結果から逃れられるような介入を依然として望みながら、独裁体制へと流れ続けている」とのべている。
この指摘は、その通りかもしれない。ただし、そこには、民主党が過去にもたらした不正や不道徳、ディスインフォメーション(意図的で不正確な情報)による情報操作などに対する何の指摘も反省もない。
「自由民主主義への深いコミットメントの欠如」を前提とする、つまり、無知な「とまどえる群れ」を前提とする、米国型の民主主義が本来もつ欠陥に対する反省もない。
あるのは、神に近いところに位置すると勝手に思い込んで、自分の利益になる政策を神との盟約(covenant)と偽って、使命として押しつけるネオコンや進歩主義的リベラリストの不誠実だけだ。トランプ独裁という「脅し」は、まさにこの「宣教師」的なやり口に基づいている。どうか、彼らのまやかしにだまされないでほしい。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。
ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)