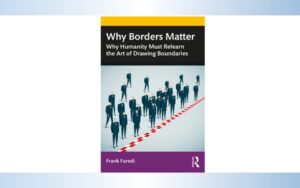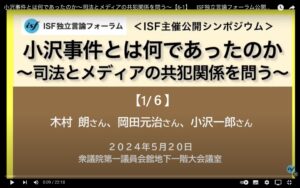「ロバート・ケーガン」の第二弾論考を批判する
社会・経済国際政治
「この記事は塩原俊彦氏のブログ『21世紀龍馬会』の12月11日付記事の転載です」
このサイトで「ネオコンの理論家ロバート・ケーガンの論考を斬る」を公表した。その後、ケーガンは2023年12月7日付のWPにおいて、「トランプ独裁: それを止める方法」をアップロードした。
彼は、その第一歩として、共和党内の反トランプ勢力を今すぐ1人の候補者に集約することだと主張している。その候補者がニッキー・ヘイリーであるべきなのは明らかで、彼女が親ウクライナ派だからではなく、残る候補者の中で明らかに最も有能な政治家であり、ドナルド・トランプに対抗できる可能性がわずかではあるがもっとも高いパフォーマーだからであると書いている。
だが、本来、ジョー・バイデン支持であるはずの彼のこの提案は、共和党候補者をバイデンに負けさせるための方法でしかないのではないか。トランプ独裁を止めようとするだけのために、ヘイリーを勝たせるために反トランプ候補者を一本化せよ、とケーガンが提案してみても、いまさら、トランプに勝てる候補者になりうるとは思わないし、民主党支持のケーガンにそんなことを言われたくもない。
ケーガンの偽善
ケーガンはいう。もし彼女が本気でトランプ大統領を阻止しようと考えているのであれば、トランプ大統領の多数派を切り崩す方法はひとつしかない。その方法とは、トランプ大統領の誕生が私たちの自由と民主主義、そして憲法に本当にリスクをもたらすものであることを、まだ耳を傾けることのできる共和党員に警告することである。こうケーガンは指摘している。
しかし、共和党のヘイリーへのアドバイス自体、何の意味があるのだろう。要するに、ケーガンはトランプ再選を恐れて、トランプ独裁を印象づけるために、反トランプの宣伝をしているだけではないか。ばかばかしいかぎりであり、彼の偽善を軽蔑する。
その偽善は、トランプの偽善を強調することで拍車をかけている。トランプは、「バイデン政権こそが真の独裁者であるのに対して、自分は民主主義の救世主だと主張する」ことで、あるいは、「バイデン政権は、主要な政敵を迫害するために司法制度を利用する独裁政権だと主張する」ことで、裁判の権威を失墜させ、共和党の有権者に、自分が司法制度の腐敗と乱用の被害者であると信じ込ませようとしていると、ケーガンはいう。
しかし、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』の「あとがき」に書いたように、米国のマスメディアが真っ当にバイデンの巨悪を報道していれば、バイデン当選などそもそもなかったのだ。その部分を引用してみよう。
「2022 年8 月、メタの最高経営責任者マーク・ザッカーバーグは、ジョー・ローガンのポッドキャストでインタビューに応じ、フェイスブックが2020 年の選挙中にバイデンの息子(ハンター)に関する記事を制限したのは、FBI の「誤報警告」に基づくものだったと語った。この報道とは、2020 年10 月14 日に公表された「ニューヨーク・ポスト」の特ダネ(https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introducedukrainian-biz-man-to-dad/)である。同紙が入手した電子メールによると、「長老バイデンがウクライナの政府高官に圧力をかけ、同社を調査していた検察官を解雇させる1 年も前に、ハンター・バイデンが父親で当時の副大統領ジョー・バイデンをウクライナのエネルギー会社の幹部に紹介したことが明らかになった」というのである。これは、「息子と海外取引について話したことはない」というジョー・バイデンの主張とは真逆のもので、ハンターの修理に出されたノートパソコンから回収された膨大なデータのなかに含まれていたものであった。
もしこの「事実」が大々的に報道されていれば、バイデンの当選はなかったとも言われる、いわくつきの問題に再びスポットがあてられていることになる(詳しくは拙稿「トランプ弾劾審議の源流はバイデン父子の腐敗問題 ウクライナ危機下のバイデン父子の動きを追うと見えてくる不都合な事実」[https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019092700005.html]を参照)。
公正を期すため、2022 年8 月26 日付のBBC(https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62688532)によると、問題のハードディスクは、トランプ自身の弁護士であるルディ・ジュリアーニからニューヨーク・ポスト紙に提供されたものだった。記事が掲載されてから1 年以上経ってから、ワシントン・ポストは独自の分析を行い、ノートパソコンと一部の電子メールは本物である可能性が高いが、大半のデータは「データのずさんな扱い」のために検証できなかったと結論づけたという。ニューヨーク・タイムズなど、かつて懐疑的だった他の報道機関も、少なくとも一部の電子メールは本物であると認めている。つまり、バイデンが真っ赤な嘘をついていた可能性がきわめて高いのだ。ゆえに、ザッカーバーグはローガンとのインタビューで、ニューヨーク・ポストの報道を抑えたことを後悔していることを認め、「ああ、そうだね。つまり、最悪だ」とのべたのであった。」
バイデンこそ「独裁者」
こんなインチキを公然と行い、バイデンを勝利に導いたマスメディアの罪は大きい。
さらに、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』や『ウクライナ戦争をどうみるか』に書いたように、ノルドストリームの爆破を命じたバイデンはまさに「独裁者」とのものではないのか。ここでも、米国の民主党系マスメディアはバイデンの悪事をまったく報道しようとしない。もちろん、証拠がない以上、私がここで書いているような断言口調で書くことは難しいにしろ、その疑いが濃厚であるとなぜ紹介しないのか。
共和党の分裂を提唱するケーガンの焦り
ケーガンは論考のなかで、共和党の分裂を促している。「憲法を守ることを今も信じている共和党の一派が、あからさまに憲法を破壊しようとし、大統領として再び憲法を破壊する意思を示している人物に断固として反対する「憲法共和党」として、そのように自らを表明したとしたらどうだろう」と提唱している。
バイデン政権の「悪」に目を瞑り、トランプだけの「悪」を言い立てるケーガンらしい提案だ。彼はそのうえで、「共和党は首尾一貫した正当な政党としては終わっている。トランプ独裁の党になるか、立憲と反立憲に分裂するかのどちらかだ」と指摘している。
この指摘もいらぬおせっかいにしか思えない。80歳を過ぎた「悪人」バイデンが世界を牛耳る恐ろしさについてまったく語らないまま、共和党について何をいおうと、それはいらぬおせっかい以外の何物でもない。
むしろ、こんな提案をするほど、ケーガンはトランプ再選を恐れおののき、焦っているように思えてくる。
おそらく、彼自身、あるいは、妻のヴィクトリア・ヌーランドがトランプの復讐の対象になることを恐れているためなのだろうか。ネオコンとして、世界中を紛争に巻き込み、数百万人を死傷させる事態を招いておきながら、裁判にもならない彼の主張など、まったく唾棄すべきものであると、私には思われる。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。
ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)