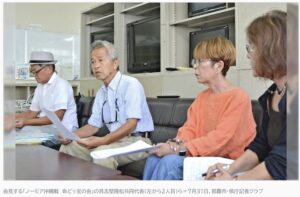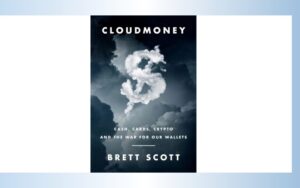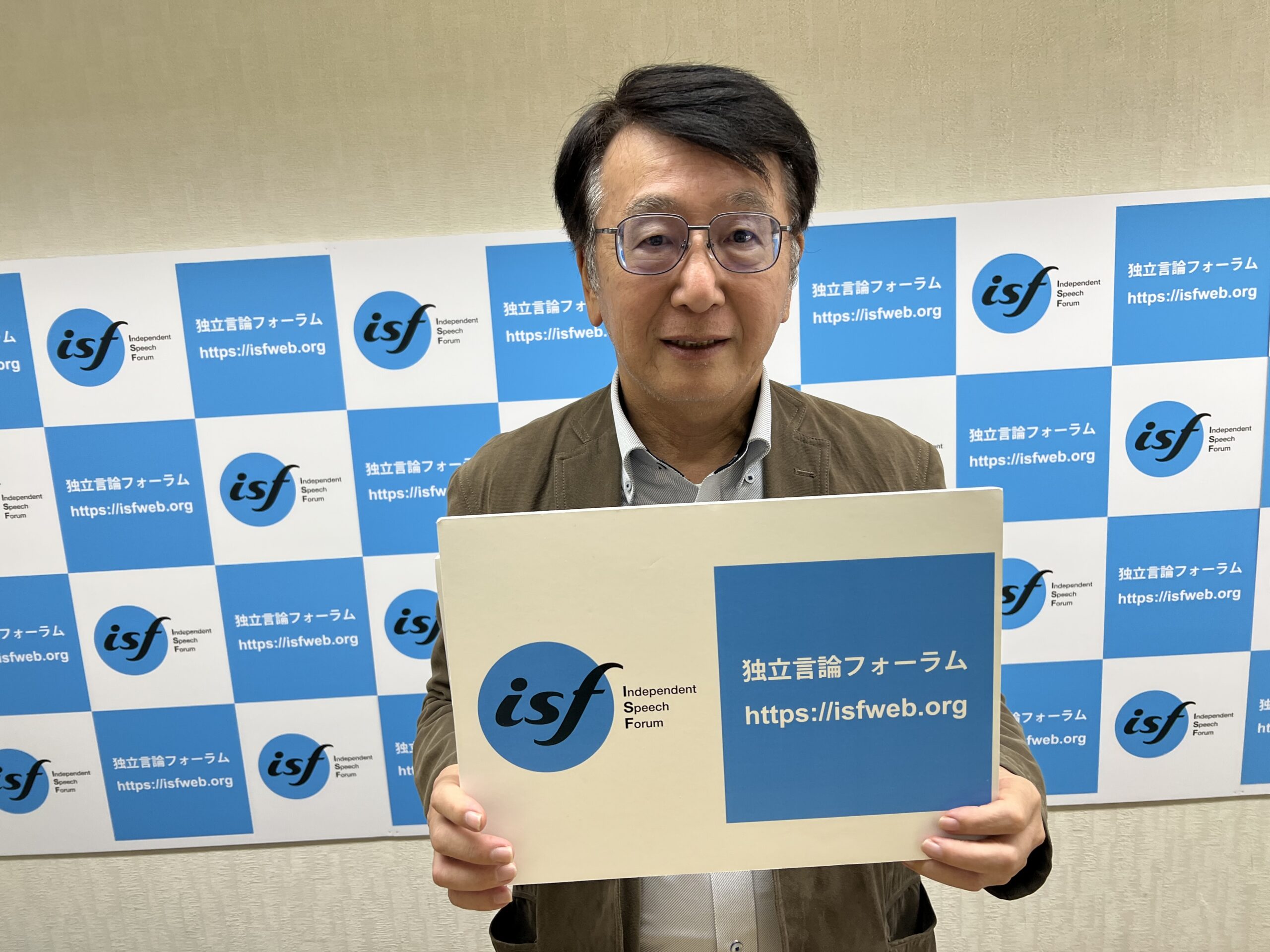「知られざる地政学」連載(19) アンチエイジングと地政学:未来を考える材料(上)
映画・書籍の紹介・批評国際

拙著『知られざる地政学』〈上下巻〉において、本当は、「老化」について論じる予定であった。だが、紙幅の関係で、これを断念した。それでも、老化をめぐって多少なりもとも資料を収集し、考察のための準備をしてきた。というわけで、今回は「アンチエイジングと地政学」に関連する問題について考えたい。
なぜかというと、地政学に老化の問題が深くかかわっているからだ。平均寿命が長くなれば、それだけで人口構成に大きな影響をあたえ、年金や保健などの社会保険制度の維持が課題となる。食糧確保問題の深刻化、就業年齢の変化はもちろん、所得格差による寿命の差が広がれば、社会の不安定要因になるかもしれない。こうした抜本的な変化は、人類の陸海空およびサイバー空間というすべての空間に大きな変動をもたらすことにつながる。
もっとわかりやすいのは、ウラジーミル・プーチンや習近平が100歳まで生きる世界を想像することだろう。米国の上院議員の高齢化(WPによると、現議会は、上院は史上最高齢[中央値65歳]、下院は史上3番目に高齢[中央値ほぼ58歳]である。上院議員のうち33人が70歳以上であり、50歳未満は9人しかいない。アメリカ人の年齢の中央値は38歳である)や、旧統一教会との関係やセクハラ疑惑で有名な故細田博之の例からわかるように、100歳を過ぎても、政治家が辞めない事態はもうすぐそこまで迫っているのだ。
ゆえに、老化にかかわる問題は、空間の支配に関心を寄せる地政学や地経学にとっても大きな関心事なのである。というわけで、今回は基本的な問題について論じるところからはじめたい。
老化は病気
2018年6月18日、世界保健機関(WHO)は現行の国際疾病分類(ICD)の第10回を改訂した第10回(ICD-11)を公表した。約30年ぶりの改訂だった。ICDは国際的に統一した基準で定められた死因および疾病の分類のことで、この改訂によって、これまでの「老人性衰弱」というコードに代えて「老齢」(old age)を意味するコードMG2Aが採用された。「老齢」は特定の病気ではなく、「一般的な症状」として分類されたことになり、「老齢」という診断を受けることが可能になったという(デビッド・A・シンクレア著『ライフスパン:老いなき世界』473頁)。
老いを病気とみる視線が育てば、アンチエイジング(抗加齢)医学が進みやすくなる。すでに、テロメア(染色体の活動的な先端部分にあるDNAの反復配列)の減少、エピジェネティックな変化(「エピジェネティクス」という言葉はギリシャ語の「epi」に由来し、ゲノムの「上」を意味する。エピジェネティクスは、ゲノムのDNA配列を変えることなく、ゲノムの機能を調節する可逆的なメカニズムである)、タンパク質恒常性の喪失、マクロオートファジー(微小自食作用、細胞が傷ついた内部構造を分解する)の無効化、栄養感知の調節解除、ミトコンドリアの機能不全、細胞の老化、幹細胞の枯渇、細胞間コミュニケーションの変化、慢性炎症などが老化因子に関連しているとみられている(「アンチエイジング医学(抗加齢医学)とは」を参照)。

フーコーに学ぶ
アンチエイジングを地政学に関連づけるとき、まず、思い浮かぶのは、歴史的変遷である。ミッシェル・フーコーは、「権力がいかなる手段を通じて行使されるか」に注目して、17世紀以来の主要な権力形態として、技術に注目しながら二つの極を指摘している。第一の極は、「規律を特徴づけている権力の手続き」である「人間の身体の解剖学的政治学」(解剖-政治学)であり、身体の調教、身体の適正の増大などを技術的に可能にしたこととの関連で発展した。一方、第二の極は、人口を「調整する管理」としての「人口の生に基づく政治学」(生-政治学)であり、繁殖、死亡率、健康の水準などを管理する技術の誕生とともに発展した。このふたつをつなぐ「権力」を「生-権力」とよぶ。
具体的には、近代以降、常備軍は他国の常備軍に対しては、解剖-政治学に基づいて、生死を賭けてこれを殲滅せんとするが、常備軍の内部においては生-政治学の立場から、保健衛生を重視し、感染症を予防する体制がいち早く整えられるのである。生-政治学の重視は、受刑者に対する苛酷な身体刑の大幅緩和につながったが、本当は、違法行為自体が身体への攻撃から財産の直接的詐取へと移ったことも関係している。
ここまでの話をわかりやすくいうと、「個人の生」と「人口の生」という生-権力に焦点をあてるフーコーの分析は、個人に主体性・主観性をもたらした近代化と深くかかわっている。だからこそ、フーコーは技術変化に注目するわけである。生-権力は服従者を「死なせることができる」という生殺与奪権をもった君主の権力から変化したもので、個人として主体的に生きることを余儀なくさせる主権国家の権力として現れる。つまり、人々を抑圧する権力から、人間を主体化する権力への移行である。その主権国家の権力は人口という全体を守るための衛生という考え方とともに生まれ、衛生は「人口=全体」と「個人=個体」に働きかける。そして、医療、医学の進化がその生-権力の働きを強化することになるのである。
フーコーの思想といま
私は、2021年6月11日に「論座」に公表した「民主主義の脅威という話:ハーバーマス、アガンベン、フーコーから読み解く」におて、フーコーの思想といまを重ね合わせて考察したことがある。そこで論じた内容を紹介しよう。
生-政治学は、公衆衛生を理由に、国民にワクチン接種を強制したり、健康診断を強いたりすることで、国民を生かすための権力を使って国民を抑圧するようになる。これは、国家が「社会的な身体がその生命を確保・維持・発展させる権利」を使って巨大な権力をもつことを可能にしたといえる。
そのために重要な役割を果たしたのが、「知識」であり、「科学」であり、別言すれば、「専門家」ということになる。そこで、フーコーは「権力-知識」という関連概念を分析し、「『真実』は、それを生産し維持する権力のシステムと、それが誘発する権力の効果と、それを拡張する権力の効果と、循環的な関係で結ばれている」と結論づけた(この点については、同じ「論座」における拙稿「日米ロで広がる陰謀論の裏側/上」で論じたことがある)。ここで、ニューヨーク大学の上級講師、ジェフ・シュレンバーガーが『アメリカン・アフェアーズ』に掲載した論文「我々はフーコーをどうやって忘れたか」のなかで、「フーコーは、現代医学の進化は、それが政治的に利用されてきたことと切り離して理解することはできないと示唆している」と指摘していることを紹介したい。
フーコーは1963年に出版された『クリニックの誕生』から1980年代初頭に行われた最終講義まで、バイオメディカル・サイエンスの政治的意味合いについて重点を置いていた。その結果、先進工業社会での国民の健康を監視・管理・最適化するためのさまざまの機関の広がりを指す言葉として「バイオパワー」という造語を生み出したり、出生率、長寿、公衆衛生、住宅、移民の問題などの問題に注目したりすることで、現代国家が対象者の生物学的生活(biological life)に全般に関与していることを示す「バイオポリティクス」といった言葉をつくり出したのである。「長寿」さえ、すでに「バイオポリティクス」のなかに入っていたことに注目してほしい。
問題は、こうした生-政治を支える知識、科学、専門家をどこまで信じるのかにかかっている。フーコーを素直に読めば、彼は科学を信じていなかったのであり、とくに科学が権力と結びつくことに強い警戒感をもっていた。したがって、シュレンバーガーはつぎのように記している。
「彼の研究が提示する立場からすると、政治的決定を「科学」に委ねることは単にもっとも優れた知識を持つ個人を責任者にすることではない。逆に、それは、権力の行使を劇的に再配置することを意味している。パンデミックの間、公衆衛生の専門家に決定権を委ねることは、国家の権限を劇的に拡大し、基本的な権利、特に言論や集会の自由を放棄することを必然的に伴うことになった。選挙で選ばれたわけではない保健当局の命令で、感染予防に反する可能性のあるニーズや価値観の一部が干されたのである。これは、このようなアプローチに合理的な議論がないと言っているのではない。問題は、このような政治手法が理性的な議論を完全に回避しようとするものであるということだ。
このような理由から、フーコーは民主的熟議の原則と現代の公衆衛生官僚制の間に根本的な緊張関係があると考えたのである。」
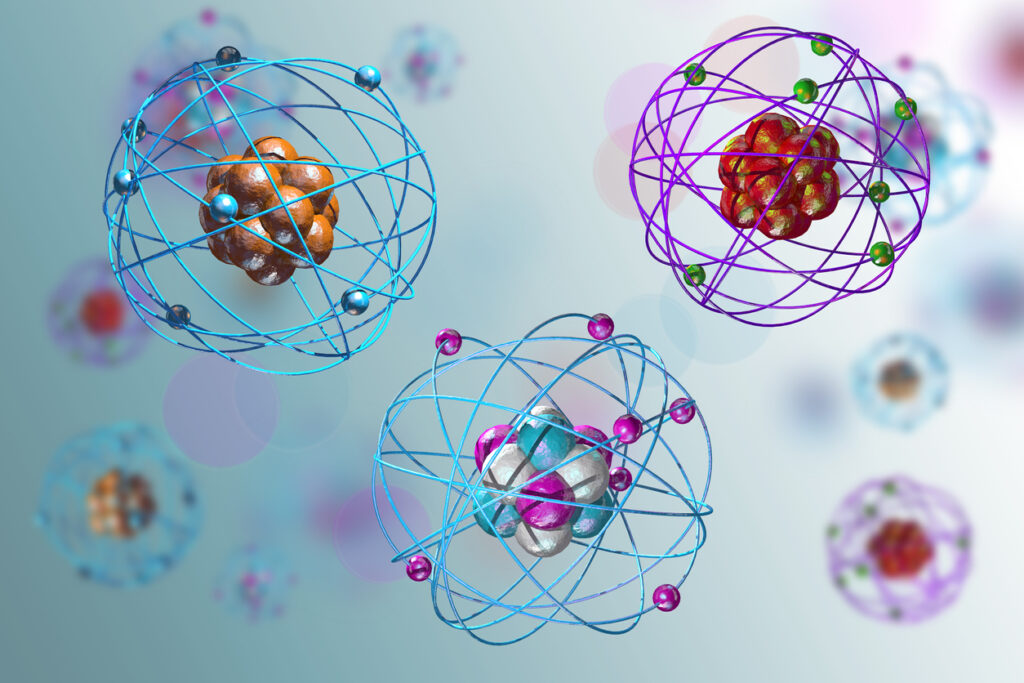
「分子政治学」
この論考での関心は、こうしたフーコーやシュレンバーガーの考察の延長線上で、アンチエイジングを主権国家の生-政治学と関連づけることである。そこで参考になるのは、「現代の生-政治学は分子政治学になった」(contemporary biopolitics has become molecular politics)と主張するニコラス・ローズの論考だ。
まず、分子政治学の源流に、「優生学」があることを認めなければならない。この優生学の歴史については、『優生学の歴史』が参考になる。重要なのは、1930年代に米国のカリフォルニアで盛んであった優生学がドイツに影響をおよぼしたという事実である。1933年までにカリフォルニアは他の全州の合計よりも多くの人々に強制的に不妊手術を施していたのであり、ドイツの国民社会主義ドイツ労働者党(ナチス)はこの不妊手術の実践的なノウハウを学んだ。ドイツ本国ではエルンスト・ヘッケルが優生学を推進したが、米国で優生学を広めたチャールズ・ダベンポートの影響下におかれていたと考えるほうが正しい。もう一つ忘れてならないのは、ジョナ・ゴールドバーグが『リベラル・ファシズム』で主張するように、1930年代にファシズムが進歩主義的運動と広範にみなされており、左翼の多数によって支援されていたという事実である。
ともかく、この優生学の「根」は、第二次世界大戦後、遺伝学に看板をつけかえることで生き残った。「遺伝学者たちは自らの過去を振り返り、病気の根源を探るという観点から遺伝学の問題空間を再構築した」と、ローズは書いている。遺伝学そのものが、大まかな社会的カテゴリーで考えることをやめ、病理と正常という誤解を招きやすい外見の下に、その根底にある決定要因、分子レベルでの遺伝子とその機能様式にまで踏み込もうとしたのである。それが、「分子政治学」の名前の元になっている。なお、『知られざる地政学』〈上〉の121~134頁において、スーザン・ライト著『分子政治学』について詳しく紹介している。つまり、「分子政治学」は重要な視角を提供している。
ローズは、1930年代、生物学は生命現象をミクロ以下の領域で可視化するようになったとし、「つまり生命は分子化されたのである」としている。この分子化は、単に分子レベルでの説明の枠組みの問題ではなかった。単に分子レベルでつくられた人工物を使うという問題でもなかった。それは、生命科学のまなざし、その制度、手続き、道具、活動の場、資本化の形態の再編成であったというのがローズの主張だ。
この分子政治学の延長線上に、ヒトゲノム解析が登場する。拙著『知られざる地政学』〈上〉において紹介したように、2000 年 6 月 26 日、当時のビル・クリントン大統領は衛星中継でトニー・ブレア首相とともに、世界で初めて全人類の遺伝暗号の「ワーキング・ドラフト」の作成を祝福するに至る。まさに、主権国家主導で、分子政治学がゲノムにまで手を突っ込んだ結果であった。10 年間で 20 億ドルの資金がヒトゲノムの DNA を構成する約 30 億個の塩基対の順序を解明するために使われた。ゲノムの研究の約 3 分の 1 は、非営利団体ウェルカムトラストからの資金提供により、英国の科学者によって完成され、残りは国立ヒトゲノム研究所所長のフランシス・コリンズ博士やセレラ・ゲノミクス社社長兼最高科学責任者のクレイグ・ヴェンター博士らによって成し遂げられたとされている。
コリンズ博士は、「ヒトゲノムの 97%を含む重複する断片のマップを開発し、このうち 85%の塩基配列を決定している」とした。だが、現時点からみると、彼らの研究成果はまったく不十分なものであったことがわかっている。例によって、主権国家は「嘘」をつき、そのカネを使って国家にすり寄る科学者によって、「嘘」が増殖・拡散するのである。
その後、ヒトゲノム・プロジェクトは予定より2 年以上早く、2003 年 4 月、ヒトゲノムの完成配列の作成を終了したとしてプロジェクトの終結を宣言したが、これもまた、まったくの「勇み足」であったようにいまでは思われる。完成配列とは、1 万塩基に 1 個以上の誤りがなく、配列がほぼ連続し、ごく少数の短いギャップがあることを意味し、配列は、ゲノムの「ユークロマチック部分」(遺伝子が存在する部分) の 99 パーセントをカバーし、99.99 パーセントの精度をもつとされた。
拙著『知られざる地政学』〈上〉(175頁)には、以下のように書いておいた。
「だが、その 99%という数値は遺伝子が存在する部分だけに適用されたものにすぎない。染色体の両端を覆う「テロメア」や、2 本の腕をつなぐ「セントロメア」など、繰り返しの多い、つまり配列が難しいDNA はすべて無視されていたのである。テロメアは、細胞が分裂するたびに縮小し、分裂の可能な回数が制限されるため、老化の原因となる。」
「知られざる地政学」連載(19)
アンチエイジングと地政学:未来を考える材料(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
●ISF主催公開シンポジウム:鳩山政権の誕生と崩壊 ~政権交代で何を目指したのか~
●ISF主催トーク茶話会:斎藤貴男さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)