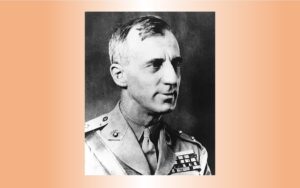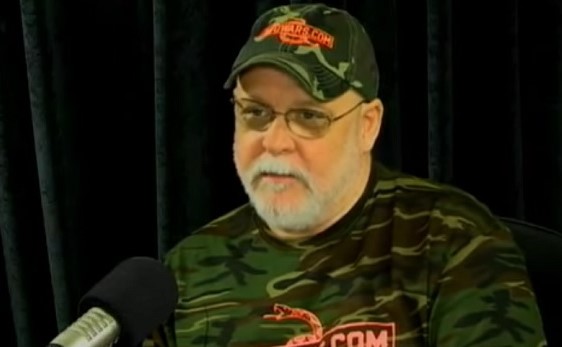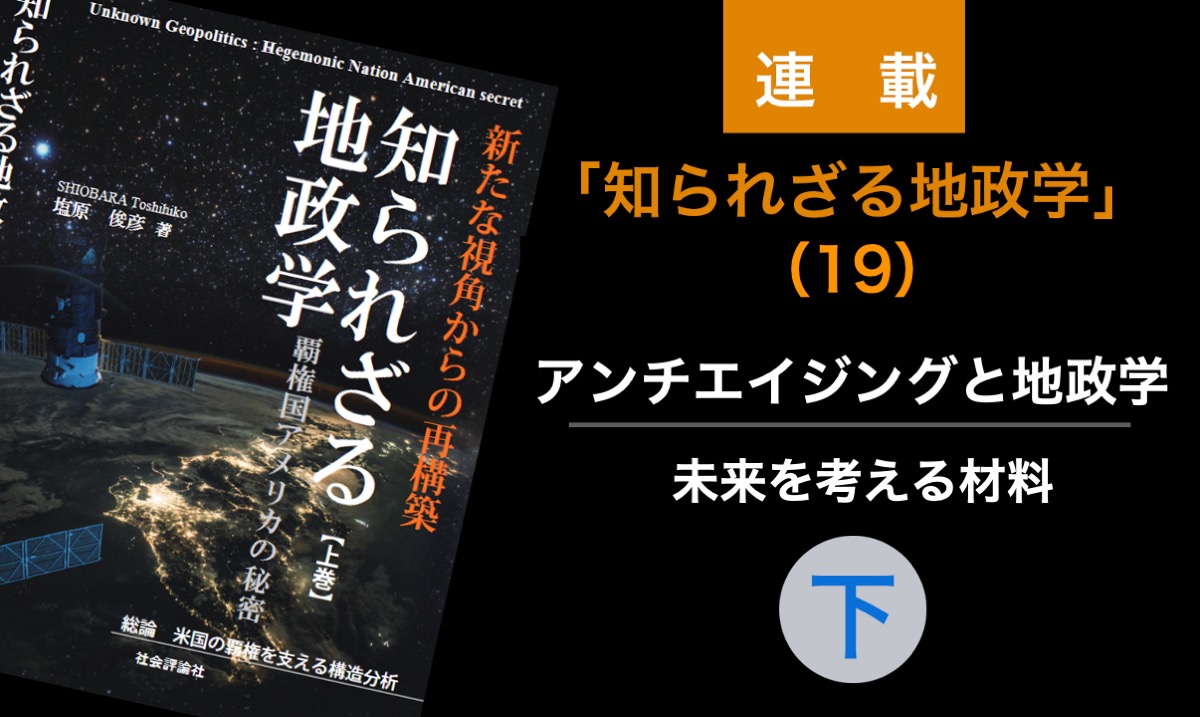
「知られざる地政学」連載(19) アンチエイジングと地政学:未来を考える材料(下)
映画・書籍の紹介・批評国際
「知られざる地政学」連載(19)アンチエイジングと地政学:未来を考える材料(上)はこちら
「機能重視」という視点
もう一つだけ補助線を引いておきたい。それは、「機能重視」という視点が19世紀以降の生物医学を「機能的/機能不全」という二項対立に導いているという問題だ。道徳的、文化的、技術的な価値をはらんだ「正常」と「病的」は、健康と病気に関する科学的な認識を再創造し、治療的正常化の新時代を切り開いたと説いたのは、ジョージ・カンギレムである(G. Canguilhem, On the Normal and the Pathological. Dordrecht, 1978, & Ideology and Rationality in the History of the Life Sciences, 1988を参照)。
スティーブン・カッツとバーバラ・マーシャルによる論文は、「自然と文化の関係について、何世紀にもわたって哲学的、神学的、人類学的、経済学的なドグマが対立してきたにもかかわらず、自然は人間の改変の限界を超えているという考えは不変だった」と指摘している。これは、伝統的に、生命、健康、フィットネス、規範性、身体、老化など、自然を中心とする一連の概念が、自然を、変えることも、製造することも、逆戻りさせることもできないものとみなしていたことに対応している。いわば、自然は「現実」であり、その上に、対立し、しばしば抑圧する「外部として文化」が位置づけられてきたのである。
しかし、この自然のなかに、「機能不全」(dysfunction)を見出すことで、器官の性能が理想的な機能状態とどの程度一致することが期待できるかを決定するという近代医学の視角が生まれる。
老化の場合、人間は自然に老いるだけとみなせば、それだけのことだ。だが、年齢に相応した、すなわち、標準に比較した身体機能の低下に注目すれば、そこに「正常」ではない「病的」なものを見出せるようになる。こうして、すでに老化さえ病気とみなすようになっている。
「生物学的年齢」
この機能重視の視角は「生物学的年齢」なるものをクローズアップさせている。細胞の健康状態をみることによって、その人の生物学的年齢を数値化することが真剣に研究されるようになっている。
なかでも、2013年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のスティーブ・ホーバス教授(人類遺伝学・生物統計学)が、前述した「エピジェネティクス」という新分野に基づく「時計」を使うことを提案し、大きな前進がもたらされた(2023年12月19日付「ニューヨーク・タイムズ」を参照)。DNAは、一生の間にさまざまな遺伝子をオン・オフする分子変化を蓄積する。そこで、ホーバスは、何千人もの人々のこれらの変化を分析し、それらが年齢とどのように相関するかを決定するアルゴリズムを開発したのである。
ただし、この「エピジェネティック・クロック」は、個人ではなく、大規模な集団を評価するために設計されているため、個人の生物学的年齢と同一視することはできない。ただ、血液や唾液を分析し、エピゲノムの変化を集団の平均値と比較することで、生物学的年齢に近いものを算出して、健康を考える契機になるというのである。
こうして、機能重視は、機能を通じた「差異化」によって、ビジネスとの親和性をますます強めつつある。
「老年医学」(geriatrics)の発展
ここで示した巨視的な見方を前提にしたうえで、今度は老化そのものを扱う学問について考えてみよう。
「老い」をめぐる医療は、「老年医学」(geriatrics)として、国家と結びつきながら発展してきた。ジョン・E・モーリー著「老年医学の歴史」によると、近代の老年医学は、イグナーツ・レオ・ナッシャー(Ignatz Leo Nascher)による「geriatrics 」(老年病学ないし老年医学)という言葉の発明によって20世紀に誕生した。geriatricsは、アテネの立法評議会(ゲロウシア)を運営していた60歳以上の男性グループ「ゲロンテ」に由来する。あるいは、ギリシャ語で「老人」を意味するγέρων geronと、「治療者」を意味するιατρός iatrosに由来するという。なお、1908年にノーベル生理学・医学賞を受けたイリヤ・メチニコフは、老化を科学する「ジェロントロジー」(gerontology)という誤った言葉をつくった。ジェロンテはフランス語で「人間」を意味しており、老化とは何の関係もない。「ジェラトロジー」(geratology)が適切な言葉であると、モーリーは書いている。
近代老年医学は英国で発展する。英国人女性、マージョリー・ウォーレンは近代老年医学の発展に大きな功績を残した。彼女の革新のなかには、環境を整え、積極的なリハビリテーション・プログラムを導入し、高齢者側の意欲を高めることを強調することがあった。1946年にアムルリー卿とスターディー医師が高齢者と慢性病患者のケアについて国会下院で演説したのを機に、高齢者医療が国民保健制度の一部に組み込まれるようになる。こうして、1959年、「高齢者ケアのための医療学会」(Medical Society for the Care of the Elderly)から名前を改めた「英国老年医学会」(British Geriatrics Society)が設立された。
これに対して、米国では、1942年6月に「アメリカ老年医学会」(American Geriatrics Society)が組織された。最初の年次総会は1943年に開催される。1953年には、Journal of the American Geriatrics Societyが刊行されるようになる。
他方で、老年医学は民間基金からの支援に依存しており、1945年に80人のメンバーにより、「アメリカ老年学会」(Gerontological Society of America)が設立された。Journal of Gerontologyは1946年に創刊されたが、1988年には会員の多様な関心を代表する四つのセクションに分割される。1995年には二つの表紙に分割され、生物学と医学が1冊、心理学と社会科学がもう1冊となった。
1978年には、「米国老年精神医学会」(American Association of Geriatric Psychiatry)が設立される。1950年には、第1回「国際老年学会議」(International Congress of Gerontology)が、ベルギーのリエージュで開催される。14カ国からの出席者があった。この第1回会議では、老化の定義、老化と病気の二分法、老化の社会的側面に焦点が当てられた。こうして、老年医学は官民を巻き込みながら地歩を固めたのである。
米国アンチエイジング医学アカデミー(A4M)の誕生
注目されるのは、1992年になって、12人の医師が「米国アンチエイジング医学アカデミー」(American Academy of Anti-Aging Medicine, A4M)を設立し、老化を治療可能な状態や病気としてとらえることに専念したことである。アンチエイジング(抗加齢)医学の分野は、米国専門医制度委員会(ABMS)や米国医師会(AMA)のような確立された医療機関には認められていないが、非営利団体でありながら、ウェブサイトを使ってさまざまなアンチエイジング製品やサービスを宣伝しており、なかでも物議を醸しているヒト成長ホルモン(hGH)は有名である。
2006年に公表された「アンチエイジング文化、生-政治、グローバリゼーション」という論文では、「現在、A4Mは世界65カ国に1万2500人以上の会員を擁している。日本、スペイン、フランス、イタリア、ベルギー、シンガポール、タイ、韓国、メキシコ、ブラジル、アラブ首長国連邦など、さまざまな国で定期的にセミナーや会議、研修プログラムを開催している」と紹介されている。
興味深いのは、先に紹介した老年医学の権威(AMA、アメリカ老年医学会、アメリカ老年学会)とA4Mとの対立である。とくに、米国医師会(AMA)の一部の代表者は、アンチエイジング医療介入のためのヒト成長ホルモン(hGH)の使用は違法であり、犯罪であるとまで主張している。この対立の背後には、商業的利益によって動機づけられたA4Mへの根強い警戒感がある。ただし、私からみると、老年医学の権威の側の正当性にも疑問がある。国家や民間基金の支援で研究を行っている以上、その見解は決して中立的ではないからである。
未来を展望する格好の材料
このようにみてくると、ここで紹介した生-政治学の分子政治学への変化こそ、今後の世界全体の未来を展望するための格好の研究材料になるのではないかと思えてくる。実は、アンチエイジングのための医療はすでに進展している。
たとえば、「メトホルミン」と「NMN」(ニコチンアミド・モノヌクレオチド)の摂取がアンチエイジングに効果がありそうなことを、最初に紹介したシンクレアが『ライフスパン:老いなき世界』のなかで書いている。「ラパマイシン」や「セノリティクス」(老化細胞除去薬)と呼ばれる新しいタイプの薬剤もある。ただし、こうしたものはそう簡単に入手できない。ゆえに、サプリメントなどのかたちで販売されることになる(その結果、いんちき商品が出回っていることについては、2023年11月6日付の朝日新聞を参照してほしい)。そうした動きをA4Mなどは喜んでいるに違いない。
こうして所得格差が寿命格差となって、大きな社会問題となることも、すでに予測の範囲内にある。たとえば、「ロンドンの裕福な地域で生まれた赤ちゃんは、グラスゴーよりも12年長生きであることが新たな調査で明らかになった」と、2023年3月21日付の「デイリーメイル」は報じている。平均寿命がもっとも長い20地域のうち18地域がロンドンと南東部である一方、平均寿命が最も短い20地域のうち10地域がスコットランドにあるというのだ。
あるいは、2023年10月3日付の「ワシントン・ポスト」の長文記事「慢性疾患の蔓延が私たちを早死にさせる」は、「アメリカにおける格差の拡大を示す最良のバロメーターは、もはや所得ではない。生命そのものである」と書いている。米国では富の不平等が拡大しているが、同紙は、死亡格差(裕福な地域社会と貧しい地域社会との間の平均余命の差)が何倍にも拡大していることがわかったという。「1980年代初頭には、最貧困層の人々が毎年死亡する確率は9%であったが、この10年間でその差は49%に拡大し、新型コロナウィルスに襲われたときには61%に拡大した」と指摘している。
こうした現実は将来、世界をめぐる支配関係にどのような影響をおよぼすのだろうか。地政学はこの問題にも無関心ではいられない。何しろ、地政学は空間だけでなく、時間を超えた視点からの分析を課題としているからである。
残念ながら、こんな視角から地政学を語れる日本の研究者はほとんどいない。その出発点となるのが拙著『知られざる地政学』〈上下巻〉なのであると書いておこう。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
●ISF主催公開シンポジウム:鳩山政権の誕生と崩壊 ~政権交代で何を目指したのか~
●ISF主催トーク茶話会:斎藤貴男さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)