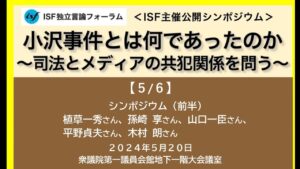「アジアでは日本に従え」──対米従属という国体護持のために(後)
安保・基地問題2.軍事力を増強し、既存秩序をリードする日本
・アメリカを巻き込む
中国が急速に力を付け、相対的に米国が力を落としている。トランプ時代には「米国第一主義」であったし、バイデン政権でも内政は混沌としている。
日本の安保関係者は、「なんとかアメリカに、東アジアに対する現状の関与を維持してもらいたい」とのスタンスを前面に出している。日本の外務・防衛官僚らからは「米国をどう巻き込むかが重要」という声が次々聞こえてくる。従来の「米国が日米協力の『青写真』を描き、日本がその『宿題』をこなしていく──」そんな構図は、大きく変わりつつある(『朝日新聞』20年7月27日付。佐藤武嗣朝日新聞編集委員)。
中国からの侵攻などの際にアメリカからの協力を得るため、「日本はアメリカの安全保障政策とりわけアジア太平洋戦略への『協力』をこれまで以上にアピールする必要に迫られて」いると評される(原彬久『戦後日本を問いなおす』ちくま新書)。
この10年、日本自らの軍事力を高める取り組みが二重にも三重にもなされ、米軍と自衛隊の一体化が可能な限り進められてきた。その代表例としては安保法制の制定や敵基地攻撃能力の保持に向けた動きなどがあげられる。
安倍首相(当時)は安保法制成立後の国会において、安保法制とアメリカの関係について、「守り合える同盟となり、その絆を一層揺るぎないものとした」と語った。また、敵基地攻撃能力の推進についても、首相辞任直前に発表した談話で、「助け合うことのできる同盟はその絆を強くする」と日米同盟の強化をその推進理由の一つとして上げている。

Kagoshima, Japan – October 29, 2014 : Democratic Party of Japan poster with the Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, at the street in Kagoshima, Kyushu, Japan.
「米国の力の相対的低下を自衛隊が補う目的での日本の軍事力強化」という意味に加え、「日本の軍事力強化により米国をこの地域に巻き込む」との趣旨の発言が相次いでいる。例えば、安倍政権で内閣官房副長官補(外政担当)を務めた兼原信克も、「米国が公平な同盟であると考える水準まで防衛費を増やさなくては、いずれ米国も日本を見捨てるであろう。防衛費をGDP比2%、すなわち10兆円への増額を早急に実現するべきである」(「中国の軍拡念頭に、日本の「抑止力」向上を:外交・安全保障問題での課題(nippon.com)」兼原信克)とその狙いをストレートに表現している。
佐々江賢一郎元駐米大使も、メディアインタビューに答えて、敵基地攻撃能力支持の発言をし、その上で、米中対立下の日本の役割について「米国の自己回復力を待ちつつ、日本としてできる努力をする」と説明している(『朝日新聞』20年7月27日)。
米国を巻き込むための日本の「努力」の他の代表例には「自由で開かれたインド太平洋構想(FOIP)」がある。日本政府はFOIPを日本が提唱したとして積極的に推し進めており、トランプ大統領からも同意を取り付け、その後、バイデン政権においても、FOIPはQUADと共にインド太平洋地域の米国の政策の中心に据えられるに至っている。
この「自由で開かれたインド太平洋構想(FOIP)」の発案者である外務省の市川恵一北米局長は、アメリカがFOIPを支持することの重要性を、こう指摘している。「アメリカは、基本的に内向きな国でもあります。インド太平洋地域への関与を維持、確保していくのは非常に大事なことで、この地域に関心を持ってもらうよう、うまく導いていくのが日本の役割だと思っています」(NHK政治マガジン「自由で開かれたインド太平洋誕生秘話」)。
安保法制も敵基地攻撃能力も、FOIPも、これらはみな拡張主義の中国や核・ミサイル開発を進める北朝鮮に対応するための安全保障政策であるが、そこには「米国をこの地域に巻き込むために積極的に日本が動かねばならない」という強い意識がある。
・日本のリードを必要とするアメリカ
このような日本の努力が認められて、冒頭の「アジアでは日本に従え」という論調が出てくることになるのである。「アジアでは日本に従え」というのは、前述したとおり、トランプ政権時代のアジアにおける米国の空白を日本が代わりに埋め、「対立のステータス・クオ(現状)維持のための外交」を日本がリードしてきたことに対してなされた評価である。
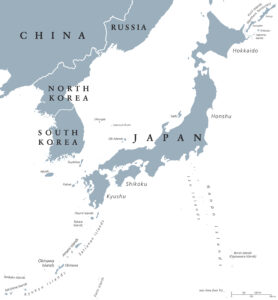
Korean peninsula and Japan countries political map with national borders and islands. Nations in East Asia. English labeling and scaling. Gray illustration on white background.
この形の日本への評価を最もよく表すのが、日本でよく知られる「アーミテージ・ナイ報告書」である。アーミテージ・ナイ報告書とは、米知日派による日本に対する提言書であり、「日本外交の教科書」と言われる程の強い影響力を持ってきた。執筆者共同代表はリチャード・アーミテージ元国務副長官とジョセフ・ナイ元国防次官補であるが、従来の外交の中で影響力をもってきた執筆陣は、トランプ氏をその登場以来こぞって批判し、共和党支持者であってもバイデン氏支持を表明してきている。
バイデン大統領就任前夜の2020年12月、第五次となるアーミテージ・ナイ報告書が発表された。この時期に発表されたのは、新政権のとる道を示し、具体的政策に影響力を及ぼすためである。
第五次報告書は、日米同盟最大の課題を中国と言い切り、台湾について日本にさらなる政治的・経済的な関わりを求めた。日米の防衛協力をこれまでの「相互運用」から「相互依存」のレベルにまで高めよとし、反撃力およびミサイル防衛をどのように追求するかが日本にとっての直近の試練であるとした。また、従来通りGDP比1%の日本の防衛費を問題視している。他、国際経済秩序の刷新、新技術分野における国際基準の設定など、様々な問題について日米同盟が核になるべき等とも訴えている。
同報告書の提言の詳細については別稿に譲るが、この第五次報告書全体からにじみ出る「国際政治の現状」が興味深い。
第一に、米国の減速傾向と日本に頼らねばならない状況がよく表れている。タイトルから「2020年の米日同盟~グローバルな課題と対等な同盟」と題するこの第五次報告書は、日本を持ち上げ、「歴史上初めて日本が米日同盟を主導するか、そうでなくとも、日米が平等な立場にある」と述べ、積極的に日本を「対等」と呼んでいる。この点が決定的に新しい。
具体的には、米国の抜けたTPPをまとめ、FOIPを進めてきた安倍首相を高く評価している。この報告書での「対等な同盟」との評価を受け防衛大学校の神谷万丈教授は、「はるけくも来つるものかな」とその感慨を産経新聞に寄稿している程である(産経新聞2020年12月31日)。
確かに、第一次報告書(2000年)では、日本に集団的自衛権の行使が認められていないことが同盟の制約であるなどと述べ、日米同盟が日英同盟のような特別な関係になることを求めていた。その後、日本は軍事力を拡大し、安保法制の整備や武器輸出三原則撤廃など大きく方向を変化させてきており、「20年かけて彼らの期待に追いついた」。そんな気持ちになった安保関係者は日本に多いだろう。
第五次報告書は日本に日米同盟をリードするよう求め、「歴史上、これほどまでに日米が互いを必要としあっている時はない」と記している。しかし、戦後、日本政府は一貫して米国を必要としてきたのであって、ここでの初めての現象は、米国が日本に力を借りねばならなくなったということである。
この米国の傾向は、その後のバイデン政権の政策にも如実に表われ、予算難やコロナ禍に苦しみ、不安定な内政に対応を迫られるバイデン政権の対中政策は「同盟国との連携以外に存在しない」と評されるほどである。
・アメリカに代わって「ハブ」になる
第二に、この第五次報告書からは、米国の力の低下の結果、これまで米国一国でアジアの国々に影響を及ぼしてきた既存の米覇権体制の維持が困難になっている様子が手に取るように分かる。従来、米国は、日米同盟、米韓同盟など二国間の同盟関係やパートナー関係を使ってアジア地域に影響力を及ぼしてきた。米国がその中心(ハブ)となり各国と線でつながる(スポーク)ことから、ハブ・アンド・スポークと呼ばれる。
しかし、この報告書には、日本の経済力・軍事力などを利用しながら、インド太平洋地域において彼ら米知日派の希望する国際秩序を維持しようとする考えが表れている。また、米国の対アジア政策では多国間地域機構を重視してこなかった従来の傾向をシフトし、急激な対外積極策に出る中国への対策として、ASEAN地域フォーラム(ARF)等の地域ネットワークの強化も提言している。この第五次報告書の発表シンポジウムでも、東南アジアとの関係強化が極めて重要との指摘がなされていた。
ハブ・アンド・スポーク型の「後退」ともいえるこの現象や、さらには、日本など同盟国を利用してその「後退」を補完しようとする姿勢については、米国の知日派があちこちで発言している。
例えば、バイデン政権におけるアジア担当者として最高位についたカート・キャンベル氏(国家安全保障会議(NSC)インド太平洋調整官)も、就任直前の論文で、アジアにおけるパワーバランスを回復するためには、同盟関係を深めながら、「地域諸国間の新たな軍事・情報パートナーシップを促進することで、ハブ&スポーク型の従来の地域同盟システムを『タイヤ』でつなぐべきだろう」と述べている(「アジア秩序をいかに支えるか─勢力均衡と秩序の正当性(How America Can Shore Up Asian Order ―A Strategy for Restoring Balance and Legitimacy) カート・M・キャンベル、ラッシュ・ドーシ共著」 Foreign Affairs Report 2021年2月)。
なお、マイケル・グリーン氏(ブッシュ政権の国家安全保障会議(NSC)アジア上級部長)も、「中国の増加する野望とバランスオブパワー(勢力均衡)の移行に伴い、安全保障においては、今日、地域に表れつつある安全保障システムにおいて、日本のような鍵となる同盟国には各国自身がハブ(中心)になることが求められている」と述べ、日本がフィリピンなどの東南アジア諸国へ防衛協力等を行っていることを高く評価した。
そして、「米国の伝統的なハブ・アンド・スポークは良い方向に変化をしている」と日本が東南アジア諸国の中心となって地域を率いることに歓迎の意を示した(Suga in Southeast Asia: Japan’s Emergence as a Regional Security Hub, Michael J. Green and Gregory B. Poling, 2020年10月)。グリーン氏は、第五次までの全てのアーミテージ・ナイ報告書の執筆に参加しており、日本への強い影響力をもつ米知日派である。
この点、確かにトランプ政権はアジアを軽視し、例えば東アジアサミットも欠席を続けて、東南アジア諸国からの批判を受けた。他方、日本は、近年、ASEAN(東南アジア諸国連合)やASEAN加盟国との関係を深め、防衛協力をすすめてきている。
例えば、2016年には日ASEANの防衛協力の指針として「ビエンチャン・ビジョン」を発表(19年に「ビエンチャン・ビジョン2.0」)しているが、これは、日本の防衛省が展開する防衛外交の「ビジョン」としては初とも説明されているもので、能力構築支援、防衛装備品移転、技術協力、訓練・演習などの実施を謳っている。
ハイレベルの安全保障対話、各軍司令官の実務者会議、「日・ASEAN乗鑑協力プログラム」等がASEAN各国との間で続けられている。また、防衛装備品・技術移転でもASEAN諸国を対象に力を入れており、ODAによる巡視船の供与、海上自衛隊の演習機の有償貸与やヘリの中古部品、器材の無償供与なども行われている。
ASEAN諸国自体は米中の狭間に挟まれ、極めて難しい立場に置かれている。中国との間に南シナ海の領土問題を抱え、他方、経済的には日本以上に中国に頼っている状況にある。しかし、この米中対立が激化する現状において、「自分たちが巻き込まれかねない戦争を起こしてくれるな」との意識が強く、中小国ならではの米中両にらみの強かなバランス外交を行っている。
米中ともにASEAN各国を自陣営に取り組むべく相当な働きかけを続けてきているが、「Don’t make us choose(米中いずれか選ばせるな)」(シンガポールのリー・シェンロン首相)と叫ぶASEAN諸国には過度な圧力はかけられない現状にある。米英豪の軍事同盟AUKUSの設立が発表された際にもASEAN諸国からは懸念が表明された。
他方、日本からの働きかけも功を奏し、実際、ASEANの国々からの日本の評価は高い。世論調査での「米中以外の第三国協力を求めるとしたら」という問いに対し、「日本を選ぶ」という結果が他国を抜いて高く出ている。米国からすれば、米国に代わって米陣営の代表としてASEANに働きかけてくれる日本の存在は大変に貴重である。
「(スポークをつなぐ)タイヤ」あるいは「日本がアメリカに代わるハブ」という点ではASEANへの働きかけに限られない。日本はFOIPを自らの最大の外交指針として推し進め、日米豪印の軍事同盟であるQUADにも積極的である。米国が関わらない場面でもオーストラリアとの防衛協力を進め、2022年1月には日米地位協定に相当する日豪「円滑化協定」も署名に至っている。
近い将来、第六次アーミテージ・ナイ報告書が出されることになれば、このような日本のイニシアティブが再び大歓迎されるに違いない。
 猿田佐世
猿田佐世
新外交イニシアティブ(ND)代表、弁護士(日本・米ニューヨーク州)。米議会などで政策提言を行うほか、国会議員等の訪米活動を企画。近著に『米中の狭間を生き抜く─対米従属に縛られないフィリピンの安全保障とは』。