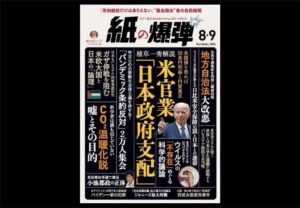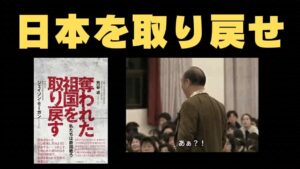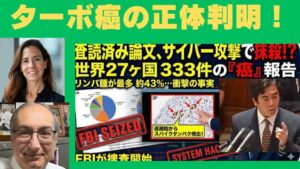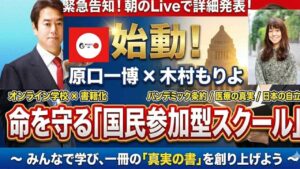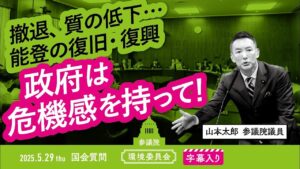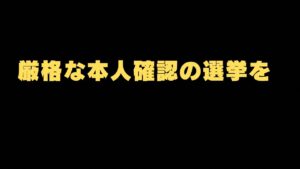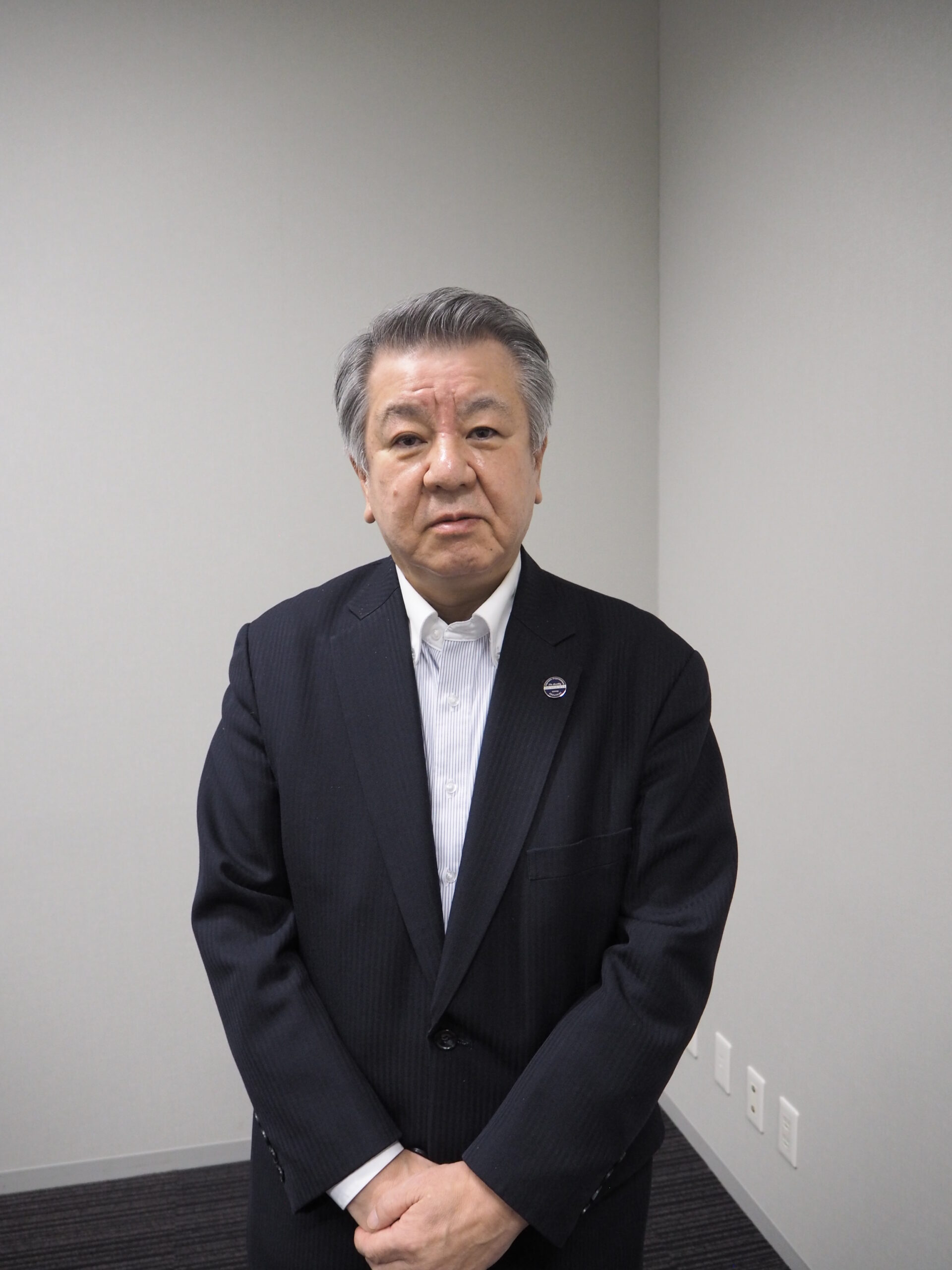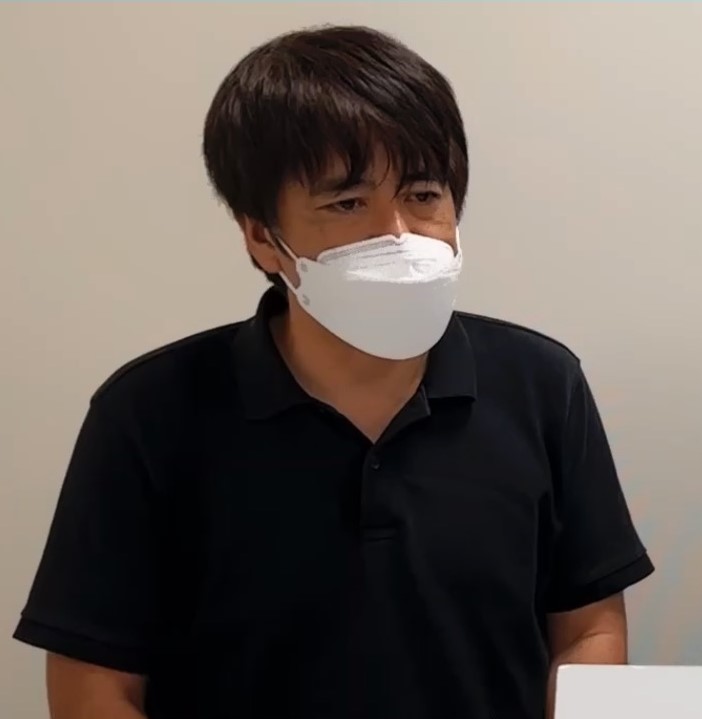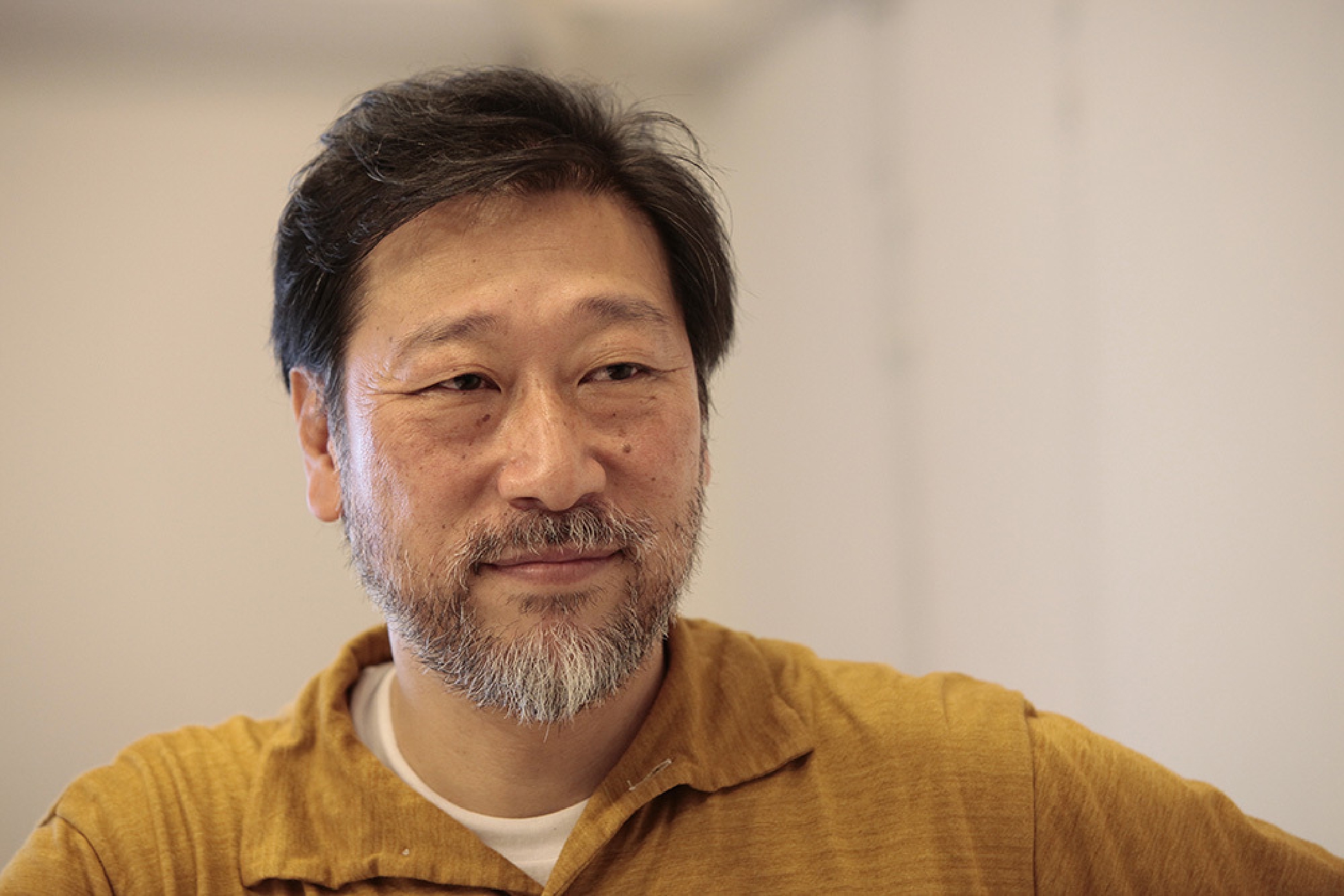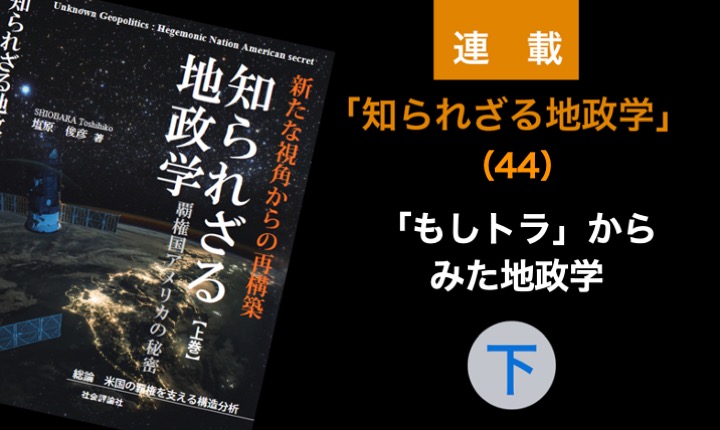
「知られざる地政学」連載(44)「もしトラ」からみた地政学(下)
国際
「知られざる地政学」連載(44)「もしトラ」からみた地政学(上)はこちら
トランプに対する福音派の対応
ここでは、「もしトラ」を実現する原動力にみえる福音派によるトランプ支持について考えてみたい。道徳的な正しさと聖書を重んじるとされるキリスト教福音主義の信者が、なぜ刑事事件で有罪判決を受け、さらに数々の裁判を待つトランプへの絶対的とも呼べる支持に傾いているのかについて論じることで、アメリカ社会の「特殊性」に目を向けたいのである。
アメリカの教会員数は、キリスト教、とくに歴史的にアメリカの宗教の中心であったプロテスタントを自認するアメリカ人の割合とともに、数十年にわたって減少し続けている。NYTによると、20世紀半ばには、アメリカ人の68%が自らをプロテスタントと称していた。ギャラップ社によれば、2022年までには34パーセントがプロテスタントであった。当初、減少のほとんどは、よりリベラルなプロテスタント主流派に影響を与えた。しかし近年では、福音派の教会への出席率も低下し、リベラル派よりも保守派の方が教会を離れたと回答する割合が高くなっている。2021年には、記録上初めて、アメリカ人の50%以下しか教会の会員でなくなった。
ハーバード大学のCooperative Election Studyからまとめたデータによると、2008年には共和党員の半数以上が少なくとも月に1回は教会に通っていたという。2022年には、半数以上が1年に1回以下の頻度で教会に通っていると回答している。
もちろん、トランプは最初から福音派の支持を集めたわけではない。定期的に教会に通う白人福音派共和党員は、テッド・クルーズ陣営に最も集中していたことが知られている。2016年4月公開の情報によると、クルーズ支持者の約半数(48%)が白人福音派プロテスタントで、そのほとんど(クルーズ支持者全体の35%)が毎週教会に通っていると答えていた。トランプ支持者(34%)とケーシック支持者(26%)の白人福音派の割合は少なかった。だが、そんな人物が大統領に当選したのである。そして、再び大統領になろうとしている。
知るべきアメリカの過去
おそらく大切なのは、アメリカの過去を知ることだろう。そうすれば、トランプのような人物が大統領になっても不思議ではないことがわかる。
19世紀、アメリカで黒人と白人が奴隷制廃止の道徳運動を起こしたとき、農園主は白人至上主義を神学的に擁護する文章を書くよう説教師に金を払ったという(「不道徳にもかかわらず福音派がトランプ大統領を支持する理由」を参照)。人身売買は、奴隷所有者の宗教のためだけに許されていたわけではない。それは神の設計を反映したものであり、何としても守るべき社会の正しい秩序だったのだ。
戦争を経て、奴隷制度はなくなった。しかし、このアメリカ特有の信仰はなくならなかった。1877年にラザフォード・B・ヘイズ大統領が南部から連邦軍を撤収させたとき、南部の説教師たちは、神が北部の侵略と「黒人の支配」から自分たちを救済してくださると民衆に語ったからである。20世紀初頭の著名な説教者トーマス・ディクソンは、クー・クラックス・クランを道徳の擁護者として賛美するベストセラー小説(『クランズマン』[The Clansman])を書いた。この小説は『クランズマン』という題名で演劇化され大成功を収め、10年後にはD・W・グリフィス監督の1915年の映画『国民の誕生』の原作となる。
大恐慌の後、企業の大物たちが信用を失うと、全米商工会議所のメンバーたちは、グリフィス監督の牧師、ジェームズ・ファイフィールドに報酬を支払い、市場を祝福し、社会福音を説く人々を呪う、20世紀版の奴隷所有者宗教を普及させたのだ。この「神の下に一つの国家」を求める運動は、ニューディール、共産主義、公民権運動といった「不道徳」からアメリカを救うことを約束したのである。そうした動きが、過度の反共運動につながり、それが反共重視の「アメリカ・ファースト委員会」、すなわち、「Make America Great Again」(MAGA)の源流へとつながっている(拙稿「米国大統領選と日本の安全保障の行方。」『潮』2024年6月号を参照)。
こう考えると、トランプ支持者がアメリカに一定数、存在しても何の不思議もない。ここでの説明は善悪を説くものではない。アメリカという「新大陸」にあって、こうした人々が一定割合存在したという事実をわかってほしいのだ。その意味で、トランプ現象は決して異常ではない。むしろ、アメリカという国家の歴史の反復とみなすべき現象なのだ。
宗教とは何か
ただし、話はここで終わらない。福音派の大量の支持を集めるようになっているトランプと宗教との関係について、もう少し深く考えてみる必要があるからだ。ここでは、最近になって二つの興味深い考察を公表した、WPのコラムニスト兼編集委員のシャディ・ハミドの分析をもとに、アメリカにおける宗教事情について紹介したい。一つは、2024年6月13日に公開した「トランプは福音派であることの意味を変えた」という記事である。もう一つは、論文「世俗の停滞 神なき時代に宗教はいかにして耐えるか」(『フォーリン・アフェアーズ』2024年7/8月号)だ。
ハミドは、「アメリカでは、20世紀の大部分は70%前後で推移していた教会員数が、2020年には50%を下回った。しかし、2023年のピュー世論調査によると、アメリカ人の88%が聖書の神、あるいはその他の崇高な力や霊的な力を信じている」という現状を説明するために、宗教そのものの定義からはじめている。
宗教を、キリスト教やイスラム教といった「特定の方法」(a particular way)を信じることだとみなすと、科学の発展や商業的繁栄の前に、そうした宗教は消滅しかねないかもしれない。ところが、実際には、宗教は厳然として存在する。これを理解するには、宗教の定義を変える必要がある。
そこで、ハミドは、宗教を、「主として社会的なもの、つまり、他者と一緒にいるときに生き生きとするもの、あるいは他者と同じことをしているという知識から生まれるもの」とみなすことを提案している。こう考えるとき、「宗教は、物質的なものを超えた、より深いニーズに応えている」ことに気づく。人間は、魅惑的な世界を求め、その産物である意味をつくり出す存在だから、人々が意味を必要とする限り、宗教はそれを提供するのに適した存在でありつづけるのだ。
ハミドは、「宗教を信仰している人は、そうでない人に比べて、平均してより幸福で、より満たされ、より仲間とつながっている傾向がある」と指摘している。このつながりや幸福感をもたらすことが「より深いニーズに応える」ということなのだ。この際、宗教には、世俗的なイデオロギーにはない、究極的な意味への関心があるという利点がある。
福音派の変貌
アメリカの福音派の変貌は、長い年月をかけてもたらされた。「1990年には、白人福音派の40%が民主党支持者だった」のだ。今日、この割合は15%に近づくまでに低下している。民主党は自分たちの支持層を占める無宗教のアメリカ人の増加を疎外したくないので、宗教についてあまり、あるいは説得力のある形で語らない。逆に、トランプはその知られざる地盤を取り上げることで、しっかりとした基盤に整備したのである。
ハミドによれば、「アメリカ人の宗教心は薄れつつあるが、福音主義者は増えている」。ただし、これは、「トランプ大統領が「福音派」の意味を変えてしまった」ことの結果である。福音派はもはや聖書を尊重するだけの人ではなく、党派政治に関心をもつ人に変貌したのだ。これをハミドは、「言い換えれば、ほとんどのアメリカ人はまだ信仰しているが、その信仰をより広いコミュニティと結びつけるような形で表現する能力を失っている」と表現する。「そのため、彼らはその信仰心を別の場所に、つまり、ますます党派政治に向けるのである」というのだ。
「世俗化のパラドックス」
どういうことか。ハミドの説明はつぎのようなものだ。
「たとえ宗教が個人にとって重要でなくなったとしても、社会全体にとっては重要である可能性がある。愛や友情と同じように、宗教は存在しないことでその存在感を示すことができる。社会が世俗化すればするほど、宗教に固執する人々が目立つようになる。世界各地で、宗教が公的生活のなかで依然として共鳴しているのは、宗教が政治闘争の混乱のなかで前面に出てくる基本的かつ基礎的な関心事に通じているからである。良きにつけ悪しきにつけ、宗教は市民とは何かという問いに答えを与えてくれる。政治の目的そのものを明らかにすることができる。そして市民に、自分たちの権利を導き出すより深い源とより高い権威を提供することができる。」
つまり、「世俗化のパラドックス」とハミドが呼ぶ現象が福音派を通じたトランプ支持という党派政治になって現出しているというのだ。
「福音派はかつての彼らとはまったく違う」
別の説明もできる。2024年1月8日付のNYTは、「トランプは異なるタイプの福音派有権者と結びついている」という記事を掲載した。記事は、「福音派であるということは、かつては定期的に教会に通い、救いと改心に焦点を当て、中絶のような特定の問題に対して強い信念を持っていることを示唆していた」が、今日では、文化的・政治的アイデンティティを表す言葉として使われることが多くなっていると指摘している。この傾向は白人アメリカ人の間でもっとも顕著で、トランプの大統領就任期間中、教会への出席率が全体的に低下しているにもかかわらず、「福音派」を自認する傾向が強まったという。
アイオワ州ではとくにその変化が顕著で、同州の人口の約4分の1を占める自称福音派は共和党政治に影響力をもつ有力者であるが、宗教的慣習は全米のどの州よりも顕著に変化している(写真を参照)
2010年から2020年にかけて、同州の教会信者人口(信徒と何らかの関わりをもつ人々)は約13%減少し、ニューハンプシャー州を除くどの州よりも急激に減少したという。同州のカルフーン郡の農村では、2010年から2020年にかけて、教会への信者が31%減少した。しかし、同郡の有権者の70%以上が2020年にトランプ氏に投票したのである。
どうだろうか。たしかに、かつての福音派とは異なる自称福音派が増え、彼らは党派政治によって「より幸福で、より満たされ、より仲間とつながっている傾向」を実感しているようにみえる。

2023年12月、アイオワ州シーダーラピッズでドナルド・トランプ前大統領の選挙キャンペーンが開催した「Commit to Caucus」イベントで祈りを捧げる参加者たち
(出所)https://www.nytimes.com/2024/01/08/us/politics/donald-trump-evangelicals-iowa.html
ここで紹介したアメリカ国内の宗教的変化は、いまでも「コミュニティ」が残存するアメリカで顕在化した動きなのかもしれない(拙著『帝国主義アメリカの野望』に書いたように、アレクシ・ド・トクヴィがその著作『アメリカの民主主義』のなかで、「アソシエーション」(association) を強調したことを思い出してほしい。このアソシエーションとは、共通の目的のために集まった、仲間や同盟者、さらに組織体を意味するようになる)。そうだとしても、格差社会のなかで取り残されたと感じる人々の内心からの叫びのようなものが込められているようにも感じられる。
そうであるとすれば、格差社会が世界中に広がるなかで、理不尽な立場に置かれている人々の苦悩をどう導いていくべきであるかは大きな政治課題となるだろう。
地政学は、ここで論じた「宗教」の変貌にも注意を払って、それがおよぼす社会への影響にも敏感でなければならない。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:日米合同委員会の存在と対米従属 からの脱却を問う
☆ISF主催トーク茶話会:エマニュエル・パストリッチさんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:安部芳裕さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:浜田和幸さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)