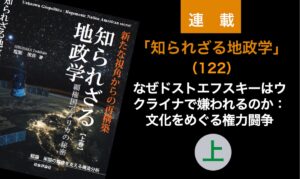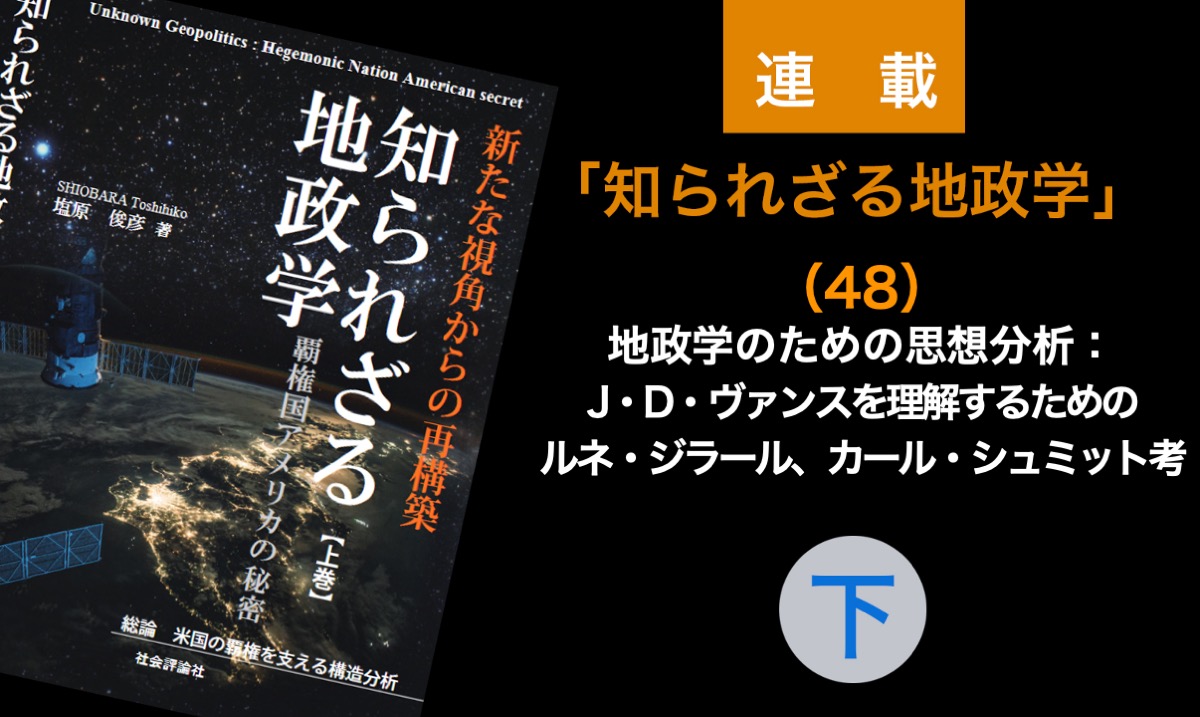
「知られざる地政学」連載(48)地政学のための思想分析:J・D・ヴァンスを理解するためのルネ・ジラール、カール・シュミット考(下)
国際
「知られざる地政学」連載(48)地政学のための思想分析:J・D・ヴァンスを理解するためのルネ・ジラール、カール・シュミット考(上)はこちら
ヴァンスとシュミット
つぎに、ヴァンスとカール・シュミットとの関係を紹介したい。2024年6月13日付のNYTに掲載されたヴァンスへのインタビューのなかで、彼は興味深い発言をしている。それは、2018年に当時のトランプ大統領によって最高裁判事に指名されたブレット・カバノーを承認するための上院司法委員会の公聴会で、高校時代のレイプ事件が焦点となり、「信じられないような人格攻撃キャンペーン」が行われたことに関連している。ヴァンスはこうした民主党支持者、すなわちリベラル派について、「2019年と2020年のリベラリズムについて私が考え続けたことは、この人たちはみんなカール・シュミットを読んでいるということだ。そして、ここでのゴールは権力の座に返り咲くことだ。カバノーの件でもそうだったし、ブラック・ライブズ・マターの瞬間でもそうだった」と語った。
このヴァンスの発言を理解するには、補助線を引く必要がある。7月13日付のNYTの記事がそれを教えてくれている。記事はつぎのように書いている。
「ヴァンスは、第三帝国の知的支柱の多くを提供した政治理論家であり、ナチスの法学者のことを指していた。シュミットはリベラリズムを軽蔑していた。しかしヴァンスによれば、リベラル派はこの断固として非リベラルな思想家、つまり敵を倒すために行政権力を独裁的に行使することを称賛した人物に夢中なのだという。」
さらにつづけて、「シュミット的リベラリズムの彼の例は、長靴による独裁ではなく、ポリティカル・コレクトネス、つまり「言ってはいけないことは何もない」という「絶対的専制的」な力を含んでいた」と指摘している。
そうだからこそ、共和党支持者であるヴァンスも同じ土俵にのったのだ。先のインタビューで、ヴァンスは、「選挙に異議を唱え、選挙の正当性に疑問を呈することは、実は民主主義のプロセスの一部だと思う。トランプが「選挙は盗まれた」と言い、人々が「彼は間違っている」と言うとき、私は「いいだろう、それについては議論できる」と言う。「アメリカ社会の基盤を脅かしている」と言われれば、目を丸くせずにはいられない」と語った(この問題は「連載【43】 情報統制の怖さ」[上、下]に詳しい)。
シュミットの思想
この「ねじれ」を理解するのは難しいかもしれない。そこで、シュミットの思想について、わかりやすく説明するところからはじめよう。彼については、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』、『帝国主義アメリカの野望』などで何度も紹介してきた。
彼は、ドイツの保守的な法学者、憲法学者、政治理論家であり、「しばしば、リベラリズム(自由主義)、議会制民主主義、自由主義的コスモポリタニズムの最も重要な批判者の一人と考えられている」という(スタンフォード大学の資料を参照)。
リベラリズムも議会制民主主義も批判の対象としているから、シュミットの思想はきわめて重要であると、私は考えている。シュミットはヒトラーが政権を握るまでは国家社会主義の支持者ではなかったが、1933年以降はナチス側についた。彼は1933年にナチ党に入党した。1935年になると、彼はニュルンベルク法で「異国人とドイツ人を平等に扱う」という公約が削除されたことを称賛した。そんな彼の主張全体について、私は支持しているわけではない。ただ、世界中にいまでも跋扈する御用学者よりはずっと参考になる、洞察力ある論考をシュミットは数多く残してくれたと思っている。
私が「シュミット好き」になった理由
まず、私が「シュミット好き」になった理由を説明しよう。それをわかってもらうために、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』のなかで、『ブラッドランド:ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』と『ブラックアース:ホロコーストの歴史と警告』で知られる、エール大学歴史学部教授のティモシー・スナイダーを批判した文章を書いたことを紹介したい。スナイダーは、2022年5月19日付の「ニューヨーク・タイムズ」(NYT)に、「私たちはそれを言うべきだ。ロシアはファシストだ」という意見を掲載する
そのなかで、「結局のところ、ナチスの思想家カール・シュミットが言ったように、ファシズム政治は敵の定義から始まるのである」と書いている。しかし、この記述は間違いだ。シュミットは、「政治的な現象は、敵/友の集団が常に存在する可能性という文脈でのみ理解することができ、この可能性が道徳、美学、経済学を意味する側面に関係なく、そう理解することができる」と『政治的なものの概念』(The Concept of the Political, Expanded Edition, The University of Chicago Press, 2007, p. 35)で指摘したにすぎない。ファシズムが敵/友を区別するのではなく、政治が敵/友を区別するのである。
こんな「大嘘」を書くスナイダーのことなどどうでもいい。私が、シュミットを気に入ったのは、「政治が敵/友を区別する」というシュミットの主張であった。なぜかというと、キリスト教徒と異教徒への厳しい視線という、キリスト教神学の教えと、このシュミットの主張に抜き差しならぬ関係を感じ取ったからである。
シュミットは『政治神学』のなかで、近代国家の教義の主要概念はすべて世俗化された神学的概念であり、これらの概念を使い続ける政治理論には神学的基盤が必要であると主張している。これもまた、私がシュミットを気に入った理由の一つである。
念のために書いておくと、私は『復讐としてのウクライナ戦争』において、キリスト教神学に基づく「ヨーロッパ精神」を批判しようとした。その意味で、シュミットの政治哲学は、キリスト教神学の影響下に欧米が置かれてきたことを実証している論拠を提供してくれるのではないかと思わせるのだ(本当は、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』は地政学からみた思想史という視角を日本で唯一、提供しているのだが、その価値に気づいてくれる人があまりにも少ない)。
シュミットのリベラリズム批判
シュミットは、リベラリズムには真の政治的決定の必要性を否定する傾向があり、個人が敵味方の区別をつけることによって構成される集団を形成することは必要でも望ましいことでもない、と主張している。そうみなすことで、リベラリズム信奉者は、文明、技術、社会組織の改善によって、だれもが有利になるように解決できない人間同士の対立は存在しない、あるいは、平和的な討議の後、友好的な妥協によって解決できない対立は存在しないと考えるようになる。
さらに、シュミットは、いつの日かグローバルな覇権主義者が、他のすべての共同体から敵味方の区別をつける能力を奪うことによって、グローバルな脱政治化を強制することができるかもしれない、あるいは、いつの日かリベラリズムがグローバルな文化的覇権を獲得し、人々が敵味方の区別をつけることに関心を持たなくなるかもしれない、と認めているようである。
だが、こうした楽観論は偽善的であり、シュミットに言わせれば、多元的な寛容を人々の喉に押しつけようとしているようにみえる。「政治が敵/友を区別する」にもかかわらず、これを真正面から認めないために、リベラリズムは、真の政治的決断の根拠となる、アイデンティティの実質的な指標を提供することができないというのだ。政治的共同体は、敵味方の区別をつけることによって自らを部外者と区別し、政治生活に関与しようとする集団が存在するところに存在すると考えるシュミットにとって、この現実を考慮しないリベラルズムは偽善にすぎないように映るのである。
「例外状態」
シュミットは、法規範は混沌には適用できないと主張している。この混沌とは、「例外状態」、つまり「非常事態」を意味している。別言すると、「例外に関する主権者の決定がいかなる重大な法的制約も受けないのであれば、例外状態を決定する権限は、何を例外状態とみなすべきかを決定する権限に等しい」ことになる。このとき、主権者は全権を掌握する権利をもち、それをいつ主張するかを決定することができる。すなわち、「君主とは例外を決定する者である」ともいえる。
ここで、思い出すべきは、「主権」を論じたジョルジョ・アガンベンの『ホモ・サケル』である(この問題については、拙著『官僚の世界史』の注になかで論じている)。「ホモ・サケル」は「聖なる人間」を意味している。いわば、法のなかで規定されていない、法や規範の埒外におかれた人間であるために、この人間を殺害しても処罰されないが、儀礼によって認められる形では殺害してはならないとされる。
ホモ・サケルは生け贄(犠牲)問題に通じる
ホモ・サケルは、彼に対してすべての人間が主権者として振舞うことを可能にするが、主権者自身は彼に対してすべての人間が潜在的にはホモ・サケルであるような者として顕現する。主権者はその主権がおよぶ範囲内で、他者をどのように扱うことも許された者となる。国家が主権者と位置づけられるようになれば、国家はその主権のおよぶ範囲内の人間を殺しても殺人罪に問われない資格を獲得することになる。
問題はホモ・サケルがそもそも法にとっての「例外状態」として、「剥き出しの生」という自然状態にあり、法的状態とはまったく分離されていたのに、西洋の法においては当初、例外的な状況下で法的状態と自然状態が互いに互いをその内部に含み合うような関係になり、最終的には両者が重なり合い、まったく区別できないものになった点にある。法的な概念としての「主権」が確立すると、もともとは例外状態におかれていたホモ・サケルとの関係が他者全体にまで広がることになるというのだ。
ところが、仏教のもとでは、あるいはカースト制においては、例外状態としての自然状態と法的状態があくまで分離されている。他方、キリスト教世界では、ホモ・サケルという例外状態が法的状態と重なり合うことで、法が機能するようになり、普遍性へと近づく。ここに、「法の支配」(rule of law)を優先する、西洋のキリスト教世界がたまたま出現したことになる。
どうしてそうなったかというと、それはイエス・キリストが神の子として、生身の人間の姿をとって現われたからである。人間は自然の一部であり、その人間でありながら神であるキリストがたまたま現れたことで、自然状態と超越的視点をもとに生じる法的状態が重ね合わされてしまったのである。
ここまでの説明は、ルネ・ジラールの問題提起した生け贄(犠牲)問題に通底していることに気づいてほしい。人類にとっても普遍的問題をしっかりと対峙し、真正面から向き合うことの重要性に気づかなければならない。
アガンベンの議論
西洋においてこの主権者の座に最初に君臨したのは「法権利」である。それは、「規制は例外があって生きる」ということを実践していることになる。つまり、「法権利は、法権利が例外化の排他的包含によって自分の内に捉えることのできる以外の生をもたない」からである。これは例外が主権の「構造」であることを意味している。
ゆえに、アガンベンは、「主権とは、法権利が生を参照し、法権利自体を宙吊りにすることによって生を法権利に包含する場としての、原初的な構造のことである」としている。主権の構造を理解する手掛かりとして、ホモ・サケルを考察すると、神に生け贄にしてはならないホモ・サケルは、人間の裁判権の外におかれているだけでなく神の裁判権のもとに移行されてはいないが、すでに神の側にあることになる。ホモ・サケルの犠牲化の禁止は、ホモ・サケルと奉献される生け贄とを同一視することを禁じるだけでなく、ホモ・サケルに加えられる暴力が聖なる事物に対して加えられるような冒瀆にはあたらないということを含意している。
ゆえに、ホモ・サケルは犠牲化不可能という形で神に属し、殺害可能という形で共同体に包含されるのだが、主権による例外化において、法は自らを例外化から外し、例外事例から身を退くことによって、例外事例へと自らを適用するのである。この手続きによって、法は自らを特権化する。
こう主張するアガンベンからみると、ホッブズの主権に対する議論はおかしいことになる。万人の万人に対する戦いという自然状態は、都市が「まるで解体してしまっているかのよう」な例外状態として想定されたものであり、誰もが他の者に対して剥き出しの生でありホモ・サケルであるという状況としてみなさなければならない。このとき、ここでの安全を確保するために臣民がとるべきなのは、自分の自然権を譲渡することだという論理で、主権権力を基礎づけることではない。
その安全は主権者が自分の望む相手に対して望むことを行うという自分の自然権の保存に求められるべきであり、現に、国家は個人との自主的な契約に基づいているのではなく、主権的暴力が剥き出しの生を国家の内に排除的に包含することによって成り立っている。それは人々をホモ・サケルへと追いやる、締め出すことを意味している。ゆえに、「近代において、生は国家の政治の中心にしだいにはっきりと位置づけられ(フーコーの用語では、生政治的となり)、現代にあっては、すべての市民が、ある特殊な、だが現実的きわまる意味で、潜在的にはホモ・サケルの姿を呈している」と、アガンベンは主張するのである。つまり、法の特権化のもとに主権国家の暴力が正当化されるという恐ろしい現実が隠蔽されるようになるのだ。
わかってほしいのは、こうした特殊な理解のもとに、法を特権化した西洋の「独善」であるということだ。そうした西洋の独善をシュミットは教えてくれている。しかも、この法の特権化は主権者と独裁という問題を惹起する。そして、その思想はトランプにまで着実に影響をおよぼしている。だが、ヴァンスがいうように、それは決してトランプだけの問題ではない。リベラル派もまた同じ独善に陥っており、そこには、独裁の芽吹きがある。いやそれどころか、「現代ビジネス」で近く公表するように、アメリカはヘゲモニー国家として外国に対してもう何十年もの間、独裁的にふるまってきた。イラク戦争で、何十万人もの市民を殺害しようと、アメリカ大統領は決して犯罪に問われることはなかったのだ。
シュミットは人生の後半、国際法の研究に従事した。その成果については、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』や『帝国主義アメリカの野望』で紹介した。その研究はいまでも優れた分析のための視角を提供している。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)