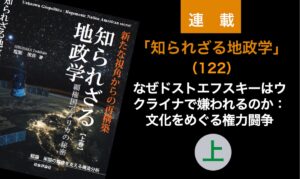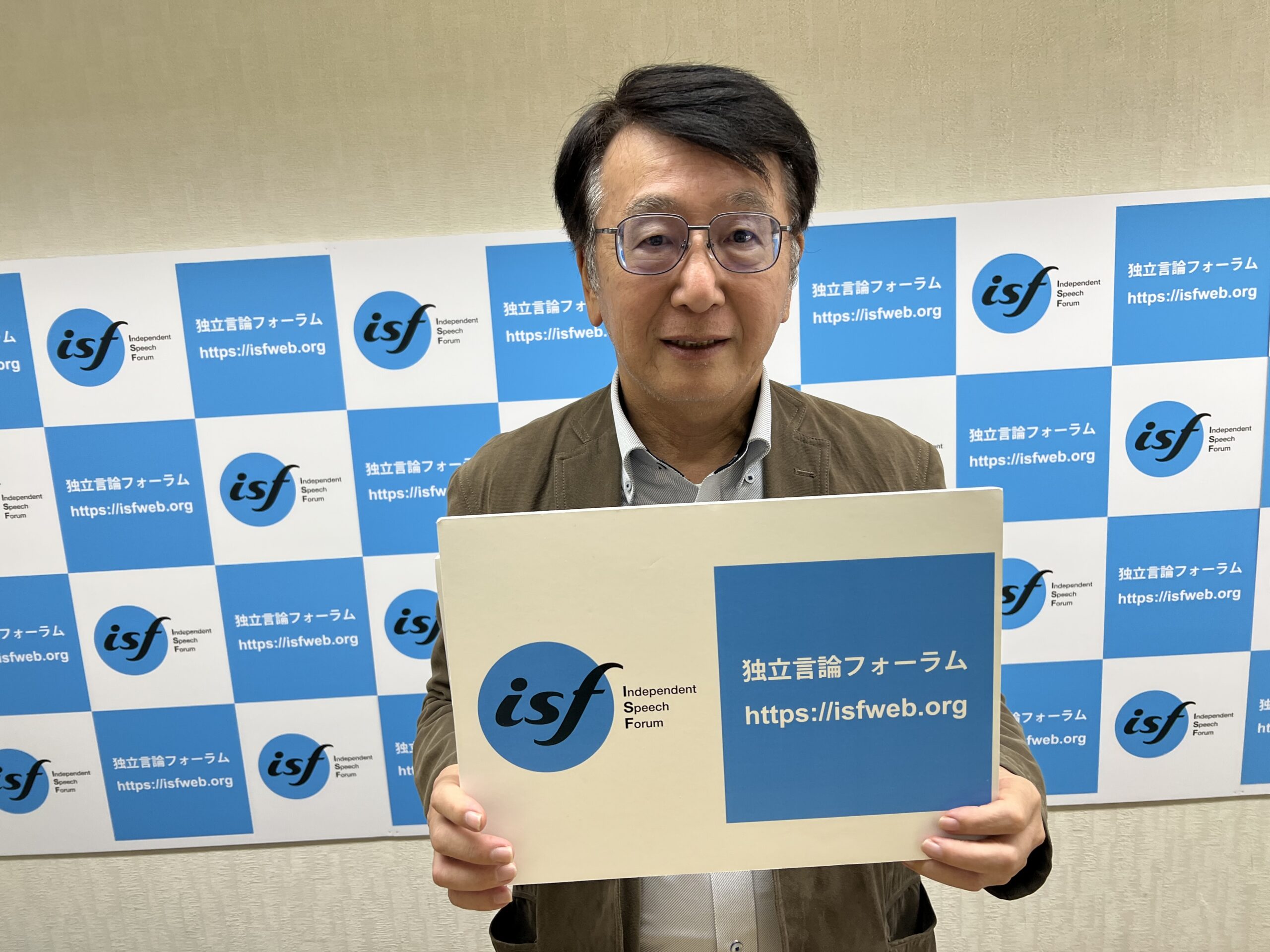「主権者教育」の弊害
社会・経済「主権者教育」のいかがわしさ
「主権者教育」の推進が叫ばれるようになって久しい。2015年に改正された公職選挙法が2016年に施行され、有権者の年齢が満18歳に引き下げられたことがきっかけのようだ。学習指導要領も改訂され、高等学校の公民科に「公共」という科目が2022年に新設された。高校生のうちに18歳を迎えて有権者となる若者たちに、「主権者」としての意識を涵養することが、教育現場に求められるようになった。
ヘソ曲がりの私は、「主権者教育」なる新造語はいかがわしいと感じてきた。「主権者」とはどういう意味か、ろくすっぽ議論されないまま流通していることに危惧をおぼえる。
われわれは、訳知り顔で高校生に「主権者教育」を施す前に、みずからにこう問うてみなければならない――「主権者」とはそもそも何を意味するのか、と。
この語は、英語では“sovereign”(フランス語では“souverain”)である。手持ちの辞書を引くと、「上の」という意の“super”から派生したこの語は、まずもって「君主」という意味をもつ。つまり、王や女王など「最高位の支配者」を表わす。次いで「主権者」という訳語も記されている。
このように「主権者(サヴリン)」には、「一国の最高権力者」という強い意味がある。形容詞としても、「君主に帰属する」「最高権力を持つ」「至高の」という意味で使われる。また“sovereignty”という名詞も別にあり、こちらには「権力が最高であること」「君主の身分」という意味がまず載っていて、「主権、統治権」「独立国、主権国」という意味が続く。
「主権者」が「君主」のことだとすれば、つまり、他からの干渉を受け付けず、一国をもっぱらみずからの裁量で統治することのできる最高権力者のことを、「主権者」を呼ぶのだとすれば、「主権者教育」とはまずもって、そのような最高権力者となるための教育、つまり「君主教育」を意味することになる。
なるほど「帝王教育」というものは昔からあった。王族の子弟が将来わがまま放題の支配者とならぬよう、熟慮と自制を教え込むことは大事なことだった。となると、ひょっとして「主権者教育」とは、「主権在民」の時代にあって、民衆という暴君による専制つまり衆愚政を防ぐためのしつけ教育、という底意を秘めたものなのだろうか。とにかく、いかがわしさは拭えない。
こんな妙なことを言い出すと、こうたしなめられるかもしれない――「国王主権」の時代ならいざ知らず、「国民主権」の今日では「主権者」の意味が変質しており、かつてと同列に論ずること自体間違いだ、と。
そうだろうか。ここで、「国王主権」に代わって登場した「国民主権」とはいかなるものか、という問題が浮上してくる。
国王主権から人民主権へ
「主権」という言葉の語義変遷もそうだが、「主権国家」の歴史的由来は恐ろしくこみ入っており、容易に見極めがたい。代わりに、「国王主権」から「人民主権」への転換に位置する歴史的出来事を、ざっと思い起こしてみよう。「革命」がそれである。
中世ヨーロッパを広く覆っていたカトリック教会の支配がかげりをみせた近代、いわゆる「世俗化」の動きが加速していく。現世の支配者である国王は世俗的権力の自立性を主張したが、みずからの権力を安定させてくれる宗教的権威をなお必要とした。その要請を受けて唱えられた理論が「王権神授説」だった。近代初期の絶対王政とともに確立されたのが、絶対的「主権」の概念だった。この「国王主権」――同語反復のようにも聞こえるが――の時代には、英明な啓蒙専制君主が求められ、「帝王学」の書としてマキアヴェッリの『君主論』が読まれたりした。
ブルボン朝のフランスでは、17世紀後半、ルイ14世の絶頂期を迎える。70年以上の在位期間に、親政を行ない、相次ぐ戦争により領土を拡大し、ヴェルサイユ宮殿を造営し、貴族文化を花開かせ、「朕は国家なり」と言ったと伝えられる「太陽王」は、まさに「国王主権」の象徴のような存在であった。
これに続いて18世紀後半に興ったのが、フランス革命である。ルイ16世を処刑し君主制を廃したこの大転換の思想的支柱をなしたのは、ルソーの「一般意志」論と、それを承けたシエイエスの「人民主権」論であった。絶対君主という単一主体の「主権者」の意志に代わって、集合的主体としての「人民」の総意、つまり「一般意志」が、統治の絶対的原理とされた。革命は、個々人のレベルを超えた普遍的権力主体としての人民一般を「最高支配者」つまり「主権者」に据え置いたのである。
この場合「主権者」に擬される「人民」(フランス語peuple、英語people)は、有象無象の集合体でこそあれ、個々人を指すものではない。国王ルイ14世はまさしく「主権者」だったが、革命指導者ロベスピエールはべつに「主権者」ではなかった。
一国の最高権力者を「主権者」と呼ぶという点では、「主権在民」もしくは「人民主権」の時代でも変わらない。最高権力を国王から奪取し、その玉座に就いたのが、「人民一般」だった。この革命的転換を表わす一語こそ、「人民主権」にほかならない。
「人民主権」は革命後の共和国の原理となり、第二次世界大戦後には日本にも移植された。ただし「人民」という訳語は採用せず、「国民主権」という無難な言葉を使って、それまでの「天皇主権」からの急激な転換を軟着陸させようとした。とはいえ、その発想の基本は、あくまでフランス革命以後の「主権在民」にある。現人神としての天皇にではなく、総体としての日本国民に「主権」が帰されるようになったからといって、そのメンバー一人一人のことを「主権者」と呼んでよいわけがない。
そうした言葉の濫用に基づいて、個々人に「主権者教育」を施すというのは、単一主体に至上権を帰する旧式の「主権=君主」概念を引きずっている。あたかもそれは、帝王学の手ほどきを庶民に振りまくようなものなのである。
そんな語義穿鑿などどうでもいい、と鼻白む人もいることだろう。若年層の投票率が低下している現状を打開することのほうがはるかに大事だ、と。だが、「主権者教育」に取り組めば取り組むほど若者のあいだに政治的無関心が広がるとすれば、どうだろうか。
「主権者=有権者」、「市民=政治的主体」
「公共」という高等学校公民科目は、2025年春、大学入学共通テストの新科目として実施される。この科目でとくに力を入れて教えられているのは何か。民主主義における選挙制度の重要性であり、つまりは、公職選挙時に投票することのすすめである。「主権者教育」は、選挙権拡大による投票率低下を抑えるために行なわれている。
「主権者教育」で言う「主権者」とは、「有権者」のことなのである。では、「主権者教育」は「有権者教育」だと解して、これを推進すればよいのだろうか。
しかしここに陥穽がある。
「主権者教育」を受けて、あたかも自分たち一人一人が、国民主権下での権力主体であるかのように教え込まれた者たちは、実際の選挙に臨んで、どう思うだろうか。選挙権を行使したところで、選挙結果はそれとほとんど無関係なものに映る。吹聴された「一票の重み」など空語に過ぎないことが露呈し、彼らは失望する。そしてその無力感は、政治的なものに対する不信を確実に増大させる。投票率はますます下落することだろう。
なぜそのような結果となるのか。選挙で投じた一票が、「政治的なもの」の意義を知らしめることは総じてまれである。「主権者教育」によって、自分たちは君主に擬せられる権限の持ち主だと暗示された者たちが、しかしその権限を選挙時の投票行動に限定させられたうえで、そのほとんど唯一奨励された活動に意味が何一つ見出せないとすれば、政治一般に幻滅するのは必定である。「主権者教育」をまじめに学べば学ぶほど、自分が教わったことが建前でしかなかったことに思い至って、愕然とすることだろう。
「政治的主体」であることは、「主権者」であることとは意味が異なる。ましてや、「有権者」であることと同義ではない。「主権者教育」の普及以前に使われていた「政治的教養」のほうが、含蓄豊かな言葉だった。なぜなら、「政治的なもの」とは何かという、いっそう根源的な問いを惹起させるからである。「政治的主体」を表わす語としては、君主のイメージを改鋳し平板化しただけの「主権者」は、お粗末というほかない。
「主権者」といういかがわしい言葉ではなく、政治的主体を意味する由緒正しい基本語を、じつはわれわれは持っている。「市民」という言葉がそれである。
「市民であること・市民性」を、英語で“citizenship”と言う。「シティズンシップ教育」という言葉は現に用いられている。カタカナ書きでピンとこない言葉は使っても、「市民教育」や「政治教育」という率直な言い方は避け、それに代えて「主権者教育」という看板を掲げてお茶を濁しているだけではないか、と邪推したくなる。そしてそれは、「人民主権」とは言わずに「国民主権」という言い方をして、「天皇主権」改め「象徴天皇制」と何とか折り合いを付けようとしたことと、どこか似ていないだろうか。
国民一人一人を「主権者」と呼ぶのは言葉の濫用だが、普通選挙制下の国民が等しく「有権者」であるのは間違いない。そのことと、市民一人一人が「政治的主体」だということとは意味水準が異なる。「市民」とは「政治共同体のメンバー」を意味するからである。
推進すべきは「市民性の涵養」
わが国には「市民」という意識は稀薄だと言われる。なるほど「市民(シチズン)」は外来語である。しかしそれを言えば「主権者(サヴリン)」だって同じである。「市民」という言葉によそよそしい響きがあるからといって、この語は避けたほうがいいということにはならない。逆である。いまだ根ざしていないからこそ「市民性の涵養」という意味での「市民教育」が必要なのである。なぜなら、それはもともと「政治教育」と同義だからである。
およそ「政治的political」なるものの原点に位置する古代ギリシアの「ポリスpolis」(都市国家)とは、都市住民の自治共同体という意味であった。その担い手たる政治的主体が、「ポリテースpolitēs」(市民)と呼ばれた。同じく「ポリス」由来の言葉に、「ポリティコスpolitikos」(政治家)がある。「市民」と別に「政治家」がいるわけではない。両者はもともとも同根なのである。「政治」とは元来、市民による都市運営のことだった。
このように、対等な自由市民同士の自治こそ「政治的なもの」の原風景をなす。
では、そのような「市民」は、古代、中世、近代のさまざまな政治風土には出現しても、現代日本には不在なのか。そんなことはないだろう。わが国の至るところで、地域に根ざした住民本位の活動は見られる。かつて「町衆」や「旦那衆」が活躍したように、今日でも祭りの共同開催からまちおこし協議まで、市民・町民・村民の自発的参加はそれなりに盛んである。自分たちが暮らしているまちを大切にしたい、その美しい景観やかけがえのない伝統を守りたい、という切なる願いから立ち上がる住民運動は、各地で起こっている。住民自治の精神がこの国にまったく欠如しているわけではない。
そのような活動の担い手のことを、根源的意味での政治的主体、つまり「市民」と呼んでさしつかえない。ところが、国家に従順な「国民」を「主権者」と呼び直して選挙時に投票を呼びかけはしても、行政の管轄には属さない自発的活動の主体のことを、遠巻きに「市民」と呼んで、彼らの「市民活動」を、政治的に正規なものとは見なさないのが、わが国の「市民性」の実態である。「市民」はいまだに市民権を得ていない。「市民活動家」をうさん臭く思うこと自体、政治的なものについての無理解をさらけ出している。
「主権者教育」の名の下に選挙権の行使の重要性を教える実質上「有権者教育」に、意味がないとは言わない。しかしそれに劣らず重要なことがある。「政治的なもの」とはべつに選挙に関する知識に限らず、まちやむらで暮らすわれわれの日々の生活の諸局面、たとえばゴミ問題への取り組みといった共通の関心事に広がっていることを学ぶこと、これである。その意味での「政治的教養」つまり「市民性の涵養」こそ、今日求められているように思われる。そして、そのようにして底上げされた「政治的なもの」の基盤の上にはじめて、主権者としての人民の「総意」を占う選挙民主主義も活性化されることだろう。
「自主独立精神の涵養」も大事
では、「主権」という概念にアクチュアリティはないのかと言えば、そんなことはない。
「主権者」という言葉がわれわれにしらじらしく聞こえることには、もう一つ別の事情がある。これは、わが国は果たして「主権国家」と呼べるのか、という問題に関わる。
先に述べたように、「主権」と訳される“sovereignty”には、「至上権」という意味のほかに、「自主独立であること」、ひいては「独立国」という意味がある。
「主権(サヴリンティ)」とは、他のいかなる勢力にも干渉されることなく、一切を自己決定する統治のあり方を指す。ある国の王室が他の国の王室と姻戚関係にあり、一国の統治が他国の影響下に置かれているとすれば、それは独立が侵害されていることを意味する。国家内部での絶対的「主権」概念の確立は、国家間における「主権」の原則の相互承認と時を同じくしていた。ここに近代の「主権国家」という考え方が成立した。とりわけそれは、近代初頭にヨーロッパ中で繰り広げられた凄惨な戦争の教訓として、であった。
国際政治上、対等な「主権国家」であるかどうかは、一国が独立国であるか他国の属国に堕すかの分かれ目をなす大問題だった。開国期日本の最大の関心事もこれだった。自立を尊び隷属を厭う気風がそこにはみなぎっていた。近代国家の仲間入りを果たしたかに見えて治外法権という主権侵害的ハンディキャップを背負った明治期日本が、不平等条約の屈辱から脱するには50年以上にわたる富国強兵政策と外交努力が必要であった。
ところが、そのまた半世紀後、大日本帝国は戦争に惨敗し、戦勝国の占領下に置かれるに至った。主権はここに完全喪失した。それを回復したかに見えるサンフランシスコ平和条約締結後も、それと同時に結ばれた日米安全保障条約の下で、日本各地に米軍基地が多数残存し、日本の法規に服さないアメリカ軍が駐留し続けている。かくして、今日なお日米地位協定により占領期以来のアメリカ軍支配が温存されたままである。その半独立状態は戦後80年経とうというのにいっこうに改善されていない。それどころか、沖縄の辺野古米軍基地の新設強行に典型的に見られるように、対米従属の軛(くびき)はいよいよ強固になっている。
日本国が「主権」をいまだ完全回復できていないという恐るべき現状こそ、わが国における「主権」問題の核心である。「主権者教育」を高校生に賢しらに仕込む前に、われわれの国は「主権国家」と言えるか、胸に手を当てて考えてみたほうがいい。
「人民主権」という統治の原理を、敗戦国日本は戦勝国アメリカから仕込まれた。また、「主権国家は主権を持つ」は同語反復的命題であり、万国共通の近代政治の根本原則である。その自明の原理をアメリカ人民相手に主張することに、何の躊躇があろうか。
もとより、「主権者教育」が排他的民族国家主義の醸成を意味するとすれば願い下げだが、このままでは100年以上続くことが必至の情勢の対米従属という深刻な問題に目を向け、「主権国家」としての真の自主独立を希求する意識の涵養ということであれば、「主権教育」という新しい学びにも、大事な意味があろう。ただしそれは、高校生対象に限られはしない。そう、日本人民、そしてわれわれ市民一人一人の学びでなければならない。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:ウクライナ情勢の深刻化と第三次世界大戦の危機 9月30日(月)13時半から
☆ISF主催トーク茶話会:伊勢崎賢治さんを囲んでのトーク茶話会のご案内 9月23日(月・祝)15時から
☆ISF主催トーク茶話会:仙波敏郎さんを囲んでのトーク茶話会のご案内 9月25日(水)18時半から
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
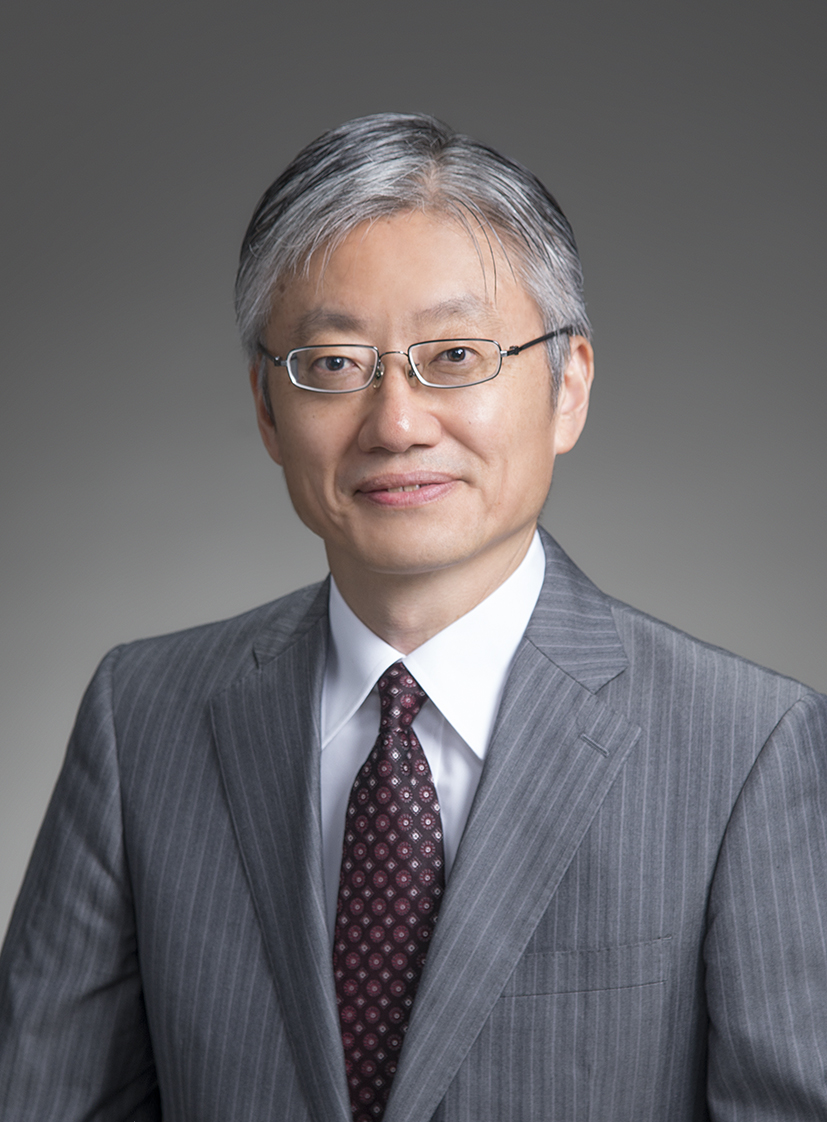 森一郎
森一郎
1962年生まれ。東北大学大学院情報科学研究科教授。著書に『死と誕生』、『死を超えるもの』(以上、東京大学出版会)、『世代問題の再燃』(明石書店)、『現代の危機と哲学』(放送大学教育振興会)、『ハイデガーと哲学の可能性』(法政大学出版局)、『核時代のテクノロジー論』(現代書館)、『ポリスへの愛』(風行社)、『アーレントと革命の哲学』(みすず書房)。訳書にアーレント『活動的生』、『革命論』(以上、みすず書房)等。