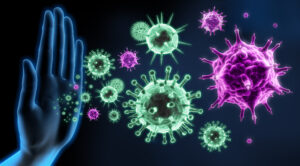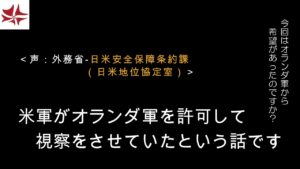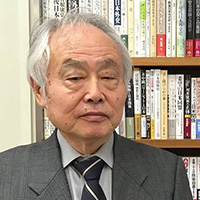登校拒否新聞号外:スクールマイノリティの現況
社会・経済本年6月29日午前9時51分付で、旧ツイッターのアカウント「不登校新聞」(@futokoshinbun)は「NPO法人全国不登校新聞社は6月末をもって解散いたしました」とツイートした。その直後、10時43分には同新聞編集長の石井志昴氏のアカウント「石井しこう」(@shikouishii)が「6月末をもって23年間務めた不登校新聞を退社しました。今後は「不登校ジャーナリスト」として活動していきます」とツイート。
https://x.com/futokoshinbun/status/1806852912204886465
https://x.com/shikouishii/status/1806865983245873400
解散したのに代表者が退社とは妙だ。
巷では解散理由が明かされていないためにさまざまな憶測がなされている。新聞社の母体となっているフリースクールで起きた性加害事件の問題が背景にあるのではないかと。この点に関しては、新聞の初代編集長であった山下耕平氏もブログ「迷子のままに」上で認めている。氏は問題が明るみに出た段階で新聞社の理事を務めていたが紙上にて問題を扱うことを提言したところ彼以外の理事全員が反対したということで辞任。裁判となったこの事件の被告が新聞社の創刊時に編集スタッフとして勤めていたという事実がありながら、不登校新聞はこの問題を報じることなく解散した。
https://maigopeople.blogspot.com/2024/03/blog-post.html
事件の経緯とフリースクール側の対応については北海道江別市の親の会「もぐらの会」が詳しくブログ上にまとめている。その過程について、ここで詳しく追うことはしない。裁判は賠償金の支払いにより和解しているが問題はむしろ二次被害ということで尾を引いた。弁護士ドットコムニュースには2023年6月10日付で、原告に取材した黒部麻子氏の記事「有名フリースクールで発生した性暴力事件、「置き去り」にされた被害者が望む「検証」のあり方」と「「二次加害だ」批判された文科省イベント中止、有名フリースクールで起きた「性暴力事件」とは?」が掲載されている。和解の条件には口外禁止が盛り込まれているという。しかし原告以外にも複数の被害者がいることが証言されている。
http://moguranokai.seesaa.net/article/482664311.html
https://www.bengo4.com/c_18/n_16117/
https://www.bengo4.com/c_18/n_16115/
私は中学校には一日も通わなかった。いわゆる「不登校」であるが、そう意識したことはない。と言うと怪訝に思われるかもしれないが、そう思う人はこの問題の歴史を知らないのである。「不登校」という言葉は精神科医が使い始めた用語だ。「登校拒否症」「学校恐怖症」などと言われて児童精神医学において問題とされていた事柄が思春期外来を開いた児童精神科医によって「不登校」と言い替えられた。しかし、たんに言葉を替えたという問題ではない。言葉は用語であり概念である。新しい言葉が使われる時には論理の転換がある。拙著『不登校とは何であったか?心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(社会評論社)で詳しく論じたように社会病理論という論が言葉の変換をもたらしたのだ。その一方で「不登校」という言葉を使わずに登校拒否と言い続けた専門家も少なからずいる。識者であれば、その名をいくつか挙げることができるだろう。
はっきりさせておきたいことは「不登校」とは、通り一遍の言葉ではないということだ。精神科医が使い始めた用語なのである。そう言うと登校拒否もそうだと言われるかもしれない。たしかに「登校拒否症」「登校拒否児」という言葉は精神科医が言い出したものだ。それに比べれば「不登校」のほうが穏やかだと思われるかもしれない。とはいえ「拒否」よりも「不」のほうが価値中立的という意見が外ならぬ精神科医から発せられていることに注意して欲しい。「不登校」は今や行政用語である。そういう意味で「不登校」という用語を使うことに反対はしない。しかし、私はこの言葉に対して生理的な違和感を覚える。その理由を学問的に追求してきた。
そのような時に不登校新聞社が解散したという報を受けて私は喜んでいる。読んで字のごとく、この新聞は「不登校」という言説の発信源であった。母体となるフリースクールの見解が新聞という媒体により配信されたのである。「不登校」に関する報道は、例えば『朝日新聞』などにおいて毎年のごとく石井編集長に取材するという形式を取った。私がこのような報道のあり方に疑問を感じてきたのは「不登校」という言葉が使われているから、という単純なものではない。特定の団体を背景とした機関の意見のみが繰り返し配信されるという言論のあり方に偏向があるからだ。
では、具体的に何が問題なのか?
不登校新聞を通じて配信された「不登校」という言説は「不登校当事者」「不登校経験者」をつくり出した。それこそ旧ツイッターには「不登校を経験した」という当事者があふれている。私はこの点にこそ違和感を覚える。
「中学校には一日も通わなかった」というのは「不登校」ではないかと言われるかもしれない。しかし「不就学」という行政用語もあることを考えてみて欲しい。就学はしているから「未就学」ではないが「中学校には一日も通わなかった」というのは実態として「不就学」である。つまり川崎市立西生田中学校の就学率は100パーセントではなかったのである。私は「不登校を経験した」のではない。中学校という義務教育学校に就学しなかったのである。国民皆就学という国民教育の理念はいまだ達成されていない。それが「不登校児童生徒」の増加という問題にすり替えている。私に言わせれば「不登校を経験した」という当事者たちはこの点に関する政治的な意識が欠けている。年度をまたいで欠席しているような例は不就学に近い。問題はそこで当事者たちが何を経験したかという個人的な心象ではなく理由は何であれ学校に通えていない学齢期の児童生徒たちが「学校教育を受ける権利」(憲法第26条)――就学権の保障を受けているかどうかという権利保障の問題である。
文部行政は「不登校特例校」、改め「学びの多様化学校」を設置して対応している。昨年3月31日には初等中等教育局長の名で通達「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」が出た。「学び」とは「不登校」界隈のジャーゴンである。「勉強」は禁句なのだ。完全なるダブルスタンダードである。「不登校児童生徒」には「学校外の居場所」で「多様な学び」が強要される。――なぜか?
その子たちは「学校になじめない」という含意があるからだ。画一的な学校教育が個性的な子どもたちを不登校に追いやっているとする論理の基調がある。であるから「不登校」は言説なのだ。その発信源が消失したとなれば勢い登校拒否新聞でも発刊しようかと思った次第。論理の基調を変えることはできるだろうか。
最近、私が注目した二つのニュースがある。
一つは「「時代は変わっているのに学校が変わらない」不登校から東大現役合格も 急がれる学校以外の“居場所”づくり」というタイトルで去年7月4日にTBSテレビが報じたものだ。活字化されて同局のブログに掲載されている。社会部厚労省キャップの岡村仁美氏が東京大学1年生の磯田大翔さんにインタビューしたという内容。彼は国立大付属の中学校に在籍していたところ1年生の夏頃から学校に行かなくなり3年生の頃から熊本学習支援センターという所に通うようになった。その後、私立高校に進学して東京大学に入った。タイトルにある「時代は変わっているのに学校が変わらない」というのは、その学習支援センター長の主張である。同センターには大学生がボランティアで入っているという点に留意されたい。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/580719?display=1
もう一つは「不登校の子、高校受験に調査書の壁 特別枠設ける自治体も」というタイトルで今年8月3日付で配信されたフリー記者の国分瑠衣子氏の記事である。彼女がインタビューしているのが東京学芸大学大学院1年生の成澤乃彩さんである。彼女は中学1年生の春に起立性調節障害の診断を受け学校に行けずにいたが、3年生の12月からは放課後の教室で勉強を始めた。公立高校の後期入試に合格して、信州大学教育学部に進学。今年から東京学芸大学の大学院に籍を置いている。ここで提起されている「調査書の壁」というのはいわゆる内申書の問題である。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4c51dcde7278e667c6390c1c5c1c1b8eac1ee531?page=1
最初の例は私立高校に進学したからか内申書の問題は触れられていない。しかし、後者においては本人が県立高校への進学を望んだこともあり、この点が壁となったことがテーマとされている。
どちらもかなり高学歴の例である。
この二つの例を引いたのは、それこそ不登校新聞がぜったいに取り上げないような例だからだ。「不登校」という言説空間において「進学できた」というような話はタブーとされてきた。あくまでも「多様」なのである。いかにしてヨコに広げるかということだけが問題で、それが結局はタテに収まるという点は不問に付されてきた。
私が「不登校を経験した」という言い回しに違和感を覚えるのは、それがヨコの経験であって、タテの経験ではないからである。小学生2年生から学校に行かなくなって、そのまま中学を卒業したという例がある。一昔なら「全欠」というような例で、個人的にも何人か面識がある。このような場合、「不登校を経験した」というのではおかしい。夜間中学などで使われてきた表現を借りると「オール0」「形式卒業」ということになる。彼らは「不登校を経験した」のではない。そもそも通学した経験がないのだ。
つまり「不登校を経験した」と言えるのは、その後になって進学したという例に限られる。学校に通っていなかった期間があるから、その間の出来事が「不登校経験」として意味づけられるのだ。通わないまま、そのまま終わってしまったら中卒で――あるいは中学校を除籍されて小卒である。「不登校経験」を語るためにはタテ軸が必要となる。
中学校に一日も通わないままどうなったかと言うと、内申点が考慮されない通信制高校に進学することになった。市の教育相談センターから内申点がつかない以上、公立高校への進学は難しいというような説明を受けたからだ。川崎市は全国に先駆けて内申点摘除という制度を導入した。不登校生徒に関しては内申点を外して試験を認めるという制度である。当時、この制度はなかったけれども、かりにこの制度があったとしても私は利用することが難しかったろう。何しろ同年齢の制服姿を見るだけでも嫌気が差すくらいの学校嫌いだったのだから。
小学校6年時より通学をしていないが勉強は続けていた。中学校に入ると担任の教員が定期試験の用紙などを持って家庭訪問に来たので答案を渡した。平均点を越えていたことは記憶している。それが期末試験の頃からすべての答案が返ってこなくなった。
先の報道において「時代は変わっているのに学校が変わらない」という意見があった。しかし、確実に時代は変わっている。学習支援センターでは大学生が教えている。彼らが教育系大学の学生であれば教員の卵がボランティアに務めていることになる。それがしかし「学校以外の“居場所”づくり」と報道される。通学していない生徒が学習支援センターで教科学習に特化して勉強を教わったと考えれば東大現役合格という結果も理解できる。何度も言うが、それがタブーとされるのが「不登校」という言説空間だ。この点、現実を見据えているのは後者の報道だ。放課後の教室で勉強したということは教員の指導も得たということだろう。内申点の問題があるから公立高校の後期入試を狙ったという戦略が功を奏した。知りたいのはこういう戦略的な情報である。
私は何らかの理由で学校に行っていない者たちをひっくるめてスクールマイノリティと呼んでいる。『高校転入・編入マニュアル』の戸所保忠氏は「学校不参加生」という言葉を提唱された。「不登校」という用語の原語をNon Attendance at Schoolと考えれば(と言うのも、この点において私には異論がある)「不参加」のほうが適訳だというわけである。しかし学齢期の子どもが義務教育諸学校に籍を置くというのはやはり義務なのだ。参加せざるを得ないからこそ、そこで通学できないことのデメリットがある。
いくら「多様な学び」と言葉を濁そうとも学校に通学していない就学年齢期の者たちが「学校教育を受ける権利」を十分に保障されない現実は変わらない。学校教育とは教科学習だけではない。部活動なども含めての学校教育である。何年も学校に通わずスポーツ選手になったような例があるだろうか?
学校には通っていないが塾には通っているという例もある。単純にそれを通学と認めれば「不登校児童生徒」の数は減るのだが、ここにあるのが塾は学校ではないという「教育学の壁」だ。教育という理想が学校という現実を見損なっているのだ。教育という営みにおける理想は否定しないけれども、それがいったい誰にとっての理想なのか、という反省が必要だ。給食の時間だけ登校(?)し出席点を稼いで公立高校に進学、大学院に入って、今は大学の事務職員をやっている友人がいる。子どもというのは存外にズル賢い存在である。
私は通信制高校の指定校推薦を使って大学に進むことができた。なにせ英語もゼロから独りで勉強している。学力らしいものはない。ろくに同年齢と話すこともままならない。おっと、不登校経験を語ってしまった。博士号を取ったのはけじめをつけたかったからだ。義務教育課程の平常点がないから公立高校の進学が閉ざされるというのならこっちにも考えがある。教員の専修免許が修士課程で取れるのならその上の学位を取ってやろう。おかしなように聞こえるかもしれないが、学位は学歴ではない。私に学歴はない。ただ、学位はある。「多様な学び」など求めてはいないし「学校外の居場所」も必要ない。映画館の待ち合い席が居場所だったし将棋道場での人間関係に学ぶところが多かったからだ。おっと、口がすべった。
ヨコは理想論であるがタテは現実である。
タテを見据えてヨコを考えなければ、かえってスクールマイノリティたちの間に格差を生じさせることになる。多様は一様においてこそ意味をなす。戦前のように地主か小作かという身分差によって進学ルートが決まる複線型の時代は終わった。新教育と知られた男女共学、六三制という単線型の時代だ。しかし、それだからこそ競争が生じる。画一的な学校教育を批判することは易しいけれども、水平性を担保する公教育の理念を逸するようなことがあっては本末転倒である。何年も学校に通わずにいながらも最終的には高学歴となった者たちがいる。「学校になじめなかった」と言うべきか、それとも学歴社会にフィットしたと言うべきか。どちらの見方を取るかはあなたの自由だ。後者の途を拓くことも識者の任務なのではないか。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:ウクライナ情勢の深刻化と第三次世界大戦の危機 9月30日(月)13時半から
☆ISF主催トーク茶話会:伊勢崎賢治さんを囲んでのトーク茶話会のご案内 9月23日(月・祝)15時から
☆ISF主催トーク茶話会:仙波敏郎さんを囲んでのトーク茶話会のご案内 9月25日(水)18時半から
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。