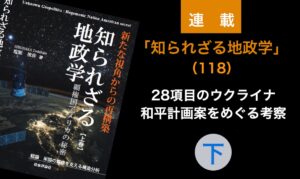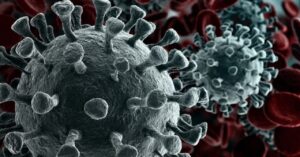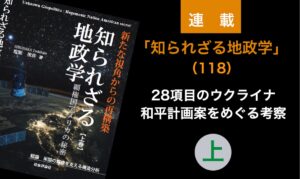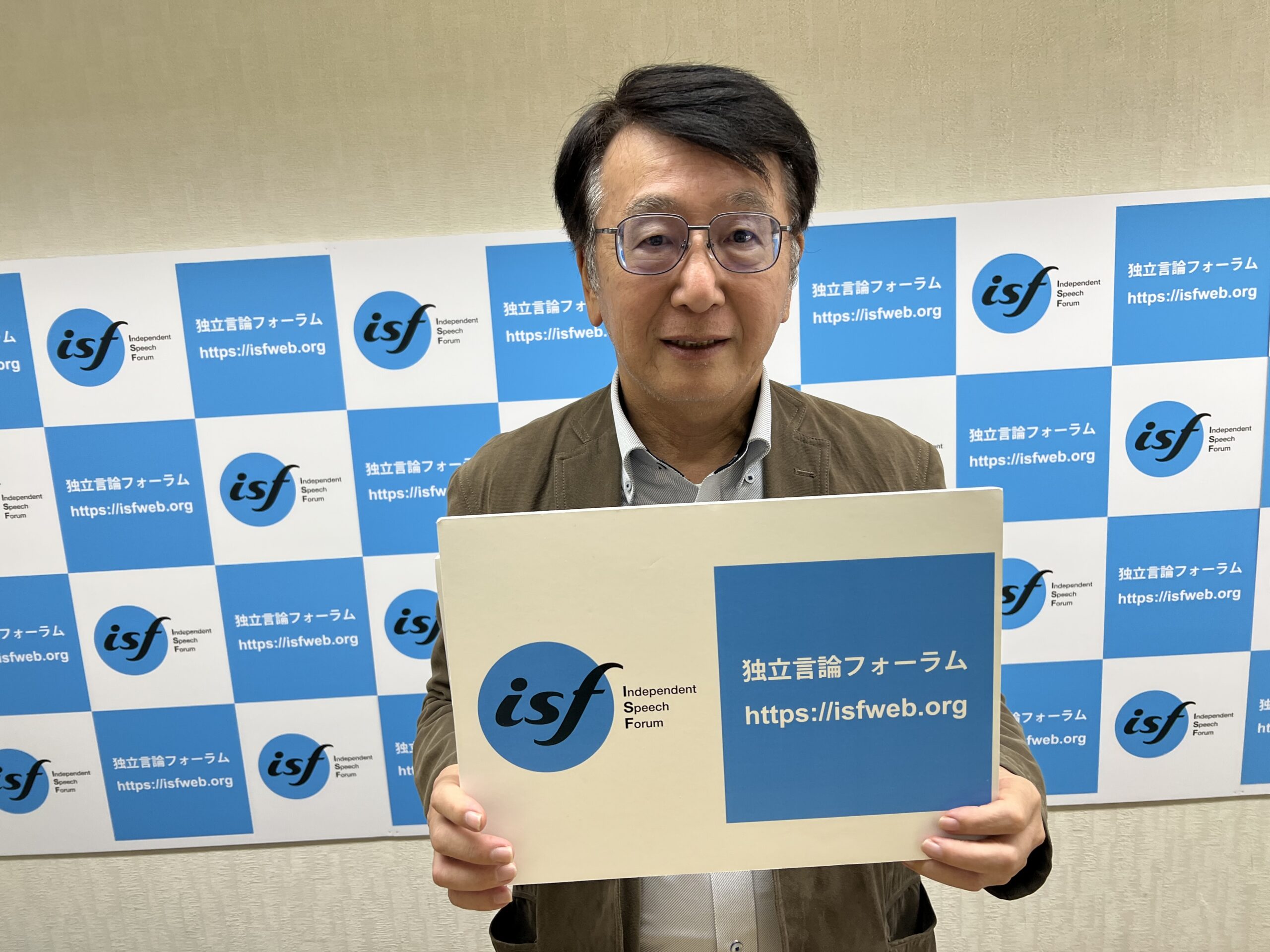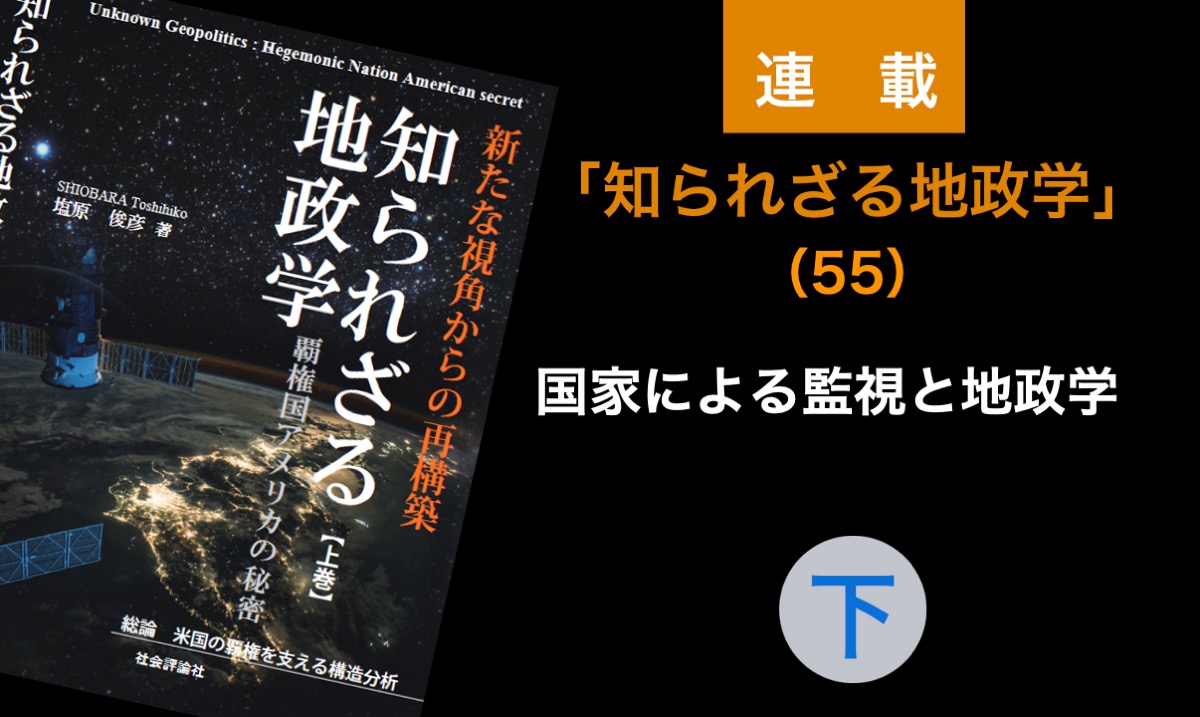
「知られざる地政学」連載(55):国家による監視と地政学(下)
国際
「知られざる地政学」連載(55):国家による監視と地政学(上)はこちら
たとえば、「マレーシアはいま、明らかにアメリカの監視下にある」
その意味で、「もしトラ」ではなく、「もしバイ」であっても、アメリカによる監視体制は強化される一方だろう。それを促進しているのが、長年つづく対ロ制裁であり、第三国への制裁(二次制裁)である。あるいは、イランや北朝鮮などへの制裁回避を監視する目的でも、米政府による監視がもはや世界中に広がっているとみなすべきなのだ。
たとえば、「マレーシアはいま、明らかにアメリカの監視下にある」と、中東の通信社、アルジャジーラは、「マレーシアのチップ産業が米国の対ロシア制裁の矢面に立たされる」という記事(2024年6月3日付)のなかで書いている。米商務省は、ロシアの軍産複合体による軍事転用を防止するために、①ロシアの高度な精密誘導兵器システムの生産において重要な役割を担っている、②ロシアの国内生産が不足している、③世界の製造業者が限られていることなどから、最も懸念される――品目を、「共通高優先品目リスト」に収載し、同品目の対ロ輸出を禁止している。これが意味するのは、米政府がこうした品目の取引を厳しく監視しているということだ。
記事によると、マレーシアの半導体メーカー、ジャトロニクスは、ロシアの軍事サプライヤーとの関係疑惑を理由に米国政府が制裁を5月1日に発表した300近い企業の一つとなった。ジャトロニクスが電子部品やコンポーネントをロシアの軍産複合体に供給しているロシアに拠点を置く企業に供給していたというのである。
ジャトロニクスは2022年4月から2023年9月までの間に、ロシア国内の企業に300万ドル以上の製品を50件以上納入した。そのなかには、マイクロチップ、半導体、半導体の原料であるシリコンウェハーが含まれているという。
2023年12月、アメリカはマレーシアに拠点を置く四つの企業に対し、イランに無人機の部品を提供する手助けをした疑いで制裁を行った。さらに、6月はじめ、米財務省の高官がマレーシアを訪れ、「イラン産の石油とテロリスト・グループの資金がマレーシアを経由することを許しているとして、政府に制裁のリスクを迫った」とも、記事は書いている。
いずれにしても、アメリカはマレーシアの個別企業の取引実態についてさえ、監視の目を光らせてきたし、いまもそうだということになる。
おそらく、アメリカにとっての同盟国のうち、欧州や日本については、各国政府に個別企業取引を監視させているが、それ以外の国については、アメリカ政府による監視体制が構築されている可能性が高い。
研究機関も監視下に
いま注目されているのは、研究機関の監視である。拙著『知られざる地政学』〈上下巻〉で詳述したように、主権国家は「科学」や「科学技術」、あるいは「テクノロジー」を世界中に流布し、それらを自国の企業によって生産させたり、特許権を取得させたりしながら、それらの影響力や利益の維持・拡大につなげ、ヘゲモニーを獲得できる。それを意図的に実践してきたのがアメリカだ。
近年でいえば、トランプ前政権は政権交代直前の 2021 年 1 月、「米国政府支援の研究開発に関する国家安全保障戦略についての国家安全保障大統領覚書33号」(National Security Presidential Memorandum-33, NSPM-33)を出した(『研究インテグリティ(Research Integrity) に係る調査・分析報告書』を参照)。大統領就任後、バイデンは、NSPM-33 を追認する一方で、2018年に司法省ではじまった、大学・研究機関の中国のスパイ研究者の摘発キャンペーンである「China Initiative」は 2022 年 2 月に終了させた。
他方で、2022年1月4日、大統領府科学技術政策局(OSTP)は、「NSPM-33 実施ガイダンス」を発表する。同文書の目的は、「連邦省庁に対し、NSPM-33 の実施に関する指針を提供すること」であり、NSPM-33 で取り上げられた、研究セキュリティの確保に関連する5分 野(①情報開示の要件と標準化、②デジタル永続的識別子、③開示義務に違反した場合の結果、④情報の共有、⑤研究セキュリティ・プログラム)についての詳細なガイダンスが含まれている。
2023年11月には、米中経済安全保障審査委員会は議会に対する2023年年次報告書を発表した。同報告書は、1965年高等教育法第117条のさまざまな改正を勧告した。たとえば、①教育省に対し、米国の大学・カレッジが過去10年間に受け取った中国・香港由来の贈与・契約を分析し、1暦年あたり25万ドル以上の贈与・契約(単独または総額)に対する現行の第117条報告基準の妥当性を評価するよう指示する、②教育機関に対し、不正確な情報や、第117条に基づき過去に開示された情報の変更を修正するための補足報告を提出することを義務づけ、報告遅延に対する罰則を設けることを各機関に義務づける、③大学やカレッジが潜在的な中国側パートナーと懸念される中国政府機関とのつながりを特定するために利用できる公開データベースを作成するための省庁間グループを設置する――などだ。
2023年12月、米国と中国共産党の戦略的競争に関する下院特別委員会は、米国と中国の経済競争に関する報告書を発表し、議会が取るべき更なる行動として、基礎研究のために連邦政府から補助金を受ける大学に対し、リスクベースのセキュリティ・レビューを実施し、前述した国家安全保障プログラム覚書33(NSPM-33)を完全に実施することを義務づけるよう提言している。NSPM-33 は、研究開発のための米国政府資金の受領者による利益相反の開示を義務づけ、年間5000万ドルを超える連邦科学技術支援を受ける機関に対し、研究セキュリティ・プログラムがあることを証明することを義務づけるよう、資金提供機関に指示している。このようなセキュリティ・プログラムには、サイバー・セキュリティ、海外渡航のセキュリティ、輸出管理、内部脅威のトレーニングなどの要素を含めるべきであるとされている。
これからわかるように、ここでも「国家安全保障」を名目にした研究機関への監視強化が実践されつつある。このアメリカの変化は世界中の同盟国に転移しており、そうした状況を調査した結果をまとめたが先に紹介した、2024年2年に公表された『研究インテグリティ(Research Integrity)に係る調査・分析報告書』ということになる。
当面の課題は「6G」
こうした科学や科学技術への監視において、注目されているのは、ホワイトハウス科学技術政策室のアラティ・プラバカー室長だろう。彼女は以前、国防総省の未来技術研究機関である国防高等研究計画局(DARPA)を監督していた。2024年6月3日付WPによると、現在、ホワイトハウスの科学技術政策室にいる彼女のチームは、半導体、電気通信、量子コンピューティングといった軍事応用技術における米国の技術革新をいかに加速させるか、同時に人種差別をすることなく中国と米国の研究交流をいかに抑制するかという、難しい問題を任されている。「彼女のチームはすでに、2030年頃まで配備されない6G世代について、中国よりも米国の無線技術を支持するよう同盟国から確約を取りつける工作を行っている」という。中国が5Gの研究開発を急ピッチで進め、ネットワークの展開も早めているため、米国当局は5Gで足元をすくわれており、5Gではなく6G対策をはかっているのだという。
子どもを理由にした監視強化
このように、「国家安全保障」を理由にした規制強化はたしかに広がっている。だが、もう一つ、米政府は「子どもの保護」を名目に監視強化に乗り出しつつある。拙著『帝国主義アメリカの野望』の「第四章 デジタル帝国間の競争」に書いたように、アメリカは基本的に市場主導型の規制を前提としており、デジタル分野での国家介入や国家監視には、もともと抵抗感が強かった。それでも、子どもの保護を名目にして、インターネット規制に向けた舵が連邦レベルでも切られたのである。
拙著『帝国主義アメリカの野望』では、つぎのように書いておいた。
「性表現が青少年に与える悪影響に対処する目的で、1996 年のコミュニケーション品位法(Communications Decency Act, CDA)、1998 年の児童オンライン保護法、2000 年の児童インターネット保護法というかたちで、徐々にインターネット規制に舵が切られたのだ。ほかにも、1998 年には、デジタル・ミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act, DMCA)が制定され、2000 年10 月から施行された。これらの米国の連邦法がその後、世界中でインターネットなどのサイバー空間への国家規制に道を拓いたことになる。その後、欧州評議会が2001 年になってサイバー犯罪条約を採択するに至る。」
こうした伝統もあって、現在、「バイデン大統領の下、民主党主導の連邦取引委員会は、子供のプライバシー、健康データ、敏感な個人情報に対する監視を強化しようとしている」と、2024年6月13日付のWPは記している。これは、最近の壊滅的なデータ漏洩を考慮し、野放図な商業監視とデータセキュリティの甘さを深く憂慮して、連邦取引委員会がハイテク企業への規制を強化し、子どものプライバシーといった個人情報保護に本腰を入れようとするものである。
しかし、エネルギー・商業委員会の議員らは、超党派の2大法案である「アメリカプライバシー権法」(APRA)と「キッズ・オンライン・セーフティ法」の採決に臨む予定だったが、失敗した。審議からはずされてしまったのだ。この二つの法案は合わせて、企業が特定の製品を提供するために必要なデータのみを収集し、未成年者への潜在的な危害を防止するための措置を講じることを義務づけるものであった。委員会のメンバーは数年前からこれらの問題に取り組んでおり、とくにデータ・プライバシーに関する交渉では、超党派の幅広い支持を繰り返し得てきた。
APRAは、アメリカ人の個人データを積極的に貪る企業に対し、要求に応じてデータを提供、修正、削除することを義務づけるとともに、さまざまなオプトアウト(事業者などが、当人が自ら行動し拒否するまで、意思を確認せずに製品やサービスに関して情報を勝手に送りつけたり個人情報を第三者へ提供したりすること、また、当人がその情報送付サービスなどから出ることを選ぶ意思を表示してそれらを拒否すること)や同意に基づく仕組みを導入することでデータの収集を最小限に抑えるなど、一連の新たな義務を課すことを目的としていた。しかし、大企業の利益を代表する共和党と、住宅、雇用、医療などにおける差別に敏感な民主党の双方からの賛成が得られず、法案成立が絶望的となってしまったのである。
結局、アメリカでは、連邦レベルの包括的なプライバシー保護法がいまだに成立していない。このため、子どものプライバシーだけでもしっかりと保護しようとしているが、それもどこまで規制強化できるかわからない。
CCTVの広がり
最後に、監視カメラとして使用される閉鎖回路テレビ(CCTV)のキットの普及状況について紹介してみよう。通常、「監視カメラ統計:最も監視されている都市はどこか?」というサイト情報がこの問題の解答として使われることが多い。
まず、中国が別格であると指摘しなければならない。2023年5月23日に更新された情報では、中国は、「人口14億3000万人に対し6億2600万台のカメラがあり、人口1000人当たり439.07台のカメラがあったことになる。ほぼ2人に1台の割合である。中国の諸都市を除く都市別でみると、インドのハイデラバードが人口1080万1,163人に対し90万台のカメラ = 1,000人あたり83.32台、同インドール60.57台、同デリー19.96台、シンガポール17.94台、モスクワ16.88台、バグダッド15.56台、ソウル 14.47台、サンクトペテルブルク13.49台、ロンドン13.21台だった。因みに、東京は人口1000人当たり約1台である。

図 人口1000人当たりの都市別CCTV設置台数
(出所)https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/
CCTVによる監視問題については、中国が「セーフシティ」や「スマートシティ」という名で世界中の都市に「監視システムの輸出」に積極的に取り組んでいるという問題がある(詳しくは拙著『サイバー空間における覇権争奪』を参照)。権威主義的国家が首都などの大都市にこの監視システムを導入し、顔認証システムと合わせて運用し、反政府活動の防止に利用するといったケースも増加している。リアルタイム認証も広がっており、まさに、1949年にジョージ・オーウェルによって刊行された『1984年』に登場する「ビッグブラザー」と呼ばれるオセアニアのピラミッドの頂点に立つ独裁者による監視社会に近づきつつあるように思えてくる。
アメリカでは、州によって顔認証システムの捜査への利用方法が異なっている。2024年6月29日付のNYTによると、デトロイト市警は、顔認識によって不当逮捕につながった既知の7件のうち3件に責任がある(他はルイジアナ州、ニュージャージー州、メリーランド州、テキサス州)と書いている。
2024年8月16日付のWPは、「イラン、監視衛星で中国の支援を求める テヘランは、高性能カメラを搭載した小型衛星を専門とする2つの中国企業との契約を模索している。情報機関の評価では、軍事利用の可能性が懸念されている」という記事を公表した。中国の監視技術が世界の権威主義的国家を席捲しつつある現実を忘れてはならないだろう。
愛媛大学の事件を忘れてはならない
ついでに、日本における顔認証問題についても書いておきたい。2019年7月22日、愛媛県警松山東署による誤認逮捕事案が公表された。松山市内の路上でタクシー内にあった運転手の現金入りセカンドバックを何者かが奪ったとされる事件で、愛媛大学の女子大学生が窃盗容疑で逮捕されたのだ。この誤認逮捕の理由は、「映像を見た捜査員の思い込みが原因だった」とされている。つまり、タクシー内に取り付けられていたドライブレコーダーの映像が犯行の決定的証拠とされたのだが、犯人とされた人物と逮捕者がまったくの別人であったのである。
この誤認逮捕はドライブレコーダーの映像を安易に利用することのリスクを示している。この捜査で警察が顔認証ソフトを利用したかどうかはわかっていない。ただ、誤認逮捕された女子大生の手記によると、「指紋採取やポリグラフ検査、3D画像の撮影など、すべての任意捜査に素直に応じてきました」という。にもかかわらず、「3D画像はきちんと解析したのか、ポリグラフ検査の結果はどうだったのかという私からの質問に対しては、はっきりした回答を得ることができませんでした」と、彼女は明確に指摘している。
3D画像の撮影というのは、「3D顔認証」という最新技術にかかわっている。これまで多くの顔認証では人の顔を平面でとらえる2D顔認証が主流だったのだが、3D顔認証は顔の凹凸までもデータ化し、化粧やヒゲがある場合でも認証を可能にする。すでに、iPhoneXなどで3D顔認証が採用されている。つまり、県警はこの最新顔認証システムを利用しながらも、犯人を間違え、まったくの別人を容疑者として逮捕するに至ったことになる。まさに、安易な顔認証技術への依存が決定的な誤りを引き起こした実例だ。にもかかわらず、この捜査上の失敗の原因や予防策が公的な場でしっかりと議論されたという話は聞こえてこない。「日本の国家公安委員会はまったく仕事をしていないのではないか」とはっきりと指摘しておこう。
日本の誤魔化し
日本は例によって、CCTVを「防犯カメラ」という名前で呼ぶことで、監視ビデオが至るところに広がりつつあるという認識を覆い隠そうとしている。このカメラは監視行為をしているにもかかわらず、「防犯」という不正確な文言によってその本質が覆い隠されてしまっているのだ。
防犯カメラはいわゆる閉鎖回路テレビ(CCTV)であり、監視がその役割の本質なのだ。このCCTVへの規制をめぐっては、日本では2003 年7 月に国会に提出された「行政機関等による監視カメラの設置等の適正化に関する法案」が審議未了で廃案となって以降、監視カメラをめぐる問題は一部の自治体で条例がつくられたほかはほとんど議論されていない。つまり、公的権力によるCCTV利用が場当たり的に推進されており、「2020東京五輪」はこのための最大の推進力となった。
にもかかわらず、日本のお粗末な主要マスメディアは、この問題を真正面から取り上げようとしない。政治家は官僚に丸め込まれて、国民のプライバシーを守ろうといった問題意識自体が希薄だ。逆に、警察当局は法的規制がないことを利用して、事実上、どんどんCCTV網を拡充している。はっきりいえば、政治やメディアの貧困がこうした事態を招いているのだ。
このように、国家による監視は地政学上の重要テーマの一つになりつづけている。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:ウクライナ情勢の深刻化と第三次世界大戦の危機 9月30日(月)13時半から
☆ISF主催トーク茶話会:伊勢崎賢治さんを囲んでのトーク茶話会のご案内 9月23日(月・祝)15時から
☆ISF主催トーク茶話会:仙波敏郎さんを囲んでのトーク茶話会のご案内 9月25日(水)18時半から
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)