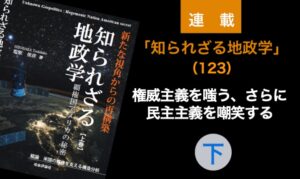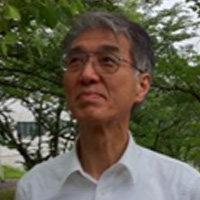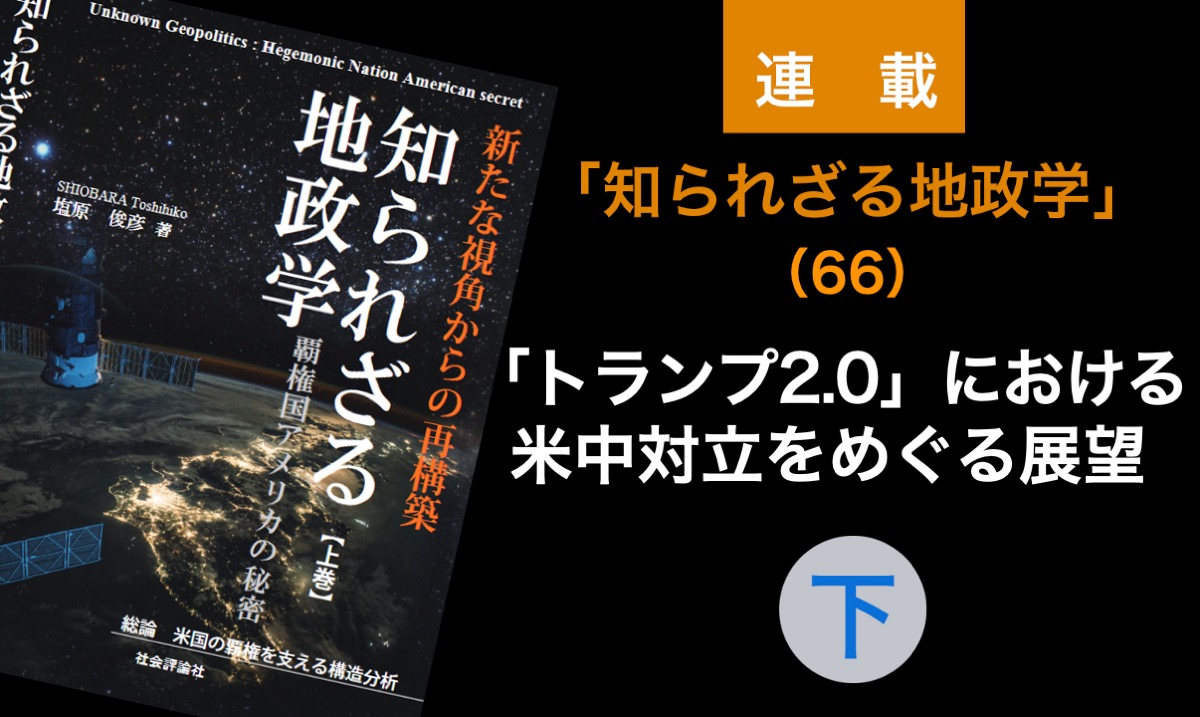
「知られざる地政学」連載(66):「トランプ2.0」における米中対立をめぐる展望(下)
国際
「知られざる地政学」連載(66):「トランプ2.0」における米中対立をめぐる展望(上)はこちら
対中関税政策の「闇」
私がもっとも懸念しているのは、対中関税政策にともなう「闇」の部分である。それは、関税の免除をめぐる恣意的な政策がとられることで、「腐敗」の温床となるのではないかという懸念を意味している。
トランプは11月19日、グローバル金融機関キャンターフィッツジェラルドの最高経営責任者(CEO)ハワード・ルトニックを商務長官および米国通商代表部(USTR)の監督者に任命する計画を発表した。トランプは、ルトニックが「関税および貿易に関する議題を主導する」とのべた。
ルトニック自身は、選挙戦中にトランプや一部の強硬派アドバイザーが言及したような普遍的な関税よりも、より的を絞った関税を支持するとのべている。彼は、「中国と取引をしたいと考えている」と主張しており、ルトニックは9月、CNBCの取材に対し、関税は交渉の道具であり、米国製品と競合する外国製品にのみ課すべきだと話している。
「政治化」の中身
すでに拙稿「連載(64)「トランプノミクス」:関税は地経学の絶好のテーマ」(上、下)で指摘したように、普遍的な関税については法案を通す必要があり、時間がかかる。このため、個別に関税を高める可能性が高い。
そこで問題になるのが、関税の「個別性」だ。それは、個別企業の要望に基づく恣意的な関税設定を意味している。そう、ロビイストの要望に応じて、つまりカネの多寡に応じて、対中関税政策が歪められる可能性が大なのである。
11月23日付の「ニューヨーク・タイムズ」は「トランプの通商政策は友人を利し、ライバルを罰する可能性がある」という記事を公表した。記事は、「ワシントンの弁護士やロビイストによれば、次期大統領の関税計画の全容が明らかになる前にもかかわらず、彼らのサービスを希望する企業からの依頼が殺到しているという」と書いている。
おそらく、「トランプ1.0」において、特別免除を申請できるプロセスが儲けられたときのような事態が繰り返される可能性がある。「トランプ1.0」下では、「何十万件もの関税免除申請が提出されることとなった」と、この記事はのべている。さらに、「中国関税の除外申請を扱った米国通商代表部には5万件以上の申請が寄せられ、商務省には鉄鋼とアルミニウムの関税に関する除外申請が50万件近く寄せられた」と指摘している。
「トランプ1.0」下で有名な例はアップルだろう。同社のティム・クックCEOは、トランプ大統領に繰り返し働きかけ、政権による対中貿易制限の緩和を実現し、iPhoneやその他のアップル製品に対する適用除外を確保した。
このとき、中国側にもお目こぼしがあった。「トランプ1.0」下では、中国テクノロジー企業であるZTEに対する制裁が解除され、また、中国企業であるファーウェイへの一部の販売を継続するための例外措置が講じされた。つまり、中国側もうまく立ち回れば、関税強化の網の目から逃れられる可能性がある。
こうした個別対応は、中国で電気自動車(EV)を製造するテスラを所有するイーロン・マスクにとっても望ましいだろう。
実は「トランプ1.0」にも「腐敗」
2024年7月に「関税免除の政治経済学」という興味深い論文が公表された。それによると、2018年7月からトランプ大統領の米通商代表部(USTR)は、拡大し続ける中国からの輸入品に一方的に関税をかけ始め、2019年9月までに年間5500億ドル相当の商品輸入のほぼすべてを平均約20%の関税率でカバーするまでに成長し、理論上は年間1100億ドルという過去最高の関税収入が得られるようになった。さらに、中国からの輸入品に新たな関税を課すと同時に、USTRは、輸入業者が個々の製品について関税の免除を申請できる「デノボ・プロセス」(de novo process)も確立した。
この関税免除のプロセスは、「米国の利益への害を防ぐため」と公言された目的で開始された。①その製品に関税をかけるとアメリカの利益に大きな損害が生じる、②代替製品が米国内でも中国以外の第三国からも入手できない、③その製品が中国にとって戦略的に重要でないとみなされる場合――免除が認められる可能性が高くなる。
とはいえ、その判断基準は曖昧だ。ゆえに、きわめて恣意的な免税措置が実際にとられた。論文は、「最終的に承認された1022件の提案は、最終的に却下された5993件の申請と比較して、選挙献金が多く、ロビー活動への支出が多い企業によるものである」と指摘している。さらに、「本来は独立した立場であるはずの政府の裁決プロセスが、少なくとも部分的には支持者に報酬を与えるために利用されているだけでなく、同じプロセスが反対派の支持者を罰するためにも利用されていることがわかる」とも書いている。
おそらく、「トランプ2.0」下でも、「トランプ1.0」と同じことが繰り返されるのではないか。これが「トランプ2.0」の腐敗した実態となるだろう。
中国の出方
それでは、中国側は「トランプ2.0」にどのように対応するのだろうか。2007年から2010年にかけてオーストラリアの首相を務め、習氏が指導者になった後の2013年にも再び首相を務めたケヴィン・ラッド(現駐米大使)が2024年10月に刊行したOn Xi Jinping: How Xi’s Marxist Nationalism is Shaping China and the World(Oxford University Press)という本がある。ここでは、同書を紹介しながら、習近平国家主席の今後について論じたThe Economistの記事を参考にしてみたい。記事は、「習近平は、ラッドがマルクス主義ナショナリズムと呼ぶ方向に舵を切った」と断じている。 つまり、党を粛清し、その統制を強化し、経済政策を市場原理から中央計画の強化へとシフトさせ、より好戦的な外交政策に乗り出したというのである。 ラッドの見解では、「習近平は2032年の4期目の任期終了までに、理想的には戦争なしで台湾を手に入れたいと考えている」という。ラッド自身は、 「彼を阻止できるのは、米国、台湾、同盟国による効果的かつ信頼性の高い軍事的抑止力だけだ。そして、習近平が、中国がそのような関与を失うという現実的なリスクがあると信じている」と書いている。
どうやら、そこに問題があるらしい。習がそのリスクをどう判断するかはだれにもわからないからだ。しかも、習近平は「リスクテイカー」とみられている。「表向きは汚職を理由とする高級官僚の粛清はその表れである(何百万人もの人々が、習氏に静かに怒りを燃やしているに違いない)」、とThe Economistは指摘している。そのうえで、「台湾周辺やフィリピンが領有権を主張する浅瀬での軍事力の誇示もそうだ」と指摘し、「習近平のこれまでの行動がプーチンほど無謀でなかったとしても、今後はそうなるかもしれない」とのべている。
習近平は経済政策において、左寄りの発言で企業家を脅かしている。 2021年に開始された習近平の「互恵共栄」キャンペーンでは、新たな大規模な再分配制度が打ち出された。 その努力は、大手ハイテク企業に対する規制の取り締まりと重なり、イデオロギーによる私企業の巨頭への攻撃のように思われる人もいた。 しかし、ここ1、2年、習近平は経済再生に奮闘している。これは、民間企業をよりソフトに扱い、ハイテク製造業を促進することである。「一部のエコノミストは、福祉への支出を増やせば貯蓄を減らして消費に回すようになり、経済が活性化すると主張しているが、習金平はそのような目的のためにお金を配ることを批判している」、というのがThe Economistの見方だ。
こんな習近平は11月17日、ペルーでバイデンと会談した。中国国営通信社である新華社によると、習氏は、米国との関係において中国にとっての四つの「レッドライン」、すなわち台湾、民主主義と人権、中国の進路と体制、中国の成長の権利を強調したという。もちろん、このレッドラインは「トランプ2.0」にも向けられている。だが、その具体的な中身ははっきりしない。そして、レッドラインを越えた場合の対抗措置も判然としない。
バカにできない中国の底力
先に説明した、中国の輸出と輸入代替への注力のうち、輸入代替による中国の技術的底力についても書いておこう。それは、ファーウェイが11月に発売したスマートフォンによって裏づけられている。
この端末は「Mate 70」と呼ばれている。端末を動かす半導体は、中国が自国製チップの開発でどれほど進歩し、外国の技術への依存から脱却しつつあるかを明らかにすることになる。ファーウェイは、このデバイスに同社が新たに開発したオペレーティングシステム、HarmonyOS NEXTを搭載している。これは、中国が欧米諸国の支援するシステムから完全に脱却する初めてのケースとなる。
中国はこれまで、圧倒的に米国のモバイルOSに依存してきた。グーグルのAndroidとアップルのiOSは、中国国内のほぼすべてのスマートフォンを含め、世界中のスマートフォンの約98%を占めている。しかし、今回のスマートフォンが成功すれば、この米国企業支配に風穴を開けることができる。
ファーウェイの社名は、「China has promise」(中国には将来性がある)という言葉を縮めたものであることをご存じか。中国の技術力を侮ってはならないのである。
米中関係の将来
長期的な視点に立つと、米中間の覇権争奪は科学の力によって決するのではないかというのが私の見立てである。米国は科学を支配することで、世界統治を可能にしてきたのであり、その統治を今後も長く継続するためには、米国は最先端科学において世界をリードしつつけなければならない。
先に紹介したニカフタールは、新政権は人工知能(AI)チップだけでなく、量子コンピューティング、ロボット工学、バイオテクノロジーといった他の新興技術も視野に入れ、米国から中国への先端技術輸出をさらに制限する新たな規則を導入することになるだろうと予測している(2024年11月14日付の「ワシントンポスト」を参照)。
おそらくこうした最先端分野におけるテクノロジーが今後の米中間の力関係を決定づけることになるのではないか。そう考えるとき、トランプによる米国の科学技術戦略が気にかかる。中国は、相変わらず国家主導で突破口を開こうとしているが、こうしたやり方では最先端分野の多くで勝利を手にすることはできないだろう。
さりとて、トランプのように、カネ優先の政策では、「腐敗」がはびこるだけでいい結果を得られるとは思えない。
どうする日本?
こうしたなかで、日本政府はいつまで対米従属をつづけていくのだろうか。米中間の覇権争奪の行方ははっきりしない。そうである以上、いつまでも米国に隷従しつづけているのはいかがなものか。
前回書いたように、2025年1月に、私は、国際アジア共同体学会から2024年度の「岡倉天心記念賞」を授与される。いま、強く意識しているのは、1903年に出版された『The Ideals of the East』(東洋の理想)において、岡倉が、その冒頭で、“Asia is one”(アジアは一つである)と書いたことだ。
これはあまりにも有名な話だが、私もアジアの思想に少しずつ関心を寄せている。その発端は、『復讐としてのウクライナ戦争 戦争の政治哲学:それぞれの正義と復讐・報復・制裁』を執筆したことにある。そのなかで、キリスト教神学を徹底的に批判しようとしたからだ。
たとえば、つぎのように書いておいた(88~89頁、118頁)。
「本書の展開を先取りして書いておくと、欧米というキリスト教を中心とする文明は復讐心を含めた復讐全体を刑罰へと転化しようとする。それが可能だと錯覚させたのは、この文明化がキリスト教神学の一部の主張に立脚してきたからにほかならない。だが、その根幹にある「罪たる犯罪の罪滅ぼしとして暴力的罰が必要である」とする信念それ自体に大きな疑問符がつく。キリストの磔刑を素直に考えれば、それは、これから説明する「純粋贈与」そのものであり、その教えこそ大切なのだ。にもかかわらず、西洋の歴史は、「互酬的な贈与の(自己)否定」がもたらしうる帰結を否認し、抑圧することを繰り返してきた。これこそ、キリスト教神学による贖罪の利用という「咎」であり、現代までつづく西洋文明のもつ、隠れた「咎」なのである。」
「ここまでの論理で決定的に問題なのは、罪というものを贖う(罪滅ぼしをする)ことではじめて神の報復を避けられるとする信念が犯罪を処罰するという、世俗国家の刑罰にまで適用されることが当然とみなされるようになった点である。つまり、復讐の刑罰への転化という近代メカニズム自体のなかに、キリスト教神学でいう贖罪の考え方が挿入されているのである。しかも、その罪滅ぼしは暴力的犠牲(violent sacrifice)という「暴力」を伴ってなされるのであり、いわば「暴力への暴力による贖い」という応報主義をそのまま受け入れている。そこでは、贈与と返礼という、価値などの量ではかることを前提とする債権・債務に置き換え可能な関係そのものを拒否する「純粋贈与」という、キリストの磔刑の本質的な意味がまったく否定されてしまっている。天秤によってイメージされる均等性原則はそれ自体が間違っているにもかかわらず、この原則がキリスト教神学によって強化され、近代にも引き継がれ、戦争による復讐劇につながっているのである。」
こうした批判は、芦東山の「無刑録」への傾倒につながってゆく。だからこそ、「連載(52)自民党総裁選・立憲民主党代表選と外交・安保問題」(下)において、芦東山の話を書いておいたわけである。
アジアの片隅に位置している日本という国家の地政学的意義を考えながら、歴史や道徳や法律について、深く思考しつづけなければならないと思うこの頃だ。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)