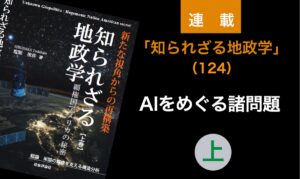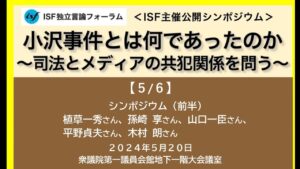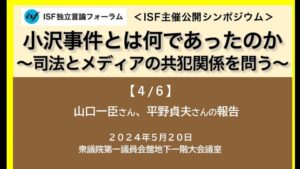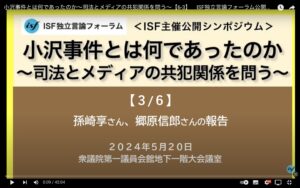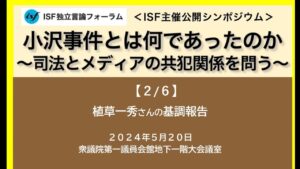CO2を悪者扱いすることの愚かしさ 松田 智(市民記者)その4
社会・経済これまで解説してきたように、「人為的CO2地球温暖化説」には科学的根拠が乏しく、従ってCO2削減=脱炭素が無意味であることは、科学的にはほぼ明確になりつつある。しかしこの説は国連が旗を振り日本を含むG7等米国系諸政府が公認していることもあり、広く行き渡ってしまった(ただし、BRICS等の非米国系諸国では、まともに相手をしていない)。その結果、CO2は削減すべき「悪玉」であり、極論としては「この世から無くなったら良いもの」の一つに数えられるまでに至っている。しかしこれは、科学、特に化学や生物学・生態学の知識不足から来る大きな誤解である。そこで今回はまず、脱炭素政策批判の前提としての、主に炭素(C)とCO2をめぐる科学的な基礎知識を振り返ってみることにする。
まず、元素としての炭素の特異性について。人間を含む全ての生物体を構成している物質の大部分は、水分と微量の無機物を除くとタンパク質を中心とする有機物、すなわち炭素化合物である。かつ、人間を含む多くの生物は、食料として有機化合物を摂取しないと生きて行けない。無機物だけで生きて行ける生物は、緑色植物など、無機物から有機物を合成できる特殊な能力を持つもの(独立栄養生物)だけである。その意味で、人間などの有機物依存型生物(従属栄養生物)が生きて行くには独立栄養生物の作ってくれる有機物が必須であり、これは持続可能社会を考える上でも基本的な前提条件になる。簡単に言えば、緑色植物なしに動物類は生きて行けないと言うことである。宇宙空間で長く生き残る難しさも、この点が大きい。「霞を食っては生きて行けない」とは、よく言ったものである。
都会で何の苦労もせず食料にありつき、マネーゲームなどに狂奔している人々は、自分の生存を支えてくれる植物の存在、それも一人当り1ヘクタール近い面積が必要である事実など、全く知らないだろう。それでいて、カネ勘定ばかりしていて「農業などGDPの1%程度しかないから保護に値しない」などと、天に唾するようなことをほざく輩が結構いたりするのだ。もしも食料が入手できなくなったら、いくらお金を積んでもムダなのに。全く「身の程知らず」なことではある。人間とその社会において「食べる」は絶対条件であり、故に農林水産業は必須である。この一次産業をないがしろにする国家は、滅ぶしかないのだ。「アリとキリギリス」のたとえは、単なる寓話ではない。
さて、化学において炭素は特異な位置にあり、炭素化合物すなわち有機物だけで化学の一大分野を占める。化学には物理化学、無機化学、有機化学、高分子化学、分析化学、生化学、環境化学などの諸分野があるが、炭素という1種類の元素だけで有機化学と言う1分野を構成している。他にはこんな例はない。なぜ、炭素だけが特別なのか?
理由の一つは、炭素化合物すなわち有機物が非常に多数存在するから。これは、炭素と言う原子が結合の腕を4本持ち、それらが1本から3本まで結合でき、長い鎖状でも丸い環状でも複雑な構造でも構成できるからである。炭素は原子量12の軽い元素であるが、有機物はメタンなどの小さな炭化水素から始まり、核酸やタンパク質の中には分子量が数百万に及ぶ巨大な分子がある。これらは非常に長い炭素骨格に酸素・窒素・水素・リン・硫黄や各種金属元素などが結合して出来上がっている。
さらに、これら巨大分子もひとたび完全に分解されれば最終的にCO2、H2O、N2のような気体となり、特にCO2は水に良く溶ける点が自然界で循環するために非常に重要な特徴になる。結合の腕が4本ある第14族(炭素族)元素には、炭素、ケイ素、ゲルマニウム、スズ、鉛がある。この中で酸化物が水に溶ける気体になるのは炭素だけである。つまり、自然界で容易に循環できる第14族元素は炭素しかない。しかもケイ素より重い元素では、炭素のように柔軟な分子を作ることが出来ない。これは生物体を構成するためには致命的な欠陥であって、それ故、もし生物体が地球外に存在するとしても、有機物つまり炭素骨格の化合物からなることは必然である。
こうして見ると、生物体を構成し自然界で循環できる元素は、第14族では炭素のみ、他には酸素・窒素・水素などごく限られた種類に限られることが分かる。それらの中で、大きな化合物の骨格を作れるのは炭素のみである。そして、有機物の最終酸化物であるCO2が気体で、かつ水に溶けやすい特性を持つことが、自然界で循環するために必須の性質である点を押さえておこう。すなわち、生物体を構成する炭素が自然界で循環するためのカギ物質が、CO2である。これだけでも、CO2を「悪者」扱いするなど、もっての外だと分かるはずだ。
地球環境の中で、絶えず循環している元素としては、酸素・水素(主に水の形で)・炭素・窒素・硫黄など、ごく限られた種類だけである。リン・鉄その他の金属類も全く循環しないわけではないが、循環量は非常に少ない。循環するためには、最終酸化物が気体であることが、強い制約条件になっている。なお、リン・硫黄・鉄など比較的重い元素の循環には、細菌類や鳥類など生物の働きが重要な役割を果たしていることも知っておくべきである。特に、鳥類の糞にはリンが多く含まれ、リンの貴重な供給源となる。鳥類は食物連鎖の比較的上位に位置するから、これを支える植物・昆虫・小動物・魚類などが要る。つまり健全な生態系が必須なのである。
さて、炭素循環の第一段階は、大気中CO2からの有機物合成、つまり光合成である。自然界の中で人間や多くの生物にとって光合成ほど「有難い」化学反応はない。何しろ、大気中CO2と水だけから有機物(最初は簡単な単糖)と酸素(O2)を作ってくれるのだから。これが出来るのは緑色植物と藍藻類など葉緑体を持つ生物に限られる。なお、大気中CO2を固定する反応(=炭酸固定)として通常の光合成の他に、水の代わりに硫化水素(H2S)を使うタイプ(一部の光合成細菌が行う)や独立栄養微生物(硝化細菌、鉄細菌、水素細菌など)が行う非光合成的炭酸同化があるが、CO2固定量はO2発生型の光合成が圧倒的に多い。以前に紹介した地球上の炭素循環で、地面=植物が吸収するCO2量が約100Gt-C/年の規模であることを述べたが、この量は人類起源CO2総量の約10倍強にも達するほど大きい。
そのため、光合成で作られる有機物=バイオマスをエネルギー化できるなら、化石燃料など不要になるのではないかと、一時期には騒がれた。何しろ、光合成総量の1/10でもエネルギーに使えたら、他のエネルギー源は不要になるくらい豊富なのだから。これは主に1980年代、石油危機後の「石油代替エネルギー」探しの過程で話題になった。それで実は、私の博士論文は、このバイオマスエネルギーがどの程度有効なものなのかを、具体的に検討することで書かれた。研究結果の一部を紹介すると、バイオマスを実際にエネルギー化、例えば「バイオ燃料」を製造する際に必要なエネルギーが大きい場合が多く、当初の予想よりも正味で得られるエネルギーは少ないとの結論になった。しかし「バイオ燃料」が一般に「カーボンニュートラル」であるとの「信仰」は根強く、今でもその誤解は晴れていないと思う。この件については、以前にアゴラに書いた(https://agora-web.jp/archives/2051597.html)。
その一例としてSAFと呼ばれている航空燃料を挙げておく。SAFはSustainable Aviation Fuelの略で「持続可能な航空燃料」と訳される。従来のジェット燃料が原油から作られるのに対して、廃食用油、サトウキビなどのバイオマス燃料や都市ゴミ、廃プラスチックを用いて生産される。廃棄物や再生可能エネルギーが原料のため、従来のジェット燃料と比べて約60〜80%のCO2削減効果があるとされる。故に航空分野ではCO2削減に最も効果が高いとされており、世界各国で官民挙げてSAFの利用に取り組んでいる。しかし、このSAFにも問題は多い。この件もアゴラに書いておいたが(https://agora-web.jp/archives/240904062744.html)、ここでもバイオマス燃料は「カーボンニュートラル」であるとの「思い込み」が、大きな役割を果たしている。
結論的に言えば、バイオマスの有効な用途は、人間の都合で言えば、1)人間の食料、2)家畜その他の食料(飼料等)、3)紙パルプその他の化学原料、4)エネルギー源、5)土壌生態系保持用物質(大地に返すべき腐植物質、焼却灰その他)、の順となるべきである。つまり、バイオマスは食料その他の用途に使えるだけ使い、最後に廃棄する段階でエネルギー化できるなら良しとすべきであって、食料・飼料になるサトウキビからいきなりバイオ燃料(この場合はバイオエタノール)を作って燃やしてしまうなど「もっての外の沙汰」なのである。おりしも最近、経産省が2030年度までにバイオ燃料をガソリンに最大10%混ぜる燃料の供給を業界に求めると報道された(https://www.yomiuri.co.jp/economy/20241111-OYT1T50177/)。これなども愚かの極みと言うしかない。昨年のガソリン内需量は約4400万kLだから、その10%は約440万kL、バイオ燃料はガソリンより発熱量が低いので必要量が多くなり、500万kLにもなる。そもそも、これをどうやって調達するのか?まさか食料になるトウモロコシやサトウキビを使うのではあるまいな?人間の食料を自動車に食わせる超愚行なのに。それ以外の原料では調達困難なはずだが。しかも製造コストがまた絶望的だ。こんなことを石油業界に求める感覚が、どうかしている。正に狂気の沙汰。
話を戻す。光合成で作られた有機物=バイオマスは、動植物や微生物の身体・細胞になり栄養になり、一部は木造建築などに使われて長く残るが、通常は比較的短時間で代謝されたり燃やされて、最終的には大半がCO2やH2Oとなって大気や大地に還る。この大規模な物質循環の中で、人間を始め全ての生物が、生まれては死んで行く営みを繰り返していると言うのが、この世界の実相である。この事実は、どんなに科学・技術が進んでも変わらない。AIやIT技術がどんなに進歩しても、バーチャルの世界では「食って行けない」ので、人間は、呼吸して食事を摂り排泄しながら生きて行く。故に、これらの物質循環系を大切に保持しなければ、人間社会の持続可能性はあり得ない。産業面で言えば、食料生産(=農林水産業:一次産業)や廃棄物処理と言った、地道な泥臭い現業こそが重要なのであって、パソコンをいじっているだけでは持続可能社会は実現出来ないのである。
炭素固定と並ぶ重要な生物反応として、生物的窒素固定についても紹介しておこう。この反応はマメ科植物などの例で知られているが、実際に窒素固定を行っているのは、ある種の特殊な細菌類である。これらの細菌類はニトロゲナーゼと言う特殊な酵素を持っていて、これが窒素固定を行う。空中窒素(N2)は反応しにくい物質だが、これに水素をくっ付けてアンモニア(NH3)を作ると言う離れ業をやってのける。人間がN2とH2からNH3を合成するには、現状では数百℃、数百気圧と言う高温高圧を必要とするが、ニトロゲナーゼはこれを常温常圧(!)で行う。しかも、くっつける水素はH2ガスではなく、どこか(の有機物)からH原子を持ってきているらしいが、メカニズムの詳細はまだ明らかにされていない。光合成も恐ろしく複雑な反応だが、窒素固定もまた、未だ人知の及ばない複雑精妙な反応系である。
このニトロゲナーゼ、分子量数百万に達する巨大分子であるが、なぜか酸素(O2)に極端に弱い。恐らく、太古のO2が無かった時代に生じたからだろうと言われている。酸素に触れるとすぐ失活するので、窒素固定微生物や豆類は、これを保護するために様々な工夫をする。中には、ポンプを空回しするような機構(酸素を除去するためだけにATPを消費する:普通はあり得ない)もあり、この酵素を酸素から護って維持するために涙ぐましいまでの努力を傾けるのである。我々が口にする肉類その他のタンパク質等のかなりの部分は、この生物的窒素固定で作られた有機体窒素からなる。その有り難さを、身に沁みて感じ、味わうべきであろう。
なお、炭素と異なり、自然界における窒素の循環量は、人間由来対自然界が1対1に近くなっている(炭素では1対10以上)。それだけ、工業生産による人工的窒素固定量が増えているわけである。これは必ずしも喜ぶべきことではなく、土壌や水環境中に窒素化合物(NOxやNH4+)が増えることにより窒素濃度が上昇し、海洋や陸水の富栄養化、硝酸性窒素による地下水汚染などの諸問題も起きている。本来なら、窒素固定量を制限すべきなのかも知れないが、食料生産には窒素肥料が欠かせない。実際、作物の反収(単位面積当りの生産量)は概ね、ある程度までは窒素肥料の投入量に比例するからである。「窒素汚染」はまだ広く認識されていないが、いわれのない「CO2汚染」などより遙かに深刻な問題である。さらには、コストと手間をかけて合成したアンモニアを燃料に使う試みが、石炭火力からCO2発生を減らす方策として行われている。これについては別稿で論じるつもりだが、結論は「どこからどう見ても、愚かの極み」と言うに尽きる。
CO2循環に話を戻す。大気中CO2濃度約420ppmから計算されるCO2量は、約700〜800Gt-Cである。1年間に大気と地表を循環するCO2量は、約200Gt-C/年である。従って、大気中CO2の平均滞留時間は3.5〜4年程度と計算される。つまり、4年経つと大気中CO2は大半が入れ替わってしまう。従って、IPCC報告書に出ている、産業革命時代(1850年頃〜)からのCO2排出総量(蓄積量)と気温上昇に比例関係があるとの説(https://www.jamstec.go.jp/rigc/j/reports/ipcc6/03.html)には科学的根拠がないと思う。排出量累積値は減ることがない増加関数(必ず右肩上がり)で、一方地球平均気温はここ100年程度で見れば緩やかに上昇しているから、両者をプロットすれば、あたかも比例しているように見えるのは当たり前なのだ。つまり、これは実際の因果関係があってもなくても成り立つグラフである。この種の「グラフのトリック」は、数限りなくある。私にはこんな図を有難そうに戴き「CO2排出量はあと○トンまでに制限せよ」などと「予言」する人の頭が理解できない。
現実には、地球気温は毎年のように上がったり下がったりしている一方、観測の範囲で大気中CO2濃度は毎年ほぼ一定ペースで増加しており、両者の相関度は低い。しかも以前に見たように、大気中CO2濃度上昇幅約2ppm/年のうち、人類起源の占める割合は数%しかなく、かつ大気中CO2は3〜4年で大半が入れ替わると言うのに「1850年以来のCO2排出総量が気温上昇に効く」などと言うことが、一体あり得るかどうか・・?私にはそのメカニズムが想像もできない。
1957年の国際地球観測年事業の一つとして始まった大気中CO2濃度測定記録では、その頃320を割っていたCO2濃度は、その後毎年少しずつ上昇し、今では約420ppmに達しているが、地質調査などから大昔はもっと高い時期もあったようだ。何億年も前には7000ppmと言った高濃度の時期もあったらしいが、その頃「灼熱地獄」だったとの証拠はない。もっとも、7000ppmと言えばとんでもない高濃度に思えるが、0.7%に過ぎない。大気中の水蒸気でも通常1〜3%あるし、大気中の微量成分であるアルゴンでさえ約1%ある。しばしば「観測史上最高」と言われる今の大気中CO2濃度は、長い地球の歴史から見れば、まだまだ低濃度の領域にある。その濃度を人間の手で変えようとしてもほとんど効き目がないことは、科学データが示している。
最後に、人間社会における炭素源について触れる。今の人間社会に供給される有機物のうち、プラスチックやゴムなどの大半は石油化学製品つまり化石燃料由来であり、残りは農林水産業由来つまりバイオマスである。後者は大気中CO2から光合成で作られるが、人工光合成はまだ実用化されていない。H2Oを分解してH2を得るのは何とかできるが、CO2を還元して糖その他の有機物を合成する段階が難しいからだ。もし手間暇かけて人工光合成が出来たとしても、結局は植物を育てる方が簡単で安い、となる可能性が高いと私なら思う。まして医薬品その他の超複雑な天然有機物の合成は、絶望的に難しい。結局は、微生物や植物の細胞などを培養して作らせる方が早い。タンパク質や核酸などの巨大化合物もそうである。従って、人類の炭素源の大きな部分は将来もずっとバイオマス依存であり、現在は大きな部分を占める石油が枯渇したら、しばらくは石炭を使うことになる(C1化学と言う分野があり、石炭活用技術は既にある)。故に、大気中CO2を炭素源に使うのは、上記の人工光合成が実用化された後の話になるからかなり先の話で、石炭類さえも枯渇しそうになった時代になる。今、脱炭素などとのぼせ上がっている人たちは、頭を冷やして良く考えることだ。今すぐ「脱化石燃料」などをやって、生きて行けるものかどうかを。
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 松田 智(市民記者)
松田 智(市民記者)
まつだ・さとし 1954年生まれ。元静岡大学工学部教員。京都大学工学部卒、東京工業大学(現:東京科学大学)大学院博士課程(化学環境工学専攻)修了。ISF独立言論フォーラム会員。最近の著書に「SDGsエコバブルの終焉(分担執筆)」(宝島社。2024年6月)。記事内容は全て私個人の見解。主な論文等は、以下を参照。https://researchmap.jp/read0101407。なお、言論サイト「アゴラ」に載せた論考は以下を参照。https://agora-web.jp/archives/author/matsuda-satoshi