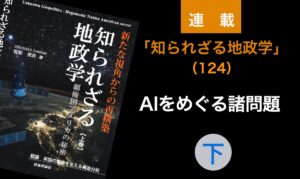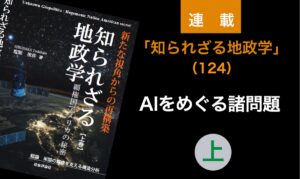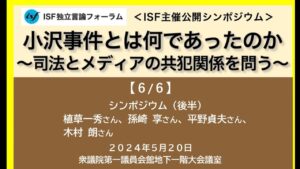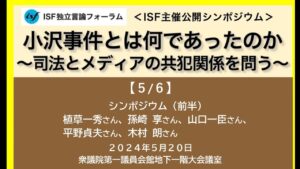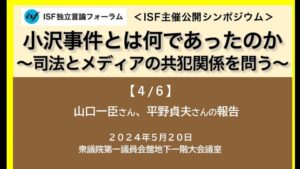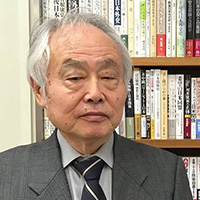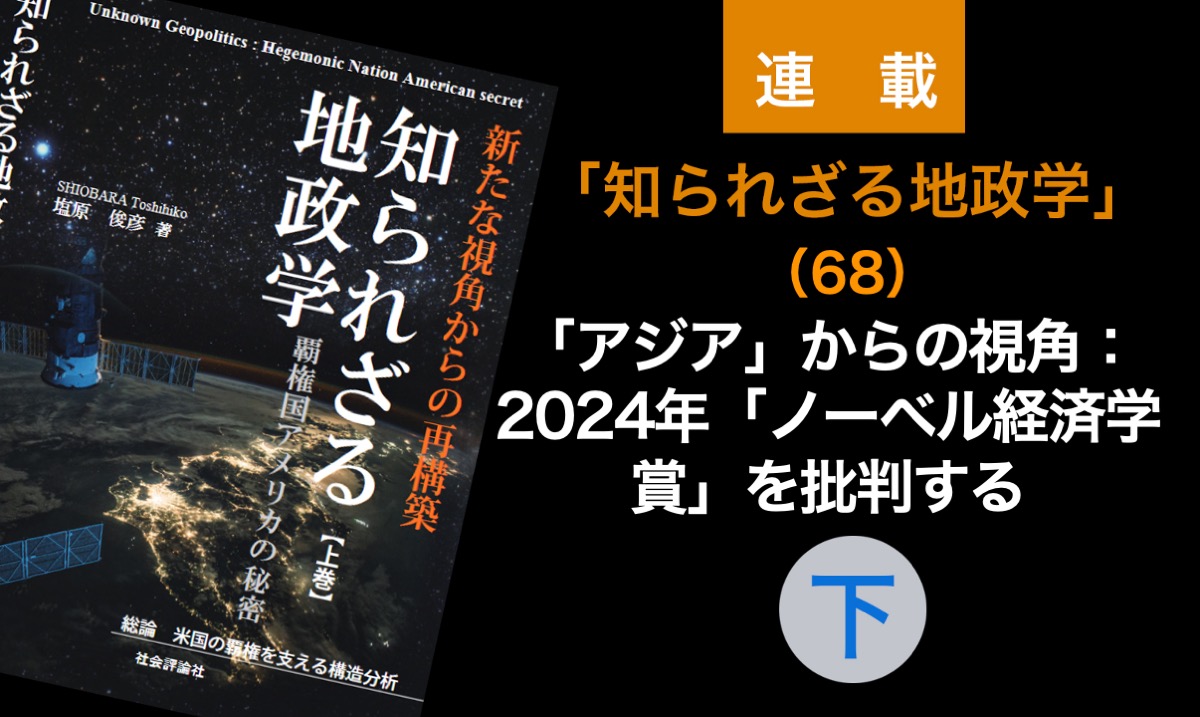
「知られざる地政学」連載(68):「アジア」からの視角:2024年「ノーベル経済学賞」を批判する(下)
国際
「知られざる地政学」連載(68):「アジア」からの視角:2024年「ノーベル経済学賞」を批判する(上)はこちら
AJRは中国をどう見誤ったか
彼女は、AJRの定義によれば、中国の政治制度は独裁的であるため、「抽出的で非包摂的」である。「そうだとすれば、1980年代以降の驚異的な成長をどう説明できるのだろうか? 」と問いかけている。
彼女によれば、AJRの答えは、毛沢東の死という「重大な岐路」と、それに続く鄧小平の改革連合構築への努力によって、中国は好転したというものだ。さらに彼らは、中国のような極貧国には「追いつく」ことがたくさんあったからこそ、搾取的制度の下での成長が可能だったのだと主張する。最後に、彼らはこうまとめているという。「歴史は常に偶発的な形で展開するからだ」と。
これに対して、彼女は、「私は、彼らが「中国の異常さ」を「運」のせいにして振り払えることにも同様に驚いている」、と皮肉交じりに書いている。
「毛沢東の死後、鄧小平が権力の座に就いたとき、彼は一党独裁政治に民主主義の特質(具体的には、競争、説明責任、権力の一部制限)を挿入した」という事実こそ、本当はきわめて重要なのだ。この点については、Yuen Yuen Angが2018年5/6月号の『フォーリン・アフェアーズ』誌のエッセイ「中国的特徴をもつ独裁」で指摘している。さらに、2023年1月に『ニューヨーク・タイムズ』紙に公表されたエズラ・クラインとのインタビューにも詳しい。
具体的には、鄧小平と彼の改革派チームは、最高レベルの集団指導の規範など、権力に対する部分的なチェックを導入し、腐敗や悪い政策の実施について苦情を申し立てる権限を市民に与えた。彼らは、国家指導部からのトップダウンの指示と、多数の地方政府や企業家によるボトムアップの適応を融合させた「指示された即興」を実践し、中国国内で多様な発展の道筋と政策の革新を生み出し、しばしば地方の状況に合わせたものとなったのである。
その後、「習近平は2012年に権力の頂点に立つと、鄧小平の部分的自由化を着実に覆し、個人主義的支配を復活させた」、とYuen Yuen Angは書いている。習近平は、中国を金ぴか時代から脱却させ、よりクリーンで質の高い発展を遂げる「赤い進歩の時代」へと導くためには、権力の集中が必要だと考えているというのだ。
そのうえで、彼女はつぎのように書いている。
「もしあなたが、西洋の民主主義は本質的に「包括的で搾取的でない」一方で、西洋以外の非民主主義国家は「非包括的で搾取的」であるという単純な二元論に同意するなら、言葉に欺かれることになるだろう。民主主義国家は、非包括的で抽出的な性質を鋭く含むことができ、その逆もまた然りである。」
欧米批判
さらに、Yuen Yuen Angは、「資本主義的民主主義のイデオロギー化は歪んでいる」と記している。開発プログラムに翻訳されると、それは常にトップダウンで画一的なキャンペーンとなり、貧困層を無力化するというのである。そればかりか、それは西側資本主義と民主主義に長年くすぶっていた問題を検知する目を体制側に奪わせてしまったという。この問題は「腐敗」(corruption)をめぐる議論のなかに典型的に表出している。
彼女の指摘、すなわち、「豊かな民主主義国を清廉潔白、貧しい国を腐敗していると一貫して評価したことで、エリート層は、豊かな国々における「アクセスマネー」(合法化されたエリート層の権力と利益の交換)の隆盛が市民を怒らせ、ポピュリズムに向かわせていることに気づかなかった」という記述は正鵠を射ているのではないか。
米国で長年つづくロビイスト活動は、実は、金権政治を制度化したものにすぎない。「アクセスマネー」をロビイストに渡し、それをロビイストによって政治家に仲介してもらうことで、贈収賄罪を免れているのである。これが意味しているのは、他国の法律からみると、明らかな汚職に該当する行為が平然と行われても「お咎めなし」であるということだ。この制度が金権政治を蔓延させているとみなすことができるだろう。
ロビイスト問題を国際的に分析した拙著『民意と政治の断絶はなぜ起きた』の30頁につぎのように書いておいたので、参考にしてほしい。実に、わかりやすい誤魔化しについて紹介しておいたのだ。
「このレッシグの指摘はハーバード大学の理論経済学者アンドレイ・シュライファ―がその著書『普通の国:共産主義後のロシア』(A Normal Country: Russia after Communism)のなかで指摘したことと対応関係をもっている。
彼は、「いくつかの国では、腐敗は合法化されている。なぜかというと、賄賂という言葉が使われていないからである。たとえば、米国では、政治家は好意と交換に選挙運動寄付金を受け取っているのだが、それは他国では賄賂をもらうことである」と指摘している。この記述を読んだとき、筆者はシュライファ―がロビイストのことを頭に置いていることにピンときた。ロビイストという言葉こそ出てこないが、彼がここで言っているのは、ロビイストが贈収賄の隠れ蓑となっているということではないか。そう思えたのである。」
こう考えると、こんな国が主導する価値観をそのまま受け入れて、世界全体をながめると、とんでもなく歪んだ世界像になってしまうことになる。「豊かな民主主義国(とくに米国)=清廉潔白」、「貧しい国=腐敗」ではなく、「米国=腐敗蔓延」という視角に立たなければ、現実をみたことにはならないのだ。
たとえば、あのドナルド・トランプでさえ、2020年の大統領選では、「沼を干上がらせよ」(Drain the Swamp)と叫び、既得権益を批判した。この言葉は、「蚊を退治するには蚊が育つ大元である沼地そのものをなくさなければならない」という含意で、20世紀はじめに「貧富の格差をなくすには資本主義そのものを解体せよ」というように社会主義運動家が使っていた文句らしい。トランプとしては、ワシントンという沼地を正直で説明責任を果たす街に変えるといった意味なのだろう。エスタブリッシュメント、既得権益者の外部に位置していたトランプは、エスタブリッシュメントの腐敗を批判することで、既成の秩序に挑戦した、あるいは、「自分も入れろ」と主張したのである。
だが実際には、生き血をすする蚊の群れにまぎれて、自身も「クレプトクラート」(盗賊政治家)になろうとしているようにみえる。そう、この言葉は掛け声だけに終わり、いまや、トランプは「沼を泳ぐ」ようになっている(詳しくは、「現代ビジネス」に公表した拙稿「手口を全暴露!これが腐敗で焼け太りする「トランプ流関税悪用術」だ」を参照)。
厳しい批判
彼女の「欧米中心の政治的・観念的な秩序を支持しながら、社会のなかで民主主義的価値観を説くことは、明示的であれ暗示的であれ、偽善的である」という指摘は正しい。別言すると、「民主主義だけで国家が豊かになり、強大になるという大げさな約束をするのではなく、多様で周縁化された集団に声を与え、権力に責任を負わせるという、民主主義本来の価値を称えるべきである」、と彼女は主張しているのである。
この主張は、民主主義を標榜している国がまったく非民主的なウクライナを支援している現実を想起させる。前者では、金権政治が蔓延し、情報統制下にあるにもかかわらず、その事実に大多数の国民は気づいていない。後者では、ロシア語を話していないかどうかの「言語パトロール」の動きがあり、無理やりバスに押し込める「バス化」と呼ばれる強制動員が行われている(前回の「知られざる地政学」連載[67][上、下]を参照)。
さらに、Yuen Yuen Angは、つぎのように主張している。
「今日、多くの専門家や権力者は21世紀を「ポリクライシス」(多危機)の時代としてとらえているが、これもまた西洋中心的な考えであり、主に豊かな世界の資本主義と民主主義の二重の危機によって引き起こされたものであることに気づいていない。私は時代を異なる視点で捉えている。これはパラダイムシフトの可能性を秘めた時代である。」
能天気なAR
アセモグルとロビンソン(AR)は、2024年7月19日付で、NYTに「民主主義の危機に対する我々の解決策」という意見を公表した。それは、「リベラルデモクラシーがこの街で唯一のゲームであり、歴史の終わりが私たちに迫っていると誰もが考えていた1990年代を覚えているだろうか?」という出だしではじまっている。
ベルリンの壁崩壊の数カ月前の1989年、元米国国務省政策企画局次長のフランシス・フクヤマは、その時流を先取りして「歴史の終わり?」という論文を発表し、1992年になって、The End of History and the Last Manを刊行した。その45頁に、「つまり、勝利を収めているのはリベラルな実践というよりもリベラルな思想である。言い換えれば、世界の大部分において、リベラルデモクラシーに挑戦できるような普遍性を主張するイデオロギーは存在せず、人民主権以外の普遍的な正統性の原則もない」と書いている。それほど、リベラルデモクラシーをもてはやす人が多かったのは事実かもしれない(このリベラルデモクラシー自体を批判したのが拙著『帝国主義アメリカの野望』である)。
しかし、その民主主義が危機を迎えているというのがARの大前提である。20世紀を通じて民主主義が成功した理由は、政治的平等主義(人々は自らの生活や国の統治方法について発言権をもつ)と経済的平等主義(進歩の成果は、少なくともある程度は共有される)の存在に集約されるが、「経済的平等主義は、過去40年間で失われてしまった」うえに、「人々が政治に対する影響力をほとんど失っているという感覚と重なった」と指摘している。それにもかかわらず、ARは、「民主主義が唯一の選択肢ではないにしても、民主主義が依然として最良の選択肢であることは事実である」と根拠なしに記している。
政治的平等主義と経済的平等主義をつなぐ、いまの資本主義の問題点を解きほぐすといった視角はまったくみられない。先にのべた「豊かな民主主義国を清廉潔白、貧しい国を腐敗していると一貫して評価したことで、エリート層は、豊かな国々における「アクセスマネー」(合法化されたエリート層の権力と利益の交換)の隆盛が市民を怒らせ、ポピュリズムに向かわせている」という視点はゼロである。ポピュリズムなるものが受け入れられているのは、金権政治という腐敗の蔓延に対する人々の怒りの証であり、彼らのほうがポピュリズムを批判するエスタブリッシュメントやその信奉者よりもずっと誠実なのだ。
この結果、ARは、これまで民主党を支持してきた一部がむしろトランプを応援するようになったかをまったく理解していない。そのため、トランプ政権になると大変なことになると脅しているだけだ。まったく能天気な分析にすぎないのである。
しかもARは、自分たちの主張が豊かな者、すなわち西洋中心主義者の論理にすぎないことに気づいていない。要するに、「上から目線」なのだ。その結果、ARはだます側に立っている。それは、西洋中心主義がだましている視角と同じものなのである。
岡倉天心のアジア
話はここで終わらない。岡倉天心の思想に戻りたいからだ。最初に紹介した柄谷行人の論文は、1902年、日露戦争の直前にインドに滞在していたときに岡倉が英文で書いた『東京の思想』を紹介している。“Asia is one”ではじまる有名な本だが、柄谷はそれを分析してつぎのように書いている(139頁)。
「岡倉は東洋のoneness(一つであること)を美術において見た。というよりも、彼はそのような「東洋」を発見したのである。彼が世界史を美学的に見る視点を獲得したのは、フェノロサから学んだヘーゲル哲学を通してである。『東洋の理想』というタイトルにおいて、「理想」は達成さるべき何かではなく、すでに現実的に存在するような、ヘーゲル的理念Ideeである。ヘーゲルによれば、歴史とは、理念が自己表現する舞台であり、そして、芸術はこの理念が感性的に具現される形態である。ヘーゲルにおいて、芸術は哲学的認識の下位におかれている。しかし、実際は、彼の哲学が全体として美学的なのである。岡倉が、アジアの歴史を、理念の自己実現としての美術の歴史ととらえたのは、その意味でヘーゲル的である。しかし、その場合、直接に言及していないが、彼はヘーゲル的な西洋中心主義を逆転するだけでなく、その弁証法そのものを標的としている。ヘーゲルにおいては、矛盾が重要である。それが、闘争を生み歴史を発展させるものだからだ。しかし、岡倉においては、インド哲学のadvaitism(不二一言論)、いいかえれば、相違し多様なるものonenessを持ち込む。かくして「アジアは一つである(Asia is one)」という言葉が出てくるのである。」
こう書いたうえで、さらに、柄谷はつぎのように記している(140~141頁)。
「岡倉にとって、東洋のonenessは、西洋列強による植民地化という運命のもとにある東洋の同一性を暗黙に意味していた。しかし、彼は、そうした消極的な同一性ではなく、積極的な同一性を見いださねばならなかった。そして、それは美術の観点において以外に見いだされない。実際、東洋のonenessは、西ヨーロッパと違って、政治的・宗教的な観点からは不可能だからであり、第二に、美術が西洋と対抗しうる唯一の領域だという自信が岡倉にあったからだと言える。この本における審美主義は、フェノロサとは違って、明瞭に政治的な意図をはらんでいる。岡倉にとって、実は「東洋の理想」などない、「東洋」が一つの理想なのである。」
日本の「偉大な特権」
杞憂かもしれないが、柄谷のつぎの指摘も重要だ(142~143頁)。
「彼(岡倉)は狭義のナショナリストではなかった。なぜなら、彼はつねに「東洋」を視野においていたからである。他のナショナリストが日本の独自性を強調するのに対して、岡倉は日本の思想・宗教がすべてアジア大陸に負うことを率直に認める。彼は、『東洋の理想』においてインドの仏教哲学、『茶の本』において中国的仏教(禅)を原理的なベースとさえするだろう。だが、彼はその上で、日本の「偉大な特権」を見出す。それは、日本において、歴史的に、インドや中国などで起こりそこでは消滅してしまったものがすべて保存されてきたということである。たとえば、仏教はインドで消滅し、中国で発展された禅仏教もそこでは消滅している。それらがすべて残っているのは日本だけである。美術にかんしても同様である。」
こんな岡倉は、日本の「島国的孤立」が「日本を、アジアの思想と文化を託す真の貯蔵庫たらしめた」と言う。そうであるならば、いつまでも西洋中心的価値観だけに重きを置くような学問のあり方をもうそろそろやめてほしいと思う。
Yuen Yuen Angのような厳しい批判が日本人のなかからも出てきてほしいとも思う。私が「岡倉天心記念賞」の受賞者として強く心に決めているのは、せっかく貯蔵庫にある視角を西洋中心主義批判に活用するということだ。
アメリカによる文化的ヘゲモニーの奪取
最後に、再び柄谷行人の「美術館としての歴史」からの引用を紹介したい。アメリカによる文化的ヘゲモニー奪取の構造を分析した部分である(146~147頁)。おそらく、この分析は社会科学や自然科学を含む科学全般にも通じる。どうか、心して熟読玩味してほしい。
「第一次大戦以後に、アメリカは大英帝国にとって替わって、経済的・軍事的なヘゲモニーを握った
しかし、それはまだ文化的ヘゲモニーではない。アメリカがヨーロッパの文化的ヘゲモニーを奪取したのは、実は、美術館によってである。たとえば、1929年にニューヨークの近代美術館が設立され、フィリップ・ジョンソンが31年に近代建築展をやってモダン・アーキテクチュアを持ってくる。さらに、館長のアルフレッド・バーが、36年に「キュービズムと抽象美術」、ついて「幻想芸術、ダダとシュールレアリズム」という展覧会をやって、これまでのヨーロッパのモダン・アートの流れを幾何学的抽象の系列と表現主義的な系列とに分けて総括した上で、アメリカにおける抽象表現主義こそがそれらを総合しつつモダン・アートのフロンティアに立つのだというシナリオをつくった。そのあと、クレメント・グリンバーグをはじめとする批評家たちがモダン・アートのパラダイムを明確に論理化し、さらに、その論理を別な形で使いながらサブ・パラダイムを競合させ交替させてゆく過程を組み立てた。しかも、美術館や批評ばかりか、美術市場もその過程に加わる。この意味で、世界の美術は、アメリカという「美術館」のなかに吸収されたと言ってもよい。もちろん、それはある飽和点に達したように見える。そして、他方で、multi-culturalismの動きが興隆している。それはある意味でフェノロサが目指していたものに近いだろう。しかし、岡倉が気づいていたように、そのことは言説的な闘争discursive struggleを伴うことなしにありえない。」
文化的ヘゲモニーに対する考察も、いま現在の地政学・地経学の分析に大いに参考になる。どうか、誠実に生きようとする人は、ここでの私の考察を肝に銘じてほしい。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:トランプ政権と東アジアの危機回避 ~米中対立の行方~
☆ISF主催トーク茶話会:真田信秋さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:船瀬俊介さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:大西広さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)