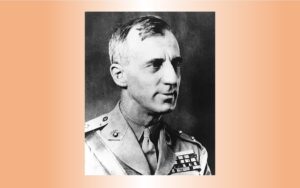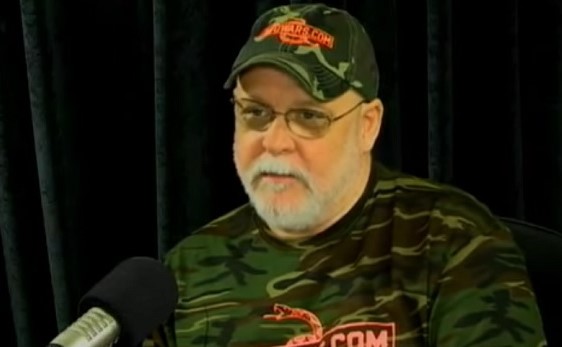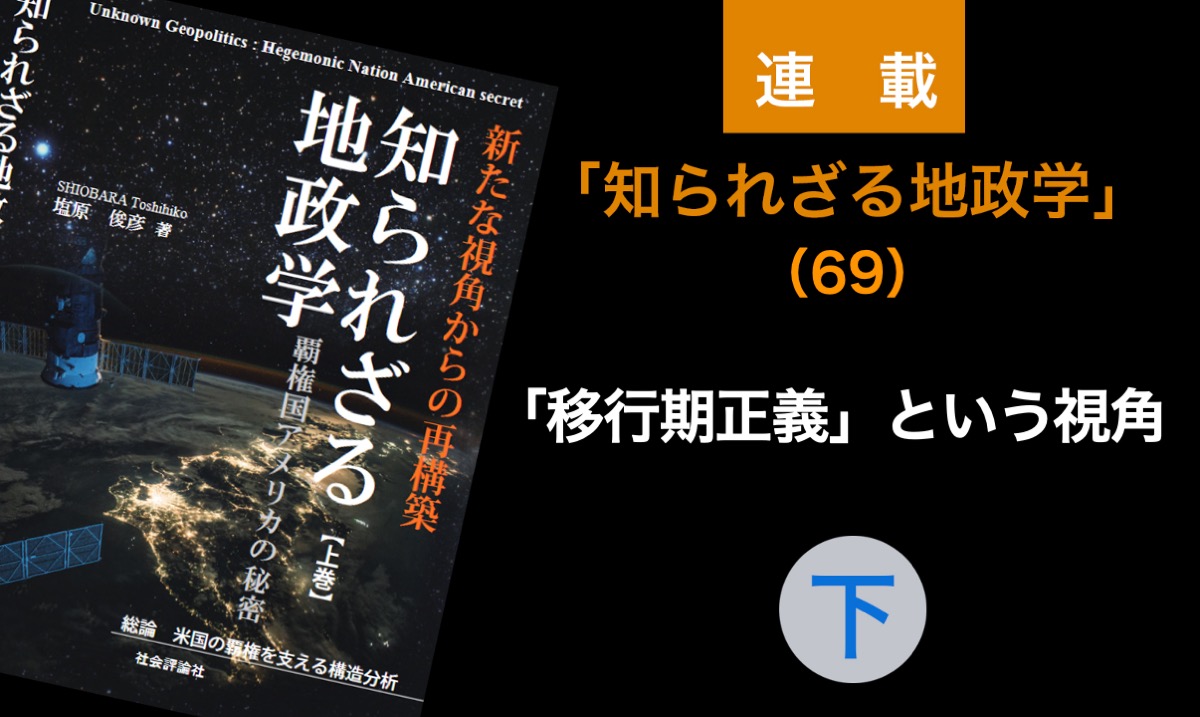
「知られざる地政学」連載(69):「移行期正義」という視角(下)
国際
「知られざる地政学」連載(69):「移行期正義」という視角(上)はこちら
アメリカにおける「移行期正義」問題
今回の政権移行は、ある人にとって、英語で「最良の者による支配」を意味する「アリストクラシー」から、「最悪の者による支配」、すなわち、「カキストクラシー」(kakistocracy)への移行のように映るのかもしれない。
なお、The Guardianの説明によると、カキストクラシーはギリシャ語のkakistos、つまり「最悪」から借用されたもので、それ自体はおそらく原始インド・ヨーロッパ語のkakka、つまり「排便する」という意味から来ている。「ナンシー・フリードマンが2016年に言語に関するブログで書いたように、「カキストクラシーとは 「クソによる政治 」である」と言える」という。
トランプが復讐心に燃えていることは周知の事実だ。2024年11月14日付のWPはつぎのように報じている。
「トランプは、選挙戦終盤の保守派のトークショーで、次のように発言した。自身に対して2件の刑事事件を起こした特別検察官ジャック・スミスを「国外追放すべき」だと。また、民主党のカマラ・ハリス氏と並んで選挙戦を戦った共和党の元議員リズ・チェイニー氏を「過激なタカ派」と呼び、「9つの銃口が向けられる」べきだと発言した。さらに、元統合参謀本部議長のマーク・A・ミリー将軍を処刑すべきだと示唆する発言をし、ソーシャルメディアに「過去の時代であれば、その行為は死をもって償うべきほど悪質な行為だ」と書き込んだ。」
WPによれば、「報復措置には、刑事捜査や起訴といった厳しい処罰だけでなく、それほど劇的ではない処罰も含まれる可能性がある」。退職した政府高官は、民間部門での業務に重要な場合が多いセキュリティクリアランスを失ったり、煩雑な税務監査に直面したりする可能性があるという。加えて、トランプ支持者のなかには、政府高官や議員だけでなくその家族も含む敵対者リストを作成する者もいる。
「政治的武器」になった訴追
司法をめぐっては、訴追が「政治的武器」として使われてきた現実がある。たとえば、保守派の判事任命に焦点を当てた団体の創設者、マイク・デイビスは、ソーシャルメディアに「私は彼らの政治生命を奪い、街を引きずり回し、燃やし、壁から突き落としたい。(もちろん、法的、政治的、そして財政的にだ)」とのべ、具体的には、トランプに対する4億5000万ドルの民事詐欺訴訟の背後にいるニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズ氏に対して警告を発した。
デイビスはさらにインタビューで、「政治的目的のために情報機関や法執行機関を政治利用し、武器化している検察官、弁護士、証人、その他の工作員は、調査を受け、必要であれば起訴されるべきである」とした。加えて、ジェームズだけでなく、ワシントン、ニューヨーク、ジョージア州でトランプ氏に対する刑事事件に関与している検察官やその他の関係者も調査の対象とすべきだと付け加えたという。
バイデンによる恩赦
ジョー・バイデン大統領は2024年12月1日、声明を出し、自らの次男ハンターの恩赦に署名したのである(下の写真を参照)。米国では、Executive Clemency、すなわち行政長官による恩赦という制度がある。犯罪で有罪判決を受けたか、有罪判決を受ける可能性のある個人に対し、恩赦、減刑、猶予を与える大統領と知事の一般的な権限を指す。
バイデン大統領は、Executive Grant of Clemencyを発出し、米憲法第二章第二条第一項に定められた「大統領は、弾劾の場合を除き、合衆国に対する犯罪について、刑の執行停止または恩赦をする権限を有する」という権限に基づいて、ハンターに対して、2014年1月1日から2024年12月1日までの期間中に彼が犯した、あるいは犯した可能性のある、あるいは関与した米国に対する犯罪への完全かつ無条件の恩赦を付与するとしたのである。

ジョー・バイデン(左)と息子ハンター(右) (Reuters)
(出所)https://www.economist.com/leaders/2024/12/02/joe-biden-abused-a-medieval-power-to-pardon-his-son
一見すると、憲法に認められた権限の行使によって、息子の罪を帳消しにしただけのようにみえる。しかし、ハンターという人物に対して、連邦陪審は2024年6月、デラウェア州で銃器関連の重罪3件で有罪判決を下していたし、ハンター自身、同年9月、最高17年の懲役刑が科される脱税容疑9件についても有罪を認めていた。つまり、彼は12件の重罪で有罪判決を受けていた犯罪者だった。
そんな人物を大統領は赦した。しかも、彼はハンターを絶対に恩赦しないと明確に約束していた。たとえば、ABCが2024年6月に行った単独インタビューをみても、ビデオの8分過ぎの場面で、恩赦はしないと答えている。
それは、「法の上に立つ」大統領による法を無視した傍若無人なふるまいにみえる。これでは、「法のもとの平等」という「法の支配」の大原則に背くことになる。
バイデンによる長期恩赦
バイデンの今回の恩赦は、論文「恩赦権の歴史」にある恩赦権の三つの重要な制限(①恩赦を行うには犯罪が成立していなければならない、②大統領の権限は連邦犯罪に限定されている、③大統領は弾劾の場合には赦免状を発行できない)の①に違反している。なぜかというと、完全かつ無条件の恩赦の期間がほぼ11年と長すぎるのである。
過去をみると、ウォーターゲート事件後にリチャード・ニクソン大統領が辞任した後、1974年にジェラルド・フォード大統領がニクソンに恩赦を与えたケースがある。このときには、1969年1月20日から1974年8月9日の間に「犯した、または犯した可能性のある」犯罪が挙げられていた。ニクソンのときにも、その恩赦にはウォーターゲート事件とは無関係の犯罪(もしあれば)も含まれていたはずだが、今回もハンターの犯罪として立件されそうな案件があるとみられている2014年以降が恩赦の対象期間となっている。
いずれにしても、ニクソンの場合も、ハンターの場合も「犯罪成立」という要件を満たしていないまま、何がなんでも罪を赦すという、法をまったく無視した立て付けになっている点が大いに気になる。
トランプによる復讐に備えるバイデン
バイデン大統領がほぼ11年間も息子の恩赦を決めた背景には、2025年1月20日に大統領に就任するトランプ新大統領による「復讐」への対策がある。先の声明では、「ハンターの事件の事実を調べた合理的な人物であれば、ハンターが私の息子であるという理由だけで標的にされたという結論に達するはずであり、それは間違っている」としてうえで、「執拗な攻撃や選択的起訴にもかかわらず、5年半も麻薬を断ってきたハンターを打ちのめそうとする動きがあった。ハンターを打ちのめそうとするなかで、彼らは私を打ちのめそうとした。そして、ここで終わると信ずべき理由はない。もう十分だ」とのべている。
つまり、バイデンは「トランプ2.0」のもとで、過去の息子の罪が炙り出されることを恐れて、あえてほぼ11年もの恩赦を決めたのである。
バイデン父子が恐れているのは、2014年にハンターがウクライナ企業の取締役に就任し、巨額の報酬を得ていた事実に絡む告訴だ。NYTは、「下院共和党の調査では、大統領の息子が父親の名前をビジネスに利用していたことは明らかになったが、バイデンが副大統領または大統領としてハンターのために行動したことを証明することはできなかった」と書いている。だが、「トランプ2.0」のもとで、告訴される可能性は大いにあった。
「先制恩赦」の検討
2024年12月5日付のWPは、「ホワイトハウス、潜在的なトランプのターゲットのために先制恩赦(preemptive pardons)を検討」という興味深い記事を公表している。記事は、「恩赦の可能性が検討されている人物のなかには、バイデンのコビッド19への対応を調整したアンソニー・S・ファウチ、トランプ氏を「ファシスト」と呼んだマーク・A・ミリー元統合参謀本部議長、トランプに対する最初の弾劾訴追を主導したアダム・シフ次期上院議員(カリフォルニア州選出)、共和党の率直なトランプ批判者であるリズ・チェイニー元下院議員(ワイオミング州選出)などがいる」、と伝えている。
とくに、「トランプがFBI長官に選んだカシュ・パテルは、トランプの敵対者や批判者に対する報復を促している」と書いている。だからこそ、先手を打って、バイデンは「先制恩赦」によって、復讐・報復としての立件ができないようにしようとしていることになる。だが、それは逆に、復讐・報復としての立件自体の正当化につながりかねない。むしろ、政治家による司法の「悪用」をどう抑止するべきであるかについて、真正面から論じ、制度的手当てを構築する必要があると思われる。
なお、バイデンのホワイトハウスは12月12日、約1500人の刑期を短縮し、さらに39人の非暴力犯罪者に対して恩赦を与えると声明を発表した。今後、トランプ再登場までに、さらなる恩赦が予想されている。
FBIへの報復
ついでにFBIもまた報復対象となっている話も書いておきたい。トランプは、FBI長官クリストファー・A・レイの後任に、FBIの指導部を解任し、その任務を劇的に再編成することを公言している、忠実な支持者であるカシュ・パテルを指名したいと発表した。実は、トランプはレイを10年の任期で任命した張本人なのだが、トランプはFBIを恨むようになった。その理由の一つは、2020年11月の大統領選直前の10月14日付の「ニューヨーク・ポスト」のスクープをフェイスブックなどのSNSがリンクしないように圧力をかけ、隠蔽することにFBIが加担した事実にある(この話は「「知られざる地政学」連載[43]情報統制の怖さ[上、下]」に詳述した)。
ただし、トランプの11月29日夜の発表は正式な指名とは言えず、トランプがレイを解任するか、FBI長官が10年の任期満了前に退任しない限り、パテル氏がFBIを引き継ぐことはできない(FBI長官の任期は通常10年。リチャード・M・ニクソンがFBI長官に指名したL・パトリック・グレイが、ウォーターゲート事件に関するFBIの調査に関する文書を破棄し、ニクソン政権に調査に関するブリーフィングを行ったことが明らかになった後、ウォーターゲート事件後の政府改革として1976年にこの任期が課された。任期制限は、FBI長官の政治指導者や政党からの独立性を主張するためのものである)。
ところが、12月11日、レイはバイデン政権の終了時に辞任すると発表した。これで、パテル登場の可能性が高まっている。
元公選弁護人で連邦検察官だったパテルは、トランプ第一次政権で働き、ホワイトハウスでテロ対策アドバイザーを務めた。また、2020年の選挙に敗れたトランプ大統領のホワイトハウス任期最後の数カ月は、クリストファー・ミラー国防長官代理の首席補佐官を務めるなど、さまざまな国家安全保障ポストを歴任した。パテルはまた、国家安全保障会議のテロ対策担当上級部長や、リチャード・グレネル国家情報長官代理の上級顧問も務めた。
パテル個人もまた、復讐心に燃えている。2020年にトランプがパテルをFBI副長官に任命したいと考えていることを知ったビル・バー司法長官(当時)は、「私が死んでもそれはさせない」と反応したという(The Economistを参照)。このため、パテルは著書『Government Gangsters』の付録のなかで、何十人もの「行政府のディープ・ステートのメンバー」にバーを含めている。バーはパテルの復讐の対象者になっている。
移行期正義の問題解決のために
この問題は、政治家による司法、行政、立法への干渉をどこまで認めるかという問題に帰着する。たとえば、問題となっているFBIの歴史をみれば、FBIが大統領と議会との軋轢のなかから生まれたことがわかる。
司法省が連邦法の執行と司法政策の調整のために1870年に創設されたとき、その職員には常設の調査官はいなかった。当初は、連邦犯罪の捜査が必要なときに私立探偵を雇い、その後、1865年に財務省によって創設された偽造捜査のためのシークレット・サービスなど、他の連邦政府機関から捜査官を借り受けていた。20世紀初頭には、司法長官が数名の常設調査官を雇う権限を与えられ、連邦裁判所の財務取引を調査するために、主に会計士で構成される首席調査官室が創設された。
FBIの資料によると、セオドア(テディ)・ルーズベルト大統領の就任により、状況は変化する。彼の政権下で古い法律が積極的に適用され、新しい法律も増えたため、司法省の犯罪摘発能力が限界に達し始めたのである。1906年にはシークレット・サービスの捜査官60名が必要となり、翌年には65名となった。これらの捜査官は、他の部署を支援するためにシークレット・サービスが維持していた予備部隊約20名から選ばれた。さらに、ジョン・ウィルキー長官が管理していた、シークレット・サービスの職に就くことを希望し、財務省による審査はすでに済んでいるものの、職が用意されていない約300名の捜査官のリストからも選ばれた。
1907年3月に司法長官に任命されたチャールズ・ボナパルトは、シークレット・サービスの調査官を使う慣行が問題であることをすぐに確信した。調査官を完全に管理することができないためである。ボナパルトは年次報告で,「司法省がその直属の管理下に常設の刑事部隊を持たないという異常事態に」議会の注意を喚起した。1908年1月、ボナパルトは直接要請を行い、司法省が「財務省のシークレット・サービスに頼らざるを得ない」ことを下院の小委員会に不満を述べた。
ボナパルトの2回目の要請後の2月から3月にかけて、下院委員会はシークレット・サービスの慣行について一連の公聴会を開く。こうして、シークレット・サービスから貸付された調査官による調査の不適切性が明らかになり、小委員会は、貸付慣行を廃止する修正案を起草する。ただし、これは大統領からみると、議会の意見なしに行動するルーズベルトの能力を制限しようとするものであった。ゆえに、ルーズベルトは法案に反対するロビイ活動を行い、ジョセフ・キャノン下院議長に手紙を送り、問題のある条項を削除するよう求めた。
結局、法案は圧倒的多数で可決された。大統領はすぐに署名したが、重要なプログラムへの大幅な予算計上を危うくするほどの強い不満はなかったという。法律の1908年7月1日からの発効を前にして、ボナパルト司法長官は、シークレット・サービスの諜報員の利用ができなくなるという差し迫った事態に対処するため、司法省の小規模な再編成を開始する。司法長官は、ほとんど大騒ぎすることなく、司法省のさまざまな調査官と、司法省特別捜査官として永久雇用された9人のシークレット・サービス捜査官をまとめはじた。1908年7月26日、ボナパルト司法長官が、新たに採用した連邦捜査官たちに、司法省のスタンリー・W・フィンチ主任審査官に報告するよう命じ、連邦捜査局(FBI)が誕生した。その1年後、主任調査官室は捜査局と改称され、1935年には連邦捜査局となる。
ただし、この設立経緯から、「FBIは、テディ・ルーズベルト大統領の司法省が議会の超党派の反対を回避して欺瞞的な行為によって創設されたもの」との認識がいまでも残っている(The Economistを参照)。つまり、司法省の役人とFBI職員との結託が疑われており、それが大統領の意思決定に悪影響をおよぼす可能性があると懸念されているのだ。
「ディープ・ステート」問題も
捜査機関や諜報機関への疑いは、「ディープ・ステート」(深層国家)の存在やその打倒をめざす動きに影響をおよぼしている。ディープ・ステートとは、権力の濫用が行き過ぎて、民主的プロセスを無視して事実上国を動かしている政府機関の集まりにつけられた名称である。
米国には、現在、諜報活動に携わる17の政府機関がある。そのうちの一つである中央情報局(CIA)は独立しているが、残りはさまざまな連邦省庁の一部となっている。たとえば、すでに紹介したFBIは司法省の一部である。諜報機関はしばしば、1963年のジョン・F・ケネディ暗殺や2020年の「不正選挙」、2024年夏のドナルド・トランプ暗殺未遂など、米国を「密かに動かしている」と疑われるようになっている。
トランプは大統領の意思決定とは無関係に動く、こうした独自の諜報機関の存在を疑っている。ゆえに、自分に忠誠を誓う者がこれらを支配することで、こうした機関による勝手な活動に終止符を打とうとしているようにみえる。
米国における行政権と司法権との錯綜は、権力分立という大原則を崩しかねない。その際、重要なのは国民によって選挙を通じて選ばれた者と、そうでない者との地位の違いだろう。選挙を経ずに要職に就く者については、彼らを政治家による干渉からどう守るかについて制度の整備が求められている。
事情は、日本も基本的に同じである。大阪地検のようなひどい組織をみると、政治家が干渉したくなるかもしれない。干渉自体は否定しないが、検察制度全般について審議会のような場で多様な意見を聴取しながら、制度改革につなげるほうがいい(審議会のメンバー選考自体に大きな問題があるから、この点を改革しなければならないのは言を俟たない)。もちろん、故安倍晋三首相が行ったような人事を絡めた検察への介入はそもそもできないように改めることが望ましい。
いずれにしても、政権移行に伴う「正義」の混乱は想定可能な事態だから、それに備えるための事前の検討がもっと衆人環視のもとで行われるべきだと思う。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:トランプ政権と東アジアの危機回避 ~米中対立の行方~
☆ISF主催トーク茶話会:真田信秋さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:船瀬俊介さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:大西広さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)