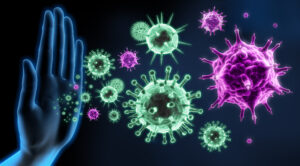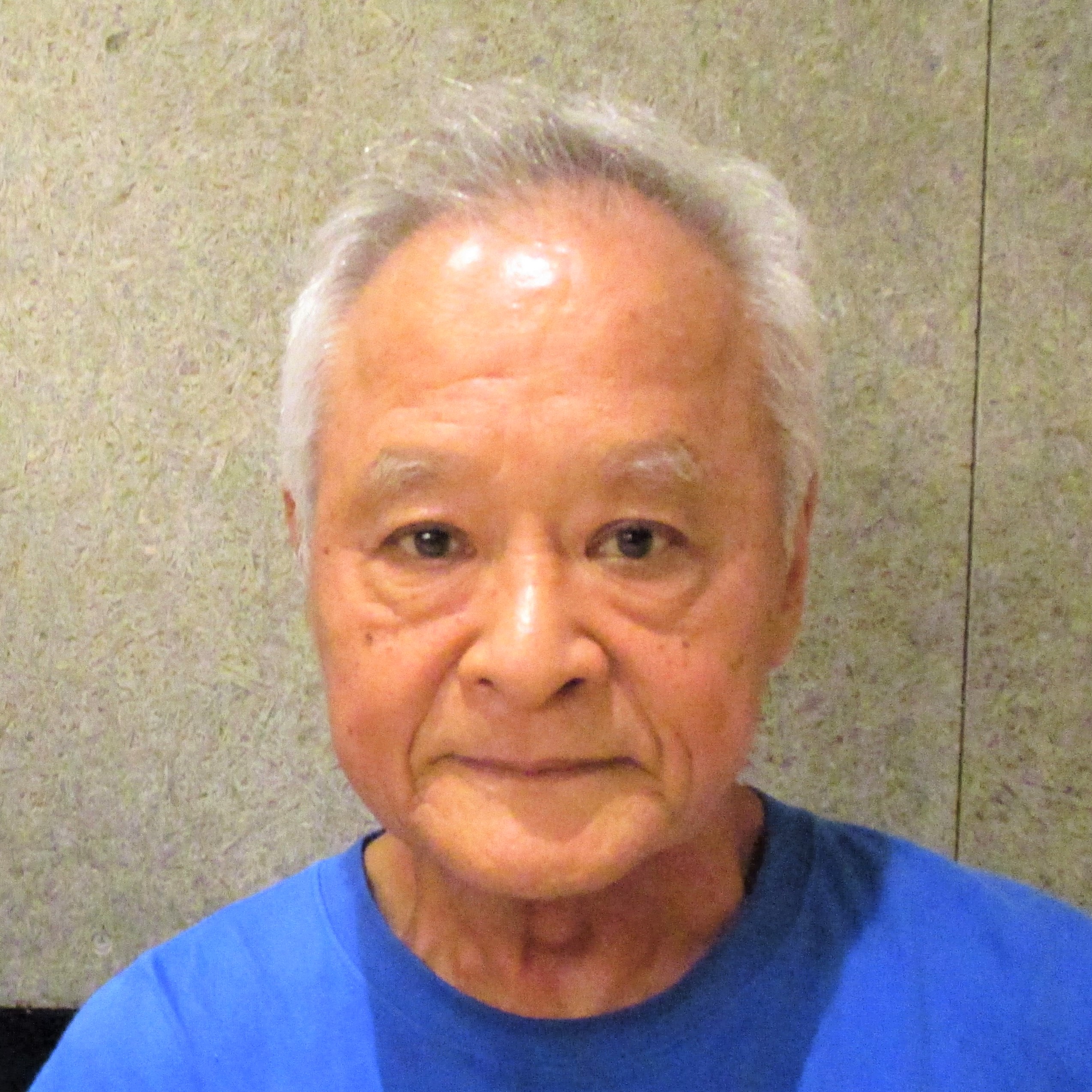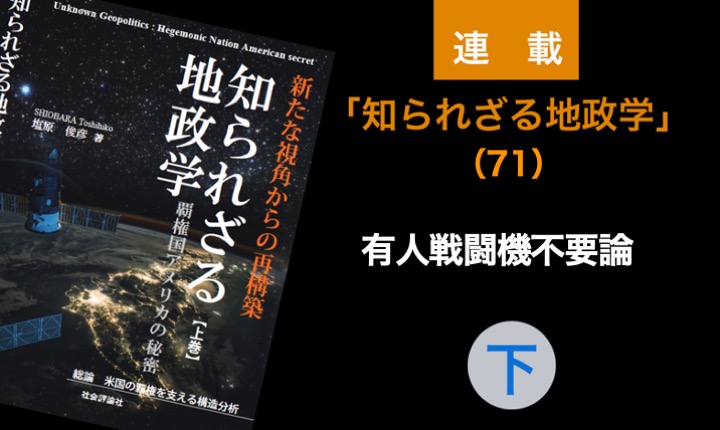
「知られざる地政学」連載(71):有人戦闘機不要論(下)
国際
「知られざる地政学」連載(71):有人戦闘機不要論(上)はこちら
防空システムの高度化
航空戦力の縮小傾向の背後には、防空システムの高度化という面もある。The Economistは、「1999年には、散在するセルビアの地対空ミサイルがNATOの航空機の悩みの種となり、ステルス戦闘機である米国のF-117ナイトホークを撃墜する事件まで発生した」と書いている。レーダーを複数の周波数で動作させることを可能にする最新のデジタル技術により、ステルス機を含む探知範囲が改善されているのだ。つまり、高価な有人戦闘機が簡単に防空システムの餌食になるようになると、どうにも出番が減ってしまうのだ。有人戦闘機を製造しても、簡単に撃墜されてしまうのであれば、「そんなものはいらない」という議論が十分に成立する。
通常の戦争を想定すると、まず、ステルス戦闘機が敵の防空システムを叩き、ステルス戦闘機以外の戦闘機からのミサイル攻撃や爆撃機からの爆弾投下を行うことになる。しかし、こうして手に入る制空権が長続きする保証はない。
他方で、そもそもステルス戦闘機などによる初期攻撃が可能か、という問題もある。敵の先制攻撃で戦闘機が破壊される可能性もある。あるいは、飛行場に被害が出れば、戦闘機が離陸できない事態も起こりうる。The Economistによれば、「米シンクタンクの戦略国際問題研究所(CSIS)が実施した戦争ゲームでは、台湾をめぐる戦争において、中国のミサイルが駐機中の米国、日本、台湾の航空機数百機を破壊する可能性が高いことがわかった」。このため、米国は自国の航空機を分散させたいと考えているが、それでは太平洋の広大な地域に人員、燃料、部品を輸送する必要が生じ、後方支援が複雑化するという。
このようにみてくると、有人戦闘機の「費用対効果」に疑問符がつけられても当然だろう。
米国は無人戦闘機に関心
それにもかかわらず、日本政府は英国、イタリアとともに2022年12月、人工知能(AI)を活用した次期戦闘機を共同開発する計画を発表した。2024年11月になって、同計画へのサウジアラビアの参画が検討されている、とNHKが報道した。
すぐに湧く疑問として、「なぜ米国の有力軍事メーカーと組まなかったのか」という問題がある。答えは、米国のロッキード・マーティンのような軍事企業は有人戦闘機よりも無人戦闘機開発に関心が移ったためではないか。あるいは、有人機と無人機との協調運用を考慮すると、有人戦闘機開発だけを共同で行うことはできないと米国側が考えたからであろう。
これは、いわゆる「第六世代」の有人戦闘機開発がAIによる高度な自律飛行能力をもつ戦闘機開発とともに、その第六世代有人戦闘機と連携できる無人戦闘機の開発を行うことに関係している。後者は、「ロイヤル・ウィングマン」(忠実な僚機)と呼ばれるもので、米空軍は2024年4月、1000機以上の最新型無人機を製造する「協調戦闘機」(CCA)プログラムの最初の契約を締結した。これらの初期モデルは、おそらく偵察や空中給油、戦闘機が目標に誘導する空対空ミサイルの運搬など、基本的な任務を遂行することになる。その価格については、「現時点では、米空軍は1機あたり3000万ドル以下に抑えたいと考えており、これはF-35のコストの3分の1程度である」、とThe Economistは記している。たとえば、具体例として、オーストラリア空軍向けにボーイングは、MQ-28ゴーストバットというステルス化されたドローンを開発している。
軍産複合体の「構造的腐敗」
ここまでの説明は、有人戦闘機か無人戦闘機かについて結論を示したわけではない。私のような門外漢には、その結論はよくわからない。ただ、一つだけ明示しておきたいことがある。それは、既存の軍産複合体の「構造的腐敗」という問題だ。
過去に米国防総省や日本の防衛省のような国防機関と兵器供給契約を結んできた軍産複合体は当然、これまで製造してきた有人戦闘機の次世代型の開発に関心を寄せるだろう。これに対して、小型で安価な無人戦闘機のようなドローン開発を担っているのは、これまで国防機関との取引経験のない中小の新興企業やスタートアップ企業が多い。その結果、前者が優先され、後者が不利益を受ける可能性が高い。
日本の川崎重工業による「腐敗」事件は、軍備発注側と供給側の癒着のわかりやすい例と言える。2024年12月23日付の日本経済新聞によると、「海上自衛隊の潜水艦を受注する川崎重工業が取引先企業との架空取引で捻出した裏金を使って潜水艦乗組員らに金品や物品を提供していた問題で、大阪国税局が十数億円について悪質な仮装隠蔽を伴う所得隠しと認定したとみられる」ことがわかったという。経費として認められない交際費と判断したというのだが、金品や飲食の接待を受けていた隊員の責任はどうなるのか。いずれにしても、発注者と受注者との強烈な「癒着」関係があったことがよくわかる。
三菱重工業、IHI、日本電気、富士通といった大企業と自衛隊との関係についても、ぜひとも調査してほしいと切望する。こうした軍産複合体は自らの既得権益を守るため、有人戦闘機を維持する方向に力点を置く。あまり根拠があるとは言えない主張を貫くには、「癒着」という人間関係が大いに役に立つ。つまり、今後、ますます贈収賄を含めた腐敗が防衛省と既存の軍産複合体との間にはびこるのは確実だろう。
政府による小規模新興企業の支援が必要
この問題について、米国の状況を論じたのが『フォーリン・アフェアーズ』に公表された共著論文「米国は未来の戦争に備えられていない そして、戦争はすでにはじまっている」である。著者は、2019年から2023年まで統合参謀本部議長を務めたマーク・A・ミリー(現在はプリンストン大学客員教授、ジョージタウン大学外交大学院特別研究員)と エリック・シュミット元GoogleのCEO兼議長である。
彼らは、「2022年には、ロッキード・マーティン、RTX、ジェネラル・ダイナミクス、ボーイング、ノースロップ・グラマンが国防総省の契約金の30パーセント以上を受注した」と指摘したうえで、「それに対し、新規の兵器メーカーはほとんど受注していない」と書いている。2023年には、国防総省の契約金の1パーセント未満がベンチャー企業に支払われたにすぎない。
こうした現実から、彼らは、「次世代の小型で安価なドローンは、伝統的な防衛企業が設計する可能性は低い」と断言している。伝統的な防衛企業は、派手で高価な機器を製造するインセンティブを与えられているからだ。ドローンはウクライナのように、何十社もの小規模な新興企業を支援する政府主導で生まれる可能性の方が高い。。創造される可能性の方が高いというのだ。そこには、数十の小規模新興企業を支援する政府のイニシアチブがある。つまり、こうした政府主導の方向転換がなければ、ドローン重視への舵を切れないのではないかというのである。
さらに、「しかし、将来に備えるためには、米国は兵器の購入方法を改革するだけでは不十分である」、とも彼らは指摘している。「軍の組織構造や訓練システムも変える必要がある」というのだ。複雑な階層型の指揮命令系統をより柔軟にし、機動性の高い小規模部隊に大きな自主権を与えるべきであるとのべている。これらの部隊には、重要な戦闘上の決断を下すための訓練を受け、権限を与えられたリーダーを置くべきであるというのだ。「AIが主導する戦争のペースが速いことを考えると、これは重要な利点である」と書いている。
軍事用AI問題
おそらく、軍自体の変革の問題は、軍事用AIの利用問題に帰着する。軍隊という組織が抜本的な変革を強いられているのだ。2019年刊行の拙著『サイバー空間における覇権争奪』をはじめとして、「論座」に公表した「「キラーロボット」の恐怖、自律型AI兵器規制の困難にどう向き合うか」、「AIが感情と意識を持つことは可能か、『クララとお日さま』『隠された泉』が教えてくれること」、「AI規制の必要性:EUの提案をめぐって、安全保障を名目にすれば、際限なく利用が認められてもよいのか」、「「ディープフェイク」の次に注目されるのはAI言語モデル「GPT-3」、目前に迫るライターの失業」、「アルゴリズムにも「監査」が必要だ、AIを動かすアルゴリズムは公平性を担保できているか」、「生態系中心主義に立脚したAI倫理は構築できるか、人間を理性的存在として特権化する「人間中心主義」の限界」、「「AI倫理」を問う(下):人間中心主義からの脱却、利便性や経済性だけを優先する判断基準をAI倫理に適用するのは間違いだ」、「「AI倫理」を問う(上):「気高い嘘」との対峙、AIを利用した権力は「全知全能」の存在に近づく」といった論考がある。
2023年に上梓した拙著『知られざる地政学』でも、第4章第5節において、「AIの安全性をめぐって」として、AIにかかわる諸問題を論じた。263~264頁の記述を紹介してみよう。
「AI規制の必要性を核兵器への規制と同じくらい重大な問題である」と主張してきたのはヘンリー・キッシンジャーである。2021年刊行の『AIの時代と私たち人類の未来』という共著(Henry A. Kissinger, Eric Schmidt, & Daniel Huttenlocher, The Age of AI and Our Human Future AI, 2021)のなかで、キッシンジャーらは地政学的な観点から興味深い考察を展開している。この本はGPT-3のレベルにあったAIを前提に語られたものだ。そのなかには、つぎのような記述がある。
「ネットワーク・プラットフォームの地政学は、国際戦略の重要な新しい側面を構成しており、政府だけがプレーヤーではない。政府は、競合する社会や経済がその国の産業、経済、あるいは(定義が難しいが)政治や文化の発展に強力な影響力をもたないように、重要な地域でこうしたシステムの利用や行動を制限しようとしたり、自国のライバルに差をつけないようにしようとしたりすることが増えている。」
とくに注目されるのは、彼らがAIを、通常兵器、核兵器、サイバーと並ぶ重要な能力とみなして論じていることである。すなわち、これらの能力を幅広くかつダイナミックに組み合わせた兵器庫のコントロールにおいて、①ライバル国や敵対国の指導者は、冷戦時代の先人たちのように、自分たちが望まない戦争の形態について、定期的に互いに話し合う用意が必要である、②核戦略の未解決の謎に新たな注意を払い、それが人類にとって戦略的、技術的、道徳的に大きな挑戦であることを認識しなければならない、③サイバーとAIの主要国は、自らのドクトリンと限界を定義し、ライバル国のドクトリンとの対応点を特定するよう努めるべきである、④核兵器国は、指揮統制システムおよび早期警戒システムの内部レビューを実施することを約束すべきである、⑤各国、とくに主要技術国は、緊張が高まる時期や極限状態において、意思決定時間を最大化するための強固で受け入れやすい方法を構築すべきである、⑥主要なAI大国は、軍事用AIの継続的な拡散をどのように制限するか、あるいは外交と武力による威嚇に支えられた体系的な不拡散努力を行うかどうかを検討する必要がある――という六つの主要な任務を志すよう求めている。
注目すべきは、⑥の指摘が、AIの軍事利用を核兵器不拡散体制の構築で防いできた実績をモデルにして、キラーロボットのようなAI兵器の不拡散体制の構築を検討するように主張している点だ。つまり、これは、前述した、OpenAIのCEOサム・アルトマンらが共同署名した「スーパーインテリジェンスのガバナンス」にあるような考えに似ている。それだけ、AIという科学技術は重大な意義をもっていることになる。」
いま、私はキッシンジャーの死後に刊行された共著(Henry A. Kissinger, Crag Mundie, and Eric Schmidt, Genesis: Artificial Intelligence, Hope, and the Human Spirit, Little, Brown and Company, 2024)を読んでいる。まだ、読了していないが、「はじめに」において、「人工知能の出現は、私たちの見解では、人間の生存に関わる問題である」と書いている(5頁)。この指摘は重い意味をもつ。さらに、つぎのように書いている(5~6頁)。
「非人間的な速度で動作するAIの将来的な能力は、従来の規制を無効にしてしまうだろう。私たちは、根本的に新しい形の管理が必要になる。世界的な科学界にとって、当面の課題は、あらゆるAIシステムに本質的な安全対策を組み込むための技術的対策を見つけることである。各国および国際機関は、いったんコンセンサスにまとまれば、監視、施行、危機対応のための新たな政治体制を構築しなければならない。そのためには、一つではなく二つの「調整問題」を解決する必要がある。すなわち、人間の価値観や意図をAIの行動と技術的に調整すること、そして、人間同士を外交的に調整することである。」
具体的な利用法
ここでは、AIが戦争をどのように変えつつあるかを説明してみよう。まず、イスラエル国防軍(IDF)は、「ゴスペル」(福音)と「ラベンダー」と呼ばれるAIツールを開発し、ハマスとパレスチナのイスラム聖戦という二つの過激派グループの工作員だと疑われる人物を、爆撃の標的として「マーク」している(The Economistを参照)。数千人のハマス・メンバーの自宅が空爆の対象としてマークされ、人間の将校はざっと監視するだけだ。「ゴスペル」や「ラベンダー」というAIツールが、さまざまな情報収集機関が収集した多様なフォーマットの膨大なデータを管理可能なフォーマットに統合し、空爆のターゲットの特定と確認につなげるのである。イスラエル国防省は、AIツールは標的の特定を迅速にするだけでなく、より正確にすると主張している。さらに、ガザ地区では、イスラエル軍が数千機のAIアルゴリズムに接続された無人機を投入し、同地域の都市峡谷をイスラエル軍が航行するのを支援しているという(『フォーリン・アフェアーズ』の記事を参照)。
米国は、F-35が高すぎるため、新世代のAI無人機(ドローン)の開発に力を入れている。たとえば、人間のパイロットの「忠実なウィングマン」として、パイロット付きの戦闘機の前方を飛行し、早期にリスクの高い監視を行うことができるドローンを開発中だ。人間が操縦する飛行機には危険すぎると考えられる陸上ミサイルの標的を、危険を冒して打ち落とすという大きな役割を果たすこともできる。そうしたAIドローンとして開発中なのが「パイロットレス実験機XQ-58Aヴァルキリー」である。
米国軍がもっとも重点的に投資しているのは、「レプリケーター構想」(Replicator Initiative)である。これは、米国軍が5年後や10年後ではなく、今必要としている技術革新の採用を加速させることに焦点を当てている。
2023年8月28日に発表されたレプリケーターは、国防総省(DOD)の国防技術革新ユニット(DIU)が主導する国防総省のイニシアチブであり、2025年8月までに無人システムを数千台配備することを目的としている。Replicatorの最初の取り組み(「Replicator 1」)は、全領域対応型消耗可能自律型(ADA2)システムの配備である。消耗可能なシステムは、比較的低コストのシステムであり、国防総省はシステム損失のリスクをある程度許容する。2024年9月27日付のメモで、ロイド・オースティン国防長官は、レプリケーターの第2の取り組み(「Replicator 2」)は、小型無人航空システムへの対抗に焦点を当てることを発表した。
自律型兵器に利用されるAI
恐ろしいのは、2024年6月にThe Economistが公表した長文の記事「AIは戦争をどう変えるか」のなかで、つぎのような記述がみられることである。
「ロシアもウクライナも、無人機が「自律型」兵器システムなのか、それとも単なる「自動化」されたものなのかということにはあまり注意を払っていない。彼らの優先事項は、妨害を回避し、可能な限り多くの敵の装甲車両を破壊できる兵器を開発することである。これまでに1000以上のウクライナの医療施設を爆撃してきたロシア軍にとって、また、自国の存続をかけて戦っているウクライナ軍にとって、誤爆は大きな懸念事項ではない。」
ここで紹介したような最新の動きを知ると、現実は、倫理や道徳を無視しながら、先へ先へと闇雲に変遷しているようにみえる。有人戦闘機が存続するにしても、もはや自律型無人戦闘機中心の時代に突入しているように思えてくる。
それにもかかわらず、2024年12月26日に開催された「AI戦略会議・AI制度研究会合同会議」に出席した石破首相の発言をみると、日本の遅れが際立っている。私からみると、不勉強な連中の野合でしかない。こうした不勉強な輩がいくら集まっても、何も解決の糸口は見出せまい。
関心のある方は、公表されたばかりの米議会報告書(Bipartisan House Task Force Report on Artificial Intelligence, 2024)を読んでほしい。日本の低水準がわかるだろう。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:トランプ政権と東アジアの危機回避 ~米中対立の行方~
☆ISF主催トーク茶話会:真田信秋さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:船瀬俊介さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:大西広さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)