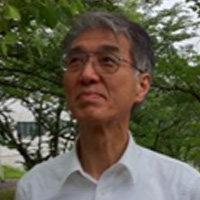編集後記:両親と夢見た甲子園
編集局便り7月になったら青空にもくもくと白い入道雲が顔を出す。高校球児たちの夢の舞台、第104回全国高等学校野球選手権大会出場をかけた各地の県予選が日本列島のあちこちで開幕する。あなたは高校野球にどんな思い出がありますか?
この季節が訪れると、私のハートの中で生涯忘れられないシーンが輝き始める。とても大切な思い出だ。
1988年8月20日、甲子園準々決勝で浦和市立(埼玉)と対戦した宇部商(山口)の捕手、城市幸弘君の大舞台にかける姿勢の素晴らしさに心打たれたからだ。「ここに来たのは、一人じゃない」。城市君は、夏の大会までのわずか1年の間に両親を相次いで胃がんで亡くした。
私と城市君の出会いは、その年の春の甲子園だった。朝日新聞宇部支局員だった私は宇部商担当として甲子園へ。開会式直後の取材で「入場行進の時にスタンドに母さんをさがす自分がいました」と聞き、初めて母親が亡くなっていることを知った。春の甲子園後、山陰のブロック大会の試合の最中に突然、泣き崩れる彼を見た。入院していた父の訃報が届いたのだ。
ニキビが残るまだあどけない少年がそれを乗り越えての夏の甲子園出場だった。浦和市立とのこの試合。五回裏、城市君が打席に立つと、速球が体を直撃した。死球と思いきや、審判は球をよけなかったとしてストライクの判定。城市君はタイムをとって空を仰いだ。瞼を閉じ、耳を澄ますと、浜風に乗って両親の声が聞こえた。
「落ち着いて」。気を取り直して打席に立つと、次の球をフルスイング。スタンドにライナーで飛び込んだ。しかし、試合は延長11回の末に敗れた。
ドラマはこの後起きた。試合が終わり、チームメートが夢中で記念に甲子園の土を袋に詰めている最中に、城市君は、スタンドに頭を下げ続けた。炎天下、両親の遺影を持って自分を応援してくれたおばあちゃんへの感謝の気持ちだ。なんてやつだ。あっぱれ。甲子園の試合は、勝ち負けだけではない。
球児の熱い戦いには、どんなドラマが起きるのか、予想もつかない醍醐味がある。城市君が最後に見せた姿はまさに「心の逆転満塁ホームラン」。多くの人たちの心の中にさわやかに駆け抜けていっただろう。我慢してもあふれる涙は、止められなかった。
※ご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
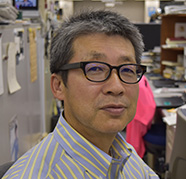 梶山天
梶山天
独立言論フォーラム(ISF)副編集長(国内問題担当)。1956年、長崎県五島市生まれ。1978年朝日新聞社入社。西部本社報道センター次長、鹿児島総局長、東京本社特別報道部長代理などを経て2021年に退職。鹿児島総局長時代の「鹿児島県警による03年県議選公職選挙法違反『でっちあげ事件』をめぐるスクープと一連のキャンペーン」で鹿児島総局が2007年11月に石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞などを受賞。著書に『「違法」捜査 志布志事件「でっちあげ」の真実』(角川学芸出版)などがある。