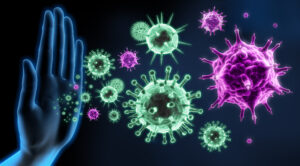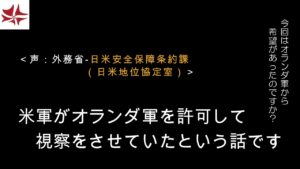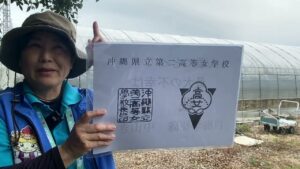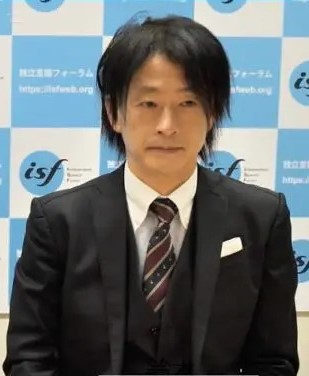モハンティ三智江 短編小説編:デーモンの肖像(中編小説4)
国際【モハンティ三智江のフィクションワールド=2024年12月17日】私が河宰類(かさい・るい)と初めて出遇ったのは1965年、フランスの首都パリでだった。私は前年から同業の写真家である海堂弓子と、被写体を求めてヨーロッパやアフリカじゅうを駆け巡っていた。
パリに戻って、そろそろ旅費が尽きかけていた私たちは、日本人画家の溜まり場になっていたリベリアホテルに出入りし、画家の卵たちの作品を写真に焼き付けるアルバイトを引き受けて、何とか食いつないでいた。
パリ6区、グラン・シュミエール通り9番地にあったリベリアホテルは1900年代初頭、日本人画学生や洋画家の卵が愛顧していた邦人御用達の安宿で、絵描きを目指し渡仏する日本人青年たちの間で人気だったのだ。
ある日、いつものようにリベリアに顔を出し、1階のゴーギャンのアトリエで通るフロアにたむろしていると、仲良くなった画家のひとり、通称ムッシュが見慣れぬ新参者を伴って現れた。
「君たち、ちょうどよかった、紹介するよ。こちら、たった今ブラジルのサンパウロから着いたばかりの河宰類君、僕が神戸二紀会で一緒だった将来を嘱望される洋画家だ。パリはこれが2度目、5年ぶりだよ」
小柄なムッシュの背後から、長身の日本人離れした顔立ちの男がおずおずと、使い古した茶革の旅行鞄を下げて現れた。はにかんだ笑みを洩らしながら、小声であいさつする。
「初めまして、河宰類です、よろしく」
私が名乗るより先に、ムッシュが、
「こちら、写真家の安奈ベレフキン、ロシア人とのハーフ、通称アンナだ」
と私を引き合わせた。
ロシア人との混血と聞いて、男の目が丸くなった。薄茶色の澄んだ瞳が好奇の色を帯びて輝く。一瞬の沈黙を割って、弓子が、
「私は、アンナの友達の海堂弓子、同業の写真家よ、よろしくね」
ときびきびした口調で自己紹介した。若い女の物怖じしない態度に三十半ば頃の男は気後れした風情だ。
おとなしい私に比べ、弓子は積極的で大和撫子らしくない、はっきりした物言いをする。私たちの友情関係で、主導権を握るのはいつも弓子の方で、彼女は大手のA新聞の専属カメラマンとして働いていたのだが、組織が肌に合わず退社して独立、やはりフリーの同業者だった私を、1964年の海外渡航の自由化に伴って花の都パリへと半ば強引に誘ったのだ。弓子の行動力に引っ張られた形で、私は渡欧どころか、相棒の運転するおんぼろジープでアフリカ大陸横断の蛮勇までやってのけてしまった。
1960年代というまだ海外旅行が一般的でなかった時代、しかも女性の社会進出もままならぬ時に、パリに高飛びした私たちは選ばれた者、ウーマンリブの走りと言ってもよく、そのことに自負を持っていた私たちだった。
ムッシュがそんな私たちのことを、ニューカマーに得々とひけらかしている。
「ユミコとアンナは女だてらに重い機材を抱えて、1年間中古ジープを駆って、ヨーロッパやアフリカを撮り回ってたんや。2万キロ制覇のアマゾネスも顔負けの女傑や。まぁ、武勇伝は後で聞かせてもらうとして、絵画作品の焼き付きもやってくれるから、必要やったら頼んだらええ、腕は確かやで」
河宰類は黒いベレー帽の下の長いまつげをしばたたかせると、改めて私たちを眩しそうに見つめた。私と弓子はまだ20代半ばの青春真っ盛り、世界を股にかける一端(いっぱし)の写真家気取りで意気軒昂だった。そんな2人にとって、彼はひと回り年上のおじさん、フランス語で言うところの「トントン(tonton)」に過ぎなかったが、どこか只者でない気配を匂わせ、端麗な容姿の裏に並でない才気を窺わせた。
率直に言うと、初めて河宰類に紹介されたとき、私は暗い雰囲気の男だなぁとあまりいい印象を抱かなかった。が、日本人離れした端整な顔立ち、長身でスマート、翳りある美男を地でいくように見えて、その暗さが上辺だけの飾りでなく、根源から来るように思えて、気になってしかたなかったのだ。
後に河宰類の作品を撮らせてもらうようになって、画風もまた同様に暗い色調の油彩が多く、塗り込められた茶や黒の重なりがおどろおどろしく、内に抱える業(ごう)のようなものをぶちまけた印象が私を捉えて離さなかった。
自画像はじめ抽象的な作品もあったが、テーマに描きあぐねているような迷いも感ぜられた。人物画であろうとも、そこには男自身が投影されており、そんな画家本人も、作品も、被写体として撮ってみたくたるような蠱惑的(こわくてき)な魅力を秘めていた。
私は、今はまだ売れない貧乏画家だと自嘲する河宰類が、そう遠くない将来才能を認められるだろうとの予感めいた直感に打たれた。 画風も人柄同様に暗い作品が多かったが、見るものを捉えて離さぬ魔物めいた吸引力があった。
それが、後に私たち女同士の会話で「トントン」との愛称で親しまれることになる河宰類と、私こと安奈ベレフキンの馴れ初め、運命的とも言える邂逅だった。
弓子は、私が類に惹かれていることをとっさに嗅ぎつけると、それとなく警告したものだ。
「アンナ、トントンは確かに魅力的だけど、ちょっと厄介なくせ者、既婚だし、近づいて火傷しないようにね」
おじさんは素敵だけど、日本に奥さんもいるみたいだし、近づかない方がいいとの暗の忠告である。が、類は若い私たちを気に入り、付き纏(まと)った。
往時ピカソ(Pablo R.Picasso)やモジリアーニ(Amedeo C.Modigliani)のみならず、サルトル(Jean-Paul C.A.Sartre)やボーボワール(Simone de Beauvoir)が足繁く通ったという、モンパルナスの4大カフェのひとつ、「ラ・クーポール(La Coupole)」に誘い出しては、他愛もないおしゃべりに興じる機会が度重なった。会計はいつもムッシュ持ちだった。
弓子も最初はツンケンしていたが、彼の魅力には抗し切れず、満更でもなく相手になってやっていた。私たちは、貧乏画家で懐の寒いおじさんに同情して、大事に取っておいたチキンラーメンを進呈したりして、たいそう喜ばれた。
おじさんはシングルベッドにトイレ付きの通称「ルージュ」と言われる狭い屋根裏部屋に逗留しており、お湯でふやかしたインスタントラーメンで空腹を満たしながら、天窓から下の通り、往時向かいにモジリアーニのアトリエがあった辺りをぼんやり見下ろしつつ、物思いにふけっていた。生前絵が売れなくて貧窮を舐めたモジリアーニに己を重ね合わせていたのかもしれない。
小柄な弓子に比べ、ロシア人の血が半分混じる私は大柄で、長身の男と並んで歩いても見劣りがせず、釣り合いが取れた。が、男の2度目のパリ滞在はそう長くなく、イタリアに飛んでしばらく後に帰国の途に着いたこともあって、私との間に芽生えた友愛が恋に進展するまでには至らなかった。
帰国後まもなくくれたエアメールには、細々した近況の末尾に、
「あなたは実に可愛い人だ、美しいおみ足をくれぐれもお大事に」
と冗談ともつかぬ求愛めいた文句が添えられ、私をどきどきさせた。
(「フィクションワールド」はモハンティ三智江さんがインドで隔離生活を送る中、創作活動にも広げている続きで、「インドからの帰国記」とは別に、短編など小説に限定して掲載します。本人の希望で画像は使いません)
「モハンティ_デーモンの肖像(中編小説4)| 銀座新聞ニュース」の転載になります。
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 モハンティ三智江
モハンティ三智江
作家・エッセイスト、俳人。1987年インド移住、現地男性と結婚後ホテルオープン、文筆業の傍ら宿経営。著書には「お気をつけてよい旅を!」、「車の荒木鬼」、「インド人にはご用心!」、「涅槃ホテル」等。