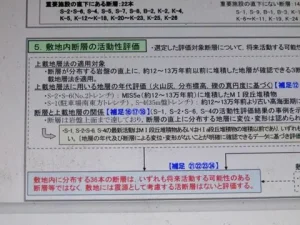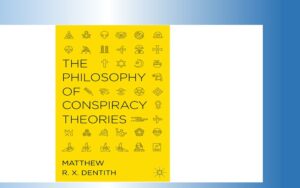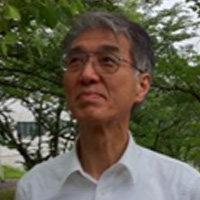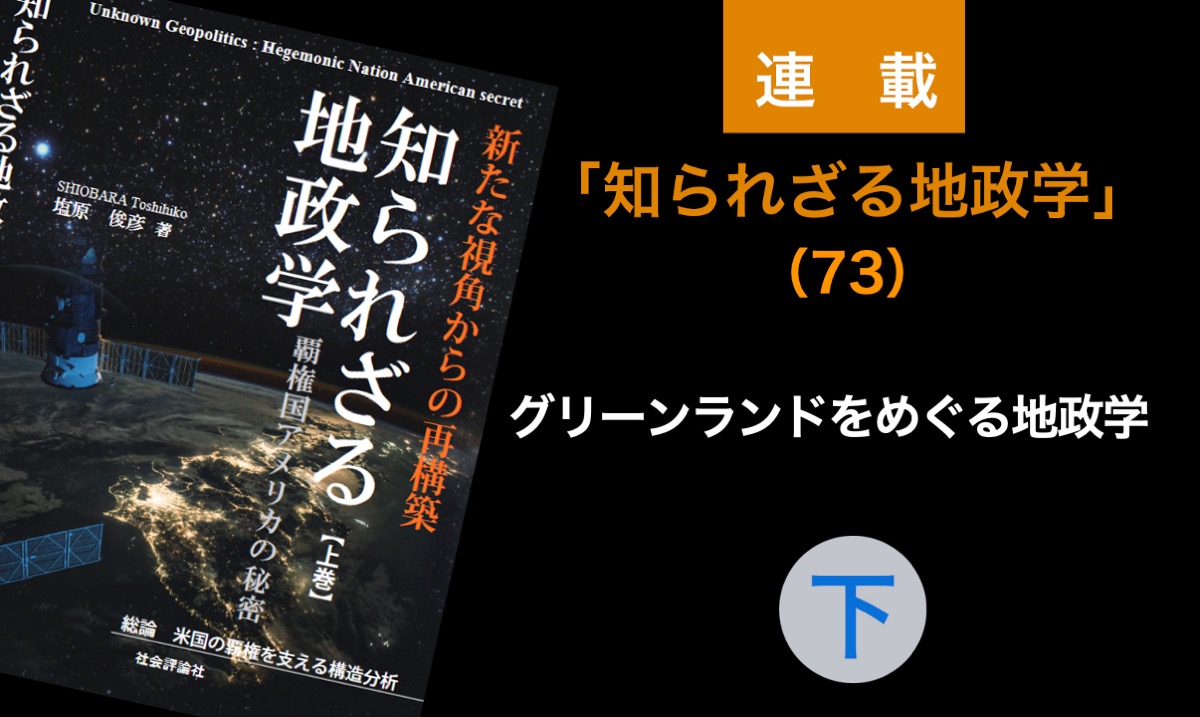
「知られざる地政学」連載(73):グリーンランドをめぐる地政学(下)
国際
「知られざる地政学」連載(73):グリーンランドをめぐる地政学(上)はこちら
第二次トランプ政権に向けて
2024年12月、トランプは、駐デンマーク米国大使にケン・ハウリーを選任したと発表すると同時に、「国家安全保障と世界全体の自由のために、アメリカ合衆国はグリーンランドの所有と支配が絶対的に必要であると感じている」、と自身のSNSに書き込んだ。さらに、1月7日の記者会見では、トランプはグリーンランドを奪取するために軍事力を行使することを否定しなかった。
同日、トランプの息子、ドナルド・ジュニアはグリーンランドの首都ヌークに私的な訪問で到着した(下の写真を参照)。
1月11日には、「アクシオス」が、「デンマークは最近、トランプ次期大統領のチームに、グリーンランドの安全保障強化や米軍の同島駐留拡大について話し合う意思があることを伝える非公式メッセージを送った」と報じた。

グリーンランドのヌークを訪れたドナルド・トランプ・ジュニア (Emil Stach/Ritzau Scanpix/via REUTERS)
(出所)https://www.reuters.com/world/trump-jr-plans-greenland-visit-fathers-interest-resurfaces-2025-01-06/
グリーンランドのいま
2021年4月のグリーンランド議会選では、グリーンランドで長く政権を維持してきたシウムット党が敗北した。クヴァネフイェルド鉱山の開発により、数億ドルの収益と数百人の雇用を生み出し、グリーンランドがデンマークから離脱するのに有利な立場になると主張したが、開発中止を約束する、環境保護の傾向を持つ民主的社会主義政党イヌイット・アタカチギイットが勝利した。ただし、当時の情報では、「世論調査によると、グリーンランドの5万7000人の住民の大半は、独立に向けての動きを希望している」という。
同党の党首ムテ・エゲデはグリーンランド首相となり、2025年1月には、新年の演説で、デンマークからの独立と植民地主義の「足かせ」を外すことを訴えた。この独立支持の背後には、デンマークに対する不満がある。2022年にデンマークの放送局DRが、1966年から1970年の間に、13歳にも満たない少女や女性たちに、本人の知らぬ間に、あるいは同意を得ずに、4500個の避妊リングが子宮内に挿入されていたことを示す記録が残っていると報道したためである(「ロイター」を参照)。2024年3月には、グリーンランド出身の女性グループが1960年代に強制的に実施された避妊キャンペーンについて、かつての植民地支配者であるデンマークに賠償を求める訴訟を裁判所に起こした。デンマークとグリーンランド当局は特別調査を開始しており、その結果は2025年5月に出される予定である。
台湾独立を阻止する一方、グリーンランド独立を支援する中国
興味深いのは、台湾独立を決して認めない中国がグリーンランドを独立させて、親中国家とするという計画だ。「ランド・コーポレーション」の2022年の報告書では、「グリーンランドに対する北京の外交的積極性は2018年以降衰えている」と指摘されている。それは、中国がグリーンランドのインフラや資源に投資することにデンマークや米国が反対し、グリーンランドとの関係が制約されるようになった結果とされている。
ただし、中国とは無関係にグリーンランドが独立しようとした場合、デンマークがどう出るかについては予測が難しい。絶対反対という立場ではないにしても、デンマークにとってグリーンランドは利用しがいのある「領土」であることは間違いない。たとえば、2014年、デンマークはグリーンランドとの関連性を理由に、北極点を含む北極圏の約90万平方キロメートルを自国の領土だと主張した。また、デンマークはグリーンランドに米軍基地を置くことを長年許可してきた(この島にはすでに宇宙軍基地があり、アメリカ軍とNATO軍が駐留している)ため、多くの人が疑うように、北大西洋条約機構(NATO)のGDPの2%という防衛支出目標を回避することができたのではないかと考えられている(グリーンランド人は協議に参加していない)。
デンマークがグリーンランドを手放そうとしない場合、トランプ政権がデンマークに高関税をかける可能性は高い。というのも、近年、デンマークのノボ・ノルディスク社が開発した抗肥満薬ウェゴビーやオゼンピックが大量に米国に輸出されるようになっているからである(拙稿「抗肥満薬をめぐる地政学」[上、下]を参照)。その意味で、トランプ政権には、デンマークをいじめる手段がたくさんあると言えるかもしれない。
軍事的拠点としての北極圏
北極圏における軍事態勢に注目すると、2024年3月、ロシアの爆撃機2機がグリーンランド、アイスランド、イギリスの間の戦略的隘路を通過した。これはウクライナ戦争がはじまって以来初めてのことだ。
中国は、北極圏を通過する、いわゆる「北方海洋航路」によってヨーロッパへの輸送路確保に重大な関心をもっている。このため、2023年夏にはアラスカのアリューシャン列島を中ロ海軍の合同パトロール隊が通過し、一部の観測筋を驚かせた。
西側諸国もまた、この地域での活動をエスカレートさせている。年に一度の大規模な演習の一環としてアラスカに派遣された約400人の米軍とNATOの隊員は2024年4月、アラスカの北極圏で訓練を行った。特殊作戦部隊としては過去最大規模だったという(WPを参照)。他の米軍は、冷戦後最大の軍事同盟演習の一環として、ノルウェーの北極圏で同時に訓練を行った。
9.11以降の数年間、米国防総省は特殊作戦部隊を、大規模な軍事展開に伴う政治的リスクをほとんど排除して、アメリカの対テロリズム目標を遂行できる機動的な部隊に変えた。このアプローチによって、人員数は2001年の3万8000人から2020年には7万3000人へと大幅に拡大され、米特殊作戦司令部は通常軍から切り離された形で権限を与えられたという。こうして、北極圏における安全保障が脚光を浴びるようになっている。
ただし、米国は自らの権益を独自に主張するために、国連海洋法条約に調印はしたが、批准してこなかった。北極海を取り囲む、ロシア、米国(アラスカ)、カナダ、デンマーク(グリーンランド)、ノルウェーのうち、同条約を批准していないのは米国だけであり、米国が北極海の問題に口を挟むこと自体が難しくなっている。たとえば、大陸棚延伸申請などで不利益を受ける可能性がある。国連海洋法条約は、200海里までの大陸棚に対する沿岸国の主権的権利を認めているが、自国の大陸棚の縁辺部が200海里を超えて広がっている場合は、「国連大陸棚の限界に関する委員会」の検討を経て勧告を受けられれば、200海里を超えて延伸させ主権的権利を行使できる。おそらくグリーンランドを入手することで、より自国優先の勝手なふるまいが可能となると、トランプは目論んでいるのだろう。
グリーンランドの価値
ここで、2025年1月11日付のNYTに公表された記事「グリーンランド購入の費用は?」を参考にしながら、グリーンランドの価値について考えてみよう。
記事は、ニューヨーク連銀の元エコノミストであるデビッド・バーカーの協力のもとに、推定されたものである。その出発点は、米国が国防上の懸念から、1917年にデンマーク領西インド諸島として知られていた地域をデンマークから2500万ドル(現在の価値で約6億5700万ドル)で購入した事例との比較考量にある。
バーカーは、米領バージン諸島とアラスカの価格を基準とし、インフレと経済成長の両方を考慮して、米国またはデンマークの国内総生産の公称変化率に基づいて調整することを提案した。「経済規模が大きいほど、より高額を支払う余裕があり、経済規模が大きいほど、より高額を要求する可能性が高い」というのが彼の基本的な見立てである。
その結果、低価格の評価では、1917年以降のデンマークのGDPの500倍の成長率を考慮して、バージン諸島の購入価格を調整した。これにより、グリーンランドの価格は125億ドルと算出された。
高価格については、アラスカ購入の720万ドルの費用を米国のGDPの成長率に合わせて調整すると、上限は770億ドルとなった。
もちろん、すでに書いたように、グリーンランドの地理的な位置と安全保障上の重要性を考慮すれば、まったく異なる議論が展開できる。米国はグリーンランドに軍を駐留させており、デンマークはNATOの同盟国であることを考慮しつつ、今後、さらに氷が溶解することで進む北極圏の利用価値を想定することが求められる。だが、それを金銭換算することはそう簡単なことではない。
さらに、稀少資源を考慮したグリーンランドの経済価値に注目しようとしても、その評価は難しい。「フィナンシャル・タイムズ」は、グリーンランドの資源は1兆1000億ドルの評価額を正当化するだろうと示唆したが、バーカーは、この皮肉な試算には疑わしい前提があるとのべた、とNYTは紹介している。「米国政府は資源採掘の利益をすべて受け取るわけではない。入札額に自らのコストと利益を上乗せできる余地を残した企業に採掘権を売却するだろう」とバーガーは言う。
やや脱線して書いておくと、稀少資源の価値は将来、いま想定されているよりもずっと低下してしまう可能性がある。技術進歩によって代替可能な別の資源が見い出されたり、そもそも資源が不要となったりすることも考えられる。ごく最近でいえば、The Economistは記事「AIモデルのトレーニングに巨大なデータセンターは必要ないかもしれない」のなかで、膨大な特注のコンピューティングクラスタ(および関連する初期費用)を完全に廃止し、代わりに、より小規模なデータセンター間で訓練のタスクを分散させる方法が見つかりつつあると報じている。そう、巨大なデータセンターをつくってから、そんなものは不要になってしまったという事態が十分に起こりうる。
こう考えると、稀少資源のために莫大な資金を投じるリスクは大きいと肝に銘じておく必要があるだろう。
資源の呪い
私には、「ロシアにおけるレントと課税の諸問題」という論文がある。このなかで、「レントは通常、労働、資本、資産の所有者によって受け取られ、しかも、所有者側からの何らの追加費用を必要としない、追加所得と理解されている」としたうえで、「自然資源の所有をめぐっては、自然レントが問題になる。そのなかには、鉱物、土地、水、森林などの所有にかかわるレントがあることになる」と書いておいた。さらに、自然レントあるいは天然資源の利用にかかわる超過利潤をどう配分すべきかという大問題がある。この超過利潤の配分が少数の為政者に限定されることで、石油などの資源開発による超過利潤が奢侈品に費やされたり、弾圧手段に回されたりして、結局、その国の民主化を損なうといった議論がある。いわゆる「資源の呪い」をどう回避するかという問題が生じるのである。
同じように、グリーンランドの資源に注目すると、その資源から得られる超過利潤をめぐる配分問題をどうすべきかが課題となる。もしろん、資源そのものの所有をだれがどう保証するのかという問題もある。
ここでは、詳しい議論は割愛するが、関心のある者は大庭健著『所有という神話』あたりを手がかりにしながら、所有について考えることからはじめてほしい。グリーンランドの話も、結局、所有論に行きつくからである。
所有の仕組み
ここでは、ごくさわりの部分だけを紹介する。大庭によれば、ある人Pさんがあるものxを「所有している」とは、「どのようにxを用益あるいは処分するかを、Pさんが一人で排他的に決定することを、xに関心をもつ他者たちが承認する」ということであるという。ここで重要なことは、所有が原理的に他者による承認を前提にしていることである。簡単にいってしまえば、「資本制=ネーション=ステート」を前提にすると、「私有制」とよばれるものは「ステート」ないし「国家」による承認を前提にしていることである。私有制といえども、国家の枠内でしか対象の用益・処分を排他的に決定できないのだ。つまり、個人も法人も私的所有を神聖不可侵と主張することはできない(注1)。土地や地下資源などの天然資源は、生態系の一部だから、なおさら、その「所有」について「他者」による承認を受けなければならない。それは国家ないし自治体や「コミュニティ」による承認ということになるかもしれない。いずれにしても、地下資源や土地が純然たる私有対象であっても、国家規制や自治的規制の対象にならざるをえないのだ。
だからこそ、グリーンランドも、その所有形態がどのようなかたちであっても、国家ないし自治体の規制対象としてこれらの枠組みから逃れられないことになる。つまり、トランプの問題提起は、こうした所有の仕組みの原理を考えさせる契機となっていることになる。その意味で、グリーンランドの今後の展開は実に興味深い。
たとえば、問題となっているような尖閣列島のような島を中国が購入したいのであれば、喜んで売却するという選択肢も十分に実現可能となるかもしれない。ほんの小さな島や領土をめぐって戦争するよりも、別の解決方法があるとすれば、それは今回のグリーンランドの売買がモデルケースとなるかもしれない。
問題は、国家単位で所有を承認し保証する制度にある。別の承認制度が創設されれば、国家以外の国連のような機関が所有を保証できるかもしれない。国境画定が難しい地域について、売買を含めた問題解決を委ねるというメカニズムができれば、地政学上の紛争解決にも役立つかもしれない。
(注1)
たとえ「私」という個人であっても、それはとりかえのきかない「唯一の私」であるかのようにみえるが、「私」が「私」を所有するためには「他者」の承認を得なければならない。その他者は「私」自身だといえば、すむのだろうか。「私」にのみ固有の能力・特性・資質を所有していることを承認するのは、決して「私」自身ではありえない。そこに、自分以外の他者を想定することが求められている。そもそも「私」の生命や身体は「私」の意のままになるというのは本当だろうか。デカルト的な心身二元論をとれば、「デカルト的な私=魂は、物体のみの世界と一人向かい合い、世界内の「この」体を所有し、意のままに動かす主体となる」(大庭p. 153)。ここに、ロックのいう「自己所有」という観念が生じ、それは土地を所有対象とすることを促した。土地を商品化しただけでなく、土地から「自由」にされた人間の「労働力の商品化」さえ生み出した。これは資本制システムの構築を意味するが、個人からみれば、このシステムは労働力を売り消費する諸関係にかかわり、同時に、それは自らの生命を維持しながら次世代の生命を育てていくことにかかわっている。とすれば、自己所有に基づく資本制システムは環境や生態系の破壊を通じて、つまり、「私」の意のままにならない別のシステムから影響を受けていることになる。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
☆ISF主催公開シンポジウム:トランプ政権と東アジアの危機回避 ~米中対立の行方~
☆ISF主催トーク茶話会:真田信秋さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:船瀬俊介さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
☆ISF主催トーク茶話会:大西広さんを囲んでのトーク茶話会のご案内
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)