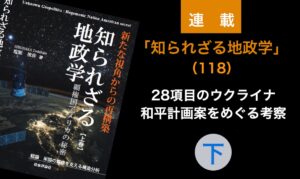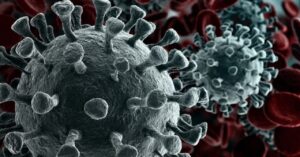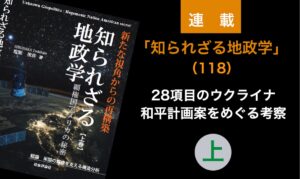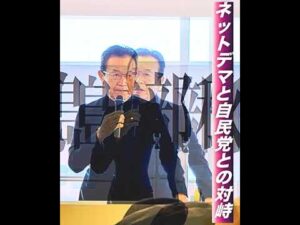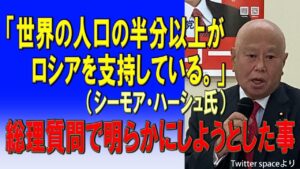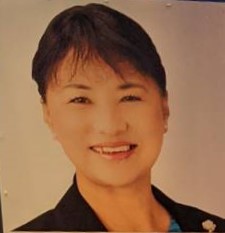登校拒否新聞11号:ランドセルが重すぎる
社会・経済『週刊新潮』の2023年10月19日号に掲載された記事「ついに不登校が30万人に この10年で約3倍に激増の「皮肉な理由」とは」がデイリー新潮という新潮社のサイトにアップされている。10月21日付。
文部科学省の調査で、不登校の小中学生が昨年度、過去最多の29万9千人に達した。全小学生の1.7%、中学生の6.0%にあたるから、2クラスに1人は不登校生がいる時代なのだ。特に過去2年間で急増し、10万人以上増えている。文科省では「コロナ禍で生活環境が変化し、生活リズムが乱れやすい状況が続いた」などと分析。一方で、ある法律による保護者らの意識の変化も理由に挙げる。その法律とは2016年、超党派の議員立法で成立した「教育機会確保法」で、不登校児童の休養の必要性を認めたものだ。要は“無理して学校に行かなくてもいい”ということらしい。
https://www.dailyshincho.jp/article/2023/10210558/?all=1
続いて「国の施策で不登校が急増?」と見出しがあり、文科省の初等中等教育局の文部事務官に意見を聞いている。それによると「昔は、学校になじめない子であれ、無理にでも登校させようとしていました。しかし、学校に行けない子は心のエネルギーが下がり、どうしようもない状況に陥っていて、無理に学校に行かせても状況は余計に悪くなるだけ。子どもによってはエネルギーがたまるまで休養させ、次の一歩を踏み出せるようにしてあげよう、というのが法の趣旨です。不登校が増えていいとは考えていません。しかし、不登校自体は問題行動ではない。学校に行けなくなったことで子どもは傷ついており、そういう子が増えるのは憂慮すべき状況です。仮に不登校になっても居場所がある、学びにつながれる、という施策を文科省として推進しているのです」という。
これに対して、記事は「だが、過去11万~12万人で推移してきた不登校生が法施行後、つまり17年以降に急増している。国の施策で不登校に“お墨付き”を与えている形では」と疑問符をつける。
昨年になって、デイリー新潮に二つの記事が掲載された。一つは「“無気力や不安”で不登校になる小中学生が急増中 専門家が指摘する「昔ならあり得ない3つの要因」」で、2024年2月13日付。執筆者はフリーライターの岡田光雄氏。
「小学校で担任教師だった頃、約4年間も不登校気味の男子がいました。その子に、校舎の写真をプリントアウトした用紙とカラーペンを渡して、『今日の君にとって、学校はどんな風に見えるか描き加えてみて』と提案したところ、彼が描いたのは校舎に牙と角がはえた絵でした。一部の子どもにとって、学校はそれほどに恐ろしい場所なんです。」そう語るのは、白梅学園大学子ども学部子ども学科で教鞭を執る増田修治教授。28年間、小学校教諭として教壇に立ち、現場の最前線で多くの不登校児と向き合ってきた経験を持つエキスパートは、年々、複雑化する学校問題に危機感を募らせている。昨年10月、文部科学省は2022年度版の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」を発表した。それによると、不登校中の小中学生の人数は29万9,048人(前年比22.1%増)に達して過去最多となり、不登校の要因は「無気力や不安」が51.8%と過半数を占めた。「こうした不登校児が増えた原因について、文科省はコロナの影響で学校へ行く機会が減って友達や楽しい思い出が作れず、生活リズムも崩しやすくなったからだろう、と見立てているようです。しかし、コロナが一番の原因ではないと分析しています。いまの子どもたちは、学びの有用感を喪失していたり、学校に息苦しさを感じているんです。子どもたちはちゃんとSOSのサインを出しているんですよ。一昔前の教師の中には、朝の出席確認の返事などで、生徒の声色や顔色のちょっとした変化に気づいて、不調を見分けられる人もいました。ところが、最近は文科省の推進もあって、出席確認や授業もパソコン・タブレットで行う学校が増えましたから、生徒の異変に気づくことが難しい。SOSに気づいてあげられる大人が周りにいなければ、子どもはどうすることもできない。そんな不条理を目の当たりにして、どんどんやる気を失っていくんです。」(増田教授)
https://www.dailyshincho.jp/article/2024/02131040/?all=1
不勉強なことに、このエキスパートという方の名前は初めて聞いた。氏によると、子どもたちが「息苦しさを感じる」のには「指導マニュアル」「受験競争の早期化」「学びの継続」の三つに原因があるという。「無気力や不安」が51.8%という文部行政の認識もさることながら「学びの有用感」という学者の観念もいかがなものか。
もう一つ、昨年にデイリー新潮に掲載された記事がある。11月18日付。「少子化なのに「不登校」激増の異常事態 「無理して通わなくていい」は正しいのか」という題で執筆者は音楽評論家・歴史評論家の香原斗志氏。
先ごろ、全国で小中学生の不登校が激増しているという衝撃的なデータが発表された。文部科学省が行った2023年度「問題行動・不登校調査」の結果、その数は34万6,482人と過去最多だったことがわかったのである。しかも11年連続の増加で、前年度からは16%も増え、はじめて30万人の大台を超えてしまった。不登校とは、病気や経済的理由をのぞき、心理的および社会的な要因で小中学校に通えない日が年間30日以上あることを指す。23年度の内訳は小学生が13万370人、中学生が21万6,112人で、いずれも前年度より2万人以上増えている。10年前とくらべれば小学生は約5倍、中学生は約2.2倍だといえば深刻さが伝わるだろう。
https://www.dailyshincho.jp/article/2024/11180600/?all=1
香原氏の主張を紹介する前に、いつも言っていることだが、「不登校とは、病気や経済的理由をのぞき、心理的および社会的な要因で小中学校に通えない日が年間30日以上あること」という定義にそもそもの問題があることを特記しておく。不登校を原因とした欠席という不可解な(しかし専門家たちはわかるらしい)定義は心因性登校拒否の除外診断的な定義から来ていると考えれば理解できると述べたのが拙著『不登校とは何であったか?心因性登校拒否、その社会病理化の論理』の趣旨である。概念の定義から崩さなければ言説は壊せない。そう学校哲学者は考える。
では、香原氏は何と主張しているのか?
とくに23年度に急増した理由としては、コロナ禍の影響も指摘されている。集団生活を送る機会が減ったり、生活のリズムが崩れたりして、学校生活に適応しにくくなったというのである。たしかに、その影響はあるだろう。子供は新型コロナに感染しても重症化しにくいとわかってからも、学校で過剰な対策を強いたことの負の影響については、早急に検証する必要がある。だが、コロナ禍がはじまったのは2020年であり、それだけでは不登校が11年続けて増加した理由の説明にはならない。学校の教室での大きな声や音に耐えられないなど、従来の学校生活のあり方に適応できない子が増えている、という指摘もある。実際、そういう子は増えているのだろう。だが、問うべきは、どうして適応できない子が増加しているのか、という大本の原因である。・・・2016年に成立し、17年に施行された教育機会確保法の影響も、大きいのではないだろうか。これは不登校などの理由で義務教育を十分に受けられなかった子供たちに、教育の機会を確保するための法律で、不登校が急速に増えているという状況を踏まえて制定されたものだ。とはいえ、8年前の2015年度における不登校は約12万6,000人で、23年度とくらべれば3分の1程度にすぎない。むしろ、この法律が施行されてから、不登校は増加の一途をたどっているのである。どうしても学校に通えない子供に、教育の機会を確保するという発想自体は、否定されるべきものではない。だが、この法律のおかげで「学校に無理して通う必要はない」という意識が急速に広まったという指摘がある。最後の最後に頼るべきシェルターとして機能するなら有益だが、安易な逃げ場になっているとしたら、この法律自体を見直す必要もあるのではないだろうか。
途中、「大本の原因」ということで氏が主張しておられることは記事を読んでいただきたい。少なくとも「急増」した理由についてはコロナ禍を考えるべきだ。それについては昨年末の書評欄においても述べた通り。教育機会確保法の制定過程についてはまた号を改めて書く。この法律が遠因としても、それ以前から「増えている」という主張はあった。「学校に無理して通う必要はない」という主張も同様だ。むしろ、そのように主張している人たちをアクターとして法律が通ったというのが実情である。定義に問題がある以上、「増えている」というのは必ずしも数字を挙げて言える事実ではない。その点が等閑視されて「増えている」から問題だという主張がまかり通ってきた。
記事を読んでもらえればわかるように、デイリー新潮という同一媒体にて配信されたものでありながら、香原氏の主張は一読して増田教授の主張と真逆のようだ。氏が「学校に無理して通う必要はない」という主張を問題としている一方、教授は「学校はそれほどに恐ろしい場所」と言っている。けれども、氏が「最後の最後に頼るべきシェルターとして機能するなら有益だが、安易な逃げ場になっているとしたら」と問題視している居場所の存在は教授も「学びの継続」という観点から問題視している。教育機会確保法、そして「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」(COCOLOプラン)という文科省の施策に問題はないか、と。
デイリー新潮の記事にはサイト上でコメントを寄せることができる。増田教授の記事のコメントは0件。香原氏の記事に対しては8件あり、そのうちの7件までが否定的なものだ。残りの1件も「小中学校の校区指定(自宅から1番近くの学校に通わせる事)も撤廃しない限り不登校は増え続けるだけ」というもので、記事の内容に関するものではない。ところが、ヤフーニュースで再配信された記事には803件ものコメントが集まっている。インパクトがあったのは「大本の原因」ということで氏が主張されたことにある。エキスパートたる教授よりもトーシローの意見のほうが波紋を呼ぶ。
コメントの大半は香原氏が「不登校」を理解していないという内容だ。しかし、そういう主張はいつも言うように画一的である。「不登校」というコトバそのものに「理解」が込められていると言ってもいいだろう。その概念規定の中にすでに一定の理解されるべき主張がある。それを知りたければ不登校新聞のバックナンバーを読めばいい。こちらは登校拒否新聞である。お間違いなく!
目についたものに次のようなコメントがある。
私はいわゆるフリースクールで教えていますが、10年前と確実に生徒の質が変わった気がします。特に顕著なのは耐性と人に関わる力に欠ける生徒が本当に多くなった。また、学校に行けなくなったという理由をかなり安易になった気がします。生徒らをサポートしながら、本当に彼らのことを思うと、どこかで‘厳しさ’を無くさないよう自らに意識を置いています。(匿名)
フリースクールからこういう意見が出ているのは驚きだ。「不登校」の定型をつくってきたフリースクールからその「理解」を質す意見が出ている。「不登校」という概念枠が現実との間に齟齬を来たしている。実際、この方は「生徒」と言っておられる。意図的に「不登校」というコトバを外していると拝察する。こういう意見もある以上、香原氏が「不登校」を理解していないというような主張は無効だ。問題はなぜ「不登校」として理解しなければいけないのか、という点にある。
中には「居場所はてめぇで作れ それが社会だ」「子供の中で二極化が進んでいる」「そうして子供は闇バイトへ」というような寸言もあった。それぞれ考えさせられる意見である。昼間からイオンモールに子どもが大勢いるという目撃談があった。今の子どもたちにはイオンモールが居場所なのかもしれない。近所にあった映画館の入る建物が私の居場所だった。隣にはイトーヨーカドーとオーパもあった。階段で一段飛ばしに5階まで上がって、映画館のトイレの横にある待合席で本を読んでいた。私は東京大学に研究職を得たことがある。その時は初心忘るべからずということで、わざわざその椅子に座りにいった。その建物まで家から歩いて40分。さらに階段を昇り降りして運動する。二極化については登校拒否新聞としても何度か問題にしてきた。「学校に無理して通う必要はない」という場合に、その帰結が二極化しつつあることは等閑視できない。通信制など選択の幅が増えているとはいえ、そこを中退する者と大学に進学する者との差は大きいと言わざるを得ない。100円ショップのアルバイトでも高卒以上という学歴が要求される社会である。高校無償化の動きも進んでいる。その結果、職がなくて家にいる人が「ひきこもり」と恣意的に概念化されて、また別の社会問題とされる。その中から闇バイトに手を染める者も出てくるかもしれない。
ランドセルが異常に重すぎる。。。
たくさんある原因の一つだと思う。(ほぐほぐ)
ほぐほぐさんは新説を提唱した。唯物論的に考えてみれば、ランドセルの重さは十分に考慮すべき要因だ。通学していない場合、給食費は払うのか、とか、不登校生が中学校に進学する場合、制服を買う必要はあるのか、とか経済的な問題は実情としてある。一昔前にはマルクス主義教育学などというものがあったがどこへ行ったのか。
では、続きは次号。節分の頃に。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。