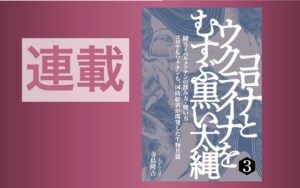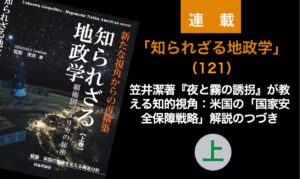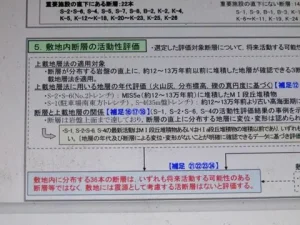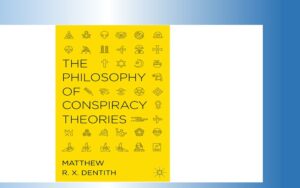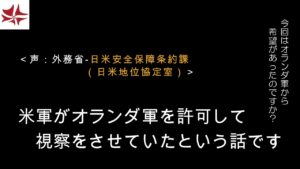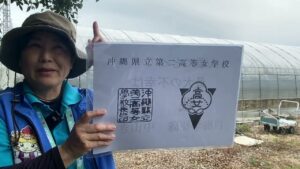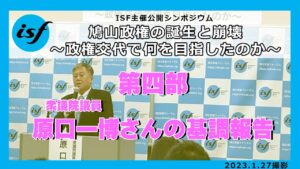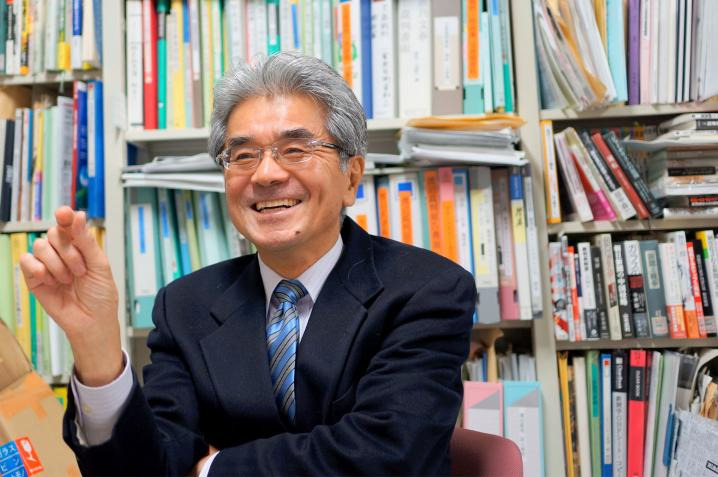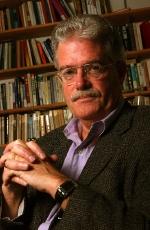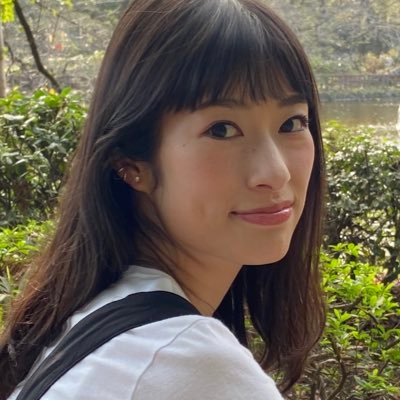登校拒否新聞12号:結局はまた行く事になる
社会・経済前号は「では、続きは次号。節分の頃に」と括ったけれど、掲載日が立春を過ぎてしまった。すると、立春どころか大寒波がやって来た。今度は花粉の飛び始める頃ということで、前号の続きである。
803件に上るコメントから目ぼしいものをピックアップしてお届けする。いつものように記事の内容とは関係なく考えさせられる意見だけを集めて構成している。元記事については前号を参照して欲しい。コメントの大半は「不登校を理解してない」という否定的なものだ。そういう一様な意見は登校拒否新聞の扱うところではない。その周辺にある多様な意見が知りたい。なお、ヤフコメ民の大半は名無しの権兵衛である。中には表示名というのを設定している人もいるが少ない。そこで、表示名がある場合は記し、その他は匿名としておく。引用に際しては、明らかな誤字は直した。
経験者からしたら不登校のメリットは無い。停滞だもん。その間に周りは先に行ってるから追いつくのに前より頑張らないいけない。結局はまた行く事になるんだから惰性でも行った方がいいよ(匿名)
通った方が、いろいろと近道だと思う。親の考えを尊重しますよ、今の学校は。あくまで尊重するだけで、結果に関しては、親が責任取ればいいので。コロナ禍で、不登校のハードルは下がったけど、社会のシステムはさほど変わってない。受験や進学には、不登校は遠回りだと思いますね。(匿名)
「学校通わなくてもいいけど、学校で学ぶべき勉強の内容はなんとかして身に付けようね」というのが僕の考えだな。(鴛鴦鸚哥丸鬱男)
増加は増加だが、生徒の9割はなんやかんや登校できている。それをどう見るか。不登校児は、3%(匿名)
最初の意見は実体験だろう。「結局はまた行く事になる」というのは一つの真理である。二つ目の意見は「行った方が良い」としながらも自己責任ということだ。鴛鴦鸚哥丸鬱男さんの意見には同意する。最後の意見は数字が合わない気もするが、言わんとしていることはわかる。中学校に行かずじまいだった当時に私がいちばん考えたことは自分以外の大多数は通学しているという事実だ。そこで出した答えが勉強だけはするということ。同じような意見はいくつかあった。例えば――、
数年前まで「中卒でも大卒でなくてもお金持ちや仕事で成功してる人はいる」というようなメディアも含めてそういった雰囲気はあったと思います。けれどうちは子供が中学校に入ると学校から聞かされるのは高卒と大卒ではお手当が違うとか聞かされ、子供はだから大学は行きたいと話ます。今は学校の成績も内伸重視で学校出席日数が足りないとなかなか難しいです。背景を見ると、学校では学校の出席が進路にも影響すると教えていますので、小学校で不登校でそのまま中学校も不登校になるという癖はつけない方がいいと思えるしそうして思うのは「学校行きたくないなら行かなければいい」と教えるより、「学校行きたくないならどこなら勉強できるか考えよう。」と親子で環境改革を考えることは大事かなと。小学校までは何とか親の言うことを聞いてくれますが中学校に行ったらなかなか難しいので小学生のうちに頑張るのがポイントです。(匿名)
自分は今年48才になりますが、中3の二学期からから親の転勤で他県に転校しました。転校先の学校は良い学校と聞いていたが、生徒も先生も何だか陰湿な人が多くいじめられた理由ではないが馴染めずすぐに行きたく無くなった。仮病を使って後半は学校には行かず、塾だけには行っていたなぁ。親も学校は行かなくても良いから塾には行きなさいと言ってくれていた。卒業の際、学校は全て出席扱いになったと記憶している。逃げ道作ってもらえたから感謝。(11*****)
昨日、ドワンゴが「通信大学」の設立を発表していました。ネット環境さえあれば、誰でもどこでも授業が受けられます。ドワンゴは、通信高校もやっています。つまり、小学校時代から、一日も学校に行かなくても、大卒になれる時代が来たということです。(匿名)
これらの意見は「結局はまた行く事になる」という真理則に適っている。進学の問題があるから学校に通っていなくとも学校の勉強はどうするか、という問題が残る。「多様な学び」がフェイクなのは、この問題に答えていないからだ。「塾だけには行っていた」という11*****さんが「学校は全て出席扱いになった」と言っていることに注意して欲しい。こういう例がある一方で、N/A――斜線とされる例がある。通信高校が通信大学を設立したのは革命的なことだ。よく「不登校」を問題にする人たちは学校が変わらないと言うが現実に変わっている。変わらないのは「不登校の専門家」なのである。
今は確かに、無理に学校へ行かないようになっています。保護者には、それをごく当たり前のように言ってきましたが、よく考えると、今の家庭環境と合っているのかどうか素朴な疑問があります。今は夫婦共稼ぎの時代です。お子さんが不登校になったら、子どもは一人です留守番でしょうか?近くに祖父母がいる場合でも、祖父母も働いています。夫婦のどちらかが仕事を長期休まないといけません。難しい問題だと思います。教育評論家(大学教員 元小学校教員)
離婚率の増加との因果関係はないものでしょうか?当方30代結婚7年目ですが、周囲は1/3以上離婚、もしくは夫婦不仲です。子どもの前でケンカをしてしまっていると、大抵は子どもは情緒不安定な気がします。離婚は選択肢としてあってもいいとは思うのですが、今後子供に与える影響だけが気がかりです…(匿名)
どちらの意見も家庭環境の変化を言っている。前者の意見は「不登校離職」というような新手の言葉で問題とされつつある。共働き世帯の場合は「不登校を選ぶ」のも難しいかもしれない。この点と合わせて考えるべきは、就業形態の多様化だ。夜の仕事に限らず、朝の9時に始まる8時間労働のあり方が変わってきている。子どもを学校に行かせる時間に親が寝ているという場合に子どもの出席率が低下するのは当然だ。離婚率との相関関係はもちろん認めるべきだろう。離婚率と欠席率との間に有意な相関関係が認められるならば「学校になじめない子ども」的な主張はいよいよ眉唾物だ。情緒不安については――、
放デイに近所の不登校の障害児が朝から毎日通ってる。こういうのは問題にしない。不登校の溜まり場になっててまともな療育や教育は受けていない。家で暴れるか放デイに行くかしかしていませんね(000*****)
小学生の子供が転校初日から、まともに授業に参加できず、暴れるようになった。前の学校では、普通に授業を受け、楽しく学校へ通えていた。授業内容は大差なさそうだった。大きな違いは、今の学校はオープン型教室であること。隣の授業まる聞こえ。ごちゃごちゃ物が置いてある廊下は丸見え。座席の間隔は狭く、ぎゅうぎゅう詰め。児童精神科は半年待ち。WISCはIQ130以上の視覚優位タイプだったため、情報量が多過ぎて落ち着かないのだろうと思われる。本人は「分からない」としか言わない。学校へ交渉し、落ち着けるスペースを設けてもらったが、登校してもそのスペースにこもり、ひたすら黒板に計算式を書くだけ。家では比較的普通に過ごせるので(転校後、情緒不安定ではある)、学校へ行かせるのを親の私があえて止めた。学校へお願いできるのは、あとは特別支援級へ入れてもらうことだが、来年4月から。(aiueo)
どちらも深刻な例だ。かつて情緒障害児として括られた子どもの中で割合にして多かったのが登校拒否児である。そういう子たちが情緒障害児短期治療施設というような所で「収容治療」を受けた負の歴史もある。しかし、暴れる子を前にして親が収容を望んだということは当時の文献にも読むことができる。今は、そういう子が放課後デイにいるということか。児童精神科は半年待ち、というのも貴重な情報だ。「病気」と「不登校」を区別するのはけっこうだが、であればなぜ児童精神科に行列ができるのか教えて欲しい。
精神科に連れて行くと学校に行かないことに簡単にお墨付きを与えてしまうから増えたんだと思う。いいか悪いかわからいけど(araki)
こういう理由もあるのだ。
今はもう児童心理の専門家が「無理して行かなくていい」「家でゲームばかりで昼夜逆転でもいい」「家にいるからと無理に勉強させなくてもいい」と声高に言うから、親も安心して休ませられる。でもその子の10年後20年後に専門家たちの誰一人として責任を取ってくれるわけではない…最後は親が抱えるだけ。安易に休ませる風潮にして大丈夫のかなぁ、とは思う(もちろんイジメとか起立性障害とかは論外で)(匿名)
一度不登校やちょっとメンタルを壊して病欠し、カウンセラーに相談すると、今は必ずと言っていいほど、「学校にいかなくていい」と言われる。きっと自殺されるのが怖いのだと思う。もっと言えば、生徒のことを思って、というより、カウンセラーや心療内科師自身の保身のために「学校に行くな」と言っているように感じる。行動療法というか、学校に行きながら慣れていくという選択肢がほぼ無くなっている。(匿名)
少しでも他と違ってるだけでやれ発達だやれグレーゾーンだって、そんなんじゃ窮屈で学校行きたくなくなるわな。何でも包含してゆったりと流れていく大河のような大らかさが今の教育にはないのよ。(匿名)
昭和の末期の登校拒否が不登校という名称に変わった時、登校刺激はよくないみたいなことを言い始めた学者がいました。(時をかける少年)
これらは心理職に対する意見だ。登校刺激というのは、それこそ行動療法的なアプローチであるが、それは良くないとした歴史がある。しかし低学年であれば有効な手段として見るべきだろう。スクールカウンセラーが「学校にいかなくていい」と言うのであれば、カウンセラーの数を増やすことはむしろ「不登校」の原因ということになる。「きっと自殺されるのが怖いのだと思う」という意見は当たってるのではないか?
子供が学校に通う義務はないが、義務教育期間中、親は子供に教育を受けさせる義務があり、就学義務違反は学校教育法で10万円の罰金(意外と安い)。だが、正当な理由があれば通わなくてもいいとも学校教育法には書かれていて、しかも正当な理由に具体的な制限がない。学校に通わなくても取れる中卒認定や高卒認定もあるが、学歴なしでも学歴不問の企業には就業できるし、起業もできるから問題ない。マスコミが布教している「いじめられたら自殺教」に洗脳された子供たちを死なせるくらいなら、学校に通わせない方がいいだろう。(匿名)
メディアが配信している言説が子どもたちの意識に無意識のうちに植えつけられるということは確かにあるだろう。私が「不登校」という概念枠を外したい理由も根本的にはそこにある。コトバの力が強いのである。暴走族なんて格好いい名前で呼ぶからいけないんで珍走族と呼べばいいと言った人がいた。テレビに珍走族と映ったら恥ずかしくて特攻服なんて着れないというワケ。「いじめられたら自殺教」については、福田ますみ氏が『モンスターマザー:長野・丸子実業「いじめ自殺事件」教師たちの闘い』(2016年)という一書を世に問うている。いじめられて自殺。だからムリして学校に行かなくてもいい――という主張ばかりが報じられている。そこに「不登校」を経験したという人が出てきて、「不登校」でも大丈夫と言う。なお、福田氏の本については書評欄に取り上げるつもりだ。
小学校教員です。子どもは学校の経験だけで出来ているものではありません。不登校の多くの子どもたちは、自宅からネットの動画やSNS等を見ています。何となくどこかと繋がっている。見たいものを見たい時に見られる。都合の良い情報を信じれば良い。そんなことが許されているのに、わざわざ学校へ行く気力など湧かなくなります。不登校のきっかけが明確でない子どもが増えていることも確かです。(wjrst)
達観した教員もいるものだ。教員のうつ病と、それに伴う離職が増える一方で、こういうドライな先生が増えるかもしれない。いいことだと思う。たぶん。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。