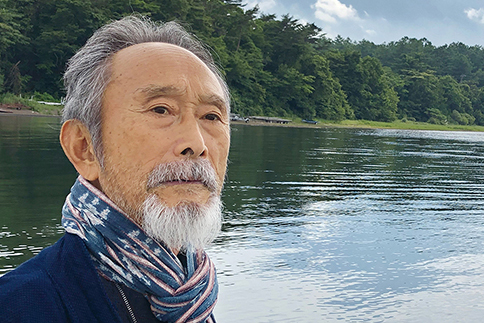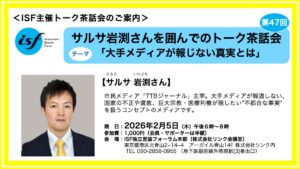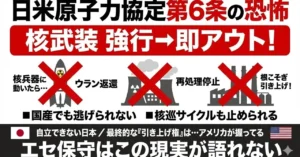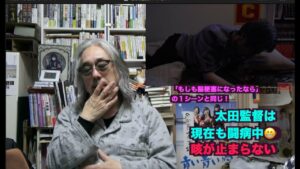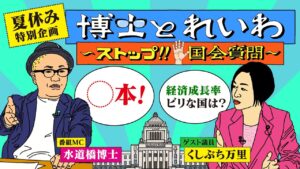☆寺島メソッド翻訳NEWS(2025年2月17日):EU諸国の幹部はタカ派が多いので、トランプの思惑は順調には進まない可能性がある 。
国際※元岐阜大学教授寺島隆吉先生による記号づけ英語教育法に則って開発された翻訳技術。大手メディアに載らない海外記事を翻訳し、紹介します。

欧州のタカ派が緊張を高めている
さて、今や我々には分かる。米国側はヨーロッパを切り離し、ロシアと再び結びつくつもりだ。米国の立場は昨日、ブリュッセルで、ウクライナ紛争について話し合うために来ていた新任の国防長官ピート・ヘグゼスによって再確認された。我々はすでに要点が見えている。ウクライナのNATO加盟は「非現実的」であり、戦争は外交を通じて「終結しなければならない」と彼は語った。ウクライナ側は2014年以前の国境を取り戻すという野望を放棄しなければならない。これにはクリミアも含まれる。そしてロシアとの交渉による解決に備えなければならない。
しかしヘグゼス国防長官の訴えるはウクライナだけにとどまらず、さらに「厳しい戦略的現実により、米国はヨーロッパの安全保障に主眼を置くことができない」と述べ、ウクライナの戦後安全保障の責任はヨーロッパ軍が負うべきだとし、米軍の関与は明確に排除した。これは、NATO同盟諸国に防衛費の増額を求めるトランプ大統領の幅広い取り組みと一致する。同氏は、これらの部隊はNATO主導の任務には参加せず、同盟の第5条の保証の対象にもならないと明言し、ヨーロッパの安全保障問題から米国が離脱することを強調した。
こうした発言は、トランプ大統領のこれまでの発言を考えると、欧州の指導者たちにとってそれほど意外なものではなかったが、軍事的関与の継続よりも外交を優先するという米国のウクライナ政策の根本的な転換を強めるものとなった。これはバイデン前大統領のより対立的な姿勢からの歓迎すべき転換だが、平和への道は依然として多くの障害を抱えている。
ヘグゼス国防長官はウクライナとロシアの和平協定の可能性について詳細を述べなかった。しかし、ウクライナ報道機関が報じたトランプ大統領の和平案の漏洩情報によると、ロシアが奪取した領土は安全保障と引き換えに譲渡されるという。ウクライナ側は、失われた領土を取り戻すための軍事的、外交的努力を放棄し、これらの地域に対するロシアの主権を公式に認めることが期待される。
この計画の真偽にかかわらず、それがロシアの和平の主な条件を反映していることは明らかであり、トランプ大統領もそれを十分承知している。彼の政権がこの地政学的現実を認識し、ウクライナがそれらの領土を取り戻す可能性が低いことと相まって、現実的な外交への重要な転換を示している。この新しい外交手続きをさらに強化するために、トランプ大統領はSNSのトゥルース・ソーシャル上で、ロシアのウラジミール・プーチン大統領と「長時間にわたる非常に生産的な」電話会談をおこなったと発表した。「我々は、互いの国を訪問することを含め、非常に緊密に協力することで合意しました。まず、ウクライナのゼレンスキー大統領に電話し、この会話について知らせる。私は今まさにそれをしようとしています」。
米国側とロシア側の直接対話が再開されたことは、間違いなく前向きな展開だ。しかし、最大の短期的な危険は、トランプが和平の枠組みが十分に整わないままプーチンに停戦を迫ろうとするかもしれないことだ。これは失敗するに決まっている。
なぜなら、ロシアが占領している4つの地域からウクライナ軍を完全に撤退させることを含む主要な要求について、ロシア側が妥協しないことは、我々も承知しているからだ。ロシアのセルゲイ・リャブコフ外務次官は、米国からのいかなる最後通牒も効果がなく、いかなる交渉も「現地の現実」を認識しなければならないと述べている。
ここで大きな問題となるのは、欧州主導の平和維持軍をウクライナに派遣するという提案である。これはロシア側からの強い抵抗に直面することはほぼ確実だ。NATO加盟国であるかどうかに関わらず、ロシアはそれをNATOの代理軍とみなすだろう。これは受け入れられない展開だ。(英国の政治専門家)アナトール・リーヴェン氏は次のように述べた。「これはロシア政府と体制にとって、ウクライナ自身のNATO加盟と同じくらい受け入れられない。実際、ロシアは両者の間に本質的な違いはないと見ている」。
もう一つの複雑な要因は、米国の安全保障面での欧州からの分離、つまりNATOの欧州化が、逆説的に欧州の主要指導者たちの強硬姿勢を強めることになり、平和への障害となる危険もあることだ。
「ロシア側が主要な要求事項で妥協しないことは我々も承知している。」
欧州連合内では、ポーランドやエストニア、リトアニアを中心とする影響力のある戦争支持連合が出現した。新しい欧州委員会はこれらの国々を外交政策と防衛の重要な役割に据え、その影響力をさらに強固なものにした。ポーランドのドナルド・トゥスク首相は、欧州理事会議長就任演説で「ヨーロッパが生き残るためには、武装しなければならない」と述べた。
同様に、EUのカヤ・カラス外務・安全保障政策上級代表は、米国の撤退に対応して欧州は防衛費を大幅に増額する必要があると主張しているが、ロシアはいかなる犠牲を払ってでも打ち負かす必要があるという立場を維持している。一方、新任の欧州委員であるアンドリウス・クビリウス氏は、欧州の防衛生産を増強するために「ビッグバン的展開」を求めている。
EU以外でも、英国は同様に好戦的で、ウクライナへの軍事支援を倍増させている。1月16日、スターマー首相はキエフで二国間防衛有効条約に署名し、すでに提供されている128億ポンドに加えて、年間30億ポンドの追加軍事援助を約束した。この協定は、英国がウクライナのNATO加盟を支持することを再確認するものでもある。
NATOのマルク・ルッテ事務総長も水曜日(2月12日)、同様の意見を述べ、「ウクライナへの安全保障支援を平等にする」必要性についてはトランプ大統領に「同意する」としながらも、「紛争の進路を真に変えるためには、さらに多くのことをしなければならない」と警告した。同事務総長の発言は、NATOが「戦時体制の考え方を採用する」ことを提唱する最近の声明に続くものだ。
こうした軍備増強の根底には、ロシアがNATOを攻撃する能力も意図もないにもかかわらず、ロシアがヨーロッパにとって実存的な脅威となっているという信念がある。米国の撤退に対するヨーロッパの姿勢として片付けられてしまうかもしれないことは、実際には平和への大きな障害となっている。ヨーロッパの指導者たちが軍事的緊張を高め続ける限り、ウクライナ戦争の外交的解決の可能性は減る。
本当の危険は、ロシアとの戦争は避けられないと執拗に予測し、それに備えることで、ヨーロッパが最終的にその戦争を現実のものにしてしまうかもしれないことだ。急速に増大するヨーロッパの軍備増強と根強い反ロシア感情に直面して、ロシア側は待つという選択肢はもうないと結論付けるかもしれない。ヨーロッパのNATO加盟諸国が引き続き緊張を高めれば、ロシアはNATOの軍事力が限界に達する危険を冒すよりも先制攻撃を決断するかもしれない。それほど極端ではない展開でも、ヨーロッパのますます攻撃的な姿勢はウクライナの永続的な平和と根本的に相容れない。
言い換えれば、トランプ政権の欧州からの離脱と外交推進は緊張緩和に向けた一歩のように見えるかもしれないが、意図せずしてその逆の結果をもたらす危険がある。米国の離脱は欧州の軍事的野心を抑制するどころか、特に東欧のEUとNATOの主要関係者がロシアに対してますます対立的な姿勢を取るよう勇気づけているのだ。
米国の撤退後、必要不可欠とされたNATOのヨーロッパ化は、大陸の軍事化と指導者によるロシア悪者化を加速させ、そもそもウクライナ紛争を引き起こした状況そのものを永続させている。ヨーロッパの指導者たちは、この機会を利用して外交に取り組むのではなく、米国の撤退を軍事的過激化の理由とみなしている。この意味で、米国当局のヨーロッパからの分離は、ウクライナ和平を達成するというトランプ大統領の公言した目標と矛盾している。
欧州の指導者たちがロシアの安全保障上の懸念を認めない限り、長期的な解決の見通しは暗いままであり、より大規模な戦争の危機が引き続き大陸に迫ることになるだろう。皮肉なことに、米国が欧州の安全保障問題から距離を置こうとする試みは、最終的に米国を、はるかに制御不能なさらに大規模な紛争に引き戻すことになるかもしれないのだ。
※なお、本稿は、寺島メソッド翻訳NEWS(2025年2月17日)「EU諸国の幹部はタカ派が多いので、トランプの思惑は順調には進まない可能性がある 。」
http://tmmethod.blog.fc2.com/
からの転載であることをお断りします。
また英文原稿はこちらです⇒Trump’s diplomacy won’t bring peace
筆者:トーマス・ファジ(Thomas FAZI)
出典:Strategic Culture Foundation 2025年2月15日
https://strategic-culture.su/news/2025/02/15/trumps-diplomacy-wont-bring-peace/