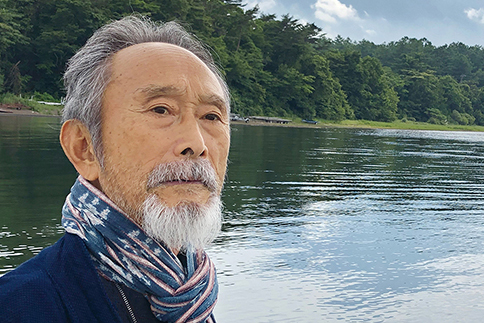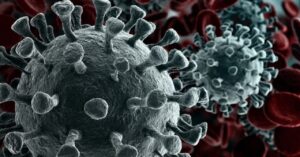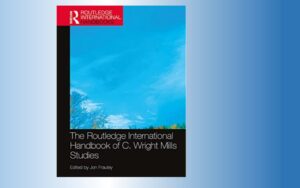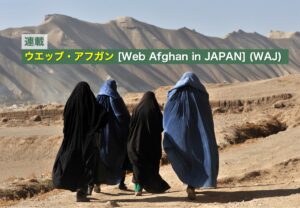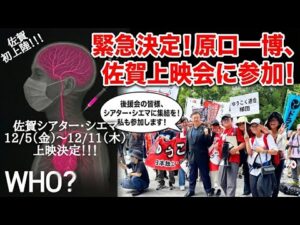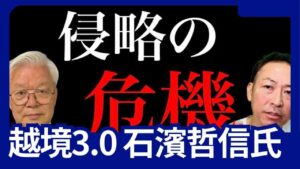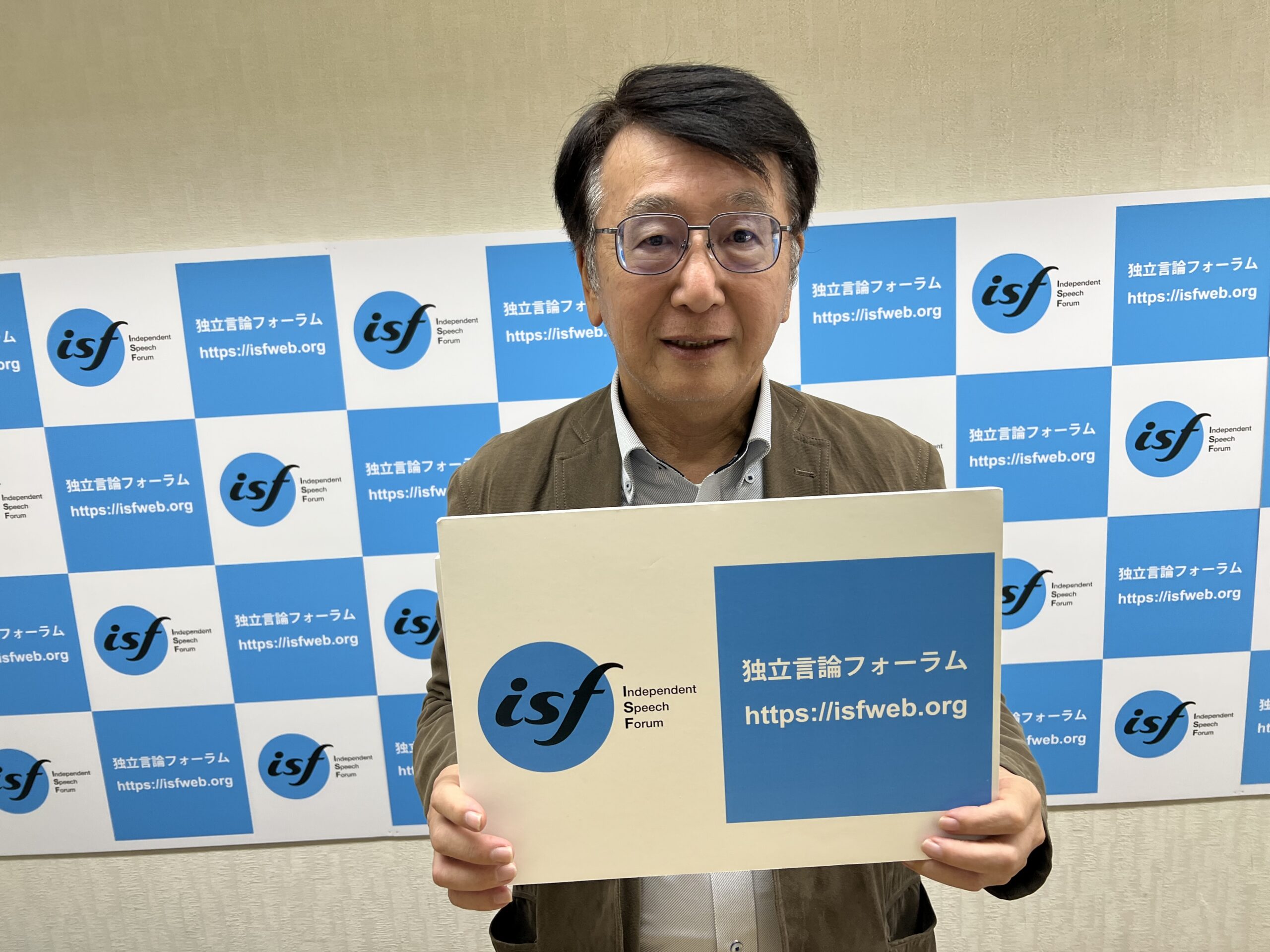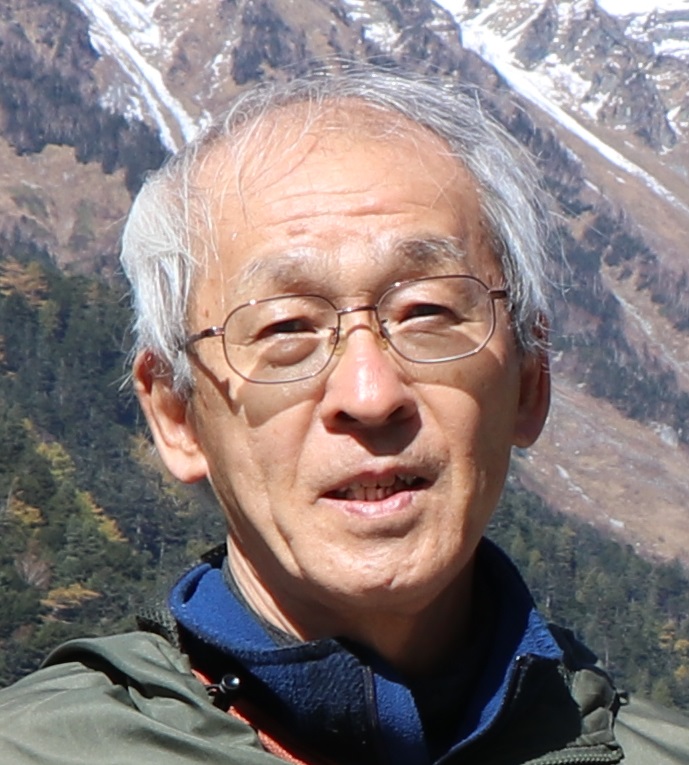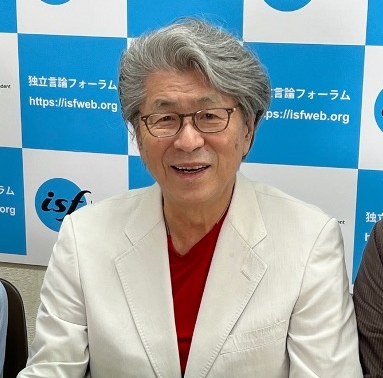☆寺島メソッド翻訳NEWS(2025年3月3日):フョードル・ルキヤノフ研究主任 「トランプが送る秋波に騙されるな。ロシアの目的はウクライナだけではない」
国際※元岐阜大学教授寺島隆吉先生による記号づけ英語教育法に則って開発された翻訳技術。大手メディアに載らない海外記事を翻訳し、紹介します。

© セルゲイ・グネエフ/スプートニク
ウラジミール・プーチン大統領は2022年2月にロシアの軍事作戦を開始した際、この紛争は単にウクライナに関するものではない、と明言していた。その目的はとは、「いわゆる西側諸国全体」に対するロシア側のより広範な闘争に関するものである、とのことだった。その西側諸国全体を形成するのは、米国の姿である、とされた。同大統領はその日の演説で、米国を「体制上重要な大国」と表現し、米国の同盟諸国は従順な追随者として行動し、「その行動を模倣し、その提示する決まりを熱心に受け入れている」と述べた。 3年後、この西側秩序の性質がこの紛争の帰結の中心となっている。
ドナルド・トランプのホワイトハウス復帰は、大西洋同盟を揺るがした。トランプ傘下の米国はもはや古い決まりに従っていない。トランプの米国は、西側諸国の優位を定義してきた何十年にもわたる構造を解体しつつある。西欧諸国に対するトランプの攻撃的な発言やNATOへの攻撃、ウクライナに対するあからさまな軽蔑は、欧州の指導者たちを困惑させている。スティーブン・ウォルトなど一部の専門家は、米国の同盟諸国はトランプの予測不可能な行動に対して最終的に団結するだろう、と見ている。しかしプーチンは、これらの欧州の指導者たちは、不満があろうとなかろうと、最終的には「主人の足元に立ち、尻尾を振る」だろう、と主張している。問題は、この変化する力学がロシアにとって何を意味するかだ。
悪を含んだ善
トランプの過激な外交政策は、観察者を驚かせた。米国大統領はウクライナを公然と無視し、米国がもはや負うべきではない「重荷」である、と貶めた。トランプにとって、西欧は米国の寛大さに寄生する寄生虫だ。反支配者層主義の大衆迎合主義に染まった彼の言い口は、民主主義と人権という西側諸国がこれまで使い古してきたお題目を、長年それらを擁護してきた国々に敵対するものに変えて使っている。この光景は、熟練した政治専門家たちにとっても奇っ怪だ。

関連記事:Trump’s Ukraine wake-up call: Points he’s now making are what Russia said all along
トランプのウクライナ軽蔑は、地政学的戦略ではなく、国内政策のための計算によるものだ。彼の関心は東欧ではなく中国にある。彼は米国の関心を貿易不均衡や北極、ラテンアメリカ、インド太平洋へと向け直したいのだ。しかし、ジョー・バイデン政権によって「善と悪」の決定的な戦いと位置づけられたウクライナは、政治思想上の避雷針となってきた。バイデン政権はロシアに対する勝利にすべてを賭けていた。トランプはいつものように、その言説をひっくり返し、破壊しようとしている。
自らと戦う西側諸国
トランプ現象は西側同盟を混乱に陥れた。西欧諸国は米国への依存と格闘している。一部の欧州指導者は「戦略的自立」について語っているが、それを実現する手段はない。他の指導者はトランプより長く生き残り、慣れ親しんだ地盤に戻ることを望んでいる。しかし、旧秩序は崩壊しつつある。かつては西側覇権の手段であった米国当局による欧州選挙への干渉は、現在、トランプ支持者らが自らの政策を推進するために利用されている。トランプの同盟者にとって、欧州連合は「バイデンの米国」の延長であり、それを内側から解体することが彼らの使命である。
大西洋危機は過去の政治思想闘争を映し出している。ある意味、これは19世紀ドイツの文化闘争、つまりオットー・フォン・ビスマルクの世俗国家とカトリック教会の闘争に似ている。今日の世界では、グローバリストのリベラル派が教皇の役割を演じ、トランプのような大衆迎合主義者がビスマルクのマントを継承している。
ロシアにとって、この西側内部の亀裂は好機であると同時に罠でもある。ロシア当局は政治思想的には自由主義のEUよりもトランプの米国に近い。しかし、トランプとあまりに密接に連携することは危険を伴う。米国における激変はロシアに関するものではなく、米国自身の帰属意識の危機に関するものだ。ロシア側は米国側の国内闘争の駒とならないように注意しなければならない。

関連記事:Trump’s realpolitik: Breaking old alliances, forging new deals
「世界の多数派」とロシアの役割
過去3年間で地政学的な変化が起きた。ウクライナ紛争でどちらの側にも立たず、西側諸国の衰退から利益を得ようとする「世界の多数派」と 呼ばれる国々の出現だ。冷戦時代とは異なり、米国側は南半球諸国をロシアに対抗するよう結集させることに失敗した。その代わりに、多くの非西側諸国は米国側の先導に従うことを望まず、ロシア側との関係を深めている。
一方、西側諸国では新たな変化が起こりつつある。トランプの米国にはもはや冷戦時代のような力はない。ロシアと米国は今や、何年も見られなかったほどの相互の礼儀をもって会話している。このタイミングは象徴的で、ルーズベルトとチャーチル、スターリンが戦後の世界を形作ったヤルタ会談の記念日と重なる。しかし、この雪解けは注目に値するが、ロシアは米国側との新たな連携に過度に参画することには警戒しなければならない。
新たな「友好関係」の誘惑を避ける
西側諸国は、その将来をめぐる存亡をかけた闘いに陥っている。ロシアは、トランプ政権という一派がロシアと関わることに有益だと考えたが、それは一時的なものに過ぎないことを認識しなければならない。トランプ政権下の米国とあまりに密接に連携することは、ロシアの世界的な地位を強化してきた「世界の多数派」を疎外する危険性があるからだ。
歴史的に、ロシアはしばしば西側諸国の承認を求めてきたが、時には自らを犠牲にしてきた。ロシア当局は常に西側諸国に承認されることを求めている、という認識は根強く残っている。ロシアがトランプの申し出を急いで受け入れ、非西側諸国の友好諸国に背を向ける様なことになれば、ロシアは何よりも西側諸国の承認を切望しているという固定観念を強化することになる。こうなれば、戦略的な失策となるだろう。
ウクライナ紛争は、新たな世界秩序の創出をめぐるものではなく、冷戦の最終章である。ロシアが決定的な勝利を収めれば、多極化した世界における主要国としてのロシア側の地位は確固たるものとなるだろう。しかし、ロシアがこの機会を生かすことができず、西側諸国の新たな関与の罠に陥れば、戦略的利益を失う危険がある。

関連記事:Russia has won a war against the West: What the Putin-Trump call really means
新たな世界秩序の形成
世界はかつての冷戦の力学には戻っていない。トランプの西側同盟の再定義の試みは、より広範で混沌とした世界政治の変革の一部である。中国や欧州連合、ロシアはいずれも、これからの10年間を形作る内外の圧力に直面している。トランプの野望にもかかわらず、米国は単独で世界を作り変えることはできない。
ロシアにとっての課題は明らかだ。ロシアは独立を維持し、西側諸国の政治思想闘争に巻き込まれるのを避け、非西側諸国との関係構築を継続しなければならない。ロシアは西側諸国による制裁や外交的孤立、経済戦争の3年間を乗り越えてきた。西側諸国が分裂している今、ロシア側は米国側との「新たな恋愛」の誘惑に抵抗しながら、自らの進路を定めなければならない。
この予測不可能な状況では、内部の安定性と戦略的忍耐力を備えた国だけが勝者として浮上するだろう。ロシアが進むべき道は過去に戻ることではなく、ますます分断化が進む世界において主権国家として立つ未来を築くことにある。
※なお、本稿は、寺島メソッド翻訳NEWS(2025年3月3日)「フョードル・ルキヤノフ研究主任 「トランプが送る秋波に騙されるな。ロシアの目的はウクライナだけではない」
http://tmmethod.blog.fc2.com/blog-entry-3003.html
からの転載であることをお断りします。
また英文原稿はこちらです⇒Fyodor Lukyanov: Trump’s America is no friend – Russia must stay the course
ロシア当局は米国当局との新たな恋愛という幻想に抵抗しなければならない。
筆者:フョードル・ルキャノフ(Fyodor Lukyanov:ロシア・グローバル情勢編集長、外交防衛政策評議会幹部会議長、ヴァルダイ国際討論クラブ研究主任)
出典:RT 2025年2月26日
https://www.rt.com/russia/613324-trumps-america-is-no-friend/