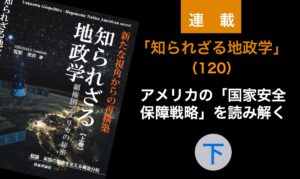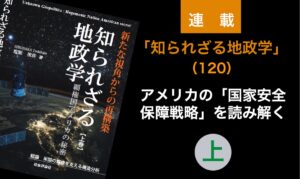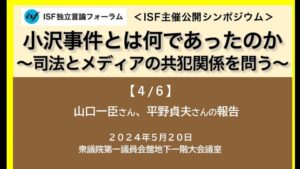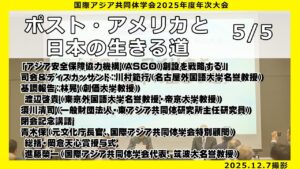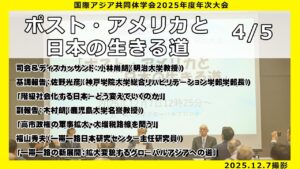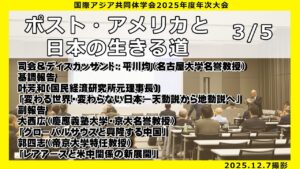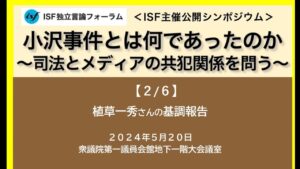登校拒否新聞14号:マイクラ
社会・経済昨年11月20日付で、集英社オンラインが2本の記事を公開した。
まずは「オンラインゲーム「マインクラフト」で不登校支援、家族での会話が増えた事例も…家から出られない子どもの居場所をゲーム内に作る取り組みとは」である。
https://shueisha.online/articles/-/252181
次に「不登校児過去最多34万人…支援団体は財源確保に課題、オンラインゲームが切り開く支援の未来とは?」となる。
https://shueisha.online/articles/-/252182
どちらも記者の福永太郎氏が「ゆるクラ」というオンラインサービスを提供している岡村和樹氏に取材した内容だ。記者は「財源確保が支援継続の課題」として次のように記す。
こうした活動を継続するには、財源の確保が大きな課題だ。不登校支援には人件費、場所代、備品代が必要で、支援環境を維持するには安定した財源が欠かせない。ゆるクラは現在、費用を一切かけない形で運営しているという。・・・人手不足のため、新規募集も停止している状態だという。岡村さんによれば、支援に携わるスタッフは本業や学業、アルバイトなどで参加できない日もあるが、ゆるクラが人件費をまかなうことで支援活動により専念できる可能性もあるという。このような財源の課題は、ゆるクラだけでなく他の団体にも共通している。「フリースクールなどの不登校支援は、運営者の多大な努力の上で成り立っているのが現状だと思います。子どもと接するだけでなく、保護者からの相談対応、学校関係者と連携などやることが多いなかで、財源確保にも動かないといけない。今後この業界にプレイヤーが増えていくか、心配な気持ちもあります。保護者からの費用で賄うのも一案ですが、子どもが不登校だと離職率や休職率が高くなってしまうため、保護者からの費用で支援を継続するやり方は健全とはいえないでしょう。今後、ゆるクラは助成金の獲得や、法人の寄付や協賛を募る動きをする必要があると考えています」
岡村さんは無料でサービスを提供する心づもりである。サービスは2023年9月に開始。グッドデザイン賞(2024年度)に選ばれた。審査委員のコメントに「活動期間がまだ短く、経済的な展開や持続性など今後の課題はさまざまあると思われる」とあるのが、やはり現実の課題となったか。
https://www.g-mark.org/gallery/winners/26049?designers=5adab959-d4dd-4fd5-8386-438968d5362a
フリースクールのオンライン化についてはまた号を改めて書く。というのも、かなりの大企業が参画し始めているという現況である。個人が用意する箱物と企業が提供するオンラインサービスという二極化が急速に進む可能性がある。「ゆるクラ」はその中間的なポジションということになろうか。利用料を取らないというスタンスは独特だ。しかし収益を上げなければ組織としての維持管理運営は難しい。
さて、集英社オンラインの記事はヤフーニュースによって再配信された。
https://news.yahoo.co.jp/articles/065f8f07b34755275a73143fef58dd1d51ad4c5c
なぜか最初の記事にはコメントが2件しかつかず、次の記事には582件もついた。理由はおそらく後者には旧不登校新聞社の石井志昴氏のコメントが「エキスパート」の意見としてついたからだ。これは360人が「参考になった」をクリックしている。ヤフコメ民の中ではkos********さんのコメントが1,951回の「共感した」と362回と「なるほど」と163回の「うーん」を得た上に45件の返信まで受けて断トツだ。
親戚に小学校2年生から不登校。カウンセラーの方に学校を連想させるワードから避けるよう言われ、パソコンなどはできる環境にいました。その子も40才。今どうかというと引きこもりです。大学入学できましたが卒業ができませんでした。親の収入で暮らしています。身の回りの事が自分からできません。親が体調悪くても洗濯などしません。パソコンなどはできるので宅配は利用しています。身の回りのことができる、世話をしてくれる人のありがたみを感じる事、自分にできることを考える力があっての記事のようなサポートと私は思います。(kos********)
ヤフーニュースは「エキスパート」の意見については「参考になった」しかクリックできないようになっている。ヤフコメ民の意見は「共感した」「なるほど」「うーん」の三つが用意されている。テレビが双方向通信と称して視聴者にボタンを押させる仕組みを導入したのと同じで、選択肢を与えて選ばせるという一方的なアンケート調査のようなものだ。実際にエキスパートとしての優れた意見が載ることもあり、この場合は「参考になった」のクリック数が桁外れに多い。そうでない場合、ヤフコメ民はむしろ自分の意見を書き込むことを選ぶ。サイトの設計の意図はともかくプラットホームとしてそこそこ機能しているのだ。以下、いつものようにめぼしい物をピックアップして紹介したい。
ちなみに上の意見は「うーん」と言いたいところだ。というのも、40才という年齢からしても、あまり学校とは関係ないように思うからである。「小学校2年生から不登校」「大学入学できました」というのはさすがにフリースクールに通っていたとか高卒認定を受けたとか、その間の出来事が何かなければ辻褄が合わない。少子化の影響もあり高校でも大学でも敷居は下がっている分、全欠でも進学は難しくないが卒業できない例が増えている。卒業できなくても大学中退なら悪くない。けれども、この場合の中退は「早稲田大学中退」とは意味が違う。
では――、
色んな角度からの支援は悪くないが、このようなケースでは追跡調査で有効性確認が必要でしょうな。今は有効性は謎、場合によってはマイナス影響になるかもしれないが発案者の良い結果に“なるだろう”という目論見でスタートしているわけだし。実証実験として3年くらいやったあと15年その後を追跡調査するなら公的資金投入もやぶさかじゃないと思うで。すべての支援形態に言える事だけど。(****)
不登校の支援って必要なんかね。勉強なんてやりたい奴は勝手にやるし、やらない奴は強制してもやらない。好んで一人になりたがる人は、そもそも居場所を求めていなかったりもすると思うが。一人でいたい人に群れろって言っても群れんだろう。こういう支援を考える人って、人とのかかわりが楽しかった人なんだろうと思うなあ。だから、そうでない人の気持ちはわからない。人とかかわることが当然で、それがいかなる場合においても正しいと思ってそう。放っておけばいいのに。(ぼぼぼ)
支援は必要かもしれないけど逃げ道ばっかり作ってる気がする。不登校の子でもこの状況をどうにかしたいとがんばってる子は応援してあげたいと思うけどやる気が出ないとかでなんにもしない子は応援する気になれない。逃げるということもアリだと思うけどそればっかりじゃ何も解決しない。(3Q)
私が不登校の支援に携わって思うのは。オンラインの支援は確かに効果的です。しかし、オンラインだけでは効果は薄いと感じています。オンラインをきっかけに、この集団なら自分も馴染める、活躍できる、よしやってみよう、となってはじめて価値が生まれると思っています。あくまでもオンラインは手段であって、大小ある何らかの社会の中で自分を活かすことが出来なければ人間的な社会活動からはほど遠いと思います。オンラインで完結ではなく、オンラインでつながれたもの(同様の好みや性格などを持つもの)同士が何か価値あるものを創造してはじめて支援、教育の成果だと思っています。(kyo********)
オンラインや通信で不登校が改善されるとか、居場所になるなど無い。独りよがりの意見である。不登校問題はこんなことでは改善しない人間的なことが問題なのである。(shi********)
いずれも批判的な意見だ。実際、コメントの大半は否定的なものが占めている。その理由はいくつかあるが、一般論としてはここに言い尽くされている。最初の意見にあるように有効性については慎重に見定めたい。例えば自由の森学園のようなオルタナティブ学校の場合、卒業生の名前もある程度、公開されており、結果が示されている。この点、支援ありきのサービスは支援者の論理が独り歩きしている感がある。ある意味、教育とは結果なのである。何が育つか、という一点で評価されるべきものだ。同僚に無理やりカレーライスを食べさせて動画に写すような教員をどの大学の教職課程が育てたのか?
「見守りましょう。」「寄り添いましょう。」では解決しない。(joh********)
こんな事をしてたら、不登校どころか引きこもりになると思う。まずは、外に出て太陽を浴び、風に吹かれよう。(vna********)
寄り添う、というのはジャーゴンで「連携」と同じように業界用語だ。教員の性加害事件が頻発する世の中である。「登校拒否児」の家に教員が訪ねていって子供部屋で寝ている子の布団にもぐり込んだという話を聞いたことがある。陽の当たらぬ密室での出来事か。風の噂である。風に吹かれ陽に当たろう。これは私が通学していなかった時分にいちばん重視したことだ。成長期は陽に当たる必要がある。日光によりビタミンDが体内で形成され骨格ができ上がる。見守っていても骨は育たない。
文科省が義務教育を放棄し始めたのか…。(suk********)
どんなものか体験したことがないから批判は出来ないと思いつつ…なぜ学校生活が豊かに送れる様な環境整備をしようという話にはならないのかな?いつも思うんだけど…学校の問題点って人手不足と無駄にある先生たちのお仕事だったりする。文科省は教育内容の見直しをして人材確保して職員配置をしっかりする。何よりも小中学校でも昼始まりのクラスを作るなどすれば不登校問題が解決する事ってあると思う。義務教育で培う必要のある力を今一度見直しをして色々な人たちで議論してより良い教育環境を作る必要があると思うんだけど…タブレットは使い方次第では毒にしかならない。ましてや自分をコントロールする力を持っていないうちから使い出すのは違うと思うから…五感を育てて、心も身体も健康にまずは育てようよ!そしたら生きていける方法を自分で見つけられるから!(jdv********)
やはり公教育の問題である。このピントは外したくない。フリースクールへの公金投入には慎重でありたい。公金は公教育に投じるべきものだ。居場所は私教育である。義務教育学校の「人材確保」「職員配置」に使うべきお金を居場所に投与するのではあべこべだ。「昼始まりのクラス」というアイデアもおもしろい。午前と午後で入れ替える二部授業は戦後、疎開児童が帰ってきた都会の学校で行われた実績がある。戦災により学校数が足りないという事情はもちろんであるが、拙著『戦後教育闘争史』に書いたように、教員が食料の買い出しに出かけて無断欠勤するために教員数が足りないという切実な事情もあった。教員のなり手が減り、子どもたちの出席率も低下するならば、二部制にすることも一考である。クラス定員も減らすことができるし給食を強制する必要もなくなる。
何、マイクラって?(nym********)
マイクラ楽しそうだけど3D酔いする自分には厳しい。実際3D酔いする人は結構いるので、3Dゲーム以外でも遊びながらプログラミングを学ぶことは可能。直ぐにプログラミングがーとか言いがちだけど、向き不向きが凄いから、出来ないからってダメな子判定はNGだと思うよ。適合が難しい子供達には別なアプローチも考えていると思いたい。考え方として悪くないけど、予算がざる見積もりなのとNPOって基本的に信用できにくい(rxh********)
マイクラで学校と似たようなことをしても「ワールド荒らし」っていう別のいじめが発生するだけだ。(sst*****)
マイクラにどっぷりハマってメタバースの世界で生きるにしても、マイクラの中にも危険なサーバーやコミュニティーがあるから、単純に良い事だとは思えない。もしかすると不登校が増えた原因がネット社会にある気もする。(kag********)
ゲームだからダメと言うつもりはないし、人間関係で困った時、顔が見えないからこそ本音が話せるって点は時にある。ただしこの不登校「児」に対しての取り組みとしてはズレてるなと思う。ゲームだけでなくSNSや動画には暴言が溢れ影響を受け、オンラインゲーム中に荒っぽい言葉遣いをしている状況を見たことある人も多いのでは?文字のやり取り、ボイチャでのやり取り、相手の表情が見えず自分の発したどんな言葉で相手がどんな表情になるのか、どんな受け止められ方をしたのか、それが分からない。傷付けた感覚は薄く、傷付けられた感覚だけが深く残る。逃げる事は悪いことでは決してない。逃げた先で心を休めるのは時には必要。ただ、逃げた先に楽しい事だけ準備してどうするんだって話し。(fm1*****)
そもそもマイクラってなんだよ?って人は3D酔いするかもしれない。マイクラの中にも荒らしがあるらしい。それを言い始めると、学校にも会社にもいじめはあるというような話になる。結局、問題は現実の3D空間と変わらないのかもしれない。その感覚を早く身に着けることが子どもにとっても大事なことではないか。この点は私がフリースクールや居場所に批判的ないちばんの理由でもある。つまり「不登校」とされる子どもだけを集めて、いわば疑似的なコミュニティをつくることのリスクだ。オンラインにおいても、そういう子だけを集めて支援者とコミュニケーションを取るということの意味だ。
不登校からのネトゲ廃人経て社会人身内にいるけど、他のネトゲ廃人見て「これじゃダメだ!」と思って学校行き始めたからゲームに逃避するだけじゃなく他人と比較できる子ならいいのかもしれん。幼保の資格あるわけじゃない、財源もない団体になんとかできるもんだいじゃなくね。(ssss)
これどうなんだろう。子どもの居場所としての試みは分かるものの、ネット上なので結局リアルな人との繋がりや居場所が出来るわけではないんですよね。私も長期間の不登校経験者なんですが「ネトゲ廃人」になるのが怖くてオンラインゲームはあえて避けてました。不登校でも家庭のサポートがあって学力維持できている子以外は危険じゃないかな?ゲームやってて、それでやる気が出て学校に行ったとしても、勉強についていけなかったらまた不登校になってしまうと思う。今の小学生って忙しくて、毎日学校に通っていても家での勉強のサポートも必要なんですよ。学校行きたくないんだもんねって優しくするばかりは本当に子どもの将来のためなの?って疑問しかない。(こめ)
原因論は外す、というのは不登校論の大前提だろう。しかし、ネットが原因という主張は強い。最近ではスマホの利用時間が問題とされている。スマホ取り上げという教育法も出てきている中、あくまでも学校の問題という従前の主張が通るかどうか。この点、オンラインゲームはあえて避ける、というスタンスはよくわかる。多かれ少なかれ、現代人は似たような選択をゲームに限らずしているはずだ。「不登校」は世間を忍ぶ仮の姿で、その実「ネトゲ廃人」なのかもしれないヨ。え?廃人を支援しますって?
こめさんが言っている「不登校でも家庭のサポートがあって学力維持できている子」は実在する。ここに現実の教育格差がある。それを補うのが公教育の役割であるのに「多様な学び」に逃げている。「やる気が出て学校に行ったとしても、勉強についていけなかったらまた不登校になってしまう」というのは通信制高校の中退例の大半が該当する。こめさんはおそらくそういう例をいくつも見ているのだろう。私を含め、案外に学校に通っていなかったタイプの人間は「勉強」の必要性を認めている。なのに「不登校の専門家」たちが一様に「学び」を売り込むから困る。
とどのつまり――、
時代が変わっても結局は嫌々でも学校に行った子供の方が有利な社会。(謎)
という3D空間にボクラは生きている。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。