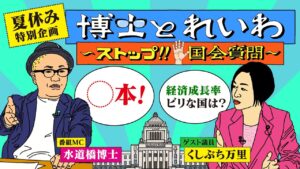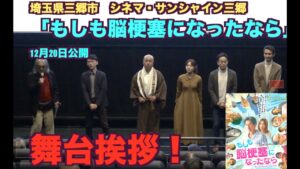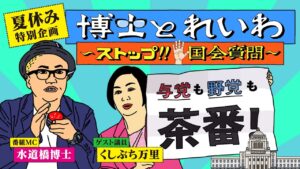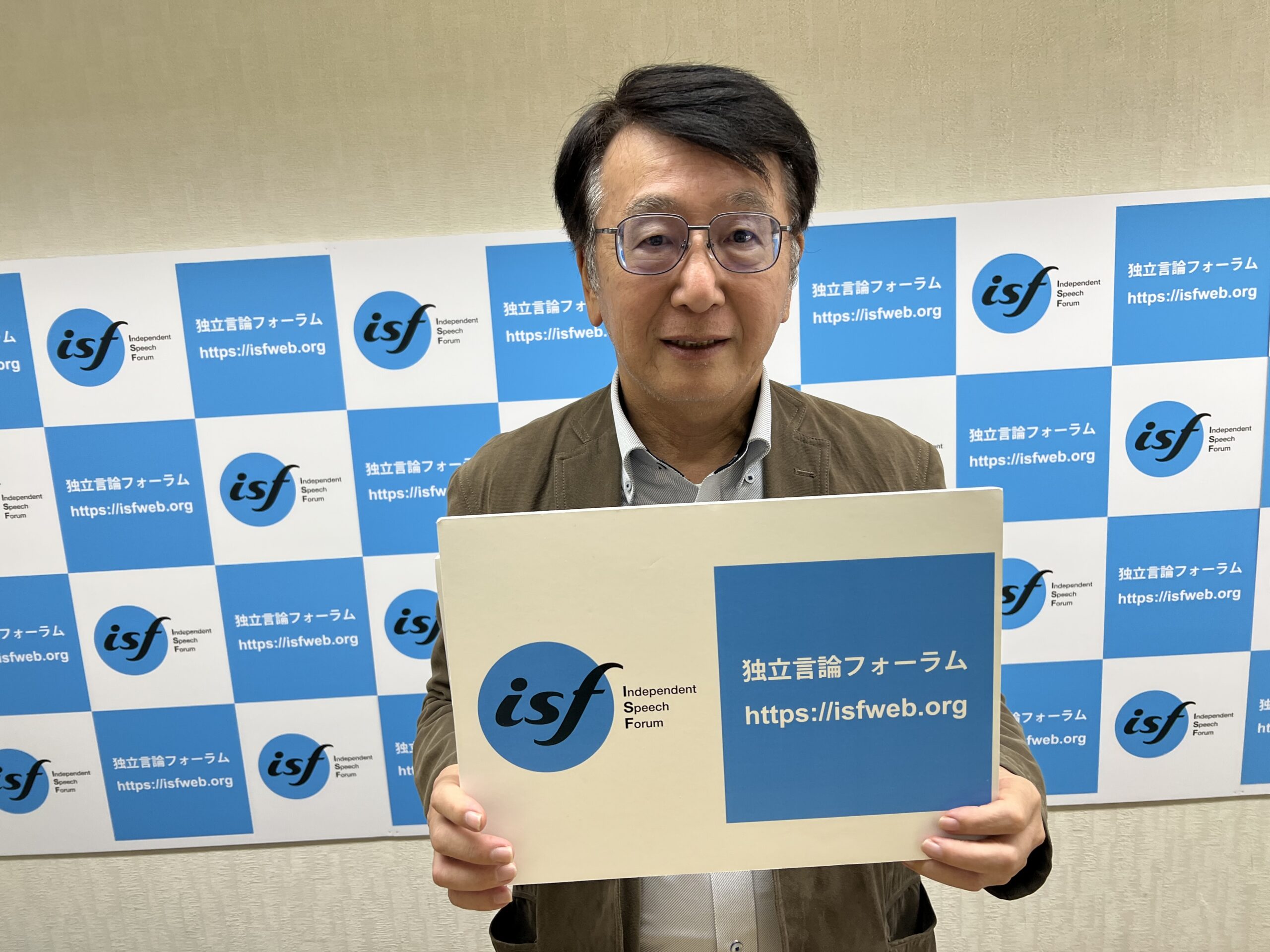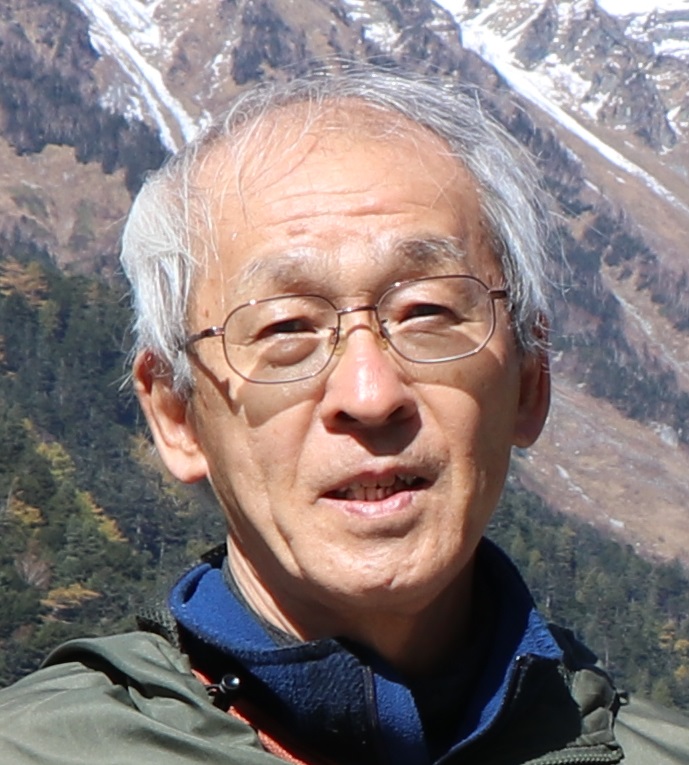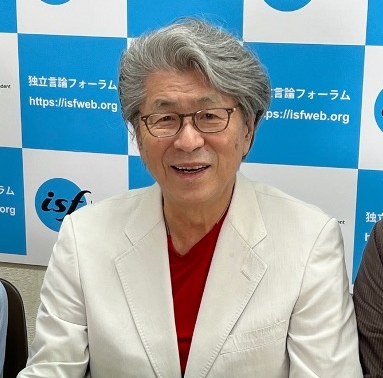秋嶋亮(社会学作家)連載ブログ/23:問題の優先順位を見失っている
社会・経済厚労省の統計によると、昨年の人口減は89.7万人と過去最大となったが、これは出生数と差し引きの数字であり、死亡者数は161万人にも上っているのだ。一昨年もほぼ同数が死亡していることからすれば、この僅か2年の間で実に320万人を超える日本人が消失したわけだ。
政府は高齢化社会特有の現象だと説明するが、この間の超過死亡は100万人規模に達しており、広島・長崎の原爆犠牲者ですら20万人位であることからすれば、その凄まじさが窺えるだろう。つまり今の日本は戦争をやっているパレスチナやウクライナが霞んで見えるほど人が死んでいるのだ。
グラフを見れば2000年以降日本の死亡者数は110万人前後でゆるやかに推移しているが、2021年頃から急激に跳ね上っている。言うまでもなくこれはコロナワクチンの接種が開始された時期と重なり、もはやその相関に議論の余地はないだろう。
国内の研究者はもちろん、海外のマスコミや専門家もこの点を強く指摘しているが、政府が因果関係を認めるはずもなく(厚労省の専門部会も否認主義を貫いており)、ワクチン接種を中止するどころか、莫大な補助金を支給し、20箇所にも及ぶ工場や関連施設を建設させているのだ。
鳥取、名古屋、横浜、仙台などでは先月の死亡者数が過去最多を記録したというが、おそらく全ての都道府県が似たり寄ったりなのだろう(今仮に変化がなくとも遅効的に多死現象が生じるのだろう)。ところが、こうした重大問題が社会全体で共有される「争点文化」はもはやこの国には存在しないのだ。
つまり人々はマスコミや、支持政党や、インフルエンサーに議題設定され、焦眉の問題を不明にされ、プライオリティ(最優先で考えるべきこと)を錯誤しているのだ。
このところSNSでは財務省解体!のシュプレヒコールがエコーチェンバー的(こだま効果的に増幅され)飛び交い、これに感化された人々が続々とデモに参加している。しかし巨大薬禍というパースペクティブから捉えれば、これは非常に高度な「大衆動員(命令や強制ではなく宣伝や扇動によって大衆を或る行動に走らせる策略)」なのである。
どういうことかと言うと、本来であればこれほど膨大な被害が生じているのだから、即刻ワクチン接種を中止し、被害者や遺族を救済するよう厚労省を叩かなくてはいけない。ところが人々はl抗議のプライオリティを間違え、モブ(情動による集合)化して財務省前に詰めかけているわけだ。
この続きは会員制ブログで購読できます。
http://alisonn.blog106.fc2.com/blog-entry-1457.html
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
☆秋嶋亮(あきしまりょう:響堂雪乃より改名) 全国紙系媒体の編集長を退任し社会学作家に転向。ブログ・マガジン「独りファシズム Ver.0.3」http://alisonn.blog106.fc2.com/ を主宰し、グローバリゼーションをテーマに精力的な情報発信を続けている。主著として『独りファシズム―つまり生命は資本に翻弄され続けるのか?―』(ヒカルランド)、『略奪者のロジック―支配を構造化する210の言葉たち―』(三五館)、『終末社会学用語辞典』(共著、白馬社)、『植民地化する日本、帝国化する世界』(共著、ヒカルランド)、『ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへ―15歳から始める生き残るための社会学』(白馬社)、『放射能が降る都市で叛逆もせず眠り続けるのか』(共著、白馬社)、『北朝鮮のミサイルはなぜ日本に落ちないのか―国民は両建構造(ヤラセ)に騙されている―』(白馬社)『続・ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへ―16歳から始める思考者になるための社会学』(白馬社)、『略奪者のロジック 超集編―ディストピア化する日本を究明する201の言葉たち―』(白馬社)、『ニホンという滅び行く国に生まれた若い君たちへOUTBREAK―17歳から始める反抗者になるための社会学』(白馬社)、『無思考国家―だからニホンは滅び行く国になった―』(白馬社)、などがある。