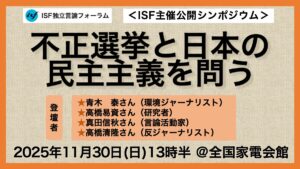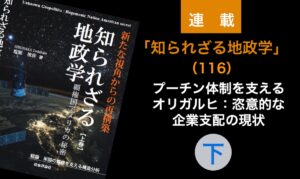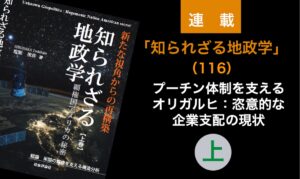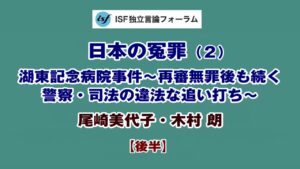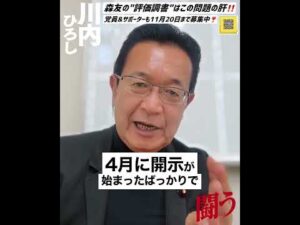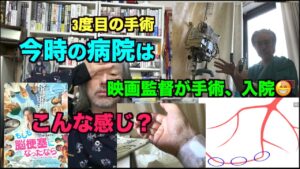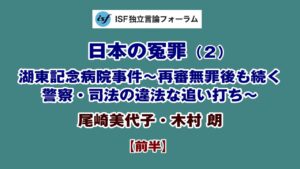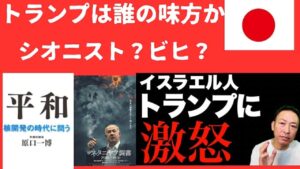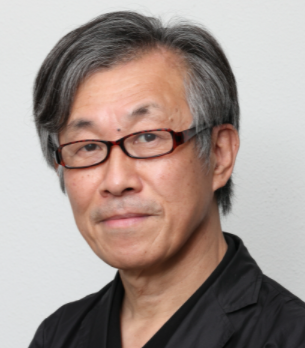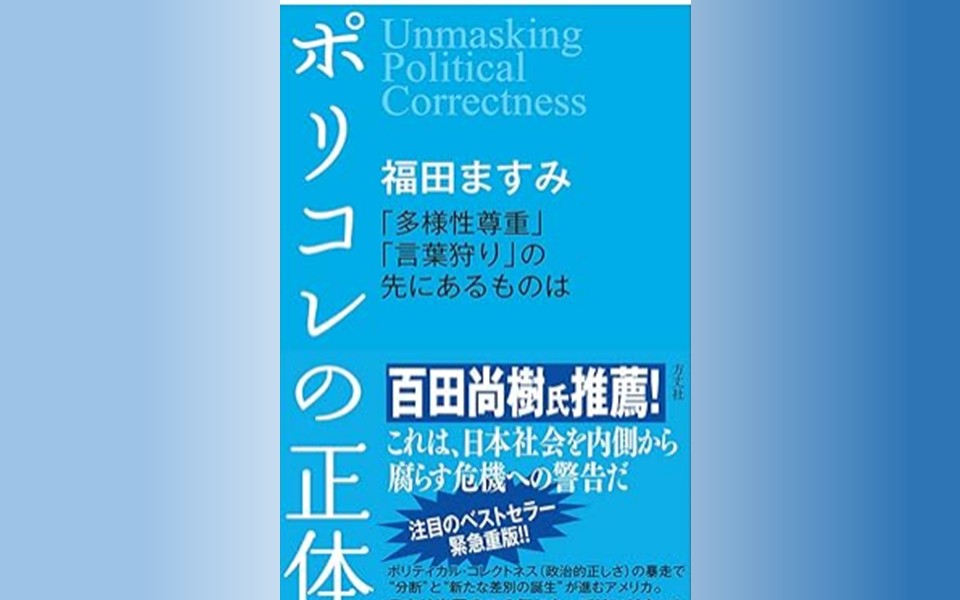
登校拒否新聞書評欄:福田ますみ著『ポリコレの正体』(方丈社、2021年12月)
社会・経済この本については「思想の押しつけ 戦えるか」という題で、福井県立大教授(当時)の島田洋一氏による書評が2022年1月16日付で『産経新聞』に載っている。現在、氏は衆議院議員である。政党は日本保守党。福田氏の本の帯文に推薦の辞を寄せているのは党首の百田尚樹氏。帯は初版から付いているが、百田氏のコメントが載ったのは重版となってからだ。日本保守党の結党日は2023年10月17日。福田氏が党員なのかどうかは確認できなかった。
https://www.sankei.com/article/20220116-DWPES6ETEFIHZD55USWDTLAQAI/
だいたい発行日が2021年12月1日の本の書評を今さら書くのはおかしい。それでも登校拒否新聞として福田氏の本に着目する理由が二つある。
一つは、氏が『モンスターマザー:長野・丸子実業「いじめ自殺事件」教師たちの闘い』(2016年)の著者ということだ。私はかねがね教育学における教育ルポルタージュの扱いが不当に低いと感じている。いじめが原因で自死に至った例は報道の対象とはなっても学術研究の対象とはなっていない。旭川という地名を例に取れば、教育学者は旭川中学校での平和教育が偏向教育とされた事件か、一斉学力テストの最高裁判決を出した旭川学テ裁判を思い浮かべるだろう。しかし、いまや旭川は女子生徒が自死に及んだ事件の代名詞である。同僚にむりやりカレーを食べさせた4人の教員の顔写真はSNS上に出回っている。教員の性犯罪はもはや日常だ。それを傍観して「不登校」が増えていると騒ぐ。教育学者が見ている「学校」と世間一般が見ている「学校」とがズレている。畢竟して、教育学――卑見では学校学であるべきもの――は教育ルポを、であるから学校ルポを科目として取り込む必要がある。つまり、福田氏は学校学部学校ルポ科の主任教授であるべき人だ。
もう一つ、この本が気を惹くのは副題に『「多様性尊重」「言葉狩り」の先にあるものは』とあること。この2点はじつは『登校拒否新聞』の論点なのである。
島田氏による書評は「思想の押しつけ 戦えるか」と題されていた。問題は、しかし「思想の押しつけ」ではないと考える。福田氏が本の42頁に引いているジェイソン・マイケル・モーガン氏の発言に「アメリカでは多様性が重要なキーワードになっていますが、内実は、肌の色や民族の違い、性的少数派など表面的な多様性を尊重するにすぎず、思想的多様性については、一切許されません」とある。つまり「多様性」が思想の多様性を抑圧していることが問題なのだ。であるから「言葉狩り」が起こる。事柄を「不登校」に引きつけて考えればわかりやすい。「登校拒否」が狩られて「不登校」一色となった。「勉強」を禁句として「多様な学び」に取って替えた。「不登校」という言葉が圧しつける「不登校」という理解は驚くほど一様で、均し並みである。この言葉がフレームワークとして機能しているのは登校拒否を「言葉狩り」したからである。拒否しているわけではない、という含意がメタレベルにある。
福田氏は「いささかの批判もネガティブな発言もほとんど許されない社会」(25頁)と言っている。これはアメリカのことだ。モーガン氏の説では、アメリカでポリコレが始まったのはフランクフルト学派が原因だという。ナチスが政権を取った際にドイツから亡命してきた哲学者たちがコロンビア大学を牙城としてソ連のレーニン主義とは違った仕方でマルクス主義の普及に努めた。確かにゼロトレランスという標語はハーバート・マルクーゼの共著『ピュアトレランス批判』という書名にあるピュアトレランスの反語である。ポリコレとは革新派の思想的手段であった。
この「いささかの批判もネガティブな発言もほとんど許されない社会」という一文には傍点が振ってある。本文には太字になっている文章と傍点が振ってある文章がある。察するに、太字は編集人によるものだ。傍点は著者自らが強調したものと見る。この社会というのを言説空間として捉えれば、同じことは「不登校」という言説についても言える。具体的には、本紙の4号「スダチクライシス」を読んでほしい。この話には事後談がある。続きはスダチ代表の小川涼太郎氏の著作『不登校の9割は親が解決できる』の書評として書くつもりだ。
福田氏が問題にしているのはアメリカでの例えばLGBTという言説が日本にも入ってきて、同様な事態を招いていることだろう。ポリコレがフランクフルト学派に由来するならば、LGBTの研究者が哲学のポストを占めている現状は理由なきことではない。「かなり以前、性同一性障害の人たちの存在が知られ始めた当時、私はそういう人たちが存在することに驚き、実際にそのうちの一人に取材して、ある媒体に記事化を打診したが、見向きもされなかった」(184頁)という彼女の経験は示唆に富む。そうして綴られる「新潮45休刊」事件については本を手に取ってみて欲しい。彼女自身、当事者として巻き込まれたこともあり筆が躍っている。
今はアメリカからの影響は抜きにして、日本における固有の問題として考えてみる。というのも、日本におけるポリコレの代表的な例が「不登校」にあるからだ。我田引水で言っているのではない。一部の識者の発言が繰り返し複数の新聞社から配信されるという事態がある。この問題についてはオルタナメディアからひっそりと配信されている本紙としても何度か言及してきた。「多様性尊重」は決して論者の多様性を尊重して成り立つ言説ではない。「言葉狩り」が異論を封じている。
「不登校」という「不」の一字を冠した言葉が流布している原因は登校拒否という言葉が狩られたというよりも、さらに根深いところにある。メディアにおける言葉狩りはアメリカ流のポリコレ以前から日本でも起こっていた。いわゆる差別用語の禁止である。これもアメリカから輸入されたポリコレの一端だと言うことはできよう。けれども、日本には「糾弾」(水平社)という戦前からの流れがある。戦後、部落差別という日本に固有の問題が差別用語を対象化した。これには井上ひさしのような文筆家が先頭に立って反対したけれども結局、使ってはいけない言葉がいくつも指定され、活字媒体はもちろんテレビ映像からもそうした言葉が消えたのである。
差別をなくすために差別用語を使わないというスタンスには賛成だ。それがポリコレであるならば反対はしない。問題は差別用語をメディアが使わないという取り決めがなされたとたん、言葉に対する感覚が衰えることにある。つまり、メディアが使っている表現であれば問題ないという無意識的な自覚が生じる。新聞に出ている言葉であれば、テレビのアナウンサーが使っている表現であれば、いかなる差別も免れているはず、と言語感覚が鈍る。言葉を選ぶことをしなくなる。
登校拒否って言っちゃいけないんだ?うん。この子たちは学校に行きたくても行けない子どもたちなんだ。決して学校を拒否してるわけじゃないんだよ。だからフトウコウって言うの?そうだよ。でも勉強しなくていいの?まずはしっかり休ませてあげて!
働いていない人を不就労とは呼ばない。
結婚していない人を不結婚とは呼ばない。
失業者と独身である。
学校に通っていない人は不登校と呼ばれる。4月から子どもが完全不登校になった。「五月雨登校していた」ならわかるが「不登校になった」とは何か?
中学3年生の時に不登校を経験――なんていう紹介文をよく見る。いったいに何を経験したのだろう?
その経験が裏返せば「理解」となる。というよりも、その「理解」を得ることが経験したと後付けで語られている。経験したからわかったのではない。経験したから自分にもわかると「理解」が追認される。スダチの小川氏がボコされたのはこの「理解」を欠いていると「不登校の支援者」たちから決めつけられたからだ。「いささかの批判もネガティブな発言もほとんど許されない社会」がそこに現出する。
ちなみに、福田氏の本にも何度か出てくる「変革の主体」という表現がいつ成立したか。それをテーマにした拙著『治安維持法下のマルクス主義』が来月にも刊行される。言葉の歴史というのが私の考える思想史のテーマである。その歴史を掘り下げれば、一見して関係ないような事柄であってもじつは通底していることが知られる。福田氏が山中泉『「アメリカ」の終わり』(2021年)などを典拠に詳しく書いているBLM運動の創始者たちはマルクス主義者をもって自任している。そのうちの一人、アリシア・ガーザの著書『The Purpose of Power: How We Come Together When We Fall Apart』(2020年)は『世界を動かす変革の力』(明石書店)という題で訳された。原題にない「変革」という用語が出ているのがおもしろい。この言葉の由来については拙著を読みなさい。進歩的知識人たちはアントニオ・ネグリのような理論家のみを取り上げる。現代のマルクス主義が現実に何をもたらしているか。暴徒が襲った商店街の惨状を見よ。
「言葉狩り」が言葉の歴史を断ち切ることで、含蓄を持った言葉がなくなり、スローガンのようなひらべったいコトバばかりが溢れかえる社会になる。しかし「副反応」「反ワク」というコトバの流通した社会は、たんに「いささかの批判もネガティブな発言もほとんど許されない社会」なだけではない。その実害により蝕まれるディストピアだ。思想の多様性が抑圧された時、人々は感情的になる。すなわちアニマルになる。
島田氏による書評が「思想の押しつけ」と言っていたのは「理解」を圧しつけることだと解釈したい。このように理解するのが正しいという「理解」の圧しつけである。私はそれを思想とは言わない。思想は正しい理解を説くものではない。間違った思想もあるからである。マルクス主義という思想が現段階において何を意味するのか。BLM運動がマルクス主義者たちによって起こされたのであれば、私は彼らの思想に共鳴はしない。間違っていると思う。しかし、そのことはそうした思想のあることを否定するものではない。マルクス主義という思想が現代においても人々を動かしていることは事実である。であるから、私はその思想をもっと深く学びたいと思っている。間違っているとしたら何が間違っているのか。それを知ることで自らの思想を練り上げたい。
その思想が変じて「正しい理解」となった時、禁句が生じる。うつ病の人に「がんばって」と言っちゃいけないんだと理解したとたん「がんばる」は禁句となる。「副作用」ではなく「副反応」と理解したとたん「副作用」は禁句となる。正しいとされる理解は使っちゃいけない言葉、不適切とされる表現を生む。
思想の多様性を担保するために最も必要なこと。それは言葉を尊ぶことだ。「にほん」と「にっぽん」、そのどちらをも認めることだ。「中国」と「支那」、どっちも認めることだ。ポリコレはそれを認めないのである。破邪顕正。どちらかを正しいとした上で、「言葉狩り」――折伏するのだ。学問がその後ろ盾となってしまってはいけない。異論のないところに議論は成り立たない。異説を容れないのであれば学問ではない。異端尋問と福田氏も言う通り、それでは宗教だ。
なお、この本に続いて小浜逸郎の『ポリコレ過剰社会』が扶桑社新書から出ている。読み比べる必要もあろうが、ポリコレそのものを主題として書評を書いているわけではないのでまたの機会にしたい。この本は小浜の遺作となった。彼には『学校の現象学のために』(1985年)という本もある。これについては「論理なき現象のゆくえ:「不登校」現象の現象学的還元」(2016年)という駄文で言及したことがあるので参照されたい。以下からダウンロードできる。
https://researchmap.jp/mendelssohn/published_papers/14150737
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。