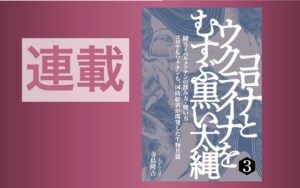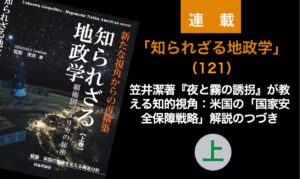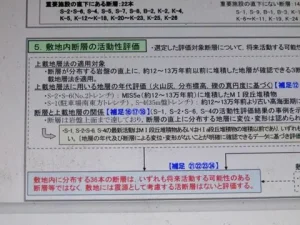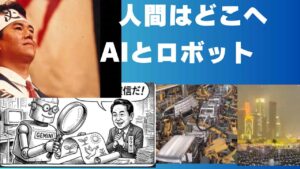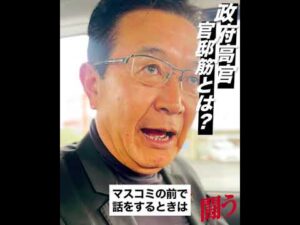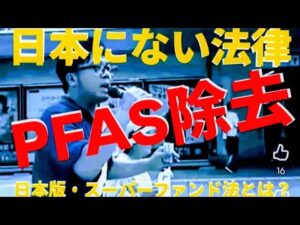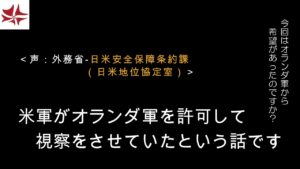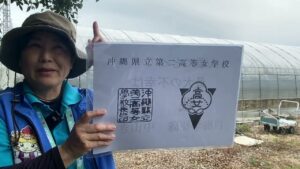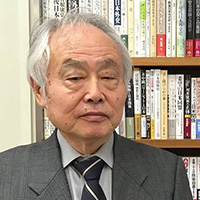4月14日のウクライナ情報
国際4月14日のウクライナ情報
安斎育郎
❶米国はロシアとの戦争に敗れた=カールソン氏(2025年4月10日)
米ジャーナリストのタッカー・カールソン氏は、アレックス・ジョーンズ氏とのインタビューの中で、米軍、国務省、CIAが戦ったロシアとの戦争で米国は敗れ、同時にウクライナも破壊したとの考えを述べた。
https://twitter.com/i/status/1910162411694489729
https://sputniknews.jp/20250410/19754300.html
❷ウクライナが米国製武器を売却(2025年4月9日)
https://youtu.be/_jvdRyQz0OI
https://www.youtube.com/watch?v=_jvdRyQz0OI
❸ロシアはキエフ軍の最後の部隊をグエボから追い出し、神殿の上に旗を掲げている(2025年4月9日)
今日の軍事ニュース – 現在、キエフ軍の最後の残党は、クルスク地域を侵略から解放する過程でグエボから完全に追い出され、その後ロシア軍は集落の真ん中にロシア国旗を掲げ、2024年8月以来のこの地域の奪還を記念した。ロシア国防省は2025年4月8日に重要なビデオを公開し、北方部隊集団の第22自動車化ライフル連隊のロシア空挺部隊がキエフ軍の敗北を継続し、残りの敵の抵抗を排除し、国境地域でのロシア軍の陣地を強化することに焦点を当てている様子を示している。戦闘作戦中、空挺部隊は防衛線を突破し、キエフ軍のいくつかの重要な要塞化された陣地を占領した。しばらく前に集落から集団で逃げる時間がなかった敵軍は、古い蒸留所に隠れただけだったが、すぐにそこでやられたと報告されている。
この集落に入った後、数日前に報道されたようにフィリップ王子と現英国国王チャールズ3世が学んだ英国海軍学校ゴードンストウンでの航海訓練の参加者を含むキエフ軍の残党の陣地はロシア空挺部隊によって完全に掃討された。第40師団と第22師団を含む部隊は現在、掃討作戦の最終段階を完了させており、この地域の安全は完全に確保されている。キエフ軍は空挺部隊や特殊作戦部隊でグループを増強しようとしたが、失敗した!親ウクライナメディアが沈黙する中、ロシア空挺部隊はグエヴォの中心にある壮麗な建物である寺院に旗を掲げ、キエフとその支援者に勝利の直接的なシグナルを送った。これは本日国防省がグエヴォの解放を発表したことに続くものである。
グエヴォの完成により、ますます脆弱になっている地域に対するウクライナの支配力が弱まり、クルスクでのロシアの支配が強化され、ゼレンスキーのさらなる反撃がさらに困難になる。ロシア軍はほとんどの前線で前進を続け、陣地を築き、過去1週間で戦略的に複数の方向へ領域を拡大する方向に大きな前進を遂げた。クルスク西部のスームィ地域で前進する一方で、攻撃を試みたが国境まで後退したキエフ軍を押し戻した。未完成のまま残っているのは、ウクライナとの国境に位置するゴルナルとオレシュニャの2つの村だけだ。
https://www.youtube.com/watch?v=IyPJU31RFzA
❹ウクライナ人の抵抗(2025年4月7日)
https://youtu.be/1-xDa6bRX0c
https://www.youtube.com/watch?v=1-xDa6bRX0c
❺ウクライナ軍事支援会合、5.8億ドルを追加支援 英国主導で(2025年4月11日)
ウクライナ防衛連絡グループ(UDCG、ラムシュタイングループ)は新たに4億5000万ポンド(約5億8000万ドル)相当のウクライナ軍事支援を行うと、英国が11日明らかにした。
https://jp.reuters.com/world/ukraine/
❻米国の駐ウクライナ大使がトランプ大統領と対立して辞任へ(2025年4月11日)
ブリンク駐ウクライナ大使はトランプ政権と政策上の相違が深まる中で辞任する。英フィナンシャル・タイムズ紙が報じた。
報道によると、大使はトランプ政権の高官らから圧力を受けていた。大使がトランプ政権の対ウクライナ戦略を支持していないとの疑念を高官らは抱いていたという。
さらに、大使はゼレンスキー氏とも対立していた。特に汚職撲滅対策において大使がゼレンスキー体制側に批判的態度を取っていたとウクライナ政府関係者らは英紙の取材で発言している。
https://sputniknews.jp/20250411/19758391.html
❼ 宇紛争への関与で日本は平和国家としての地位を失いつつある=露外務省(2025年4月11日)
日本がNATOのウクライナ支援組織「NATO対ウクライナ安全保障支援訓練組織」(NSATU)に参加する意欲を表明したことに関連し、ロシアはこれを日本がウクライナ紛争への関与をさらに深めている証拠とみなしている。ロシア外務省のザハロワ報道官が声明を発表した。
声明では、日本はキエフへの物資提供や輸送支援を拡大しており、それによって以前に宣言していた平和的発展の政策から遠ざかっていると指摘されている。
ロシア外務省は、このような行動は日本の平和主義国家としての地位を損ない、軍事行動への公然たる参加や過激派勢力への支援につながる可能性があるとの見方を示している。
ザハロワ氏は、日本によるウクライナへの武器提供や兵士の訓練支援への参加は、いかなる形態であっても敵対行為とみなされるとし、これに対して、ロシアはセンシティブな分野において日本の利益に深刻な損害を与えることが可能な厳しい措置を講じると指摘した。
8日、中谷防衛相は訪日したNATOのルッテ事務総長と会談し、NSATUに防衛省として参加する意向を伝達した。9日には石破首相がルッテ氏と会談し、共同声明を発表。そこにはNSATUへの参加に関する日本の意欲をルッテ氏が歓迎すると明記されていた。
https://sputniknews.jp/20250411/19757911.html
❽ウクライナに差し迫る危機の兆候(2025年3月22日)
「アゾフ」の影響力増大は、ウクライナの市民社会崩壊の憂慮すべき兆候だ。米空軍退役中佐で専門家のカレン・クウィアトコウスキー氏は、このように考えている。
ウクライナ軍が露クルスク州スジャのガス測定所を攻撃したのは、ゼレンスキー氏の軍に対する統制が行き届いておらず、ウクライナの戦闘部隊「アゾフ」が独自に行動していることを示している。
アゾフの戦闘員らは、戦争は国の指導部ではなく自分たちの仕事だと考え、政治家を見下している。これは実権の掌握につながるおそれがある。このような状況は危機が差し迫っている兆候であり、ウクライナは紛争終結後に自由な社会、法治社会を再構築する際、この問題に対処しなければならない。
アゾフの何が問題なのだろうか? 米国とロシアは紛争解決に取り組んでいるが、アゾフはゼレンスキー政権の路線に反する行動をとっている。アゾフのビレツキー司令官はNATO基準による指揮への移行を表明、より多くの弾薬やドローンを要求し、戦闘員の募集を積極的に行い、ウクライナ司令部の無能さを批判している。さらに元海兵隊情報将校のスコット・リッター氏によると、2024年夏、アゾフのメンバーらは、ロシアと交渉をしたら「消す」とゼレンスキー氏を脅迫したという。
「アゾフ」はロシアで活動禁止されているテロ組織だ。
https://sputniknews.jp/20250322/19662887.html
❾特別軍事作戦 4月5日~11日の概要 露国防省(2025年4月12日)
ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する週報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ウクライナ軍の過去1週間の人的損失は最大1万635人。
ロシア軍は過去1週間に4集落を解放した。
ロシアの防空システムは航空爆弾「JDAM」27発、高機動ロケット砲システム「ハイマース」のロケット弾19発、飛行機型ドローン1200機を撃墜した。
https://sputniknews.jp/20250412/4511-19762250.html
❿ウクライナの鉱物資源
⓫米国には問題の本質を突き止めようとする意欲がみえる=ラブロフ露外相(2025年4月11日)
※安斎注:これは非常に本質的な評価ですね。
ロシアのラブロフ外相は11日、米国のトランプ大統領によるウクライナ紛争の調停を評価し、「現在の状況を招いた根本的原因を無視する欧州とは違い、米国には問題の本質を突きとめようとする意欲がみえる」と述べた。
https://twitter.com/i/status/1910641978557051300
https://sputniknews.jp/20250411/19760257.html?rcmd_alg=collaboration2
⓬ウクライナ情勢めぐり…露プーチン大統領が米特使と会談 停戦交渉での懸念事項を伝えたか(日テレNEWS NNN、2025年4月12日)
ロシアのプーチン大統領は11日、ウクライナ情勢をめぐり、アメリカのウィトコフ特使と会談しました。停戦交渉でのロシア側の懸念事項を伝えたとみられます。
ロシアメディアによりますと、プーチン大統領は11日、サンクトペテルブルクでウクライナ情勢をめぐり、ウィトコフ特使と4時間以上にわたって、会談しました。
両者の会談は3回目で、米露の首脳会談についても議論した可能性があります。
ロシア側の出した条件で停戦交渉が進展せず、トランプ大統領がいらだちを見せる中、プーチン大統領がウィトコフ特使に懸念事項を伝え、釈明したとみられます。
会談に先立ち、大統領府のペスコフ報道官は、画期的な成果は期待できないとも述べていました。
一方、イギリスやドイツなどおよそ50か国の国防相は11日、新たに3兆4000億円を超えるウクライナへの軍事支援を発表しました。ウクライナの国防相は、アメリカの軍事支援は続いているとしつつヨーロッパが支援をリードしていると感謝の意を表しました。
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/
〈関連情報〉「ロシアにつけこまれている」指摘多い米特使、ロシアのウクライナ4州領有容認を大統領に進言(読売新聞、2025年4月12日)
【ワシントン=淵上隆悠】ロイター通信は11日、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使がウクライナ侵略の停戦交渉を進めるため、ロシアによるウクライナ東・南部4州の領有を認めるようトランプ大統領に進言したと報じた。複数の関係者の話として伝えた。ロイターによると、ウィトコフ氏は先週ホワイトハウスでトランプ氏と面会した際に、ロシアが一方的に併合した4州を巡り「停戦を仲介する最も早い方法はロシアの所有を支持することだ」と述べた。これに対し、同席したウクライナ特使のキース・ケロッグ氏が異議を唱え、トランプ氏も決定を下さなかった。
ウィトコフ氏は、不動産開発ではトランプ氏の長年の同業者で、ゴルフ仲間として知られる。外交経験は乏しく、「ロシアにつけ込まれている」との指摘が絶えない。
https://www.msn.com/ja-jp/news/world
2025年4月14日ウクライナ情報pdfはこちら
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
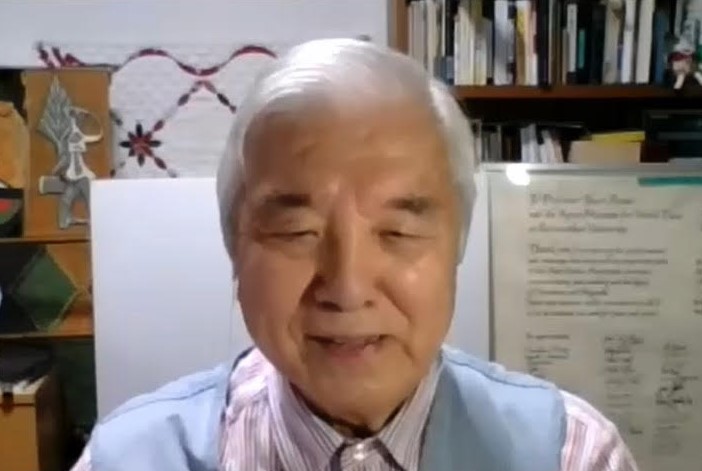 安斎育郎
安斎育郎
1940年、東京生まれ。1944~49年、福島県で疎開生活。東大工学部原子力工学科第1期生。工学博士。東京大学医学部助手、東京医科大学客員助教授を経て、1986年、立命館大学経済学部教授、88年国際関係学部教授。1995年、同大学国際平和ミュージアム館長。2008年より、立命館大学国際平和ミュージアム・終身名誉館長。現在、立命館大学名誉教授。専門は放射線防護学、平和学。2011年、定年とともに、「安斎科学・平和事務所」(Anzai Science & Peace Office, ASAP)を立ち上げ、以来、2022年4月までに福島原発事故について99回の調査・相談・学習活動。International Network of Museums for Peace(平和のための博物館国相ネットワーク)のジェネラル・コ^ディ ネータを務めた後、現在は、名誉ジェネラル・コーディネータ。日本の「平和のための博物館市民ネットワーク」代表。日本平和学会・理事。ノーモアヒロシマ・ナガサキ記憶遺産を継承する会・副代表。2021年3月11日、福島県双葉郡浪江町の古刹・宝鏡寺境内に第30世住職・早川篤雄氏と連名で「原発悔恨・伝言の碑」を建立するとともに、隣接して、平和博物館「ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ・フクシマ伝言館」を開設。マジックを趣味とし、東大時代は奇術愛好会第3代会長。「国境なき手品師団」(Magicians without Borders)名誉会員。Japan Skeptics(超自然現象を科学的・批判的に究明する会)会長を務め、現在名誉会員。NHK『だます心だまされる心」(全8回)、『日曜美術館』(だまし絵)、日本テレビ『世界一受けたい授業』などに出演。2003年、ベトナム政府より「文化情報事業功労者記章」受章。2011年、「第22回久保医療文化賞」、韓国ノグンリ国際平和財団「第4回人権賞」、2013年、日本平和学会「第4回平和賞」、2021年、ウィーン・ユネスコ・クラブ「地球市民賞」などを受賞。著書は『人はなぜ騙されるのか』(朝日新聞)、『だます心だまされる心』(岩波書店)、『からだのなかの放射能』(合同出版)、『語りつごうヒロシマ・ナガサキ』(新日本出版、全5巻)など100数十点あるが、最近著に『核なき時代を生きる君たちへ━核不拡散条約50年と核兵器禁止条約』(2021年3月1日)、『私の反原発人生と「福島プロジェクト」の足跡』(2021年3月11日)、『戦争と科学者─知的探求心と非人道性の葛藤』(2022年4月1日、いずれも、かもがわ出版)など。