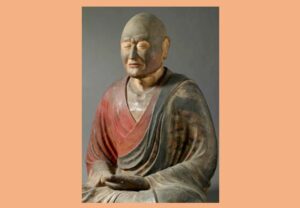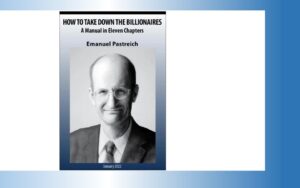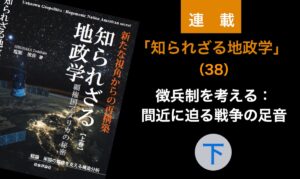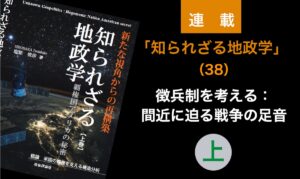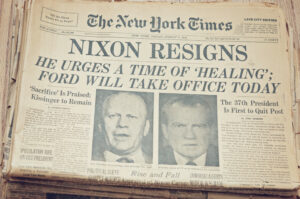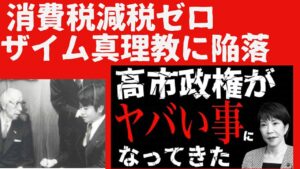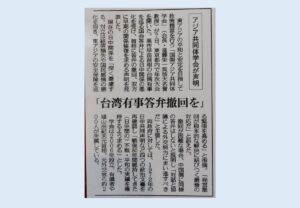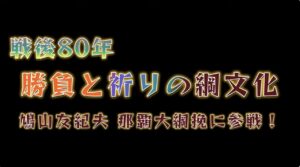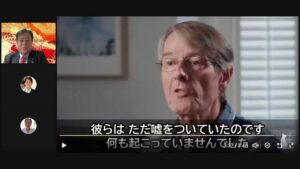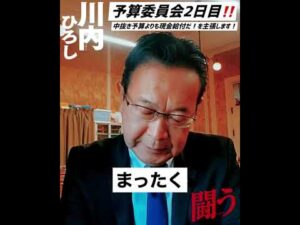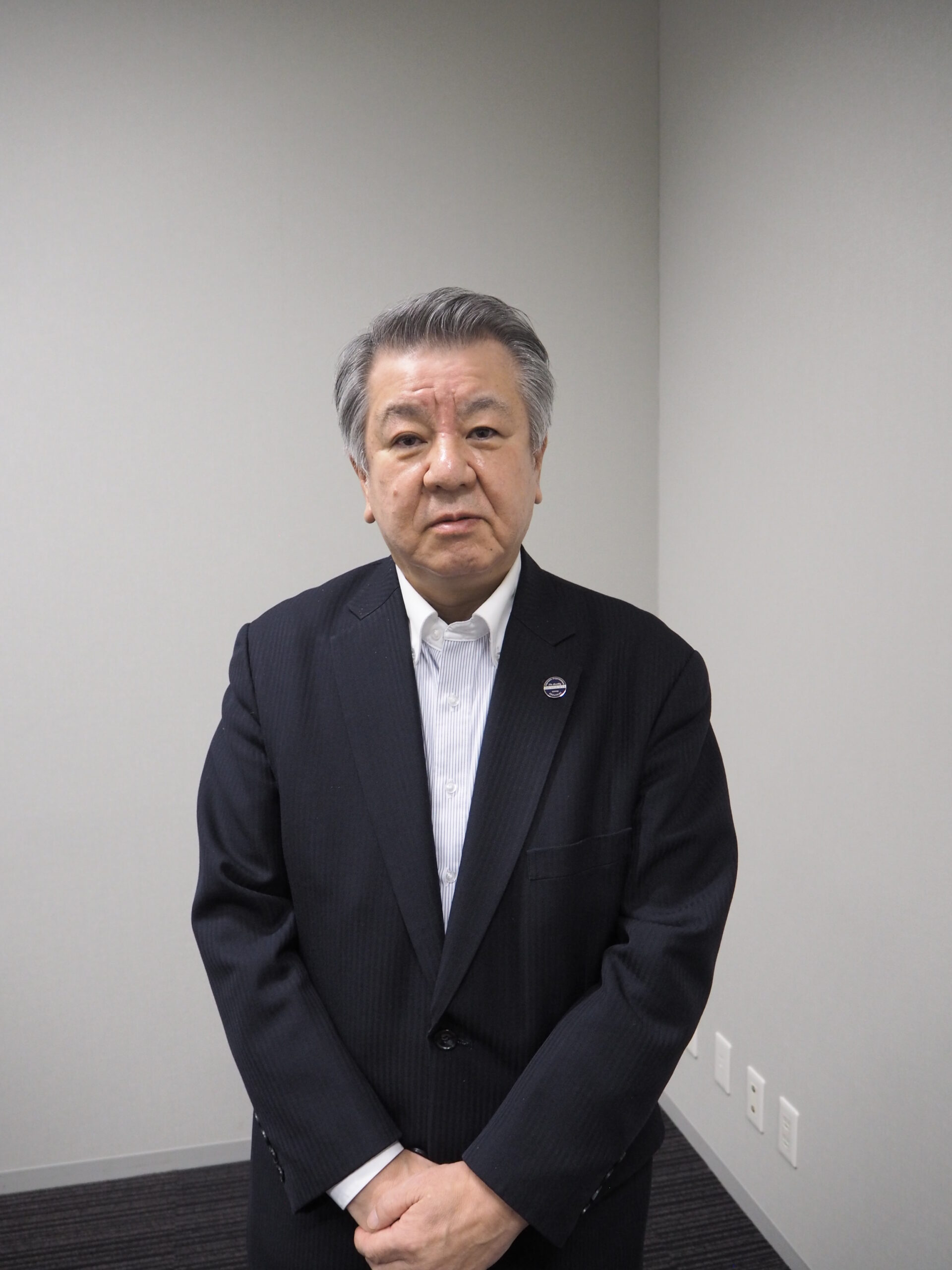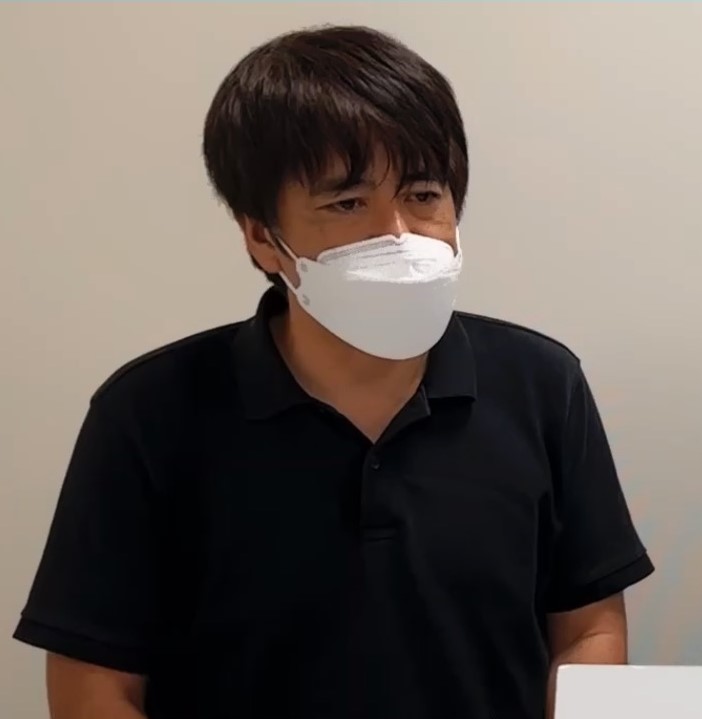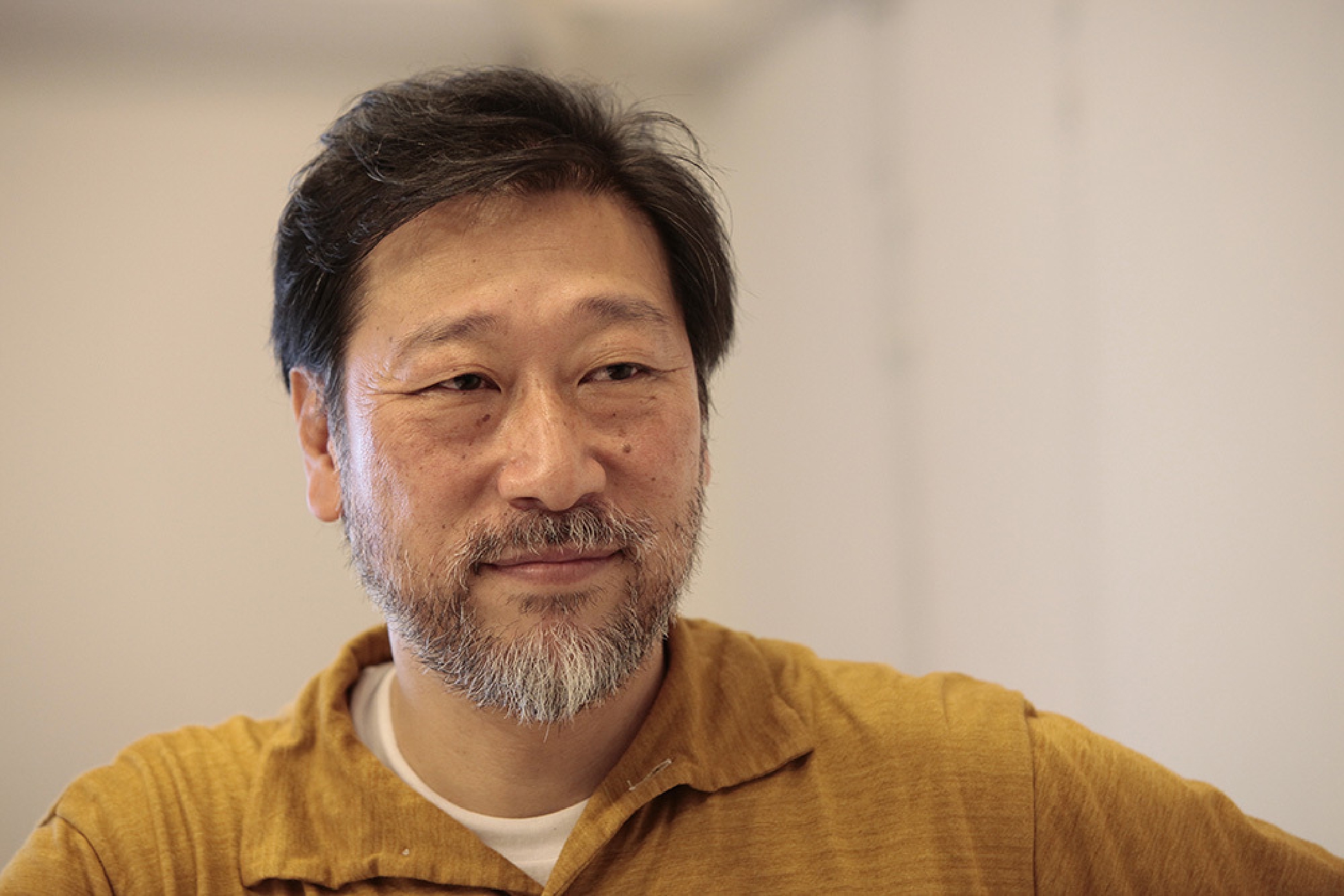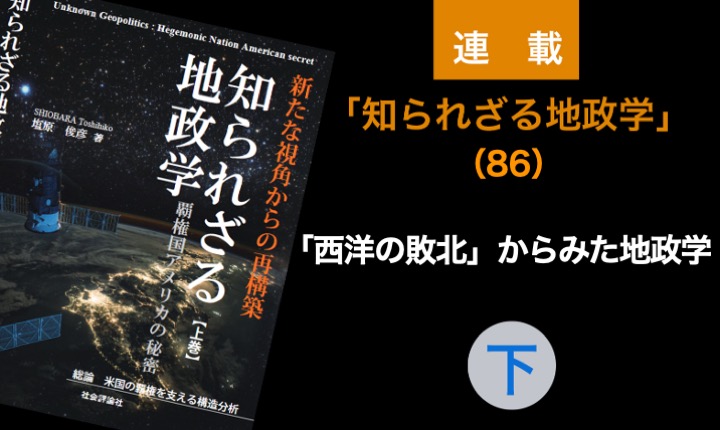
「知られざる地政学」連載(86):「西洋の敗北」からみた地政学(下)
国際
「知られざる地政学」連載(86):「西洋の敗北」からみた地政学(上)はこちら
ウクライナ戦争への対応
この「生産機械」と化したドイツは欧州における覇権勢力として復活を遂げた。それは、ユーゴスラビアとチェコスロバキアの解体へのドイツの介入や2014年のウクライナ危機につながるドイツ主導によるウクライナのEU加盟への動きなどにつながっている。しかし、ウクライナ戦争の勃発に際しては、ドイツは「責任放棄」に傾いた。このあたりの事情について、トッドはつぎのように記述している(194~195頁)。
「「不安」を抱いた直系システムの指導者は、受け身になる。イギリスとアメリカの社会、個人主義的で、しかも歴史的に支配者側だった社会でも、ドイツと並行する形で、「国家プロジェクトの不在」を確認できる。いずれも同じ「空虚」と「集団としての結束力の解体」に由来するが、ただし、そこから生じているのは、ドイツのような「消極主義」ではなく、「熱に浮かされたような行動主義」だ。しかも、この積極的行動主義は、教義によって制御された政党のリーダーではなく、[ワシントンにいる]ギャングのような集団の指揮下にある。あらゆることで生じている社会のアトム化が、被支配側では消極主義を、支配側では積極的行動主義を際立たせている。同じ一つの「慣性(惰性)の法則」が西洋諸国全体に広がり、すべてが「惰性」と化し、「魂」を失った状態になっている。」
欧州の消極主義は、「金融グローバル化の地下工作のメカニズムに捕捉され、侵略されてしまった」結果であると、トッドは考えている(197頁)。それを決定づけたのは、①ドルが「避難通貨」として広がったこと、②米国が牛耳るタックスヘイブン(租税回避地)が「ヨーロッパの財産の避難先」として広がったこと――であると、トッドは主張する。どこまで本気なのかはよくわからないが、つぎのような気になる記述がある(201頁)。なお、私個人は、タックスヘイブン問題はきわめて重要であると考えている。だからこそ、拙著『ウクライナ2.0』において、「付論 タックスヘイブンをめぐる嘘」(235~257頁)として、詳細に論じている。
「ヨーロッパの富裕層の資産の60%(ズックマンが示した割合)が、アメリカの上位機関の慈悲深い監視の下で増えているとすれば、ヨーロッパの上流階級は、精神的、戦略的な自立性をすでに失っていると言える。しかし、より危険なものは他にある。アメリカ国家安全保障局(NSA)による監視である。」
米国政府による監視が厳しいことについては、拙著『帝国主義アメリカの野望』でも紹介した。1977 年に制定された海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)を1998年に改正し、外国の企業や個人が米国にいる間に不正支払いを行う場合も、同法が適用されることになった。これは、外国企業がドル建てで契約を結んだり、E メールがアメリカに関連づけられたりしているだけでもFCPA の対象となることを意味している。「とくに、2018 年3 月に制定されたCLOUD[Clarifying Lawful Overseas Use of Data]法によって、アメリカは同盟国と2 国間協定を締結し、深刻な犯罪やテロと闘うことを名目にして、電子証拠がどこにあろうと、その電子証拠に直接アクセスできるようになった」とも書いておいた。
米国の本質――寡頭制とニヒリズム
欧州の弱体化、消極主義に対して、米国はどうなったのか。トッドは、「第8章 米国の本質――寡頭制とニヒリズム」において、「今日のアメリカに私が見るのは、思想面における危険な「空虚さ」と強迫観念として残存している「金」と権力」である」と書いている(266頁)。金と権力は、それ自体が目的や価値観にはなり得ないとして、先に挙げた「空虚が、自己破壊、軍国主義、慢性的な否定的姿勢、要するにニヒリズムへの傾向をもたらす」という。
その証拠として、トッドは「オピオイド・スキャンダル」を挙げている(同スキャンダルについては拙著『帝国主義アメリカの野望』[282~290頁]を参照)。「製薬業界が市民を殺し続けることを認める法律を市民の「代表」が可決した」事実から、トッドは「道徳ゼロ状態」を嘆き、そこにニヒリズムをみている。
ADHDをめぐる「クスリ漬け」
ここで紹介しておきたいのは、注意欠陥多動性障害(ADHD)をめぐる「クスリ漬け」という問題だ。2025年4月13日付のNYTの長文記事「私たちはADHD.について間違って考えていないか?」は、いまの米国が大人から子どもまでクスリ漬け状態にあることを教えてくれている。記事は、1990年に100万人未満だったADHDと診断された米国の子どもの数は、1990年代初頭には2倍以上に増え、1993年には200万人を超えた。そのうちのほぼ3分の2に症状改善が顕著とされた「リタリン」が処方されており、同様の興奮薬である「アデロール」も使われたと紹介している。
そのうえで、同記事は、「昨年、疾病対策センターは、11.4%の米国の子供たちがADHDと診断されたと報告した。これは過去最高である。この数字には、米国の青少年の15.5%、14歳の男児の21%、17歳の男児の23%が含まれている。米国では700万人の子供たちがADHDと診断されており、2016年の600万人、1990年代半ばの200万人から増加している」と伝えている。
さらに、「ADHDの治療としてもっとも好まれているのは、リタリンやアデロールなどの興奮薬であり、診断数の増加に伴い、近年、これらの興奮薬の市場は急速に拡大している」という。2012年から2022年の間に、ADHDの治療に興奮薬が処方された総数は、米国で58%増加した。処方率は10歳から14歳の男児がもっとも高いが、現在、興奮薬の薬物療法の成長市場は成人である。2012年には、30代の米国人に対してADHD治療用の興奮薬が500万回処方されていたが、10年後にはその数は3倍以上となり、1800万回に増加した。
驚くのは、子どもがほとんど勉強のためにクスリ漬けになっている現実である。記事は、高校2年生の夏からリタリンを服用し始めた学生を紹介しており、リタリンを使用することは、「彼が育った裕福な住宅街では、大学進学適性試験(SAT)の準備という、重要な通過儀礼」となっていると書いている。
記事には、こうした興奮薬の摂取がアンフェタミンの摂取に類似しているのではないかという指摘がある。歴史的にみると、第二次世界大戦中、米軍は数千万錠のアンフェタミン錠剤を、戦争中の退屈な期間に使うために下士官兵に配布したという。この錠剤は、長距離飛行任務に就く空軍パイロットや、徹夜で当直を務める海軍水兵にも支給された。1950年代には、郊外に住む主婦たちが家事や育児の退屈な毎日を乗り切るためにアンフェタミンを摂取していたことも紹介されている。長距離トラックの運転手たちは、何十年にもわたって、道路の退屈さに耐えるためにアンフェタミンを使用してきたという。ADHDの治療薬として、洗濯や長距離トラックの運転と同じくらい退屈な学業などに「打ち勝つ」ために興奮薬の助けを借りることで、それらに耐えられるようにしている、という疑念が明かされている。
こうした摩訶不思議な「伝統」が、有効性について多くの疑問が提起されているADHD治療薬の膨張を支えているのかもしれない。しかし、それは製薬業界や医療業界を儲けさせる手段にすぎず、道徳性など微塵もないという疑惑が濃厚だ。
プロテスタンティズム・ゼロ状態へ向かうアメリカ
宗教でも、ニヒリズムが広がっている。トッドは、「脱キリスト教の完遂を示すもう一つの指標は、ホモセクシャルに対する態度である」と書いている。すでに書いたように、同性婚は、フランスでは2013年、イギリスでは2014年に合法化され、米国では2015年に連邦レベルで合法化された。
興味深いのは、トッドが「トランスジェンダー」に明確な異議を唱えていることだ。彼は、「単に自分の好みしたがって身分証に登録するだけで「ジェンダー」を変えられるという主張、特別な衣服を着用したり、ホルモン剤を摂取したり、手術を受けたりすることで「性別」を変えられるという主張は、「性の平等」や「同性愛者の解放」とは、まったく別問題なのだ」とのべている(276~277頁)。したがって、トッドの結論はつぎのようなものになる(277頁)。
「遺伝学によれば、男(XY染色体)を女(XX染色体)に変えることはできないし、その逆もまた不可能である。にもかかわらず、それができると主張することは、虚偽を肯定することで、典型的なニヒリズムの知的行為である。虚偽を肯定し、虚偽を崇拝し、虚偽を社会の真理として押し付けたいという欲求が、ある社会カテゴリー(中流階級のどちらかといえば上層部)とそのメディア(『ニューヨーク・タイムズ』紙、『ワシントン・ポスト』紙)を支配しているのだとしたら、私たちはニヒリスト宗教を目の前にしていることになる。」
トッドの見方は斬新である。彼は、「プロテスタンティズムに由来する形而上学的な不平等主義、絶対核家族に由来する平等への無関心にもかかわらず、アメリカが偉大な民主主義国家となれたのはなぜか」と問う。その答えは、「まずはインディアン、次に黒人を「劣等人種」とし、彼らの不平等を「固定化」できたからである」というのだ。ところが、バラク・オバマ大統領の登場で、「黒人の封じ込め」は失敗した。米国に残ったのは、絶対核家族に由来する価値観――子ども同士、そして人間同士の平等に関する無関心――だけであったという。
さらに、冷戦期に対ソ連への対抗から強く求められるようになったメリトクラシー(能力主義)もソ連崩壊によって地に堕ちた。社会ピラミッドの頂点は階層化され、不平等が広がる一方となっている。つまり、「少数の最富裕層が寡頭的社会の頂点を形成し、そこでは、真の意味での少数富裕権力者(オリガルヒ)が、彼らに依存する下位の特権階級に囲まれて暮らしている」という状況になっている。ゆえに、トッドは、「ロシアの権威主義的民主主義に対する西洋の戦いを主導しているのは、「自由民主主義」ではなく、ニヒリズムによって磨き上げられた「リベラル寡頭制」なのである」としている。
「ブロブ」(Blob)
さらに、トッドは「ブロブ」(Blob)について書いている。ブロブとは、オバマ政権下で大統領副補佐官を務めたベン・ローズによって発明され、外交政策を担う「ミクロ社会」を意味していた。ブロブとは、本来、森のなかにあるネバネバとした単細胞組織を意味し、周囲にあるバクテリアやキノコを摂取しながら繁殖するが、脳はない。このイメージはとても大切だ。要するに、仲間内で暮らすが、外部に出ないから、バカでマヌケなのだ。
ハーバード大学ケネディ公共政策大学院教授で、「オフショア・バランシング論」(前方展開軍を引き揚げ、地域諸国間の勢力均衡を促進し、米国にとって決定的に不利な地域情勢が出現するまでは軍事介入を控える戦略をとるべきであったとする理論[森聡著「アメリカのリトレンチメント論争」を参照]を参照)の提唱者として知られるスティーヴン・ウォルトは、その著作The Hell of Good Intentions: America’s Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy, 2018において、「ブロブ」(Blob)を、外部との知的あるいはイデオロギー的つながりを欠いた指導者集団とみなし、軽蔑している。その典型として、ウォルトは、民主党支持者で、世渡り上手なだけのサマンサ・パワーを挙げている。バイデンは彼女を米国際開発庁(USAID)長官に抜擢し、USAIDをきわめて党派性の強い組織にしてしまったのである。
ほかにも、ブロブには、ケーガン一族がいる。ロバート・ケーガンはネオコンのイデオローグであり、その妻ヴィクトリア・ヌーランドは2014年のウクライナ危機、2022年からつづくウクライナ戦争の「黒幕」である。ロバート・ケーガンの義理の姉、フレデリックの妻キンバリー・ケーガンは戦争研究所の創設者であり、所長だ。
トッドは、こんな連中が米国の好戦的な外交を導いてきたことを厳しく批判している。
「ゼロ状態」の米国
トッドは、「英米圏が「無気力国家」の段階を超えたのは、2020年頃だと思われる」と書いている(362頁)。ロシア、ドイツ、フランスの指導者層がいまだに民族的・国民的気質を保持しているのに対し、アメリカ圏の指導者層は、本来の文化的基盤を失っているとも指摘する。アメリカについては、1990年頃までは、帝国的ではあっても国民国家として存在し、生き生きとした文化的中心を維持していたが、「今日のアメリカはもはや国民国家ではない」と断じている。真の意味での指導者層を失い、国として方向を定める能力を失っているというのだ。
さらに、2015年頃には、米国も「ゼロ状態」に至ったという。この「ゼロ状態」とは、「国民国家として存在していない状態」という意味ではなく、「その国の本来の価値観によって統御されていない状態」を意味している。すなわち、プロテスタンティズムに由来する道徳性、労働倫理、国民を駆り立てる責任感などが消滅したことを意味する。ゆえに、「ワシントンの決定は、もはや道徳的でも合理的でもない」のだ。
トランプ政権
いまのトランプ政権をみていると、このトッドの指摘は正鵠を射ているという印象をもつ。それにしても、方向性を失い、道徳性すら感じられないトランプ政権のいまの状況は、今後の世界全体の秩序の維持を難しいものにさせている。
ただ、いい面もある。それは、ヘゲモニー国家アメリカの混迷によって、アメリカ主導で築かれてきたこれまでの世界が「インチキ」に満ちた虚構にすぎなかったことに気づくチャンスを与えてくれているからだ。
その意味で、ニヒリズムに傾くにはまだ早い。インチキを糺すことで、まだ活路が見出せるかもしれないからだ。
私は最近、2024年に亡くなった松岡正剛著『日本文化の核心:「ジャパン・スタイル」を読み解く』を読んでいる。連載(82)「アジアの文化的隆盛に思う」(上、下)に書いたように、日本文化のもつ底力に励ませられるのだ。
大切なのは、「西洋の敗北」に気づくことにあると思う。そのうえで、アジアに別の何かを見出せるのではないかとつくづく感じている。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)