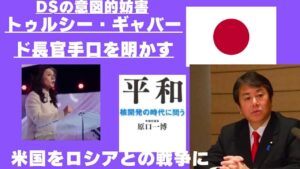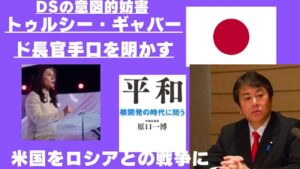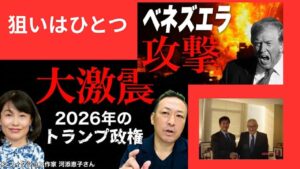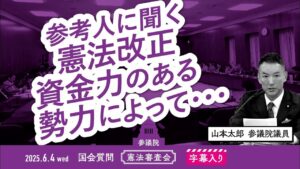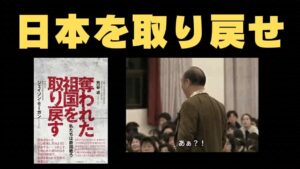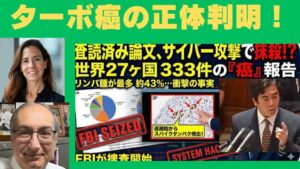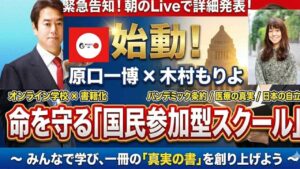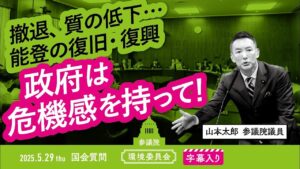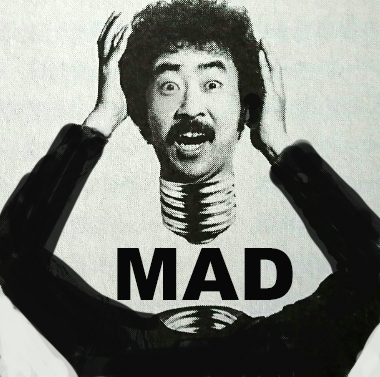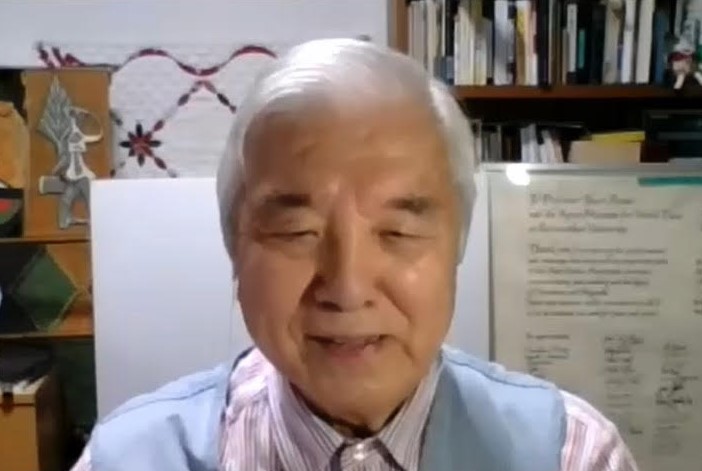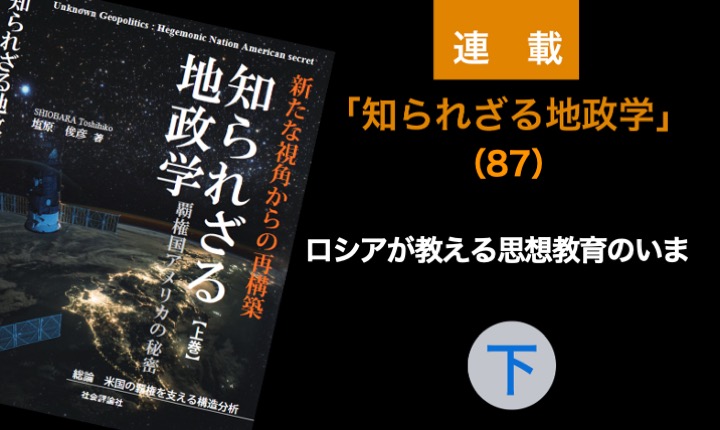
「知られざる地政学」連載(87):ロシアが教える思想教育のいま(下)
国際
「知られざる地政学」連載(87):ロシアが教える思想教育のいま(上)はこちら
新しい思想への評論
ハリチェフやポロシンらの新しい思想を評論してみよう。第一に、彼らがポリティカル・エンジニアリングを基礎としている結果、その思想は図式的で簡便性を特徴としている。わかりやすさは人々への伝播を容易にする。第二に、「ペンタ」の5項目が水平的でありながら、「国家」(公的機関への信頼)や「国」(愛国心)への帰属を重視しているようにみえる。その意味で、プーチンの意向に沿った価値観の序列づけが意図的になされているように感じられる。
ここで、宮本武蔵が書いたとされる『五輪書』を思い浮かべてほしい(注2)。全体は「地・水・火・風・空」の五つの章で構成されている。兵法書だが、この大元には、仏教で「五大」と呼ばれる概念がある。「ブリタニカ国際大百科事典」によれば、もともとは、インドにおいて物質を構成する主要な要素と考えられた5元素をいう。すなわち、地大、水大、火大、風大、空大の五つを指す。仏教においては,これらの5元素は究極的には否定されるが、諸要素の実在を認める学派によって肯定されているという。密教ではこれらの5元素を哲学的形而上学的にとらえ、識と合せて、この六つが宇宙を構成する要素であるとする。
わかりやすいのは、五輪の塔がこの思想に基づいて建てられていることを思い出すことだろう。松岡正剛著『日本文化の核心』(146頁)には、この「五大」を下から上へ積み上げていくと(地面から空に向かわせると)、「地輪・水輪・火輪・風輪・空輪」という五輪になり、これを建築物にすると、五重塔や五輪塔になると書かれている。「下から四角・丸(球体)・三角・半丸(半球)、宝珠形の形になっている」という。この形の石を積み上げると、石灯籠(五輪塔)になり、お墓によくある卒塔婆も、上部がこの形に彫られている。
何が言いたいかというと、垂直的に「ペンタ」を並べてみると、 ハリチェフやポロシンらの水平的な「ペンタ」とだいぶ様相が違ってみえてくるということだ。
『大学』の教え
ここで、二宮金次郎が薪を背負って歩きながら読んでいる本、『大学』を思い出してほしい。そこには、「修身・斉家・治国・平天下」という言葉が書かれている(注3)。これは、「まず自分の身を正しくし、つぎに家をととのえ、そのうえで国家を治めて天下を平安にすることができる」といった意味をもつ。儒教・儒学の道徳教育の基本であり、戦前の日本社会のスローガンとして利用された。ここでは、「テトラ」しか項目(要素)がないが、垂直的に要素を並べてみると、本当は「ペンタ」を構成する要素間の関係がより明確になる。その意味で、五つの項目を水平的に並べたハリチェフやポロシンらの新しい思想は、あえて序列を曖昧にすることで、「国」や「国家」の優位性を隠そうとしているのではないかと思えてくる。
「国家」をどうみるか
ここで、「国家」という言葉について考えてほしい。「国の家」と書かれているが、松岡正剛は『日本文化の核心』のなかで、「この国家とは「国という家」のことなのか、それとも「家が集まると国になる」ということなのか、そこが微妙なのです」と指摘している(206頁)。英語では、ステート(state)、ネーション(nation)、カントリー(country)などと表現されるが、まったく家とは関係ないようにみえる(注4)。ドイツ語のLandも、スペイン語のPaisも家ではない。中国語では、国家(guó jiā)は、しばしば中国民族を強調するときに使われるという。
松岡によれば、日本で「国家」という文字を最初にのこしたのは、聖徳太子が制定したといわゆる十七条憲法のその四の「百姓有礼、国家自治」である。「百姓(おおみたから)に礼(いやび)有るときは、国家(あめのした)自ずからに治まる」と読むらしい。「群臣たちに礼が保たれていれば社会の秩序は乱れないし、百姓(ひゃくせい、戸籍に「良」と示された有姓階層の全体)に礼があれば、おのずと治まってくるという意味になる。したがって、「おそらくもともとの「国の家」とは、家が集まって国になっているということでしょう」、と松岡は書いている(208頁)。そのとき、「家」とは家屋や住宅のことではなく、人々がそこで「時をおくる家」のことであるとする。ただし、それは「家名をもった家」だった。それは、公家であったり、武家であったりしたことになる。
これに対して、「国という家」というイメージは、上意下達の「上」に位置する垂直的なものにつながっている。とくに、西洋において、王権神授説に基づいて統治していた絶対君主が倒された誕生した近代国家は神に代わる上意下達の統治を前提にしているように思われる。だからこそ、21世紀のロシアの新しい思想もこの影響から逃れられないでいるように映る。
「国体」をめぐって
先に紹介した教科書のタイトル「ロシアの国家性の基礎」(Основы российской государственности)のうち、ロシア語のгосударственность(その生格がгосударственности)をどう訳すかは悩ましい問題となっている。国家であれば、государствоと書けばすむ。Государственностьは、国家制度、国家機構などを意味しているようだから、「ロシアの国家制度の基礎」といった翻訳も可能だ。
あるいは、思い切って「ロシア国体の基礎」と意訳してもかまわないかもしれない。ただし、その場合、今度は「国体」という日本語が問題になる。簡単に言えば、「国体とは、「日本という国の体制」をあらわしているキーワード」であると、松岡正剛はのべている。「幕末に水戸藩の会沢正志斎が『新論』などで最初に言い出した用語」であるという。その後は尊王攘夷の前提にされていったイデオロギーとなり、「尊王」のイデオロギーを近代向けに言い換えたものが「国体」として流布したと考えればいいと、松岡は『日本文化の核心』のなかで指摘している(194頁)。
こう考えると、プーチンが「プーチン独裁」に向けた足場固めのためのイデオロギーの基礎をつくろうとしているとみなせば、あえて「ロシア国体の基礎」と意訳することもできるだろう。
ただし、「国体」というと、日本の過去の歴史を引きずることになるので、ここでは、あえて「国家性」という、より中立的な、あるいは、曖昧な訳にしたわけである。
J・D・ヴァンスとカトリック教会の対立
ここで、いま話題となっている、米国のJ・D・ヴァンス副大統領とカトリック教会との対立について紹介しておきたい。ヴァンスがカトリック教徒となったことは、この連載(48)「地政学のための思想分析:J・D・ヴァンスを理解するためのルネ・ジラール、カール・シュミット考」(上、下)に書いたことがある。
ヴァンスとカトリック教会の対立は、後述する「愛の秩序」(ordo amoris)にかかわっている。愛を水平的にみるのではなく、垂直的に順序づけるとき、問題が生じるのだ。
そもそものきっかけは、米国カトリック司教団が2025年4月7日、政府の資金削減を理由に、戦争や迫害から逃れてきた難民を再定住させるという100年以上にわたるプログラムを終了すると発表したことだった(WPを参照)。移民や難民に厳しい政策をとるトランプ政権に対して、カトリック教会から反発が出ている。これに対して、カトリック教徒であるJ・D・ヴァンス副大統領は、左派が米国市民よりも不法移民を優先しているのは「狂気じみている」とのべ、移民への思いやりを説くカトリック教会と対立するようになっている。ヴァンスは、「昔からある考え方、そしてそれは非常にキリスト教的な考え方だと思うが、自分の家族を愛し、次に隣人を愛し、そして地域社会を愛し、自国の同胞を愛し、その後で世界の残りの国々を重視し、優先する」というのが彼の考える「愛の秩序」(オルド・アモリス、ordo amoris)だという。しかし、それは、カトリック教会の見方と異なっている。
2025年2月、入院する数日前、フランシスコ教皇は米国の司教たちに宛てた書簡を送った。フランシスコは、「促進されなければならない真の 「ordo amoris 」とは、例外なくすべての人に開かれた友愛を築く愛である」と書いている。ほかにも、「神の子は人となることで、移民というドラマを生きることも選んだ。 私は、とりわけ、教皇ピオ12世が、移民に関する教会の考え方の「マグナ・カルタ」とされる使徒的憲法『移民のケアについて』の冒頭で述べた言葉を思い起こしたい」として、「追放されたナザレの家族、イエス、マリア、ヨセフは、エジプトへの移民であり、非道な王の怒りから逃れるために同地で難民となった。彼らは、あらゆる時代、あらゆる国の移民や巡礼者、迫害や必要に迫られて祖国を離れ、愛する家族や友人と引き離されて外国で暮らすことを余儀なくされたあらゆる境遇の難民たちの模範であり、手本であり、慰めである」という記述が書かれている。要するに、移民に思いやりを示す信者の義務を強調しているようにみえる。それは、ヴァンスの主張への批判ともなっている。とはいえ、4月20日、イースターの日にフランシスコ教皇はヴァンスと会った。
なお、金子晴勇著「ORDO AMORIS」によれば、愛の秩序は、「神への愛」、「自己愛」、「隣人愛」の順序の問題として主題化されるようになり、アウグスティヌスは、神への愛・自己愛・隣人愛の順序とみなす。この順序は神により造られた本来的な秩序であって、現実においては、自己愛はこの秩序にしたがわず、自己中心的な悪しき自己愛となる。
思想にどう挑むのか
ここまで深く考えれば、日本において、「国家」や「国」を守護することに重点を置きたい人は、どうすればその思想をより多くの日本国民に膾炙できるかを構想しやすくなるだろう。逆に、そうした思想に嫌悪感をもつ人は、そうした動きにどう対抗すべきかを考えるヒントを手にしたはずだ。
いずれにしても、ここで紹介した程度の「深度」において、世界中の思想の潮流を考察することこそ、地政学・地経学の守備範囲であると強調しておきたい。
【注】
(注1)ここで、復習しておきたいことがある。それは、プーチンが長く政権を握ってきた過程で、国民の思想やイデオロギーを操作することで、自らの政権の強化につなげようとしてきた事実にかかわっている。かつて、その役割を担っていたのは、ウラディスラフ・スルコフである。スルコフは2012年5月、プーチン大統領のもとで副首相兼政府官房長になり、2013年5月にいったん解任されながら、同年9月、南オセチアなどを担当する補佐官として復帰、その後、ウクライナ東部をめぐる問題に従事したあと、2020年に政界を去った。
このスルコフが提唱したのが「ソヴェリン・デモクラシー」である。スルコフは大統領府副長官時代の2006年6月、外国人ジャーナリストとの会合で「ソヴェリン・デモクラシー」について語り、同年11月、ロシアでもっとも権威のあった雑誌『エクスペルト』誌(No.43)において、持論を展開した。スルコフは「ソヴェリン・デモクラシー」の発案者として、2005年ころからこの「ソヴェリン・デモクラシー」なる概念を提唱してきた。
ただし、スルコフの主張をいくら丹念に読んでも、「ソヴェリン・デモクラシー」の意味は判然としない。ポリティカル・エンジニアリングに基づいて、人口に膾炙させることをねらっていたわけではないから、そもそも「わかりにくい」という大きな欠陥をもっていたのである。
「国家」の重要性を強調しているから、「ソヴェリン・デモクラシー」は「国家デモクラシー」といった意味に近いという程度しかわからない。国家主体を重視し、その国家主体の主権の安定性を確保したうえで、デモクラシーを実現するかのような意味に近い。ロシアでは、「管理された民主主義」(managed democracy)といった言葉で、ロシアの不可思議な民主主義を表すことがあるが、これではネガティブなニュアンスが強くなるので、「ソヴェリン・デモクラシー」なる造語がつくられたとみることもできる。
他方で、「ソヴェリン・デモクラシー」はナショナリズムとも強い関係をもつ。だが、ナショナリズムもネガティブなイメージをもつため、「ソヴェリン・デモクラシー」とナショナリズムとの関係もあえて曖昧なままにされているとも言える。
スルコフは、「ソヴェリン・デモクラシーは市民社会、信頼できる国家、競争力のある経済、世界的事件への効果的影響メカニズムの発展を通じてロシア国民によって達成される」という。しかし、この規定では、「ソヴェリン・デモクラシー」が結局、ロシアにおけるナショナリズムの強化と理解されかねない。つまり、「ソヴェリン・デモクラシー」は、思想・信条の自由や言論の自由はもちろん、競争的な多党制、秘密投票、自由な選挙運動、マスメディアへの公平なアクセス権などを前提とする民主主義とは無関係でありながら、あくまで「デモクラシー=民主主義」を標榜する不可思議な概念ということになる。
スルコフは「ソヴェリン・デモクラシー」のために、市民の連帯、主導的ネーションとしての創造的階級、文化、教育・科学を重視している。興味深いのは、市民の連帯において必要なものとして、陸海軍および特殊機関の威信維持や技術再装備に合理的予算配分を行うと指摘している点だ。これは、軍事力強化を正当化する主張だが、それだけでなくソ連時代のKGB(国家保安委員会)の系譜につらなる連邦保安局(FSB)や対外諜報局(SVR)などの強化・拡充を肯定している。
ところが、この「ソヴェリン・デモクラシー」にメドヴェージェフは異論をのべてきた。「ソヴェリン・デモクラシーという用語は、私には気に入らない。すべての価値ある民主主義は国家主権に基づいていなければならないと、いまも思っている。しかし、その特徴のひとつ、すなわち、国内の権力主権やその独立性を突出させることは、法律家として、私には、過剰に思える。ときには、有害にさえなる。なぜならこれは誤った方向に向かいかねないからだ。」
メドヴェージェフは2007年7月5日に掲載された、「ヴェードモスチ」のインタビューで、こう堂々と主張した。同じインタビューで、「国営企業が民間企業より効率的であるとは思わない」とも明言している。ただし、後に、彼とスルコフの関係は良好となる。
(注2)なぜ唐突に「五輪書」をもち出したかについて説明しておきたい。ハリチェフやポロシンのボス、キリエンコは少なくとも「五輪書」を知っているはずだと思っているからである。「五輪書」はロシア語で、«Книга пяти колец»と訳されている。キリエンコは日本刀に関心があり、その精神性に惹かれていると聞いたことがある。だからこそ、「ペンタ・ベース・モデル」の背後に、「五輪書」が多少なりとも関係しているのではないかとにらんでいるのだ。
(注3)本当は、「修身」の前に、「格物・致知・誠意・正心」という4項目がある。つまり、「格物・致知・誠意・正心・修身・斉家・治国・平天下」の8項目を一体として理解しなければならない。松岡正剛は『日本文化の核心』のなかで、つぎのように記述している(319~321頁)。
「知を致すには、モノに到る(いた)ることを疎かにしてはいけない。物に格れば、死「知を致すには、物に格(いた)ることをおろそかにしてはいけない。物に格れば、しかるのちに知に致る。知に致ってのちに意(こころ)が誠になり、そののちに心が正しくはたらく。心が正しくはたらけば身が修まるところがわかる。身が修まれば家が斉(とと)のう。そうやって家が斉って初めて、国が治まる。国が治まれば必ず天下は平らかになるだろう。」
(注4)拙著『ロシア革命一〇〇年の教訓』において、「社会」や「国家」について、つぎのように記述しておいたので参考にしてほしい(なお、縦書きのものをそのまま横書きにしている)。
「ただし、ここで想定されている「社会」は、せいぜい国家でしかない。共同体を越えた「社会」は考えられておらず、社会契約といっても、それは国家との契約の問題が議論されているにすぎない。ロックは一七世紀後半に書いた『統治二論』の第二部において、〝The first Society was between Man and Wife〟と書いている(Locke, 1680-1690, 77-5)。ここで、〝Man〟と〝Wife〟が、〝individual〟(個人)として前提されている点が重要である。まさに、個人を前提にして、夫婦の関係から出発し、家族へと広がり、会社へと広がる「仲間」として、〝society〟がイメージされていたことになるこのとき、母親と赤ちゃんとの間に〝society〟が生まれたとしなかった点に深い含意が込められている。夫婦の関係は、いわば「大人」の関係であり、「個人」と「個人」の関係から成り立っているとみるのが当然であろう。だからこそ、ロックは、「夫婦の〝society〟は男と女の間の自発的な盟約によってなされている」と書いている(Locke, 1680-1690, 78-1-2)。自発的ないし自由意志の盟約(voluntary compact)があって、初めて〝society〟というものが成り立つのである。〝society〟という概念が広まったのと同じころ、あるいは、その少し前に生まれた「本当の自分」をさらけ出す、「分けられない」存在としての個人という概念がこの〝society〟の前提にあると言える。
ここで注意喚起しておきたいのは、この「仲間意識」の醸成がそれに対立するものとしてあった権力組織を国家(state)と意識させるようになった点である。廣松は、一八世紀を迎えると、資本主義的経済の自律的な論理が明確になってくるのと相即的に、旧来不可分の一体をなしてきた政治と経済の混淆(アマルガム)から経済の自律性が目立つようになり、政治的秩序と経済的秩序の区別(いわゆる市民社会と国家との区別)が意識されるようになるとのべている(廣松, 1989, p. 193)。その結果、ホッブズ・ロック的な国家=社会理論においてCommon-Wealth(キヴィタス)という形で一体的にとらえられていたところの「生活共同体」=「政治的共同体」が、今や社会と国家とに区別してとらえられるようになるという。この分離ののちに、「国家は、市民政府を形成するにいたった高度社会として理解される」ように位置づけられるのだ(同, p. 194)。アーレントによれば、この過程は「家族(オイキア)」あるいは経済活動の公的領域への侵入であり、それは私的領域に閉じ込められていた「労働」の公的領域への拡大を意味していた。それが「社会」の勃興につながり、その結果、私的領域と公的領域の相違はやがて完全に消滅し、両者はともに「社会的」なるものの領域に侵されてしまう(Arendt, 1958=1994, p. 98)。「社会」においては、もはや公的なるものは私的なるものの一機能になり、私的所有を保護するために政府が任命されるようになる。私的利益が公的関心にもなったのである。」
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)