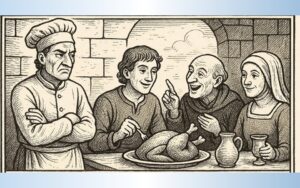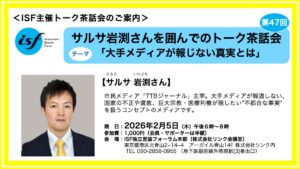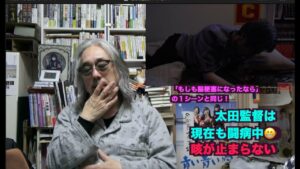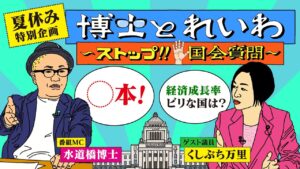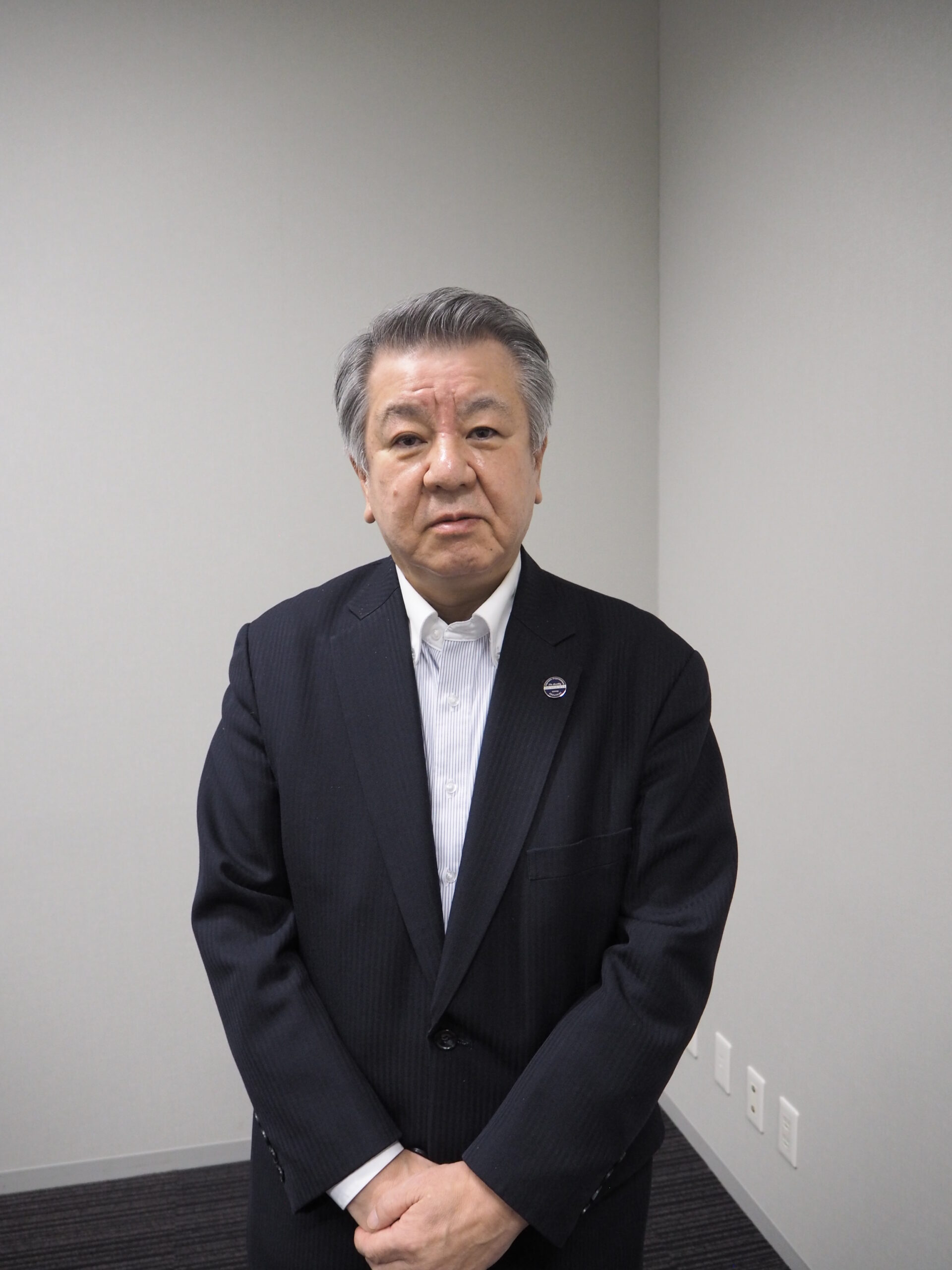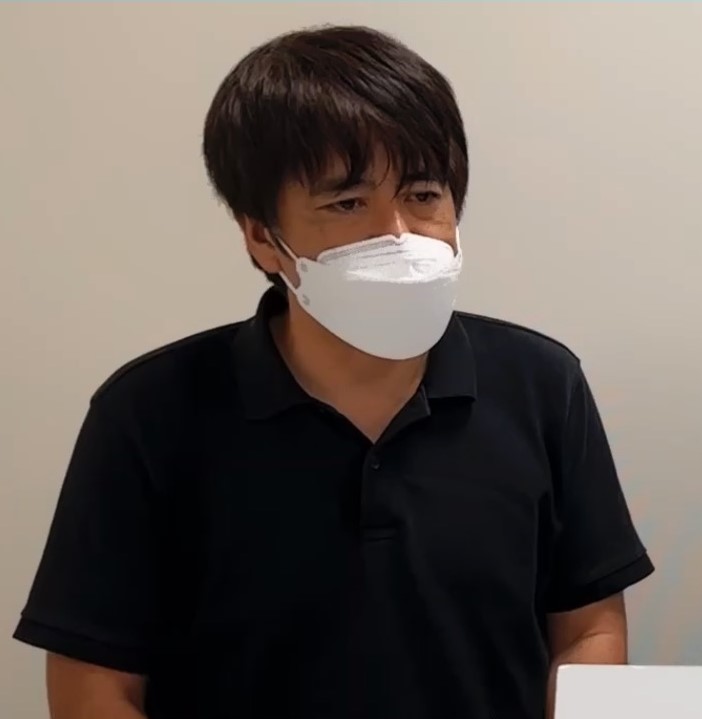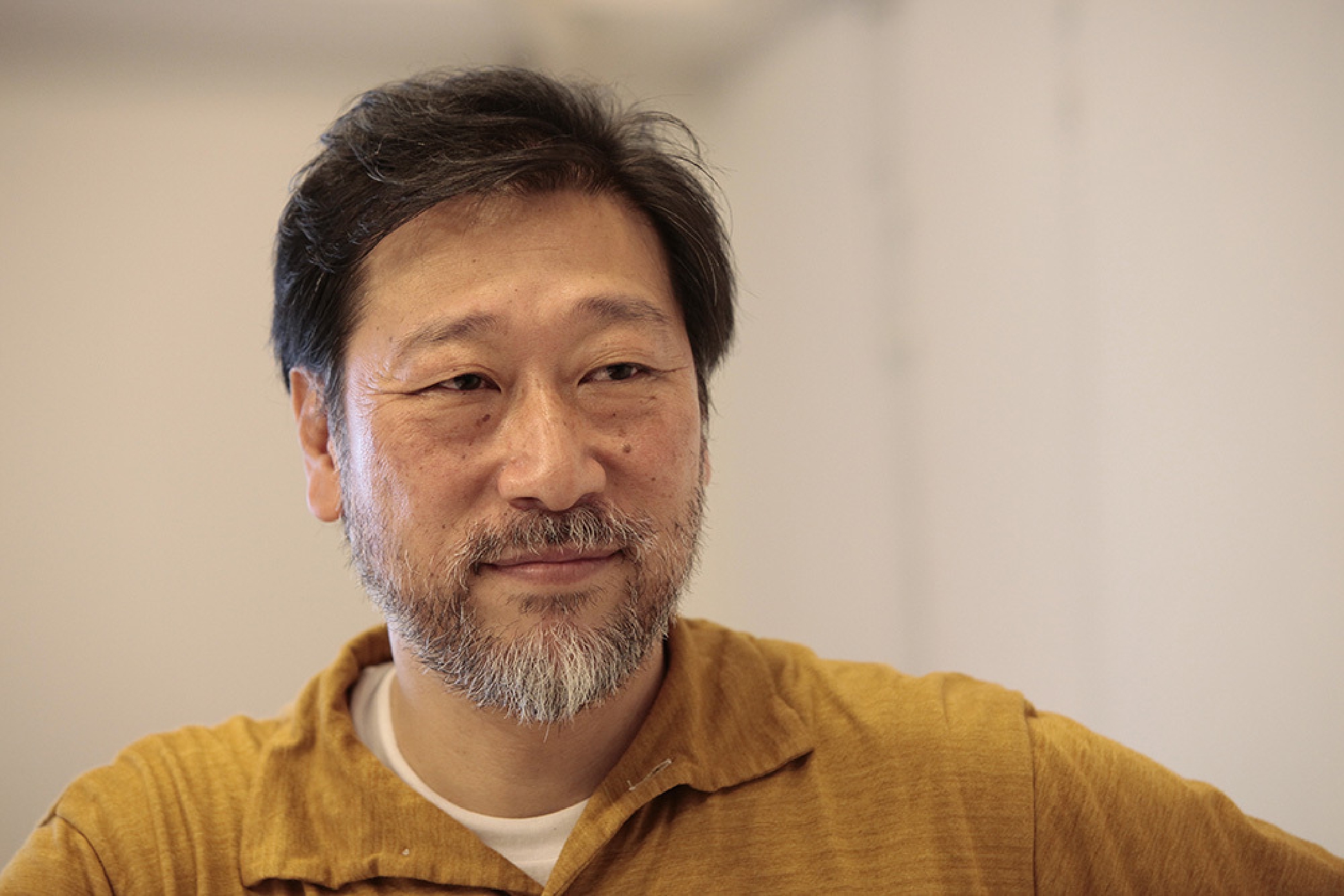登校拒否新聞16号:積極的不登校
社会・経済毎日新聞が「小学校へ一度も通わずフリースクールへ 「積極的不登校」という選択」という記事を配信した。3月23日付。記者は村瀬優子氏。
学習指導要領に縛られず、独自のカリキュラムで民間が運営するフリースクールは一般に、不登校の子供を支援する場と考えられている。一方、子供の個性を伸ばそうと、正規の小学校に一度も通わせないまま、米国やオーストラリアなどの先進的な教育手法を取り入れたフリースクールを選ぶ保護者たちがいる。・・・東京都中野区の「東京コミュニティスクール」(TCS)は少人数教育を掲げるフリースクールの一つだ。小学校1~6年に相当する各学年で9人まで受け入れる。一つのテーマを掘り下げる探求学習に力を入れ、学年を超えて多彩な活動に取り組む。豪州で従来の小学校とは異なる手法で運営される「オルタナティブスクール(もう一つの学校)」に感銘を受けた実業家の久保一之さん(58)が2004年に設立した。当初の児童数は3人だったが、次第に入学希望者が定員を上回るようになり、現在は50人の児童が在籍する。そのうち98%が小学校の入学段階からTCSに通っている。・・・TCSは学校教育法で定められた「学校」ではない。児童らは居住地の小学校に学籍を置き、TCSの学習状況を報告するなどして、小学校で卒業を認められている。しかし、学籍を巡ってトラブルになるケースも少なくないという。・・・最初から不登校を選ぶことは「積極的不登校」とも呼ばれる。一方、幼稚園で他の子供とのトラブルが多いなどの理由で、親が「公立小学校への適応は難しい」と判断し、TCSを探しあててくる例も少なくないと、久保さんは言う。「積極的不登校という言葉でくくるのは乱暴で、やむを得ない消極的な選択という側面もある」と説明する。一方、年間の学費は約100万円だ。公的な支援は限られ、保護者の負担は大きい。文部科学省によると、不登校の小学生は23年度に13万370人と過去最多に上り、11年連続で増えている。積極的不登校の統計はないという。
https://mainichi.jp/articles/20250322/k00/00m/040/124000c
続けて、記事には神奈川県茅ケ崎市にある湘南サドベリースクールというオルタナティブ学校も省略されているが、ここでは略す。サドベリースクールについては登校拒否新聞としても8号で沖縄の学校を紹介している。
さて、「積極的不登校」ということである。察するに、記者は取材したフリースクールの久保さんからこの言葉を耳にしたのだろう。記事の最後のほうに「一方」と二つ出てくる最初の「一方」の意味が通らず、何度か読み返した。なるほど。必ずしも積極的ではなく消極的ということか。しかし、理由は何であれ、公立校に就学させずに最初からフリースクールを選ぶというのは積極的な選択だ。かつては登園拒否という言葉もあったことを付言しておこう。登校拒否が「不登校」と言い換えられた理由の一つにも、それが登園拒否を連想させて高校相当の不登校(!)にはそぐわないという理由があった。「積極的不登校」というのはフリースクール界隈の業界用語だ。文科省に統計がないのは当たり前である。定義もないし、しようと思ったってできないだろう。それでも、そういうコトバが一定の意味を担って使われている。だからこそ、概念分析が必要だ。
この場合、フリースクールとオルタナティブ学校との概念上の区分もつけておく必要がある。私個人としては、オルタナティブ学校は再現可能な学校教育と定義している。つまり、シュタイナー学校など、国や地域を違えても、一定水準で同じような教育内容を保証できる学校ということである。つまり、オルタナティブ学校とは「もう一つの学校」ではない。オルタナティブ医療と同じである。抗がん剤治療の代わりに和漢薬による治療を行うとすれば、東洋医学は西洋医学に取って代わる――代替医療を提供するのだから再現性をもった、あるいは反復可能な医学ということになる。
オルタナティブ医療と同じ意味でオルタナティブ学校を定義するならば、代替可能な学校ということになる。シュタイナー学校、あるいはサドベリースクールなどはオルタナティブ学校である。この点、フリースクールは設立者となる個人の意向が強く出る。つまりシステムを欠いているのだから反復性があるとは言えない。
東京コミュニティスクールさんは「全日制マイクロスクール」を謳い、「自和自和(じわじわ)」という理念を掲げている。姉妹校となっているオーストラリアのビクトリア州のメルボルンにあるコミュニティスクールがモデルになっている。モデル校があるということは一定の再現性を備えているとも言える。横につながることで反復性を増すことはできるだろう。
http://www.fcs.vic.edu.au/index.php
いつものようにヤフーニュースで再配信された記事にはコメントが集まっている。128件だから多くはないが少なくもない。一定数の人が反応した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2dda6a4f6c5b2b2da0b6030c1767aadf489f1947
まずは言葉の問題から。
「積極的不登校」という用語はないです。そもそも、不登校の定義が「行きたくもいけない」という状態を含んでおり、「積極的」という言葉は、ミスリードです。(匿名)
この方は「不登校」が概念であることを知っている。そこに「含み」があることを知っている。けれども、その含みがまた「積極的不登校」という言い回しを生んだと私は考える。「行きたくもいけない」が含意している学校批判が転じては、こういう学校なら行ける、という理想の学校をつくる。そこに通う子がかつて「明るい登校拒否」「笑う不登校」などと言われたことから「積極的不登校」という見方も出てくる。なお、私に言わせると「状態」も用語である。「不登校」という概念を理解するのか。それとも「不登校」という概念枠を外して考えてみるのか。学校哲学は後者を志向している。
しかし、就学義務をどう考えるか?
フリースクールはあくまでもフリースクールであって、学校ではない(何かしら基準を満たさない)理由があるんだから、不登校でもないのに最初からフリースクールを選ぶって、それって親が子どもに教育を受けさせるという「義務」を果たしてないように思う。子どもにとって心地よい内容や場所を提供するだけが教育ではないと思うし。あくまでもフリースクールは「学校」に通えない子ども達の受け皿という立ち位置。(fyi********)
選択肢としてある事は良いと思う。一方でこれで良いのか?とも言える。これを国が認めたら、指導要領は、意味をなさない。それなのに、フリースクールでの学習を評価しなさいと言われる。フリースクールに公的予算をつけることに、反対した市長が叩かれていたが、それなら、民間でしないで、公的機関でして欲しい。学校に行けなくて、仕方なくフリースクールに通うのではなく、小学最初から通うつもりがないのは、義務教育を受けさせる義務を果たしていないのではないか…(jya********)
何でも「子供が選んだ」といえば聞こえはよいが、未就学児が「学校を選ぶ」って、出来るだろうか?確かに、雰囲気や、カリキュラムが楽しいとかは、子供にもわかるが、その教育を受けた先のことまでは子供はわからないわけだから、あとから「こんな特殊な教育を受けたくはなかった」ってことにはならないのだろうか?…どう考えても、これは、親の判断で決めた学校だろう。それを「子供が選んだ」ことにするのは、ちょっと無責任な気がしますね。(cho**lat)
就学義務については親が子を就学させる義務であって、子が学校教育を受ける義務ではないとよく言われる。あるいは「普通教育」を受けさせる義務であるから学校教育を受けさせる義務ではないとも聞こえる。どちらも私には異論がある。『戦後教育闘争史』などに詳しく書いたので今は略すが、そんなクリアーカットな問題ではないのである。この点については号を改めて書くつもりではある。
就学義務を考える上で問題なのは、上の意見にあるように指導要領であろう。つまり学校教育の内容は役所が決めている。それに従わないフリースクールをどう見るか、という話だ。ただ、戦後の学校教育は指導要領を「試案」としていたことは学校史の事実である。内藤誉三郎という文部次官から自民党の議員となり文部大臣になった人物がいる。彼が次官の時代に指導要領は「改定」され官報に告示されるようになった。この時までは指導要領には「試案」とあった。その後、伝習館裁判の最高裁判決で指導要領の法規性ということが判示されたので、今は一定の法的拘束性が認められているけれども、戦後の学校教育にとって指導要領は絶対条件ではなかったのである。この点も『戦後教育闘争史』に詳しく書いたから細かなことは省いて、今は言いたいことだけ言うと、指導要領に従わないからフリースクールはダメという論理は文部行政をなし崩し的に認めるものだ。
この点と関係して、もう一点。「公的機関」という見方は公立校に対しては当てはまるが私立には当てはまらない。私学は存在する。ただ、それとフリースクールのような私教育とをどう区別するか、ということが問題だ。それが指導要領だと言うかもしれないが、上のような理由からそうとは言い切れない。どちらかと言えば、教員免許の問題があろう。最近ではフリースクールにも教員免許を取得した人が多く入っている。元記事の東京コミュニティスクールさんにもそういう人が何人かいる。とはいえ、フリースクールのスタッフにも教員免許が必要となればかえって私教育としての魅力を失う。では、そういう学校に就学(?)させることに問題はあるのか?
思うに、問題はそれを「積極的不登校」とする見立てにある。「不登校」という枠組みを外せない限りフリースクールは受け皿校にとどまるだろう。オルタナティブ学校とフリースクールのニュアンスの違いもこの点に関わっているように感じる。それと関係して、フリースクールにはフリースクールとしての一大特徴がある。
小中は義務教育で中学は絶対に卒業しないといけないと思い込んでいたから、こういう選択肢がもし私の時代にあったら親に頼んでとりあえず見学には行ってたと思う。それぐらい嫌で毎日心の中で泣きながら学校に通ってた。結局高校の途中で耐えられなくなって中退したけど、我ながらそこまでよく頑張ったと思う。ある人が「学校は嫌いだったけど、友達に会えるから毎日通ってた」と言ってた。私にはそういう友達がいなかったから学校に行く意味が見出せなかったのかもしれない。高校をやめて私も一時期フリースクールに通ってたけど、そこの空気にも耐えられなくてすぐやめた。その後で通い始めた通信制高校が一番私には合ってたと思う。基本はレポート提出でたまに登校すれば単位がもらえたから。普通の学校に通えればそりゃ一番楽で良いけどね。何百人もいたら中には私のような子も一人や二人は必ずいるよね。仕方ない。無理なものは無理。(fis********)
高校中退でフリースクールに入った。それが「空気に耐えられなくてすぐやめた」というのがおもしろい。私も某有名フリースクールのイベントに参加した時にそういう空気を感じた。「通信制高校が合ってた」というのは同感だ。この方が感じた空気と私の感じた空気とはたぶん同じモノだ。居場所とはいえ学校嫌いがかえって居にくいと感じる雰囲気があったりするからおかしい。頻繁に換気だけはしてもらいたいものである。
やはり人なのである。どういう人が集まるか、ということだ。
NHKの番組で不登校がやってきたというのを観たことがあるが、色々な不登校の子ども達を取材して中々興味深い番組だったのだが、実は番組スタッフの子どもが、それも兄妹そろって不登校であるということを知ってから、いや環境のせい、もっといえば親の影響もあるのではないかと思った。無理やり行かせろ、とは私も思わないが、兄妹ともに不登校というのも珍しくないだろうか。その兄妹に関しては正直いって親の責任が半分はあるのではないかと思う。(jtwpmdt)
不登校あるある、と言ったところか。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。