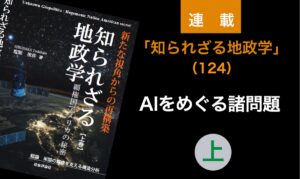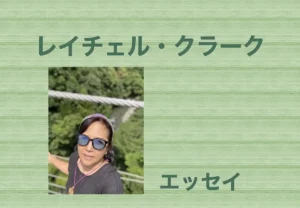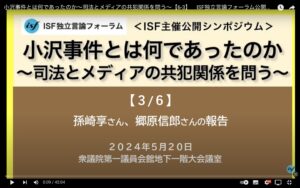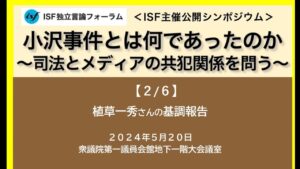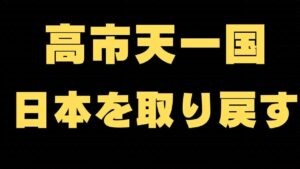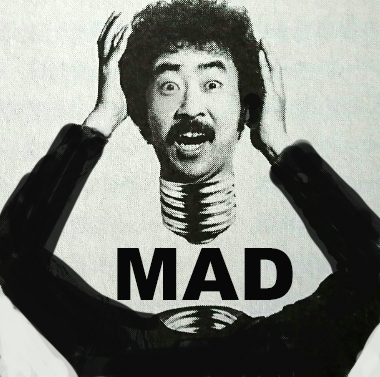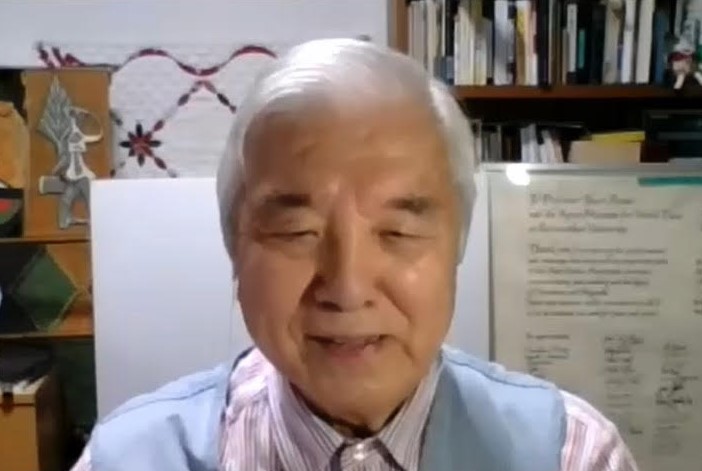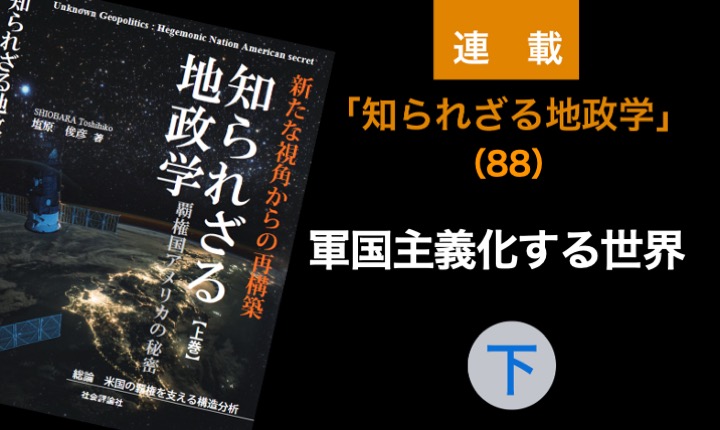
「知られざる地政学」連載(88):軍国主義化する世界(下)
国際
「知られざる地政学」連載(88):軍国主義化する世界(上)はこちら
好戦派の優位
2022年2月24日に勃発したロシアによるウクライナへの全面侵攻後、「ウクライナ=善」、「ロシア=悪」という短絡的な見方が世界中を席捲した結果、対ロ警戒派や対ロ好戦派が圧倒的に優位となった。それは、いわゆる西側の政治家、マスメディア、専門家による、暴力による領土変更の措置、民主主義の堅持の大合唱となり、同時に、軍事費増加による防衛力重視が当然であるかのような世論が広がった。
こうした現象を冷ややかに眺めていた私からみると、世論誘導はマスメディアによって露骨に行われたように思われる。テレビや新聞、すなわち、オールドメディアは、きわめて安易に、当時のジョー・バイデン大統領らによるリベラルデモクラシーの世界伝播という安直な考えに盲従した。とくに、日本や欧州のオールドメディアは「言論統制」と言えるほどの情報統制を事実上行うようになる。
拙著『ウクライナ3.0』、『復讐としてのウクライナ戦争』、『ウクライナ戦争をどうみるか』、『知られざる地政学』〈上下巻〉、『帝国主義アメリカの野望』について、書評も載せないオールドメディアのひどさは、のちに森永卓郎が『発言禁止』に書いている通りである。
この恐るべき言論統制は、欧州でも同じである。それを教えてくれているのがエマニュエル・トッド著「西洋の敗北」(これについては、「連載【86】「西洋の敗北」からみた地政学[上、下]」を参照)であり、「米欧の分裂と日本の選択」『文藝春秋』(2025年5月号)だ。
オールドメディアは、ジャニー喜多川問題や中居正広問題で明らかになったように、表面上、反省を装うだけで、実際には何の反省もしていない。その結果、自分たちの過去の報道について謝罪することもなければ、訂正することもない。
ゆえに、いまでもウクライナ戦争を停止させようとするトランプ大統領の努力を批判しつづけている。それは、戦争継続派のゼレンスキーも同じであり、欧州の政治指導者らも同じだ。なぜウクライナ戦争をつづけ、ロシアがNATO加盟国さえ侵略しかねないと煽り、軍事費増強に傾くのだろうか。
性根を改めろ!
「現代ビジネス」において4月28日に公表した拙稿のなかで、「どうして欧州は、ウクライナの「無条件の停戦」に肩入れするのだろうか。残念ながら、その理由はウクライナのゼレンスキーと同じく、いろいろと「いちゃもん」をつけて、戦争を継続させたいからにほかならない」と書いておいた。さらに、「なぜ彼らが停戦・和平の妨害をするかといえば、それは、停戦が2014年以降のEUのウクライナ支援政策全体を無駄にすることを意味しているからにほかならない。同時にそれは、EUおよびその加盟国のうち、ハンガリーを除くほとんどの国の指導者の権威失墜を意味している」とも指摘した。
要するに、2022年2月以降の対応が間違っていたのであり、それは、2014年2月、米国政府が支援して起きたウクライナのクーデターに対する対応の誤謬を糺せなかった結果なのだ。それにもかかわらず、そうした自らの過ちを糺さないまま、突っ走ろうとする。
リベラルデモクラシーを標榜する米国民主党員の多くは、いざとなれば、暴力によって自由を守ることを当然とみなしている。この態度は、戦争を起こすために民主主義を輸出して、紛争を引き起こし、戦争につなげて自らの利益に結びつけるという姿勢に転じやすい。その意味で、彼らはきわめて好戦的だ。しかも、こうした連中が米国のオールドメディアを牛耳り、大学を支配してきた。彼らは、自らの過ちを認めようとせず、自分の主張をあくまでも正しいと言い張る。その結果、暴力を用いることに躊躇せず、平然と戦争を起こし、継続しようとする。負け戦でありながら、ウクライナに戦争をつづけさせようとするのは、どう考えてもおかしい。
バチカンの話
ここまで書いてきて、亡くなったフランシスコ教皇の後釜を決めなければならないバチカンのことを思い出した。5月7日に新教皇を決める「コンクラーベ」が開催される。世界が軍国主義化しているとすれば、それに歯止めをかけてくれそうなローマ教会の今後については無視できない。
ここで、拙著『ウクライナ戦争をどうみるか』用に書きながら、紙幅の関係で割愛した拙稿を紹介したい。長い引用になるが、ご容赦願いたい(縦書きを横に印字)。
「 ローマ教皇の影響力は?
カトリックの総本山、ローマ教会のフランシスコ教皇の力はどうだろう。彼のインタビューを読むかぎり、もっと彼の考えを知ってほしい。いまの欧州の政治的指導者よりもずっとまともだと、私は思う。
(二〇二二年:引用者注)六月一八日に公表されたフランシスコ教皇とのインタビュー記事のなかで、インタビューの行われた五月一九日の段階で、彼は興味深い話を披露している。ウクライナ戦争がはじまる数カ月前にある国家元首に会ったフランシスコは、彼がNATOの動きを非常に心配しているといったと話した。なぜかと尋ねると、「彼らはロシアの門前で吠えている。ロシアは帝国であり、外国勢力が近づくことを許さないということを理解していない」と、彼はのべ、「このままでは戦争になりかねない」と締めくくったという。
彼自身の発言はつづく。「誰かがこういうかもしれない。でもあなたはプーチンに賛成しているのでしょう!」と。それに対して、フランシスコ教皇はつぎのように語ったという。
「いいえ、そうではない。そのようなことをいうのは単純で間違っている。私は、非常に複雑な根源や利益について考えることなく、複雑さを善悪の区別に還元することに反対しているだけだ。」
だからこそ、フランシスコはインタビューの冒頭、「通常の「赤頭巾ちゃん」のパターンから離れる必要がある」とのべ、「赤頭巾ちゃんはいい子で、狼は悪いもの。ここには、抽象的な意味での形而上学的な善悪は存在していない」と指摘した。そのうえで、「何かグローバルなものが現れており、その要素は互いに非常に絡み合っている」とのべている。
この二つの発言から、ロシアが悪で、ウクライナが善とする見方がいかに皮相であるかをフランシスコは知っていることがわかるだろう。
八月二四日になって、フランシスコは同月二〇日、運転するトヨタ・ランドクルーザーが爆発し、死亡した、ロシアの思想家アレクサンドル・ドゥーギンの娘ダリアについて、「自動車爆弾で吹き飛ばされた哀れな少女」と呼んで悼んだ。教皇はウクライナの独立記念日とロシアの侵攻から六カ月を記念した演説で、戦闘を終わらせるための「具体的な措置」を求め、ダリアを戦争の無実の犠牲者と呼んだのである。さらに、「罪のない人が戦争の代償を払っている!この現実を考え、伝えよう、「戦争は狂気である」と、フランシスコは語った。
これに対して、バチカン市国に駐在するウクライナ大使は、彼女は無実の犠牲者ではなく、ロシア帝国主義の「思想家」であるとツイートした。たしかに、ダリアは父親譲りの極右の思想の持ち主であったようだ。フランシスコはそんなことは先刻承知のうえだ。彼は、一刻も早く狂気の戦争を止め、平和を取り戻すことを求めているだけだ。私は、ローマ教皇の考え方に賛成する(もっとも、第5節でのべるように、教皇の姿勢は八月末以降、ロシアに厳しくなっている)。
たしかにロシアの侵略を受けたウクライナの人々には同情する。だが、被害者であることを理由に、自分たちがあくまで善であると主張するのはいかがなものか(現に、ダリアはウクライナの諜報機関によって殺害されたとの見方が確実視されている)。フランシスコのいうように、善悪は絡み合っており、そう簡単に白黒を判別できるわけではない。こうした当たり前のことさえわからずに、ウクライナだけを善とするような欧州の政治的指導者に私は失望している。」
ちょうどこの原稿を書いている4月28日、27日付の「ストラナー・ニュース」が興味深い記事を公表したので、それも紹介しておきたい。記事は、「ローマ教皇の座をめぐっては、フランシスコに代表される教会内の従来からのリベラル派と、前任のベネディクト16世に代表される保守派との争いがある」と書いている。しかも、だれが教皇になるかはウクライナにも影響をおよぼすという。なぜなら、バチカンに従属する、ウクライナ最大の宗派の一つ、ウクライナ・ギリシア・カトリック教会(UGCC)とフランシスコの関係が緊張関係にあったからである。
フランシスコ教皇は、本格的な戦争が勃発する以前から、プーチンやロシア正教会と積極的に対話を行っていたため、ウクライナのギリシャ系カトリック信者の間に強い不満が生じていた。さらに、UGCCへの総主教の地位付与を阻止した。この地位付与はUGCCに自治の面でより大きな権利を与えるものであるだが、フランシスコはそうしなかった。多くの東方カトリック教会(レバノンやエジプト)はこの地位を取得しているが、ギリシャ系カトリック教会についてはこの問題に進展はなかった。
このような背景から、UGCCとローマ教皇の関係はますます緊迫し、UGCCはバチカンから分離し、ウクライナ正教会と統合し、エキュメニカル総主教バルトロメオ一世に従属する統一ウクライナ教会を作りたがっているという噂さえあったという。
パロリンの可能性
ローマ教皇の座をめぐっては、イタリア人が有力候補の上位を占めていると、記事は伝えている。イタリア人が教皇に選出されたのはほぼ半世紀ほど前だ。266人の法王がイタリア国籍をもっていた。今回の「コンクラーベ」における主な候補者の一人は、70歳のヴェネツィア郊外出身のピエトロ・パロリンと言われている。フランシスコの弟子であり、バチカン国務長官でもある。彼は故ローマ教皇の右腕であり、最高顧問であり、性的マイノリティに忠実で、女性の権利やより開かれたカトリック教会を支持するバチカンのリベラル派の代表とみなされている。
パロリンは、昨年夏にはウクライナを訪問し、ゼレンスキーと会談したこともある。中国や中東政府との微妙な交渉を含む数十年の外交経験を持つパロリンは、安定性と制度の継続性を象徴しているとの見方が紹介されている。このため、「ウクライナとUGCCに関するバチカンの路線は、パロリンが到着しても変わることはないだろう」とみられる。パロリンはフランシスコと同様に中立を保ち、外交的に平和を呼びかけ、「ロシアとプーチンに対する厳しい発言は避けるだろう」という。
したがって、フランシスコの方針を引き継ぐ新ローマ教皇のもとでは、UGCCが総主教の地位を得る可能性は低い。この問題は宙に浮いたままとなる公算が大きい。バチカンはウクライナの教会問題に干渉したくないという意見もある。
「教皇候補」のもう一人の外交官は、バチカンの69歳のウクライナ戦争特使、マッテオ・ズッピだ。ボローニャ大司教でイタリア司教座会長の彼は、「困窮している人々に近い教会の代表 」であり、「革新的で現実的なアプローチで 」対話を行うことができるとみられている。
彼は2年前にキエフを訪れ、昨年秋にはモスクワを訪問した。ローマ教皇庁の報道局長によると、マッテオ・ズッピ枢機卿は 「教皇フランシスコから託された任務の一環として、ロシア当局と会談し、ウクライナの子どもたちとその親族との再会を促進するための追加的な努力と交流の期待を評価するために 」2度目のモスクワ訪問を行ったという。
この連載が公表されることには、新教皇は決まっている。ゆえに、これ以上は書かないが、世界の行方はローマ教皇という人物と無縁ではない。つまり、属人的な関係を無視することはできない。その意味で、トランプがコンクラーベにも影響をおよぼしている面があることを忘れてはならない。超保守的な候補者である76歳のレイモンド・バーク米枢機卿に働きかけることで、トランプ政権に影響を与えようとする動きがあるというのだ。
15年前にベネディクト16世によって枢機卿に任命されたバークは、フランシスコのリベラリズムを痛烈に批判し、フランシスコは彼をバチカンの権威体系の中でもっとも重要なものの一つである信仰教理協会総長のポストから解任した。バーク自身は、一部の司祭によるセクシャルハラスメントの報告を無視したことで非難された(彼らは他の教区に異動させられたが、処罰はされなかった)。そうやら、トランプ政権で副大統領を務めるカトリックのJ・D・ヴァンスともうまくやっていけそうな気配だ。そのため、ウクライナに関しては、専門家たちは、バークがトランプと同様に早期の停戦を呼びかけるだろうとみている。
世界の軍国主義化は、世界中に腐敗が蔓延し、いま以上に深刻化することにつながるとにらんでいる。この問題は、軍産複合体を通じた、国家と企業との癒着の広がりを引き起こし、不透明な資金の流れを生むと想定できる。この問題は重要なので、別の機会に論じることにしたい。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)