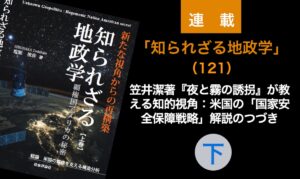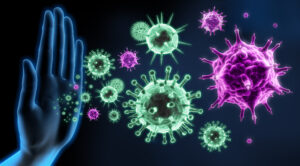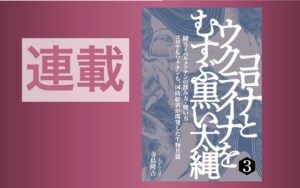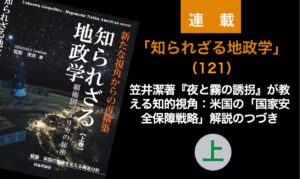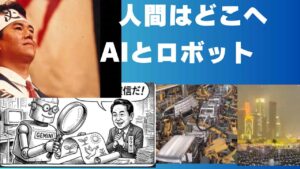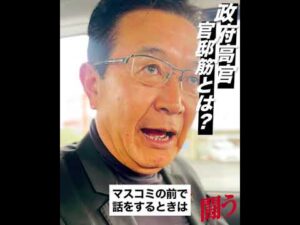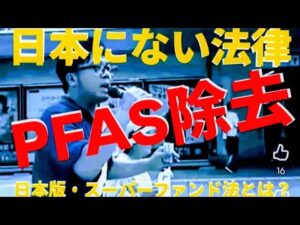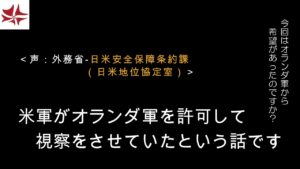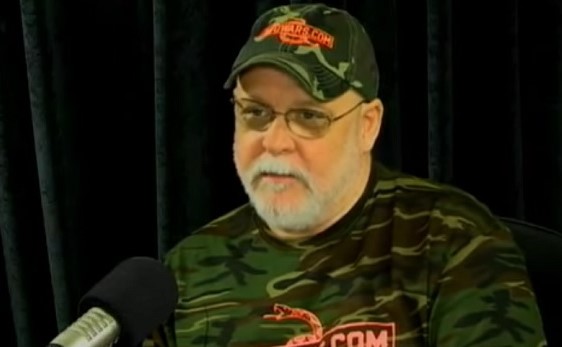登校拒否新聞17号:学校感
社会・経済4月15日、TBSが次のように報じた。
不登校の子どもたちが通いやすいように工夫された「学びの多様化学校」がこの春、鎌倉市に開設され、きょう転入学式が行われました。転入学式が行われたのは神奈川県鎌倉市立「由比ガ浜中学校」です。文部科学省が指定する「学びの多様化学校」で、神奈川県内の公立中学校としては2校目となります。きょうの転入学式には、市内在住で不登校や不登校の傾向がある1年生から3年生の男子12人、女子19人、あわせて31人が出席し、新たな一歩を踏み出しました。一般の中学校より授業時間数を4分の3に減らすなど、特別なカリキュラムが組まれ、不登校の子どもたちも通いやすいようインテリアも含めて様々な工夫がなされています。制服はなく、登校時間は市内全域から通うため午前9時半と遅めに設定されています。毎日の登校を基本としていますが、生徒の状況に合わせて学校と相談しながら登校のペースも決められます。校歌や学校行事も、これから生徒たちと検討していくということです。また、教員らは「スタッフ」、分校長は「リーダー」と呼ばれ、教室は「学び場」と言い換えられています。生徒31人は“クラス”ではなく、3つの異学年の「ホームグループ」で学んでいくということです。・・・転入学式の後、取材に応じた生徒たちは「“学校感”がないところがいい」「今まで不登校だったけど、この学校なら勉強にもついていけそう」などと新しい学校生活への期待を話しました。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1855311?display=1
法的には市立御成中学校の分校という位置づけになる。生徒は約30人。教員とスクールカウンセラーが合わせて約10人というが内訳はわからない。年間の授業時間数は1,015時間を770時間に減らす分、総合的な学習の時間を各学年140時間に増やすという。「特別なカリキュラム」とあるのは何のことだろう?
「学びの多様化学校」というのは旧「不登校特例校」である。名称の変更は某フリースクール系の学校の意見が採用されたらしい。実際、「スタッフ」という呼称もフリースクール由来である。この用語の出所については『ごっ魂ぜ』という同人誌に寄せた「学校哲学」に書いたので気になる方は読んでみてほしい。
https://gottamaze.booth.pm/items/5742387
「“学校感”がないところがいい」「今まで不登校だったけど、この学校なら勉強にもついていけそう」という生徒の意見がおもしろい。「スタッフ」「リーダー」「学び場」などと言われるとかえって学校臭く感じる。学校ほどジャーゴンに溢れた空間はない。だから「寄り添う」「連携」などと業界用語を並べれば何か言った気になってしまう。そう言えば「居場所」というジャーゴンの由来を『スクール・マイノリティのゆくえ』という小著に書いたことがある。これは解放教育から来た言葉だ。差別されてるその子の居場所が教室にない、というふうに使う。それが「居場所」という言葉の自然な用法だろう。学校に居場所がないんだ。不登校の子どもの居場所って、たまり場ですか?
言葉の歴史を知らないと字面で判断することになる。
尾木ママこと尾木直樹氏のブログに「ホント!不登校という表現はやめたい!」という記事がある。2024年7月18日付。文中、顔文字が入ってるけれど写せなかったので、気になる方はリンク先でチェックして欲しい。
不登校という表現はもうやめたいですね!
確かに『学校外学び児童・生徒』など学びを拒否しているわけじゃないのですから
多様な理由から「学校」を拒否しているだけなんですよね
『個別の学び児童・生徒』も素敵な呼称だと思います!!
大賛成です♪
『学びの多様化学校』←『不登校特例校』
最近親子の意見を聴いて改めたばかりですよ
https://ameblo.jp/oginaoki/entry-12860424402.html
尾木氏は「親子の意見」と言っておられるけれども、私が聞いたところでは、某有名フリースクール系の不登校特例校の意見が通ったということである。「不登校」という表現をなくすことは賛成だ。だが、学びの多様化学校と言い換えたところで、特例校は一条校である。そこに通学している子どもは小学校の「児童」と中学校の「生徒」だ。そもそも「不登校」ですらないのである。
TBSの報道では「今まで不登校だったけど、この学校なら勉強にもついていけそう」と生徒が言っていた。勉強についていけない、という現実的な問題がありそうだ。そうであれば勉強の教え方、時間割を変えることで解決される。制服をなくして、時間を遅らせて、短縮する。これは通信制高校や定時制高校でやっていることだ。
私の通った通信制高校ではチャイムが鳴らなかった。黒板もホワイトボードで、金魚鉢も大きな三角定規もなければ、廊下の掲示板もなかった。一切の学校らしさを消していた。もちろん制服もなかった。それでも転入生の一部は前の学校の制服を着てやって来た。それが癪に障った。授業が終わってから前の学校の友達と遊ぶのだろう。こういうタイプの転入生は心を前の学校に残している。だから他校に移っても周りの生徒とは話さない。
制服をなくすのが多様化と思えばアテが違う。
制服を脱がずに(?)別の学校に転学する。それもまた学校の姿だ。
いつも言っているように、私は中学不就学である。だから制服を着たことがない。ただ、仕立て屋に行って、サイズを測ってもらったことはある。通学するようになると困ると親が思ったのだろう。その時の記憶は今でもある。仕立て屋さんの場所も、出来上がった制服を透明袋に入れたままタンスにしまった時の様子も覚えている。以来、一度もその制服を見たことがない。ひっそりと親が処分したのだろう。登校拒否にはこういう経済的な問題もあるんだが、教育学者たちは興味がないらしい。「多様」というウケる言葉を使って、うま味のあることが言いたいようだ。
ある大学の研究員になった際に出くわした東京大学の卒業生は中高一貫校を出ていて、その学校には制服がなかったという。私にとっては学校に行かないということは制服を着ていないということと同義だった。奴らの姿を見ないように登下校の時間は外して外出した。それでも街を歩けば昼間から制服を着た連中が跋扈している。制服を着てるなら学校に行けよ!って制服組を目の仇にして育ったわけであるから、その制服がないという中高一貫校の話を聞いてずいぶんと考えさせられた。
案外にエリート校なんかで制服が消えている。一方で、転入生が前の学校の制服を来て通信制高校に通ってくる。既存の学校も変わってきてる。制服が学校らしいというのも古い考えのようだ。特例校の生徒さんは「“学校感”がないところがいい」と言っていたけれども、その見方も変わるだろう。かえって昔ながらの木造校舎で、詰襟の制服を着て『国語読本』でも読んでいるほうが学校っぽくないのかもしれない。「スタッフ」や「リーダー」のいる「学び場」なんて、俺はイヤだな。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。