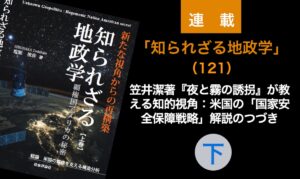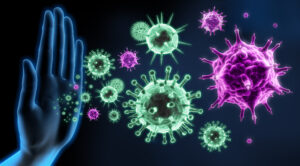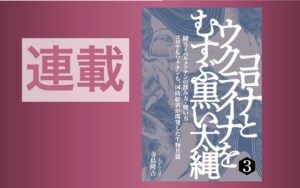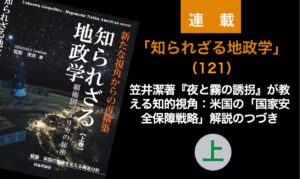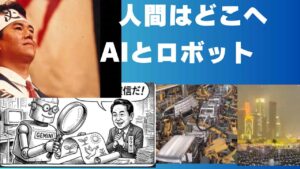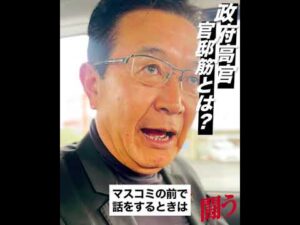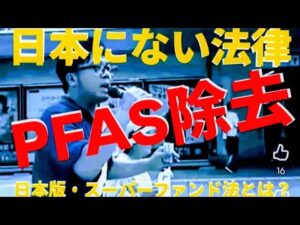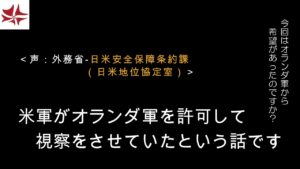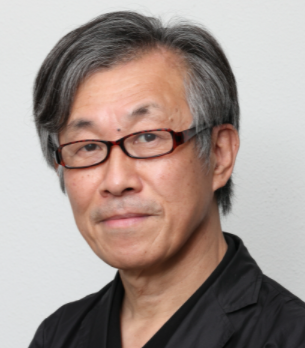登校拒否新聞18号:「病気」
社会・経済ヨミドクターという読売新聞社のサイトに「コロナ「5類」移行2年、後遺症に苦しむ子どもたち…今も登校困難で孤独感・寝たきりも」という記事が載った。掲載日は5月8日。執筆者は浜田喜将。
「多くの病院で『思春期特有の問題』と片付けられ、たくさん傷ついた」。さいたま市の中学3年の女子生徒はこぼした。小学6年のとき、コロナに感染した。高熱などの症状は1週間で治まったが、約2か月後、腹痛や頭痛、倦怠感に襲われた。学校を休みがちになり、複数の病院で精密検査を受けたものの、診断結果は「異常なし」。東京の病院でコロナ後遺症だとわかったのは、感染から1年後だった。元々、テニスに打ち込み、運動が大好きだった。中学進学後は症状が悪化し、中1の6月から登校できなくなった。現在はほぼ寝たきりで、オンライン授業の受講も難しいという。自宅で週3回、はり治療を受けており、高額な治療費がかかる。母親は「国や自治体に支援してほしい」と訴える。大阪市の私立中学3年の男子生徒も小6で後遺症を発症し、中学入学後に通学できなくなった。学校にオンライン授業を求めたところ、「学校の方針」との理由で断られた。交渉の末、授業の映像視聴がようやく認められたが、同級生と交流できず、強い孤独を感じたという。
後遺症患者に対する厚労省の直接的な支援は、医療機関の紹介や、受診を促すパンフレットの作成などにとどまる。文部科学省は、通学できない子どもについてオンライン授業の活用などを促しているが、実施の可否は学校の判断に委ねている。文科省の担当者は「後遺症の症状は様々で、一律に対応を決めづらい」と明かす。3月、後遺症を患う子どもの親や支援する弁護士ら有志が厚労省を訪れ、医療体制の充実や全国規模の実態調査、支援に向けた法整備を進めることなどを求める要望書を提出した。「出口の見えない真っ暗なトンネルをずっと1人で歩いている」「普通の高校生活を送りたかった」。要望書には、小中高生11人の悲痛な声も添えられた。保護者らは「教育が受けられず、学力低下で進学も危ぶまれている」と訴えた。東海学院大の高橋智教授(特別支援教育)は「適切な教育を受けられない現状は深刻だ。国は子どもの後遺症の実態を広く調べ、法整備も検討するべきだ」と指摘している。
https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/20250508-OYT1T50016/
途中、新型コロナ後遺症についての説明が入るが略した。というのも、独立言論フォーラムの読者であればわかるであろう。ワクチンの後遺症という見方がある。読売新聞社ではそういう見方は取っていないようだ。あくまでも新型コロナ後遺症という前提で記事は書かれている。だから、最初に出ている2人の例において、ワクチン接種の有無などは書かれていない。
病院で「思春期特有の問題」とされた、というのは内科系の診断で、「不登校」がある頃から起立性調節障害とされるようになったからである。これがホルモンバランスの問題、つまりは「思春期特有の問題」ということで扱われている。発達障害という精神科の診断と並び「不登校」の二大診断と言ったところか。もともとは「登校拒否症」という診断(?)を外すために使われた「不登校」であるが、かえって「くずかご診断」となった、ということは医師でも認めていることだ。
いつも言っているように「不登校」とは文科省が行っている学校基本調査における長期欠席の理由別分類の一つである。「病気」「経済的理由」「不登校」「その他」とある。長期欠席は「年間30日以上の欠席」と数量的に定義されている。これはもともと「年間50日以上の欠席」と定義されていた。なぜ50日から30日となったのか?
週5日制が原因である。つまり、授業日数を年間40週と数えて、半ドンの土曜日を半日、つまり0.5日と数える。と、40×0.5=20という数字が得られる。これが50日を30日と減らした理由である。だからなんだ、と言うと難しい。調査もしばらくは「年間50日以上の欠席」と「年間30日以上の欠席」を並行して数えていた。定量的な問題を残す調査であることを確認した上で、次に定性的な問題のあることを言おう。
登校拒否新聞では何回か同じことを言っている。「病気」「経済的理由」「不登校」「その他」というのは理由別分類である。つまり「年間30日以上の欠席」=「不登校」とはならない。欠席者の理由を決めるのは担任の教員である。「その他」というなくもがなの理由もある。めんどくさいから「その他にしちゃえ」と担任が判断すれば「その他」である。まあ、「その他」にも定義があるからそんないい加減なことではないだろうけども、決めるのは担任だ。だからバラつきがある。
いちばんの問題は「病気」と「不登校」の区別であろう。骨折した子が入院して欠席数を重ねたとしよう。この場合は「病気」となる。問題は二大診断である。起立性調節障害か発達障害と診断を受けた場合、担任は「病気」と判断するだろうか?
なお、この問題については「コロナ流行以後,その数が増えたとすれば「経済的理由」「病気」を理由とした長期欠席が増えたということではないのか?」と問うた論文が来月にも学術雑誌に載る予定だから、そちらのほうも参照してもらいたい。
ここではヤフーニュースで再配信された記事に寄せられたコメントを見ておきたい。この記事を書いている時点で392件のコメントが付いている。中にはやはりワクチン後遺症を疑う意見が多くある。ここで紹介するコメントは子どもの親に限る。
ウチの高校生の子はワクチン未接種ですがコロナ後遺症になりました。コロナ自体は風邪ぐらいだったのですが、治ってから1週間後に倦怠感で突然歩けなくなりました。おもりをつけたように手足が重くトイレに行くのがやっとでした。無理して学校に行くと倦怠感プラス痛みも出てきて数日ダウンしてました。結果は耳鼻科で上咽頭がだいぶ腫れてると言われて、Bスポット治療10数回通って治りました。他にも鍼と漢方やサプリ、鼻うがいに水素ガス吸引などいろいろ試しましたが。倦怠感は周りの人に理解されにくいとは思いますが決して怠けているとかではなく、コロナ後遺症は確実にあります。早く治療法が確立されることを祈っています。(yos********)
娘が小6の修学旅行で集団感染しました。クラスターです。2泊3日のバスの中はゴミ袋を広げたものをカーテンとして使うほどカオスだったそうです。担任は修学旅行当日コロナ陽性で欠席…なんで決行したのかと、終わった事だけど思わずにはいれません。発症半年後に症状が出ました。起立性調節障害として2年間治療しており、今もなお起立性調節障害として入院しています。倦怠感が強く(インフルエンザのようなしんどさとの事)日常生活が送れず、食事も取れず、鼻から胃までチューブ通し栄養を取っています。これが起立性調節障害なわけない、1年前からコロナ後遺症の疑いを訴えていますが、挙句の果てに精神的なものだと言われました。運動も勉強も得意で、色々やりたい事もあるのに、今はテレビを見ることすらしんどい状態です。先の見えない強い倦怠感が続く中、生きていても辛いだけ死にたいと訴えます…(ypo********)
うちの中3の子もCovid19感染後、不明熱1年、寝たきり登校不能になりました。子どもはワクチン未接種のお子さまもたくさんいらっしゃいます。うちは2回打たせてしまいましたが。ワクチン接種後から体調は悪かったのですが、Covid19感染でトドメを刺されたと考えています。後遺症外来の医師によれば、今となってはワクチンが原因かウィルスが原因かわからないと。検査データからはウィルスの可能性のほうが高そうとのこと。ワクチン救済制度も申請はしましたが恐らく通らないでしょう。ワクチン後遺症かウィルス後遺症かどちらか1つの病名にしぼることを目的としていません。子どもが元気になってくれたらそれでいいです。(ken********)
すべて目を通したところ、子どもの例について親が語っているのはこの3件である。いずれも深刻な例であることがわかる。最後の例にあるようにワクチン後遺症かどうかの判定は難しい。最初の例は未接種である。次の例は起立性調節障害の診断を受けているが「精神的なもの」との診立てもある。東洋医学で言うところの不定愁訴といったところか。しかし入院するほどである。
「不登校」が増えたと騒いでいる人たちは「病気」の増加に意図的に目をつむっている。長期欠席の総数が増えたことは事実だ。しかし、その内訳において「不登校」と目される例が増えたとは言えない。そもそも「経済的理由」でもなければ「病気」でもなく「その他」でもない「不登校」なる除外診断的な定義があやしい。この問題については今までもたびたび言ってきたことだから、ここでは略すとして、上のような例があることは明らかにコロナ渦により「病気」を理由とした長期欠席が増えたことになる。
「不登校」が増えたとなれば解法は「多様な学び」ということで一直線である。私は賛同しないが、御用学者を総動員してそのような方向に進むことは既定路線だろう。けれども、実態において後遺症が増えているとすれば、それでは解決にならない。文部科学省ではなく厚生労働省の問題ということになる。「登校拒否症」と言われていた頃、「登校拒否児」は「情緒障害児」とされて処遇を受けた。この「情緒障害」というのが当時の厚生省の用意した行政用語である。「不登校」と言えば学校問題、文部行政の問題かと思うかもしれないが、本来的には医療の問題である。その点が看過されて、いたずらに学校の問題とされていることに私は「不登校」という問題の淵源があると見ている。
なお、後遺症については詳しい人が独立言論フォーラムには何人もいる。今月25日には公開シンポジウム「トランプ政権と新型コロナ・ワクチン政策の転換」も予定されている。上の新聞記事については嶋崎史崇氏もXにて言及されているから参考にしてほしい。
https://x.com/FumiShimazaki/status/1920308479069466890
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ISF主催公開シンポジウム:トランプ政権と新型コロナ・ワクチン政策の転換~日本は変われるのか~5/25
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。