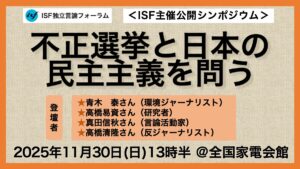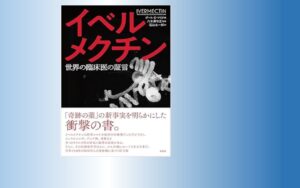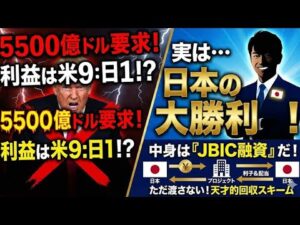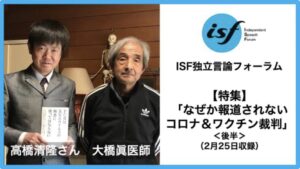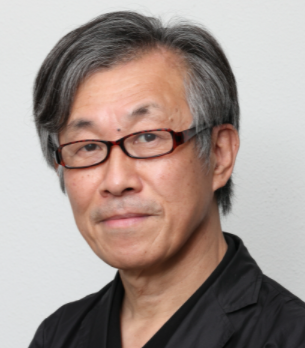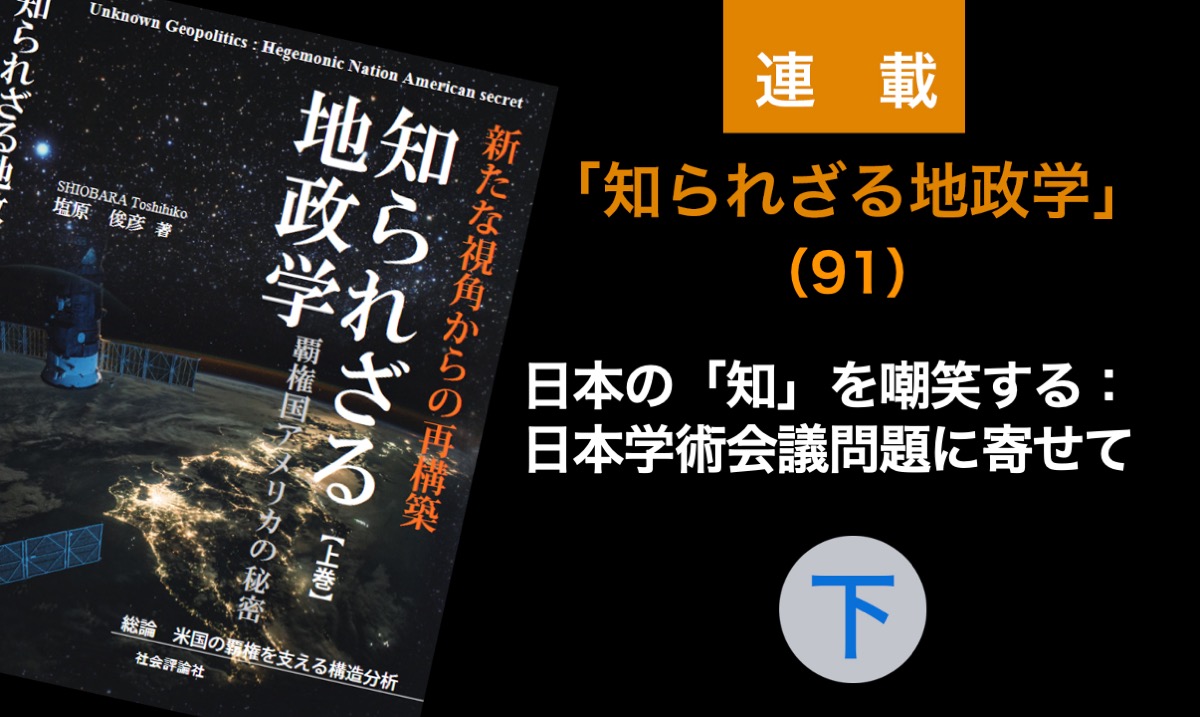
「知られざる地政学」連載(91):日本の「知」を嘲笑する:日本学術会議問題に寄せて(下)
国際
「知られざる地政学」連載(91):日本の「知」を嘲笑する:日本学術会議問題に寄せて(上)はこちら
いまトランプがやっていること
ここで、いまトランプによって進められている変革がここでの記述と深く関係しているので紹介しよう。まず、「科学の政治化」という大前提に立つ必要がある。拙著『知られざる地政学』〈上下巻〉で書いたように、科学の政治化は、科学を国家の座の隣に配置して、科学を統治に利用する現象を引き起こす。米国は科学を支配することで、世界統治を可能にしてきたのであり、その統治を今後も長く継続するためには、米政府は米国の先進性を保持したいに違いない。
ところが、「トランプ1.0」において、トランプが行った政策は、科学不信に基づく「科学への挑戦」であった。だからこそ、2024年11月6日、『ネイチャー』は社説「科学者たちは勇気と団結をもって、トランプ大統領に責任を問わなければならない」を公表したのである。そこには、「私たちは、次期政権が米国の最善の利益のために統治することを望んでいる。それは、前政権の最善の政策を維持し、トランプ大統領就任当初の政策に戻らないことを意味する」と記されている。「政策立案者や政治家は意思決定をコントロールすることはできるが、事実をコントロールすることはできない」という記述もある。
だが、残念ながら、トランプ政権は科学が米国のヘゲモニーの維持・拡大にとって重要な役割を果たしてきたことを十分に理解しているとは言えない。その典型が大学への「いじめ」である。大学への支援打ち切りは、「原則的な政治姿勢を示すものではなく、米国の国家安全保障に対する友好的な攻撃になる」。こう指摘する、コーネル大学のサラ・クレプスは、「連邦政府が資金を提供する大学研究は、米国の世界的リーダーシップを支える基幹となった」と的確に指摘している(注2)。
それにもかかわらず、トランプはすでに政治化する科学を自分の気に入らないものについては断罪して憚らない。たしかに、気候変動が人為によるものかどうか、遺伝子組み換えやワクチンの安全性などの問題で、科学が本当に事実だけを追求し、実験結果のすべてをさらけ出してきたかどうかについては、疑わしい面がある。ある時点での知見を過大評価して、事後的に誤っていたり、不正確であったりしたことは何度もあるのだから、科学者の理性、知識、礼節そのものも疑いの対象とすべきである、と私も思う。ただし、改善の余地はある。
科学的誠実性
科学の政治化は、科学者に対して「科学的誠実性」(scientific integrity)を問う。連邦予算獲得のために政治家になびいて、科学的知見を歪めることがないようにすれば、政治家に利用されたり歪曲されたりすることが減るはずだ。そうであるならば、科学的誠実性を科学者に養ってもらい、科学者の誠実性を守る仕組みづくりも必要になる。
科学の政治利用は以前からあった。たとえば、オバマ政権下では、ホワイトハウスは政府機関に対し、政府の科学者が従うべき標準的な慣行とプロセスを定めた「科学的誠実性に関する方針」の策定を指示した。2009年1月の就任演説で、「科学を本来あるべき場所に戻す」と約束した。2009年3月には、大統領は大統領覚書を発令し、公共政策の決定に影響を与える科学および科学的プロセスについて、国民が信頼できる必要性を認識した。
大統領覚書では、①政治任用官吏は科学的または技術的な調査結果や結論を隠蔽したり改ざんしたりしてはならない、②連邦政府が使用する科学的および技術的情報は通常、一般に公開されるべきである、③政策決定における科学的および技術的情報の準備、特定、使用は、法律で認められている範囲で透明性を確保すべきである、④行政部門の役職に就く科学者および技術専門家の選定は、科学的および技術的知識、資格、経験、誠実さに基づいて行われるべきである――とされ、連邦政府機関における科学的誠実性を導くための一連の原則が明確にされた。
バイデンは2021年1月27日、「科学的誠実さとエビデンスに基づく政策立案を通じて政府への信頼を回復するための覚書」に署名した。「本覚書は、2009年3月9日付の大統領覚書(科学的誠実さ)および2010年12月17日付の科学技術政策局長官覚書(科学的誠実さ)を再確認し、これを基盤とするものである」としたうえで、第一期トランプ政権を念頭に政府への信頼回復に取り組む姿勢をみせた。「連邦政府の科学者や連邦政府の業務を支援するその他の科学者の業務、および科学的事実の伝達に対する不適切な政治的干渉は、国家の福祉を損ない、体系的な不公平や不正義を助長し、国民が政府に寄せる、国民全体の利益を最善に守るという信頼を裏切るものである」という記述はおそらくトランプ政権への批判の含意をもつ。そのうえで、科学技術政策長官に対して、2009年3月9日付の大統領覚書発行以降に策定された省庁の科学的誠実性に関する方針の効果について徹底的な見直しを行うため、国家科学技術会議(NSTC)の省庁間タスクフォース(「タスクフォース」)を招集するよう求めている。同覚書で
は、科学技術政策長官は、「行政部門が科学技術プロセスに関与するあらゆる側面において、最高水準の誠実さを確保するものとする」と規定されている。そのうえで、「この責任には、行政部門および行政機関(機関)が、科学研究の実施および科学・技術データの収集における不適切な政治的干渉を禁止し、科学・技術上の発見、データ、情報、結論、または技術的成果の隠蔽や歪曲を防止する科学的誠実性に関する方針を策定し、実施することを確保することが含まれる」とされた。
注目されるのは、第6項において、「省庁の最高科学責任者(Chief Science Officer)および科学的誠実性担当官(Scientific Integrity Officials)」の任命がこの覚書の日付から120日以内に、科学研究に資金を提供し、実施し、または監督する機関の長に指示されたことである。2025年1月17日付のNYTによれば、「トランプ政権の第一期目の終わりには、科学的誠実性担当官は10数名しかいなかった。現在では30名以上となっている」という。ホワイトハウスの指示では、これらの担当官は政治任用ではなく、キャリア公務員でなければならないと定められている。
なお、2023年のホワイトハウス科学技術政策局による覚書では、科学的誠実性とは、①研究が査読(ピアレビュー)されていること、②科学者が報復を恐れることなく公然と反対意見を表明できること、③科学的誠実性に関する方針の違反は政府倫理規定違反と同様に深刻に扱われ、結果を伴うべきである――と定義されている。
だが、第二期トランプ政権下で、政治から科学を守ろうとする試みは継続されそうもない。2期目の最初の数時間で、彼はパリ協定と世界保健機関(WHO)から米国を脱退させた。それ以来、トランプ政権は連邦科学・保健機関の予算を削減し、連邦科学者を解雇し、研究を検閲して大学を脅し、国の主要な気候評価の重要な更新を準備していた数百人のボランティア科学者を解雇した。トランプは、産業界を抑制してきた規制を最小限に抑え、経済成長の中心となるエネルギー生産を促進することを目標としている。それにもかかわらず、「ついに科学に従う大統領が誕生した」と書くのは不誠実そのものだ(注3)。
先のNYTは、擁護団体である「憂慮する科学者同盟」が2405人の科学者の署名入りの書簡を連邦議会に送り、議員たちに「私たちの健康、環境、地域社会を守る科学的役割、機関、連邦研究を政治化したり排除しようとする試みに反対する」よう求めたり、ニューヨーク選出の民主党議員で下院科学委員会の委員であるポール・トンコ下院議員が政府機関に科学的誠実性に関する方針の維持と施行を義務付ける法案を提出したりする動きがあると伝えている。それでも、「共和党が多数派を占める現在の議会では、可決の見通しは暗い」と書いている。
本当は、科学的誠実さの欠如した大多数の日本の学者に、米国での問題意識を貫徹しながら、日本なりの科学的誠実さを植えつけるための教育が求められている。ところが、日本の硬直した権威主義のもとでは、こんな改革は100%できないだろう。
まず「知」からはじめよ!
つくづく感じるのは、日本の教育の低劣さだ。科学、学問、言論といった問題を論じたいのであれば、そもそも日本の学者は「知」について考えたことがあるのだろうか。本源的なところまで遡って熟考しなければ、科学、学問、言論と国家の問題を深部から論じることはできまい。
先に紹介した拙稿「日本学術会議騒動にみるもう一つの違和感」では、ウィリアム・デイヴィス著Nervous States: How Feeling Took Over the Worldを紹介したことがある。この本の書評のなかに、優れた現状認識が的確にのべられていたので紹介したい。
「知識という概念自体さえ、利害関係のない客観性の主張を失ってしまっている。我々が生きているのは、事実や情報が発見され共通の善のために共有されるのではない、競争上の優位性をあたえるために経済的価値のある商品として私有化されている「知識経済」なのだ。これは、「合意可能な共通現実」を構築するという科学の伝統的プロジェクトとは正反対のものである」
おそらく日本学術会議をめぐる騒動で侃々諤々の議論をしている人々の多くは、「合意可能な共通現実」の構築という科学の伝統プロジェクトを信じてきた人々なのではないか。専門家たる者、あるいは、いわゆる科学者は、「政治、感情、意見の対立を超えた」存在であり、そのようにみえる場合にのみ信頼できると信じているに違いない。しかし、大量の情報が瞬時に世界中を飛び交っている現在、知識を扱う専門家の評価にしても、その知識自体にしても政治や感情などと区別が判然としなくなっている。知識がすでに客観性ではなく商品性のもとに置かれていると認めざるをえないとみなす者からみると、この新しい現象への対処こそ重要なのではないかと思える。
この書評では、デイヴィスが、「知識の商品化は公共生活や経済生活が紛争によって定義づけられるようになり、戦争と平和の区別が解消されつつある、より広範な傾向の一部であるとみなしている」と指摘している。これが意味するのは、あらゆる事実が政治化されてしまい、事実や証拠に立脚した議論に基づく意見の形成すら不能ということだ。その結果、感情に頼った判断や議論が幅を利かせる。それゆえに、デイヴィスの本の副題は「感情が世界をどう支配するのか」となっている。ゆえに、私はこの連載(82)において「アジアの文化的隆盛に思う 「感情」の考察」(上、下)を書いたのである。
言葉としての知
知を英語でいうと、wisdom(知恵)とか、intellectないしintelligence(知力)、knowledge(知識)、reason(理性)といった言葉にあたると思われる。「賢い」という意味のwiseとwisdomは関係している。「理解力がある」というのがintellectないしintelligenceであることの要件のようになっている。「知っている」か否かいう面がknowledgeの関心事であり、「考える」や「数える」点に力点を置いているのがreasonだ。
いずれにしても、知は英語においても、ポジティブな面をもち、高い評価につながっているようにみえる。
それでは、「知」という漢字の源はどうなっているのだろうか。白川静著『字統』によれば、もともと「矢と口とに従う」というもので、「矢に矢(ちか)うの意があって、誓約のときに用いるもの」とされる。「神に祝禱し、神に誓約するの意の字で、これによって為すべきことが確認されるのである」と解説されている。「識(し)るなり」とか「覺(さと)るなり」といったことは、「神に約してはじめてそのことが確知され、認識されるのである」という。
どうやら、知は自分だけのものではないことが古くからよく理解されていたようだ。これから説明するように、知は個々人だけのものではなく、神をはじめとする外部たる集団や共同体(コミュニティ)と深くかかわっているのであり、漢字の「知」は、知の本質を教えてくれている。
そもそも「知っている」とは?
それでは、そもそも、「知っている」とは何を意味しているのだろうか。実は、この問いに答えるのは簡単ではない。そこで、社会学者の大澤真幸に助けを求めよう。
大澤が『生成AI時代の言語論』で指摘するように、「知っている」という心の状態と「信じている」という心の状態の区別に留意すると、「両者の間に微妙な違いがある」ことに気づいてほしい。「知っている」と思う多くは、言語ないし記号を通じて獲得したものである以上、あるいは、自分の直接経験によって「知っている」ケースは極端に少ない以上、「言語を通じて知るというのは、実は、誰かが知っていると主張していることを信じる、ということ」を意味していることになる。つまり、「知っている」というのは、「信じることを通じて知ること」に近い。
「神に約してはじめてそのことが確知され、認識されるのである」という知の原義に関連づけて考えると、信じる神に誓約してこそ認識されるものが知であるようだ。どうやら、知は、自分だけでなく、家族のような小集団、学校や会社などの組織、国家、さらに地球といった外部との関係のなかで認識されるものとみなすべきなのだろう。そこで問題になるのは、「距離」(distance)であり、距離が近いほど親近感をもち、信頼を寄せやすいという人間の特徴を思い起こす必要がある(注4)。
実践的知識と命題的知識
ここで、知の一種である知識には、実践的知識と命題的知識があるという話をしておきたい。知識には、記述してそれを知ることのできる「命題的知識」と、何かをする能力である「実践的知識」がある。たとえば、自転車に乗ることは、少なくとも表面的には、命題的知識に依存していない。能力や気質は必要だが、信念は必要ない。実践的知識である技術が必要になるだけだ(注5)。
先の「「知っている」というのは、「信じることを通じて知ること」に近い」という記述に対応して考えると、実践的知識は自分の経験に基づくものだから、言葉や記号といった外部情報を信じることなしに身につくものということになる。このとき、この実践的知識は個々人の経験に基づくわずかな知識にすぎない。
こう考えると、電子計算機の登場で人の計算能力が蝕まれたり、スマートフォンにグーグルマップやウェイズをダウンロードして以降、ナビゲーション能力が低下したりするのは、電子計算機やスマートフォン・アプリへの信頼による命題的知識の増加が自分の体験に基づく実践的知識を縮減する現象につながっていることを意味していることになる。いわば、「知識の外在化」(アウトソーシング)という技術の向上がさまざまな専門化を促し、それは、個人レベルでは、実践的知識の喪失につながり、無知を増加させるが、外部への信頼に基づく命題的知識が集団レベルの知識として蓄積されるようになるのだ。
これは、個人レベルでの実践的知識の喪失と集団レベルの命題的知識の増加をもたらす。換言すると、個人レベルでは、外部集団への信頼とその信頼を通じて知る命題的知識の重要性が高まるにつれて実践的知識は薄れ、個人としての知識は無知の領域を広げることになる。集団レベルでは、命題的知識が幅を利かせるようになるはずだ。
知とは何か
ここまでの考察と、スティーブン・スローマン&フィリップ・ファーンバック著『知ってるつもり:無知の科学』(土方奈美訳、早川書房、2021=Steven Sloman & Philip Fernbach, The Knowledge Illusion: Why We Never Think Alone, Riverhead Books, 2017)を参考にしながら、知そのものの定義を改めて考えてみよう。
実践的知識が個々人の知でしかないのに比べて、命題的知識は言語によって共有することができ、協力し合って蓄積したり発展させたりすることができる。その意味で、知識は、わずかな実践的知識と、集団や共同体(コミュニティ)に基づく信念やものの見方から形成された産物としての命題的知識からなっていると言えるだろう。
大切なことは、『知ってるつもり:無知の科学』にある、つぎの指摘である。
「知性は、個人がたった一人で問題の解決に取り組むという環境のなかで進化してきたのではない。集団的協業という背景の下で進化してきたのであり、私たちの思考は他者のそれと相互にかかわりながら、相互依存的に進化してきたのだ。」
ゆえに、同著では、「知性は社会的存在」であるとの見方が示されている。あるいは、「言語、協力、分業によって、社会脳を通じて伝えられた知識が蓄積し、文化が生まれる」と書いている。
こう考えると、知識とか知性とかいう知は、わずかな自分だけの知と「集団や共同体(コミュニティ)に基づく信念やものの見方から形成された産物」としての知から成り立っていることになる。そこで、気づくべきなのは、自分の知の圧倒的な少なさである。
以上から、知が関連する科学、学問、言論といった分野でも、自分の知の少なさに気づくことが何よりも大切であることがわかる。そう、だからこそ、もっと勉強しなければならない。それにもかかわらず、日本学術会議の瑣末な問題にこだわるのは、どうにも理解できない。こんなことでは、日本の科学、学問、言論は、世界レベルからみると、低水準のままだろう。そして、自分が不勉強であることに気づいていない彼らは、私のここでの批判に激怒するかもしれない。まあ、こうした構造を全体として崩壊させなければ、いつまでも知の低水準がつづくだろう。
【注】
(注1)2025年5月に亡くなったジョセフ・ナイは2004年に書いたSoft Powerという本で、それまで重視されてきた、軍事力や経済力といった強制や威嚇によって当事者が欲する結果をもたらす「ハードパワー」に代わって、強制ではなく「取り込み」によって当事者が望む結果をもたらす「ソフトパワー」、すなわち、魅力的な個性、文化、政治的価値や制度のような無形資産も国家安全保障にかかわっていることに注目した。
どうでもいい話だが、「NHKは8日、元米国防次官補のジョセフ・ナイさんの死去を同日朝の番組内で報じた際、冒頭の一部で別人の映像を放送したとして午前のニュース番組で訂正した」という(中日新聞を参照)。日本の「知」がいかに低レベルかを象徴する出来事であった。
(注2)Sarah Kreps, “An Attack on America’s Universities Is an Attack on American Power, How Academia Bolsters National Security,” Foreign Affairs, 2025。彼女の指摘は、科学と国家との分かちがたい結びつきを前提にしている。だからこそ、米国内における大学や研究機関の混乱に乗じて、フランスなどの欧州諸国は米国の科学者の誘致に乗り出している(NYTを参照)。
(注3)2025年4月22日、ホワイトハウスは、「アースデイに、ついに科学に従う大統領が誕生した」という記事をアップロードした。「トランプの下、米国は復活した(America is back)」と書かれても、心ある人はあきれるだけだろう。現実に根ざした環境政策を活用し、経済成長を促進すると同時に、何世代にもわたってアメリカ人に世界でもっともきれいな空気と水を提供してきた基準を維持するというのだが、トランプは5月9日に発出した覚書で、エネルギー省の職員に対し、シャワーヘッドやその他の家電製品の節水基準の執行を停止するよう命じた。1992年エネルギー政策法に従ってエネルギー省が公布した、蛇口、シャワー、浴槽、トイレの節水要件は、浴室用電化製品をより高価に、より機能的にしているとして、連邦政府は納税者の生活を悪化させるような規制を課したり施行したりすべきではないというのだ。
蛇足だが、不誠実なのは政治家だけでなく、学者や研究者も同じである。旧石器遺跡捏造事件を思い出してほしい。2000年10月5日付毎日新聞の朝刊がスクープしたこの事件は、藤村新一という、特定非営利活動法人・東北旧石器文化研究所の副理事長が遺跡に石器を埋め込むことで、石器のあった年代をどんどん古くまで遡らせ、旧来の学説をなんども塗り替えてきたことを暴露したものだった。藤村の「発見」と、それを信じた学者やオールドメディア、それに官僚は「世論」を誘導し、数多くの教科書の記述の変更がなされるまでに至る。だが、藤村の捏造が暴露された後になっても、その罪は問われることもないままに終った。彼の捏造で直接・間接に利益を受けた官僚やオールドメディアの人々もまた犯罪に問われることもなかった。嘘を見抜けず、その嘘を国家権力が教科書を通じて拡散させたにもかかわらず、国家権力自体もまたなんの責任もとらなかったということになる。小保方晴子をめぐるスキャンダルにしても、胞子様細胞・刺激惹起性多能性獲得細胞(STAP細胞)の存在をめぐる不正な研究であったにしても、その責任追及は刑事事件にまで至ったわけではない。不幸にも、笹井芳樹という理化学研究所の幹部職員が自殺したが、小保方への責任追及はウヤムヤだった気がする。私が決して許せないのは、ソ連崩壊後、市場経済化と称して、国際通貨基金(IMF)による市場経済化策を支持した似非学者どもだ。このとんでもない政策の結果、数百万、数千万人が窮乏化し、多くの人々が死亡したのだ。他方で、日本においては、マルクス経済学を信奉し、それを学生に教え込みながら、ソ連崩壊後、変節したにもかかわらず、反省のないままに教鞭をとりつづけている輩が大勢いる。不誠実な学者が圧倒的に多いのだ。
(注4)距離に注目した思想家にドイツに生まれたユダヤ系の社会学者ゲオルク・ジンメルがいる。彼は、「相互行為」とか「相互作用」と訳されている現象(英訳するとinteraction)に注目した。「ジンメルにとって、社会は個人と個人の相互作用によって成り立っており、社会学者は社会法則を追求するのではなく、こうした結びつきのパターンや形態を研究すべきなのである」というジェームズ・ファーガニスの指摘(Readings in Social Theory: The Classic Tradition to Post-Modernism, p. 146)通り、ジンメルは個人や小集団レベルでの社会的相互作用を考察し、そこで「距離」に注目した。家族のような小集団(共同体)では、個人と個人の間の距離は近い。ところが、会社や学校という共同体になると、相互の距離は離れてしまう。国家という共同体は個人からみると、大きい存在だが、きわめて大きな影響をおよぼしている。この距離に注目するアプローチは、陸海空およびサイバー空間を考察対象とする地政学に親和性をもっている。このため、長年、地政学・地経学を研究している私にとって、ジンメルの思想は重要なのだ。
(注5)この問題は、信号機をなくしてひとりひとりのドライバーに注意を促す方法に関連している。これまで、人間は技術優先による実践的知識を磨くことで、いわば「マシーン信頼」に重きを置いてきた。しかし、欧州の一部地域では、一定地区全体について、交通規制を全廃する実験が行われている。交通事故を減らす目的のためには、実は、法律は万能ではない。制限速度をなくしたり、信号機を取っ払ったりすることは危険かもしれないが、その地区を行き来するクルマもヒトも交通事故の危険を身近に感じるようになると、周囲に気を配り、クルマではなく運転者をみて運転するように迫られる。交差点では、運転者同士が見詰め合い、道を譲り合うことが当たり前になるだろう。こうして、法規制がなくても、交通事故を減らすことは可能となるというのだ。つまり、「マシーン信頼」だけが常に問題を解決するわけではないのである。だが、AIの高度化はこの人間軽視の「マシーン信頼」を広げている。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)