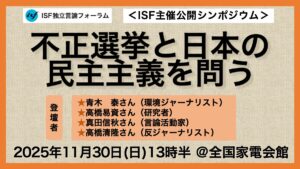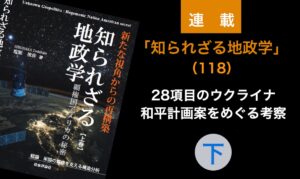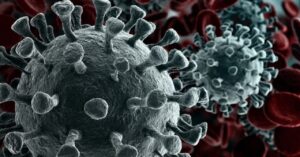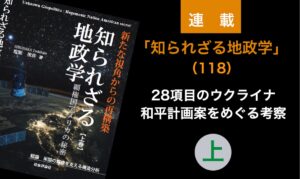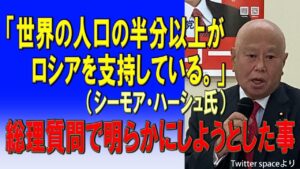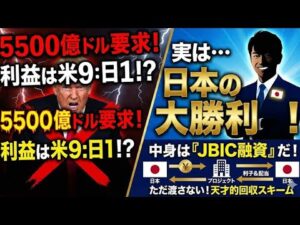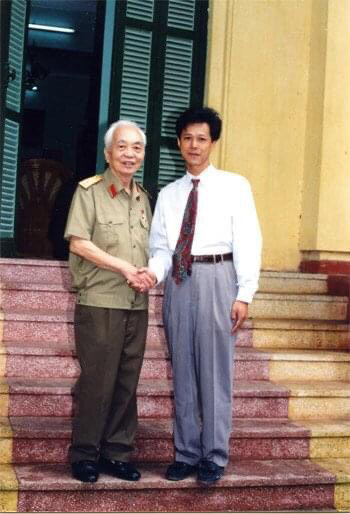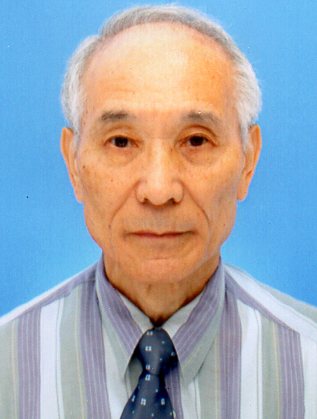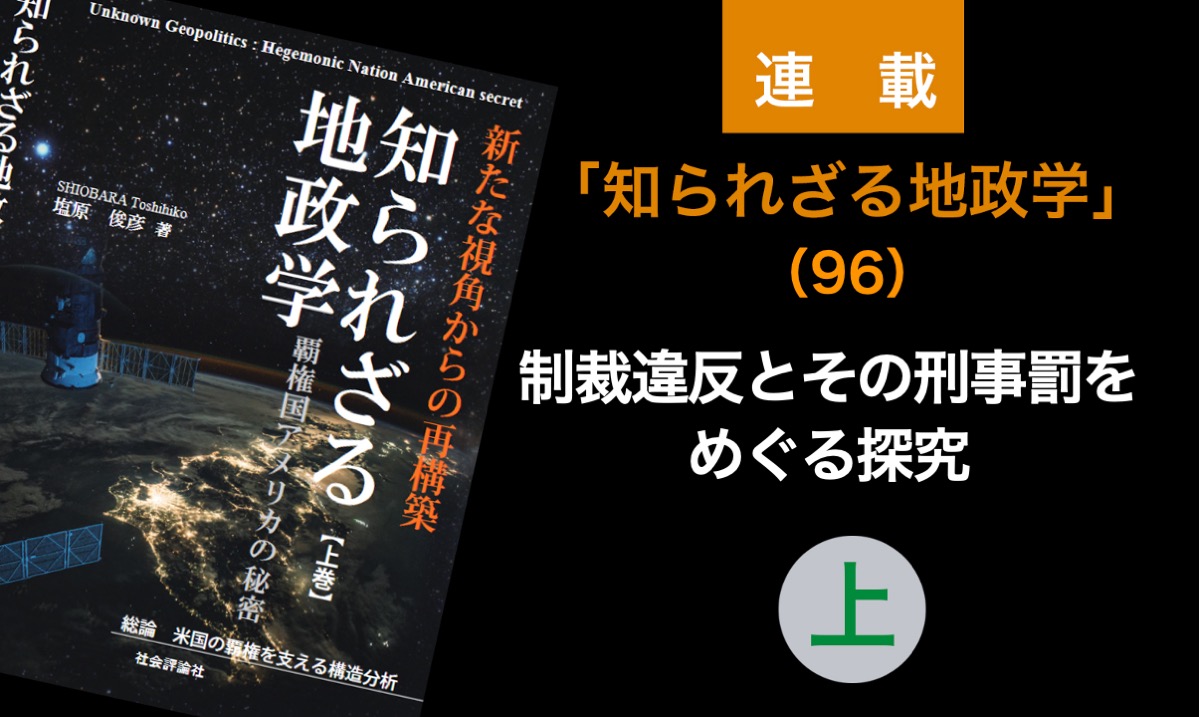
「知られざる地政学」連載(96):制裁違反とその刑事罰をめぐる探究(上)
国際
この連載において、制裁に関しては過去に何度も取り上げてきた。たとえば、第51回の「制裁をめぐる地政学」(上、下)や、第74回の「再論・制裁をめぐる地政学」(上、下)がそれである。今回は、2025年6月になって、二つの興味深い論文が公表されたので、それらを材料にしながら、改めて制裁について考察する。これまで論じてこなかった、制裁違反に対する刑事罰をめぐる問題について書いておきたいからである。
論文の一つは、「EUの制裁執行が増加」(以下、論文①)というもので、6月11日に公開された。もう一つは、「最前線は対ロシア制裁にどう取り組んでいるのか: ポーランドとバルトにおける実施と執行の力学」(同、論文②)である。
EUの制裁をめぐって
EUの制裁について概観するところからはじめたい。制裁は「制限的措置」(restrictive measures)と呼ばれている。2003年12月8日、EU理事会は共通外交・安全保障政策(CFSP)の枠組みにおける制限的措置の実施と評価に関するガイドラインを採択した。
具体的な措置としての金融制裁(制限措置)には、指定された人物や団体の資金や経済的資源の凍結、および、そのような人物や団体に資金や経済的資源を提供することの禁止がある。経済制裁には、通常、EUの制裁付属文書に記載されている特定の商品のEU域内への輸入や、対象国への輸出を禁止する輸出入禁止措置が含まれることが多い。
EU制裁の適用範囲は、すなわち、拘束可能なのは、EU域内、EU登録の航空機や船舶、EU国民、EU法に基づく法人、EU域内で活動する法人、また、EU企業のEU域外支店(non-EU branches of EU companies)に限定されている。EU制裁は域外適用がなく、EU事業体のEU域外子会社(non-EU subsidiaries of EU entities)を拘束することはない。さらにEUは、域外制裁は国際法に反するとして拒否してきた。別言すると、EUはいわゆる二次制裁に強く反対してきた。
だが、実際には、EU企業のEU域外子会社は、親会社を間接的な違反から守るためにEU制裁を順守することが多い。さらに、拙著『帝国主義アメリカの野望』で指摘したように、EUは最近になって、EU自体が二次制裁を科すと脅すようになっている(詳しくは137頁を参照)。
EU制裁と国内法
論文②によると、「EUの制裁は、国内法への置き換えを必要とせず、加盟国を直接拘束する規則によって科される」。しかし、制裁違反に対する罰則や執行当局の指定といった特定の側面は、EUの刑法調和に関する権限が限られているため、依然として各国の管轄下にあるという点に留意しなければならない。
とくに重要なのは、2024年4月24日付欧州議会および理事会指令(2024/1226)である。制裁違反の刑事罰に関する共通規則が導入されている。加盟国に対し、制裁違反の刑事罰化と売上高に基づく罰金の導入を義務づけるほか、執行基準を段階的に統一し、罰則の上限を引き上げることで、EU全体での執行基準を統一していくという方向性が示された。
まず、EU制裁の効果的な適用を確保するためには、加盟国が、通報義務などの義務も含め、EUの制裁に違反した場合、「効果的、比例的、かつ抑止力のある刑事罰および非刑事罰を設けることが必要である」と定められている。 また、これらの罰則は、EU制裁の回避に対処することが必要であるとも指摘されている。さらに、EU制裁を効果的に適用するためには、EU制裁に違反する犯罪行為の定義に関する「共通の最低規則が必要である」としたうえで、加盟国は、そのような行為が意図的であり、かつ、同盟の制裁を構成する禁止もしくは義務に違反する場合、または同盟の制裁を実施する国内規定に規定され、その制裁措置の国内実施が要求される場合に、「犯罪を構成することを確保すべきである」、とも規定されている。
たとえば、EUの制裁には、商品またはサービスの取引、輸入、輸出、販売、購入、譲渡、移転、輸送の禁止が含まれるが、このような禁止措置の違反は、「輸入、輸出、販売、購入、移転、通過または輸送の禁止が同盟の制限的措置を構成する目的地に移転させるために、第三国からまたは第三国へ物品を輸入または輸出する場合を含め、刑事犯罪を構成すべきである」、と明記されている。
あるいは、EUの制裁には、金融サービスの提供や金融活動の実施に関する分野別の経済・金融措置が含まれているが、これらの分野別経済・金融措置の違反は、「刑事犯罪を構成するはずである」、と記されている。
したがって、このEU指令によって制裁違反に対する刑事罰の方向性が示されたことになる。問題は、EU加盟国がこの指令に基づいて、どのように制裁違反に対処するようになったかということである。
期限を過ぎた国内法への反映義務
実は、加盟国は、2025年5月20日までに指令2024/1226を国内法に反映させる義務があった。一部の加盟国は、追加の(刑事)規定を制定する必要はなかったが、他の加盟国は、指令2024/1226を期限内に反映させなかった、と論文①は紹介している。
個別にみてみよう。オランダでは、制裁違反は長年、オランダ制裁法(Sanctiewet 1977)に基づき刑事犯罪として認定されており、経済犯罪法(Wet op de economische delicten, WED)に基づき起訴されている。したがって、EUの新たな指令2024/1226は、オランダの立法に改正を要しない。
ドイツは、EU制裁法違反の捜査に関する包括的な制度を既に整備している。ただし、指令2024/1226を完全に実施するためには、一部の規定を強化する必要がある。2024年秋、当時のドイツ政府は、指令2024/1226を国内法に反映させるための法案をドイツ連邦議会に提出した。しかし、2024年11月のドイツ政府の崩壊により、この法案は可決されなかった。新連邦政府は、指令2024/1226の実施を優先課題とし、新たな立法手続きを早期に開始する必要がある。
フランスは、2025年5月28日に、指令の対象となる犯罪活動に関して、法執行機関と EU の制限措置の実施を担当する当局間の調整と協力を確保する責任を有する機関(すなわち、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関するフランス諮問委員会)を指定する政令を公布し、指令 2024/1226 の国内法化に着手したばかりだ。制裁措置の違反は、フランスの法律ではすでに刑事罰の対象となっているが、この指令は、重大な過失や世界全体の売上高に基づく最高罰金額など、現在のフランスの法的枠組みには反映されていない特定の概念や手段を課すことを目的としているため、さらなる法改正が必要になる可能性がある。
ベルギーでは、EU制裁措置の違反は既に刑事罰の対象となっており、法人に対して最大96万ユーロの刑事罰金が科される可能性がある。2019年以降、ベルギー財務省の財務省は、最大250万ユーロの行政罰金を科す権限を有している。ベルギーの制裁執行枠組みは、現在、法人の全世界の総売上高の割合で計算される刑事罰金の課徴を認めていない。このような売上高に基づく罰金は他の刑事犯罪には存在しており、ベルギーの制裁執行制度は、この点において指令2024/1226に準拠して適応される必要があると考えられる。
スペインは、指令 2024/1226 の国内法への移行をまだ完了していない。2025 年 3 月 25 日、スペイン政府は、①EU制裁の違反を明示的に犯罪とする刑法改正案、②当該犯罪に対する企業の責任を導入する法案、および③EUの制裁違反によって得られた資産に対する罰則を強化するマネーロンダリングに関する規定の改正案を承認した。この法案は、EU の制裁の執行を監視するために、司法、警察、行政当局間の連携を確保するための合同調整委員会の設置も規定している。政府は 2025 年末までに議会の承認を得る意向を示しているが、指令 2024/1226 の国内法への移行期限はすでに過ぎているため、正式な移行が完了するまでは、検察は引き続き既存の密輸およびマネーロンダリング防止規定に依存することになる。
なお、最近の裁判所の判決は、EU の制裁措置に違反した場合、多額の罰金、資産の没収、個人に対する長期の懲役刑などの厳しい罰則が科せられる可能性があることを示している。執行の強化傾向は明らかであり、コンプライアンス違反のリスクはこれまで以上に高まっている。
反マネーロンダリング(AML)措置との違い
論文②は、制裁法と反マネーロンダリング(AML)規制の異なる法的枠組みの共通点や相違点に注目している。概念的には共通点がある。どちらも、マネーロンダリングや制裁の回避・迂回など、不正な目的での経済の悪用を防ぐことを目的としている。しかし、この二つの制度は、その具体的な目的、適用範囲、適用可能性、法的メカニズムの点で異なっている。これらの制度は部分的に重複しているため、その法的メカニズムや民間部門の責任に関して混乱が生じることが多い。
第一に、AML法は主に義務主体に適用される。義務主体には、銀行、資本市場、保険会社、年金基金、決済機関などの金融機関が含まれる。さらに、AML法は、弁護士、税理士、カジノ、不動産業者、公証人など、法律に明示されている特定の非金融主体にも適用される。これに対して、制裁措置は、金融部門に属するか否かにかかわらず、自然人および法人を意味するすべての法主体に対して適用される。
どちらの枠組みも、リスクベースのアプローチを要求しており、関連する民間企業は、その顧客や取引に関連するマネーロンダリングや制裁のリスクのレベルを評価する義務がある。両制度とも事実上、民間部門に対して、顧客管理を意味する顧客デューデリジェンス(CDD)、顧客の本人性確認を意味するKYC(Know Your Customer)手続き、取引モニタリング、従業員研修などの内部コンプライアンス・プログラムの実施を求めている。これらの内部システムは、マネーロンダリングと制裁措置違反の両方のリスクを特定し、軽減するのに役立つ。
第二に、AML問題と制裁を規制するEUの法律行為の形態は大きく異なる。AML法は、欧州議会と欧州理事会が採択した指令を通じてEU全体で調和が図られている。これらの指令が拘束力をもつようになるには、国内法への移管が必要となる。他方、制裁は、対ロ制裁の緊急性に対処するため、指令ではなく規制の形で導入される。規則は直ちに法的効力をもち、国内法への置き換えを必要としない。EUレベルで制定された規則は、加盟27カ国すべての国内法の枠組みの一部となる。これにより、制裁の第一の目的である、新たな状況への迅速な対応が、過度な遅延なく達成されることになる。
第三に、制裁法はAML法とは異なる用語を使用したり、類似の用語に異なる意味を付与したりしている。たえば、AML法では「実質的所有者」という用語を使用し、直接的または間接的に顧客を最終的に所有または支配する自然人として定義している。実質的所有者を決定するための閾値は、多くの場合、25%+1株または25%以上の所有に設定されている(指令EU, 2015/849, 2015 )。
制裁とAML制度のもっとも顕著な違いは、すべての民間企業が制裁違反に関連して疑わしい取引報告書(STR)の提出を義務づけられているわけではないが、金融機関は、両制度の要件が要求する仕様に従って、金融情報機関(FIU)またはその他の管轄機関に報告しなければならないという点である。したがって、金融機関は両制度に基づいて二つの異なるタイプのSTRを提出することになる。金融主体ではない自然人または個人事業者である制裁に関する法律の対象者は、制裁を受けた個人および/または団体に属する、所有、保有、または支配される資金および経済資源を凍結する義務がある。金融主体とは対照的に、自然人や個人事業主はAML法に規定されるSTRを提出する義務はない。
第四に、制裁法の複雑さゆえに生じる混乱がもう一つあるかもしれない。すなわち、規則833/2014の第3k条は、附属書XXIIIに列挙されているように、ロシアの産業能力を高める可能性のある特定の商品のロシアへの販売、供給、移転、輸出を禁止している。しかし、同規則は、既存の契約、非商業的用途、人道的目的、医療・医薬品、外交・領事用途など、禁止が適用されない特定の適用除外を概説している。これらの適用除外は合法的な活動を認めることを意図しているが、同時にリスクもはらんでいる。企業はこれらの規定を悪用して禁止された活動を継続し、制裁を回避しようとするかもしれない。最近の報告書では、人道目的の物資が軍事目的に転用された事例が取り上げられている。こうした法的免除は、明らかに迂回への水門として機能し、執行メカニズムの堅固性に疑問を投げかけている。
ほとんどの適用除外の適用を受けるには、各加盟国の所轄官庁による事前の認可が必要であり、同当局は適用除外の条件が満たされているかどうかを評価する。これらの認可はライセンスの形で発行される。これらの輸出許可は、バルト三国の金融情報機関(FIU)が許可する免除と区別することが重要である。FIUの免除は、特定の状況下で凍結された資金や資源へのアクセスを許可するなど、金融制裁に厳密に関係している。FIUの役割は、金融制裁の遵守を監督し、違反に対して罰則を科すことに限定されているため、輸出関連の免除を扱う権限はない。
ほとんどのEU加盟国では、AML規制や制裁義務に対する民間部門のコンプライアンスを監視する責任を、異なる監督機関が負っている。ただ最近になって、ラトビアではこの動きが変化し、2024年4月以降、AMLと制裁の責任の大半が金融商品取引法の下に統合された。しかし、ポーランドではこのような一元化は行われていない。
「知られざる地政学」連載(96):制裁違反とその刑事罰をめぐる探究(下)に続く
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 塩原俊彦
塩原俊彦
1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)