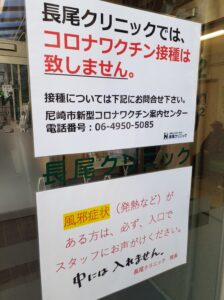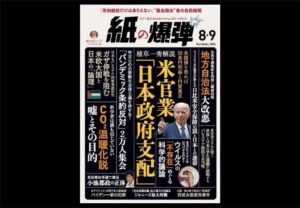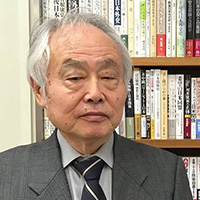日本の本当の安全保障を直視しなければならない時代になった
社会・経済安保・基地問題国際政治赤坂プレスセンターに設置される予定の統合軍司令部を通じて今後米軍は自衛隊を統合作戦司令部傘下の一部署として命令できる。自衛隊はますます独立性が損なわれることになる。日米同盟に関連した資料には「常に忠誠」という美辞麗句の割には、過去80年間の日本の巨大な経済発展にもかかわらず、またそれに対応するアメリカの科学技術の衰退にもかかわらず、在日米軍と自衛隊の間の実質的な指揮系統において対等性がないことが明らかである。 軍事に関する協議は日本からの意見を考慮することなく、ワシントンから政策決定や、 防衛予算増加の要求ばかりがくる。米軍は日本からの助言を決して聞かない。
トランプになってからその傾向がますます強くひどくなっているが、その伝統は長い。 アメリカは日本に対し、自衛隊の役割の拡大を要求している。でもそれは、統合軍司令部に従う指揮系統の中ですることで結局日本政府が 自衛隊が 中国との紛争に参加することを望んでいなくても、自衛隊が中国との紛争に駆り出されいくことの意味しかねない。 私は、日米軍事協力に見られる危険な構造について、多くの日本の専門家と直接話し合う機会があった。今まで述べてきたように重大な構造上の問題に対する日本人の懸念は明らかだ。しかし同時に、日本人にはあまり理解されておらず、あるいはタブー視されているもっと深刻な問題があることも浮き彫りとなっている。
多国籍企業への指揮統制のアウトソーシング 2001年にブッシュ政権が大規模な民営化を始めて以来、アメリカ軍はその重要な機能を企業に委託することによって壊滅的な打撃を受けた。今日、米国国防総省の計画や管理の多くは、国家の長期的利益にコミットする軍人ではなく、短期的利益を追求する多国籍企業によって指揮されている。米軍に不可欠な部分を運営する企業の多くは株式が公開されており、米国と利害が対立する可能性のある勢力を含む世界中の未公開株からの圧力にさらされている。こうした企業の利益追求は、米国が巻き込まれる紛争の数を増やす大きな原因と力になっている。
悲しいことに、今日の日本、特にITの分野でも同じような傾向が見られる。自衛隊の通信、具体的には、かつては自衛隊内で管理されていた指揮統制通信が、オラクル、グーグル、アマゾン、そして今ではパランティアのようなさらに信頼性の低い企業のような多国籍企業にアウトソーシングされている。これらの企業は、軍隊のすべての指揮統制通信に使われる通信システムをコントロールしている。
これらの企業は民営化によって軍にとって必要不可欠な存在となっているが、その役割は法律や国際条約に表記されておらず、規制されていないことが多い。要するに委託を受けている軍産企業は指揮系統の一部であるが、その役割りはあくまで不透明である。自衛隊の指揮統制においても営利企業が、単に自衛隊が使用するハードウェアやソフトウェアを提供するだけでなく、販売後もそれを管理し続け、軍が本当の独立行動を取れないことになる。
しかもその企業がイスラエルと連携があればすべての情報が瞬時にまた恒常的にイスラエルにも伝達されることになる。 これらの企業は、その気になれば、集めた情報を第三者に売ることもできる。日本人はこれらの企業がそのようなことをしないと信じているが、保証はない。実際、オラクルやパランティアのような企業は、まさにそのようなことをしてきた事例がある。
もうひとつ懸念されるのは、日本が購入しようとしている新兵器システムにおいて、自衛隊がソフトウェアのアップデートに依存しすぎていることだ。ソフトウェアのアップデートが常に必要な武器は大変脆いもので多国籍企業が儲けるが、万一苦しい状態になったら、その武器は高い値段にもかかわらず、全然役にたたなくなる。 最も基本的な機能をソフトウェアに依存している航空機、戦車、その他の軍用ハードウェアは、 機能するために常に更新されなければならず、かなりの費用がかかる。
多くの場合、そのようなソフトウェアのアップデートは、兵器システムをより効果的にするのではなく、より壊れやすくする。 常にソフトウェアのアップグレードを必要とする高度に自動化された兵器システムが優れていると思われているが、そのようなシステムが極めて過酷な環境でテストされることはほとんどない。 もちろん、自動化やデジタル化が役立つ場合もあるが、困難な環境下でも兵器システムが機能し続けるよう、細心の注意を払わなければならない。兵器のデジタル化やオートメーションに依存しすぎると、電気が来なくなったときに役に立たない。電気がない、あるいは石油がない、あるいはハッキングされる状況はあり得ないと考えるのはナイーブだ。ドローンやロボットのように自動化されなければならないシステムもあるが。戦車や飛行機、その他の装備には、手動である方が安全な機能がたくさんある。例えば、自動化されたドアや窓は、手動ドアや 窓よりも安全性が低い。しかも電力供給が止まっても混乱が生じないようにするために、通信の一部も書き込むべきだとさえ言える。 悲しいことに、何がデジタルで、何がアナログや手動であるべきかという問題は、科学者によってではなく、利益を追求するアメリカの多国籍企業で働くマーケティングの専門家によってなされるのである。
AI化の脅威
自衛隊にとっての深刻な脅威は、アメリカやイスラエルの一握りのIT企業によって推し進められている、無分別なAI化である。 AIとは、コンピューターによる分析と意思決定を支援する曖昧な言葉である。AIの意味が正確でないこと自体が危険なのだ。AIの推進は、自律走行する自動車、飛行機(ドローン)、ロボット、その他の装備の推進の一部である。これらの自律型機器や、意思決定のためのAIベースのシステムは、オペレーターが遠隔操作で武器をコントロールするという単純なプロセスをはるかに超えている。 これらの新しい自律型兵器やAIシステムは、オペレーターの承認なしに、場合によっては司令官や将軍の承認なしに、勝手に意思決定を行う。それはコンピューターが科学的な検討の結果としてやるという前提があるが、それは本当かどうか全然証明されていないし、公開されていない。
このようなシステムのリスクは甚大であり、軍へのAIの大量使用は深い懐疑的な目で見なければならない。 AIという神様が、膨大なデータを科学的に考察した上で兵器システムの決定を下すと言われているが、その確証はない。ほとんどのAIシステムは企業に所有権があって、自衛隊にそのプロプライエタリ(著作権がある)ソフトウェアに従うAIシステムを公開しない。自衛隊は直接そのソフトを変更や修正することもできない。というと自衛隊は最終的にAIシステムを所有しているわけではなく、しばらく企業からかりているだけなのだし、企業がその情報を悪用しないという前提があるが、米国軍産の腐敗をみれば全く信頼できない。 つまり、AIによって生み出されたインテリジェンス、あるいはAIによって制御されたドローンやロボットは、敵にハッキングされ、その活動をコントロールされる可能性がある。あるいは、攻撃に関する意思決定プロセスは、最終的には兵器システムを供給する請負業者によってコントロールされる。
企業がAIシステムによる決定が科学的であることをユーザーに伝えるかもしれないが、それが真実であることを確認することはない。AIが出した勧告が、科学の分析ではなくて、第三者によって出された秘密の指令に基づいている可能性も十分にある。兵器システムにおいてこのような不確実性はまったく容認できない。
さらに、AIシステムに依存するようになった者は、習慣が怠惰になり、思考が軽薄になる傾向があることが研究で実証されている。AIは兵士の機能を向上させるどころか、むしろその対応力を低下させる。 AIには使い道があるかもしれないが、AIに過度に依存すると、オペレーターの行動に悪影響を及ぼし、AIシステムが故障したり、電気が停止したりした場合に無力な、情報不足のオペレーターを生み出すことになる。
政治混乱に直面している米国は信頼できる同盟国か?
最後に、今日、日本が直面している最も深刻な安全保障上の問題は、間違いなく、米国が同盟において不変の常に信頼できるパートナーであると思い込んでいることである。日本が米国の大規模行政制度崩壊に備えることを怠っている。
この間、米国の大統領は軍部の大半の反対にもかかわらず、国会や同盟国に許可を得ない状態、国際社会を無視して行ったイラン空爆によって示された大規模なシステム不全を見れば、その危険性がどれほど大きいかがわかるだろう。安全保障の議論において、米国内政の不安定性の問題は第一義的なものであるべきだ。
自衛隊は、台湾をめぐる中国との紛争、北朝鮮との紛争、朝鮮半島における北朝鮮と中国との紛争、北方領土におけるロシアとの紛争、さらには中東や南太平洋での紛争など、将来起こりうる紛争を想定した何百ものシナリオを準備している。 しかし、日本が用意したこれら何百もの戦闘シナリオのどれにも、アメリカ側の指揮系統の失敗の可能性や、アメリカ軍内部の大規模な衝突か麻痺の可能性は考慮されていない。
私が知る限り すべての戦争計画は、米国が常に信頼できるパートナーであり、コンパスが海上で船を前進させるように頼りになると想定している。 これは危険な虚構であり、日米両軍が絶対的な同盟を維持するという意識を捨てなければならない。
アメリカ社会全体でも、軍や情報機関自体の派閥間でも、すでに大規模な内部対立が起きている。 トランプ政権の正当性、そして統合参謀本部議長を通じての指揮系統の権威は、統合参謀本部議長であり最高位の軍人であるチャールズ・Q・ブラウン・ジュニア空軍大将が憲法違反なやり方で理由なしに解任され、不法な特別アクセス・プログラムというダーティー・オペレーションを担当した無資格のダン・ケイン大将に交代させられたことで、疑問視されている。トランプ政権が腐敗し不透明な新たな指揮系統を4月に構築した時、10人以上の将官が正当な理由もなく解任された。
しかも、ICE(移民税関捜査局)による非市民、そして今や市民をも対象とした違憲の拉致事件は、軍や連邦政府の権限を行使する者の正当性についても深刻な疑問を投げかけている。 アメリカ社会で大規模な紛争が起こる可能性は高まっており、それは指揮系統に直接影響を与えるだろう。アメリカ側の指揮系統の混乱は、何よりも日本の安全保障に直結する。
結論
日本は、進められている軍事技術と戦略における様々なシフトの真の意味を科学的かつ客観的に評価し、 アメリカの兵器メーカーが要求するからではなく、むしろ、いかなる点においても兵器販売から利益を得ていない専門家による科学的評価に基づいて、何をすべきかを決定しなければならない。
日本の安全保障政策に関しては、タブー視することは許されない。軍人や軍事専門家は、国内外の兵器製造会社のコンサルタントとしての個人的利益を考慮することなく、国家の長期的利益を目標として掲げなければならない。
★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 Emanuel Pastreich(エマニュエル・パストリッチ)
Emanuel Pastreich(エマニュエル・パストリッチ)
ワシントンDC、ソウル、東京、ハノイにオフィスを持つシンクタンクであるアジアインスティチュートの会長を務めました。パストリッチは、未来都市環境研究所の所長も務めています。パストリッチさんは、2020年2月に、米国大統領の立候補を独立者として宣言し、2024年にも立候補しています。