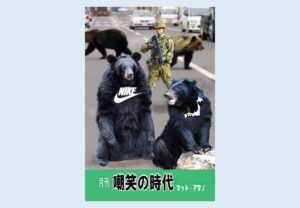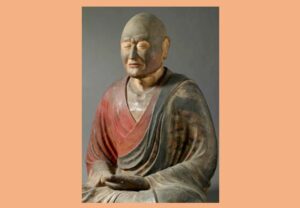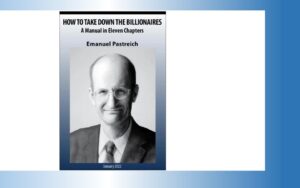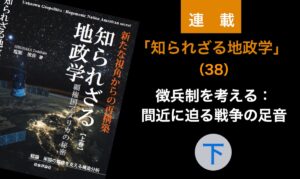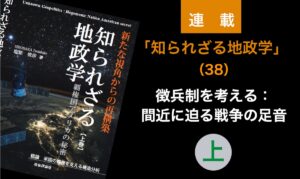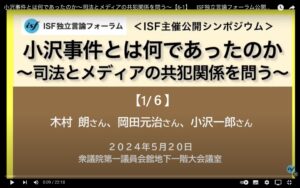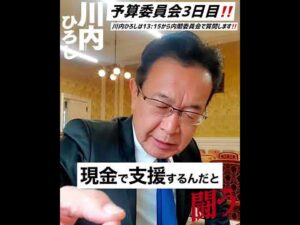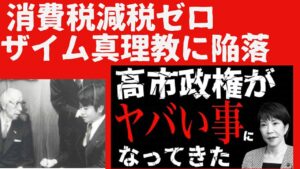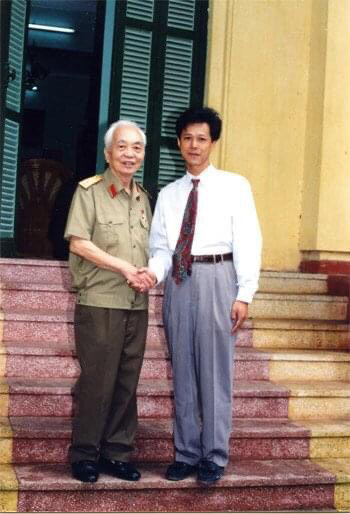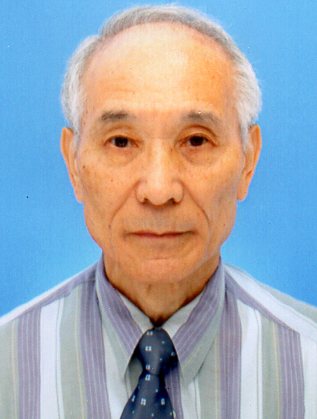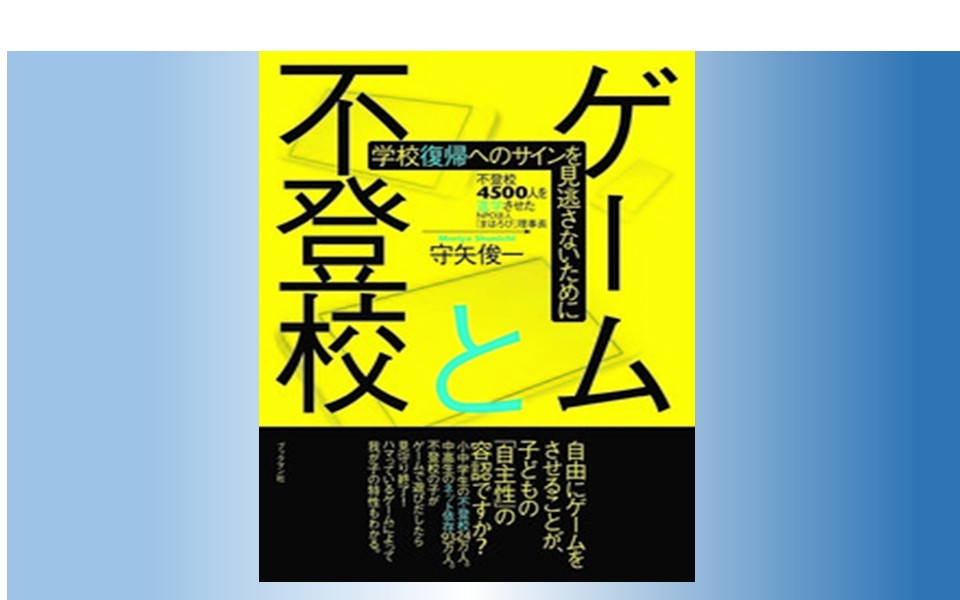
登校拒否新聞書評欄:守矢俊一著『ゲームと不登校:学校復帰へのサインを見逃さないために』(ブックマン社、2023年)
社会・経済表題にあるごとくゲームが問題である。著者はNPO法人「まほろび」の理事長。大学生の時に家庭教師を始めた。そこで受け持った中学生の子が二人とも学校に行っていなかった。家庭教師として二人の高校進学をサポートしたところ、出席数が足りないとか内申点がないとか、あるあるな壁にぶつかる。ともあれ二人とも無事に高校進学をはたすことができた。その実績から、そういう子たちのために予備校をつくることに。世は乱塾時代から高校全入の時代へと進む。そこで「落ちこぼれ」と言われる子たちの中退が目立つようになる。「落ちこぼれ」は「落ちこぼし」とのスローガンも虚しく、通信制高校では中退率を下げる術がない。守矢氏は私立の通信制高校と提携してサポート校を設立。「それを我が国で最初につくったのは、私です」(23頁)と本人が記している。
問題は2003年に起こる。この年は、私が通信制高校を卒業して大学に入った年だ。小泉内閣の構造特区構想が通信制高校を変える。前年末に公布された構造改革特別区域法の第12条により「学校設置会社」が認められるようになった。具体的には構造改革特別区域における特例措置「学校設置会社による学校設置事業」(特例措置番号816)に拠る。
通信制高校と提携しているのがサポート校である。通信制高校は授業時間も少ないし、クラブ活動などの課外授業もない。そこで、サポート校が通常の学校の役割をはたすわけである。藤井君は職員室で古典の教師がギターを弾いているのを見つけてしまった。「職員室で何してるんだ!」と弾劾したところ、その男からギターの弾き方を教わることになった。その時に弾いていたヤマハの古いギターをもらって、それを担いで学校へ行くことに。勝手に軽音部を始めたわけである。サポート校は部活動に相当する役割を提供する。あとは勉強の手助け、補習だろう。月に一度のスクーリングでレポートを提出。最後に試験を受けて単位を取ることは自学自習の習慣がないと難しい。たいていの場合、通信制高校は無試験だ。それだけに入るのは易しいが出るのは難しいという現実がある。サポート校はそのへんをサポートするわけだ。
つまりサポート校は通信制高校を母屋としている。スクーリングとレポート提出は通信制高校のほうで行っているわけで、あくまでも主従関係がある。ところが「学校設置会社」が認められるようになるとルールが変わった。株式会社による学校設置が認められるならば、会社の経営していたサポート校がそのまま母屋である通信制高校を設置できることになる。と、どうなるか?
その顛末は本を読んでいただこう。
問題は構造改革特別区域法の第12条である。
――地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第2号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第2条第1項中「及び私立学校法第3条に規定する学校法人」とあるのは「私立学校法第3条に規定する学校法人及び構造改革特別区域法第12条第2項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件の全てに適合している株式会社」と(中略)する。2 前項の規定により学校教育法第4条第1項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。(以下、略)
この中に「学校教育法第1条に規定する学校」というのがいわゆる「学校」の法的な定義で、俗に「1条校」と知られるものだ。それが「学校設置会社」を「準学校法人」として学校の設置を認めるという。そこで、広域通信制高等学校が設立されることになった。
広域通信制高校が制度化されたのは1962年9月の文部省令「高等学校通信教育規程」にさかのぼる。10月には早速、日本放送協会学園高等学校が開校。早速というよりも、この学校を開校するために省令が出たのだろう。このあたりの事情は私も明るくない。改めて調べてみる必要もあろうが、とにかく広域通信制という制度自体は以前からあった。それが構造改革特別区域法によって雨後の筍のごとく増えた。なぜか?
特区に学校をつくるという発想にムリがあるからだ。特殊な研究室を必要とする大学などの研究機関は別として、学校とは基本的には都市部に設けるものだ。わざわざ辺鄙な所に特区を設けて学校設置を許可するというのはどういうわけか。言うなれば、広域通信制高校以外に選択肢はない。「学校設置会社」の根拠法はあくまでも特区法である。その施行に合わせて、2003年3月に「文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則」が、2004年3月には「高等学校通信教育規程の一部を改正する省令」が公布された。結果的に「株立」とされる学校のほとんどが広域通信制高校として開校した。早いものだと9月に開校。2005年4月には数校が開校した。
その結果、スクーリングが軽視される傾向が見られるようになり、卒業が容易になる中で、守矢氏は自ら通信制高校を立ち上げる。けれども、それがいつのことなのか明記されていない。そして、「株式会社角川ドワンゴがつくったN高校(2016年開校)は「学校の認知度」を上げるために、教育業界では考えられないほどの「広告宣伝費」を投入し、SNSなどの最新のツールを使っての広報活動も同時に進めた」(25頁)と話が飛ぶ。たしかにN高校は株式会社ドワンゴが設立した学校法人であるが、先の「株立」の広域通信制高校の問題とどう関係しているのか。生徒の側にしてみれば、やはり在籍する学校は大きく知名度が高いほうが良い。特区法に問題があったのか、それとも企業の参入そのものが問題なのか。氏の問題意識が読み取れなかった。
さて、タイトルにある通り、『ゲームと不登校』である。ゲームの何が問題か、ということだ。この問題については前号で述べたように「因果が逆」というのが反対論の基調であった。結果としてゲーム依存になっている。原因は学校生活や勉強など別なところにあるわけだからゲームを規制するのは「因果が逆」という論である。この点、守矢氏は何と言っているのか?
ゲームというのは、そもそも「ハマる」ようにできています。人気のゲームほど、ハマります。・・・ゲームは「依存症になる」のではなく、「そもそも依存するようにつくられている」ものなのです。・・・膨大な時間を楽しく過ごせるゲームは、次々にアップデートされていきます。子どもが家のなかで、インターネットやゲームで遊ぶことで心地よく過ごせる環境が一気に整ってきてしまった今、学校現場や不登校支援の専門家たちが行う支援方法や助言が、残念ですがアップデートできていません。(47-50頁)
アップデートといえば、「家庭内暴力」を伴うような場合には警察を呼ぶことを辞さずという氏の認識は新しい。親がゲームを取り上げようとしたり、オンラインゲームの課金をめぐり親子でトラブルになったりすると、子どもが暴力を振るう場合がある。本に書いてある例では、生活安全課から15人も来たという。すでに三度目の通報である。自殺する危険性もあるため窓の側に回る要員もいるとはいえ、それだけの人数で来たということは現実に警察のほうでも身の危険を感じるケースがあるのだろう。少年係の警官が強く諫めたことで、以後、子どもの態度は改まった。フリースクールを母体とした親の会の主張では、通報だけはぜったいにやめろ。親子の信頼関係が二度と修復できなくなる、としていたものだ。
引用文は前号で紹介した国際疾病分類(ICD-11)にある「ゲーム障害」を念頭に書かれている。最近は文科省の「GIGAスクール」構想により子どもたちにタブレット端末が供与されている。wifiさえあればどの子もオンラインになれる時代である。守矢氏はwifiを解約することを提案している。そうすると、子どもは無料のwifiスポットを求めて家を出るようになる。そういう意味では、ゲームというよりも端末を通じてオンラインになることに問題がありそうだ。
ゲームがオンライン化するとクリアするということがなくなる。ファミコンであれば、だいたい30分でクリアできる内容だった。RPGであれば時間はかかるにせよ、クリアしてしまえば終りだ。この頃、スーファミを手にしたので、マリオカートをやってみようと中古ソフトを購入した。ところが、CPU相手に風船割りができないことに気がついた。学校に通っていた頃は、よく友達と風船割りをやっていたので、またやりたいわけなんだが、もう一人、コントローラーを操作してる人間がいないとできない仕組みである。ポケモンを手にした頃はもう学校に行っていなかったので、独りぼっちである。結局、誰ともポケモンを交換できないのだから、あまりおもしろくない。先日、発売されたSwitch 2というゲーム機のローンチタイトルとなったマリオカートワールドはオンライン通信により最大24名で遊べるようだ。部屋にこもっていても多人数と遊べるから楽しいだろう。
氏は「まほろび」という学校を開いているので、そこに相談に来た親と子の例が紹介されている。基本的には勉強させるというスタンスである。その場合、その子がやっているゲームの内容から指導方法を変えるという。たしかに、アイドル育成ゲームをやってる子と格ゲーをやってる子ではタイプが違う。じつに、この本ではおよそ40頁を割いて、流行りのゲームの紹介と、その分類、それに応じた指導方法が書かれている。相談を受けた子どもたちの多くは進学先として通信制・定時制ではなく全日制を選ぶという。この点、学校がオンライン化しつつある現況において、どう本人たちの認識も変わってくるか。アップデートが求められる。
その他、発達障害支援法が施行されてから、「不登校」だからといって発達障害の検査を受けることを勧められるようになったことの問題が記されている。知能検査の結果、「疑い」があるとされても、それは「診断」ではない。氏は検査方法に通じているので、このあたりは読み応えがある。ただし、起立性調節障害という診断については、とくに疑われていないようだ。氏自身が括弧をつけて明記している「不登校は治すもの」(154頁)という主張には同意できない。「子どもが本当に学校に行けないほど傷ついている状態なのかどうかは、全力で見分けなければいけません」(190頁)というフレーズは印象的だ。登校拒否と「不登校」を区別していた高垣忠一郎の主張を思い出す。これについてはまた別に記そう。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。
ISF会員登録のご案内
 藤井良彦(市民記者)
藤井良彦(市民記者)
1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。